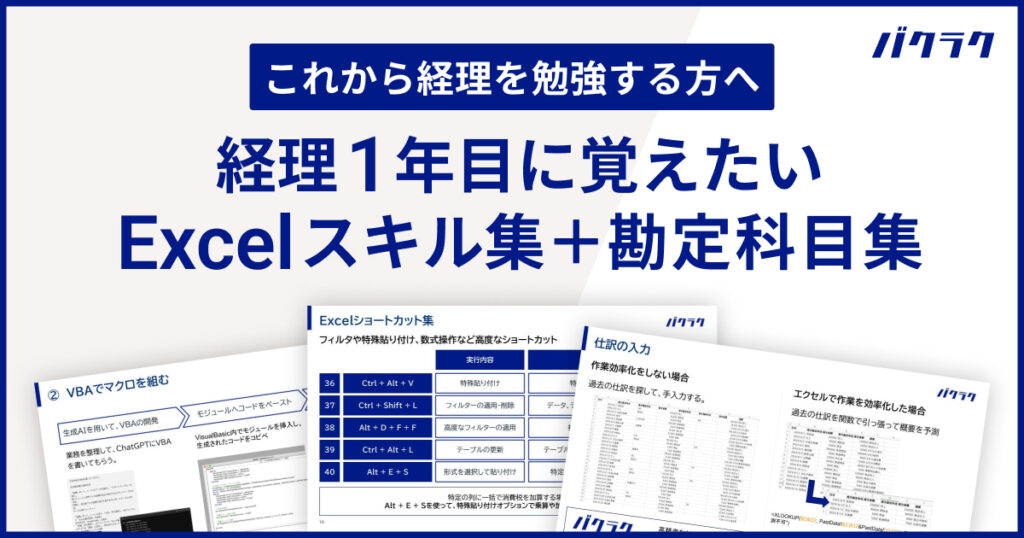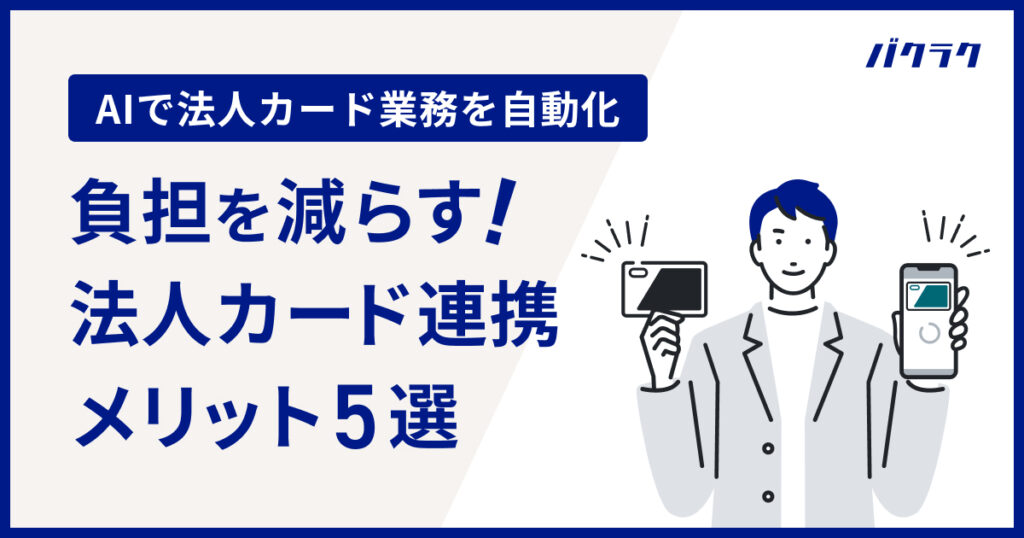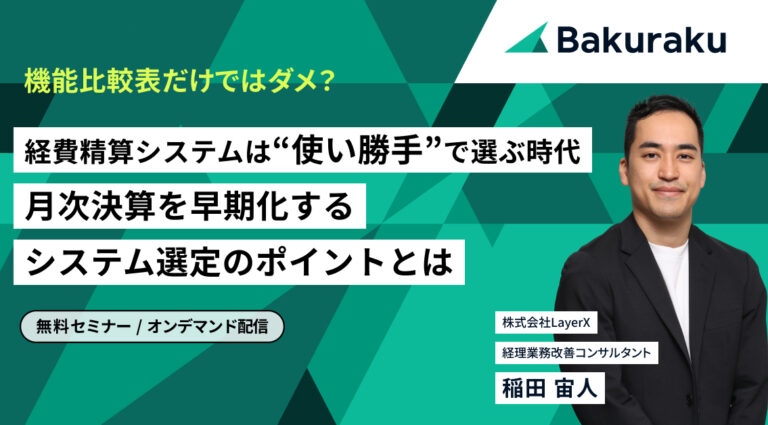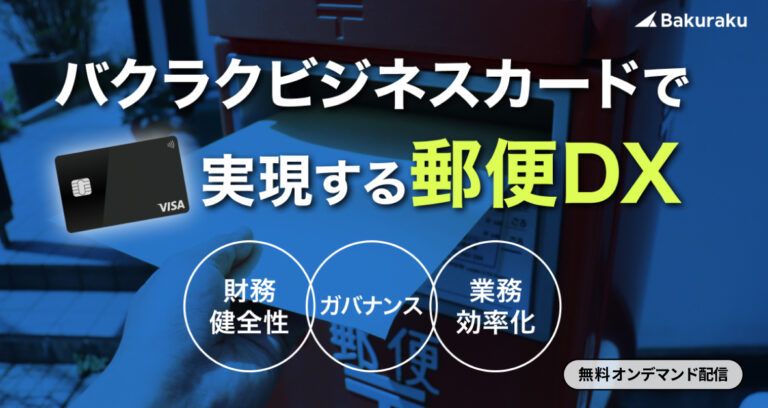
経費精算で使用する勘定科目20選!正しく計上するポイントや仕訳例も解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-04-07
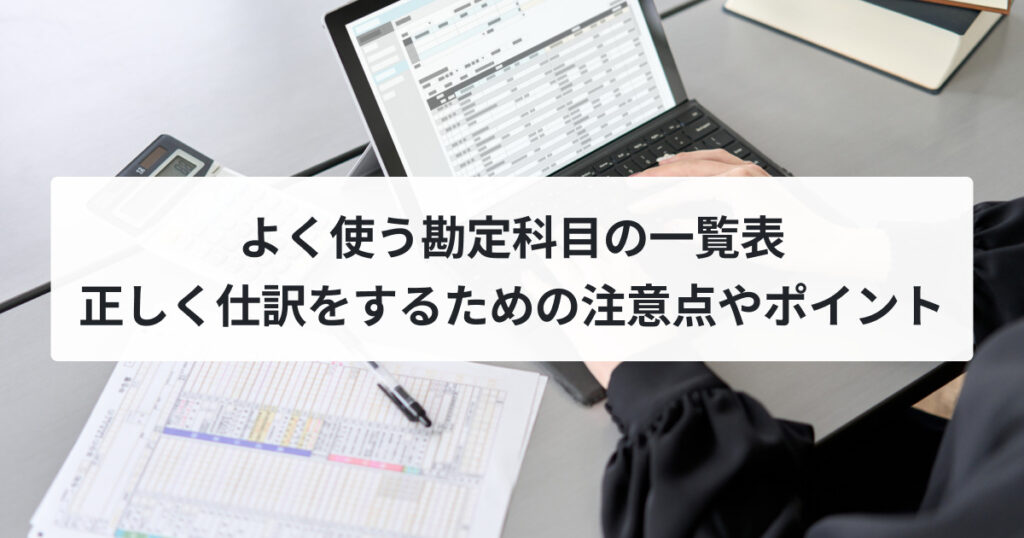
- この記事の3つのポイント
- 勘定科目に基づいた経費精算は、取引内容の記録・経営状況の判断・財務状況の把握に役立つ
- 使用すべき勘定科目が不明な場合は、経費の支払い目的や金額を確認の上判断すると良い
- 正しい仕訳には、社内ルールの統一、周知、仕訳の自動化が可能なシステムの導入などが効果的
財務状況の把握や経営判断を適切に行うには、勘定科目を正しく使用して経費精算をすることが重要です。
本記事では、経費精算で使用する勘定科目20選を紹介します。勘定科目を判断するポイントや注意点、経費精算の仕訳例なども解説しますので、今後の業務にお役立てください。
勘定科目に基づいて経費精算する理由
勘定科目に基づいて経費精算をすべき理由は、以下の3点です。
- 取引内容の正確な記録
- 経営状況の判断指標
- 財務状況の把握
それぞれの項目について、詳しく解説します。
取引内容の正確な記録
勘定科目に基づいて経費精算をすることで、経費の使い道を正確な記録として残せます。
取引内容を具体的に把握できれば、確定申告などで税金の計算がしやすくなり、経理業務の効率化につながるでしょう。支出を勘定科目ごとに細かく確認できることから、無駄な経費の削減にも役立ちます。
経営状況の判断指標
経営状況の的確な判断には、勘定科目に基づいた経費精算が必要です。
勘定科目を適切に分類することで、経営の判断指標となる財務状況を正しく把握できます。その結果、状況に応じて最適な意思決定を下せるでしょう。
財務状況の把握
勘定科目に基づいて経費精算をすることで、経費を体系的に分類でき、財務の明瞭性が向上します。
たとえば、交通費や旅費交通費などの混同しやすい勘定科目の適切な使い分けにより、正しい財務状況が把握可能です。
経費精算で使用する主な勘定科目一覧
勘定科目の使い分けに法的なルールはなく、使用する会計ソフトによって分類が異なります。勘定科目は細かく分類すれば際限がないものの、頻繁に使用する項目は限定的です。
本章では、経費精算で使用する主な勘定科目20選を紹介します。経費の例をまとめた以下の表も、参考にしてください。
| 勘定科目 | 経費の例 |
| 租税公課 | 印紙税、自動車税など |
| 地代家賃 | オフィスの家賃、共益費など |
| 給与賃金 | 基本給、ボーナスなど |
| 水道光熱費 | 水道代、ガス代など |
| 通信費 | 通話料金、インターネット料金など |
| 福利厚生費 | 健康診断費用、レクリエーション費用など |
| 接待交際費 | 取引先との食事代、接待ゴルフ代など |
| 交通費 | 取引先営業や顧客訪問での電車代、バス代など |
| 旅費交通費 | 出張時の移動費、交通費など |
| 広告宣伝費 | 求人情報の掲載費、インターネット広告費など |
| 販売促進費 | 店頭ポスターの作成費、無料サンプルの制作費など |
| 消耗品費 | コピー用紙、文房具など |
| 雑費 | ごみの処理費用、クリーニング代など |
| 荷造運賃 | 梱包資材、宅配便の配送料など |
| 修繕費 | オフィスのメンテナンス費用、専門機材の修理代など |
| 新聞図書費 | 雑誌の購入費用、メールマガジンの購読料など |
| 減価償却費 | パソコン、オフィス家具など |
| 諸会費 | 自治会費、所属する業界団体への協賛金など |
| 仮払金 | 出張費、買い出し費用など |
| 売掛金 | 後日受け取り予定の商品・サービス代など |
租税公課
租税公課は、国や地方に納める税金(租税)と、公共団体に納める公的な費用(公課)を指します。
租税の具体例は、印紙税や自動車税、固定資産税、不動産取得税などです。公課には、商工会費や町内会費、印鑑証明書、住民票の発行手数料などがあります。
租税公課として計上できるもの・できないものについて知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:租税公課とは?経費計上できるもの・できないものを徹底解説!
地代家賃
事業に使用する建物や駐車場などの賃料は、地代家賃で仕訳を行います。家賃のほか、共益費や管理費、20万円未満の礼金・更新料も地代家賃で計上可能です。
なお、自宅兼オフィスの場合は家事按分が必要です。事業用と私用の割合を算出し、事業用部分のみを経費としましょう。
以下の記事では、地代家賃の仕訳例や計上できない費用の例などを詳しく解説しています。
関連記事:地代家賃とはどんな勘定科目?仕訳例や計上できない費用の例もわかりやすく解説
給与賃金
給与賃金とは、従業員へ支払う報酬のことです。労働対価である給料のほか、各種手当も給与賃金に含まれます。たとえば、基本給やボーナス、退職金、役職手当、住宅手当などが該当します。
水道光熱費
水道光熱費は、水道・ガス・電気代などを計上する勘定科目です。企業によっては、それぞれ異なる勘定科目で仕訳を行うケースもあります。細かく分類すると項目ごとのコストを把握しやすい一方で、経理担当者の負担が懸念されます。
水道光熱費の内訳や仕訳方法・注意点については、以下の記事をご確認ください。
関連記事:水道光熱費の内訳と平均額、経費処理の方法(勘定科目や仕訳)
通信費
業務上の通信に関する費用は、通信費として仕訳を行います。通信費の具体例は、通話料金、インターネット料金、FAX代、郵便・宅配料金、テレビの受信料などです。
仕事とプライベートで使用する携帯電話の利用料金などは、家事按分をした上で仕訳を行いましょう。
通信費として計上できる費用や仕訳例は、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:勘定科目「通信費」とは?ネット代や携帯電話代などの仕訳例、注意点を解説
福利厚生費
福利厚生費は、会社が社員のために負担する給与や賞与以外の費用です。
福利厚生には、法律で定められる法定福利費と、会社が独自に設定する法定外福利厚生の2つがあります。経費精算における福利厚生費は、原則として法定外福利厚生を指します。
福利厚生費の具体例は、従業員の健康診断費用や慰安旅行費、社宅賃料、保養所の維持管理費、新年会や忘年会の費用、レクリエーション費用、慶弔見舞金などです。
福利厚生費で計上するには、全従業員が利用できる、支給額が常識の範囲内であるなど、いくつかの条件があります。具体的な条件や仕訳例について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:福利厚生費とは?経費にするための条件や費用の具体例・仕訳例を解説
接待交際費
接待交際費は、取引先との関係を築く目的で使用した費用です。たとえば、取引先との飲食代や贈答品代、取引先関係者の慶弔費、接待ゴルフ代などが該当します。
接待交際費には、いくつか混同しやすい勘定科目があります。詳しくは以下の記事にまとめていますので、併せてご覧ください。
関連記事:接待交際費とは?経費にできる範囲(上限金額・内容)や仕訳例
交通費
交通費とは、業務上の移動にかかる費用のことです。取引先営業や顧客先訪問の際に発生した電車代、バス代、タクシー代などが該当します。
交通費精算の手順や仕訳における注意点などは、以下の記事で詳しく解説していますので、ご一読ください。
関連記事:交通費の経費精算|旅費交通費との違いや交通費を精算する手順・仕訳例・注意点
旅費交通費
出張時に発生した費用は、基本的に旅費交通費で仕訳をします。移動費や宿泊費のほか、出張手当(日当)なども含まれます。
旅費交通費の仕訳例や課税・非課税を判断する基準などは、以下の記事にまとめていますのでご覧ください。
関連記事:旅費交通費とは?交通費との違いや該当する費用、仕訳例などを解説
広告宣伝費
広告宣伝費は、商品・サービスの宣伝目的で使用した費用を指します。
具体的には、求人情報の掲載費、インターネット広告費、テレビCMの費用などが該当します。そのほか、イベント出店費用、チラシ・パンフレットの制作費用、ホームページ制作費用なども、広告宣伝費で仕訳を行って問題ありません。
広告宣伝費を活用すると、さまざまなメリットがあります。詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:勘定科目「広告宣伝費」とは?該当費用・類似科目との違い・仕訳例
販売促進費
販売促進費は、商品・サービスの売上拡大や販売促進を目的とする経費を指します。たとえば、商品の訴求を目的とした店頭ポスター・POPの作成費用、キャンペーンにかかる諸費用、無料サンプルの制作費用、販売手数料などが該当します。
販売促進費の仕訳例を確認したい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:勘定科目「販売促進費」とは?具体例・広告宣伝費との違い、仕訳方法
消耗品費
取得価額が10万円未満または耐用年数が1年未満の物品購入費用は、消耗品費で仕訳を行います。コピー用紙、文房具、名刺、USBメモリ、洗剤など、消費サイクルが短いオフィス用品の購入費用は、基本的に消耗品費で計上可能です。
以下の記事では消耗品費の節約方法や仕訳のコツを紹介していますので、併せてご覧ください。
関連記事:「消耗品費」とはどんな勘定科目?具体例や雑費との違い・仕訳例を解説
雑費
雑費は、ほかの勘定科目に分類しにくい費用や、一時的かつ少額の費用に用いる勘定科目です。ごみの処理費用・クリーニング代・少額の手数料などは、雑費で計上して問題ありません。
以下の記事では、雑費として計上可能な金額の目安や注意点などを解説していますので、ご一読ください。
関連記事:雑費とは?経費計上できる具体例や上限額、消耗品費などとの違い
荷造運賃
荷造運賃は、自社の商品を出荷する際の、梱包や輸送にかかる費用を指します。たとえば、商品の梱包に必要な段ボールやガムテープ、緩衝材などの購入費用、郵便局などに支払う郵送・宅配料金が該当します。
荷造運賃は、通信費や消耗品費と混同しやすいため注意が必要です。違いを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:勘定科目「荷造運賃」とは?混同しやすい科目との違いや経理処理の注意点
修繕費
修繕費とは、固定資産のメンテナンスや修繕にかかる費用のことです。オフィスや社用車、専門機材などのメンテナンス費用は、修繕費で仕訳を行うのが一般的です。
以下の記事では、修繕費の具体例や資本的支出との違いなどを詳しく解説しています。
関連記事:修繕費とは?資本的支出・消耗品費との違いや具体例をわかりやすく紹介
新聞図書費
事業に関わる媒体の購入費用は、新聞図書費で仕訳を行います。新聞図書費の具体例は、新聞の購読料や情報誌・雑誌の購入費などです。対象は紙媒体に限らず、データベースの利用料やメールマガジン・有料サイトの購読料なども該当します。
なお、取得価額が10万円以上の場合は固定資産での計上が必要です。詳しくは以下の記事をご参照ください。
関連記事:「新聞図書費」とはどんな勘定科目?経費計上できるもの・仕訳のポイント
減価償却費
減価償却費は、償却資産の購入費用を耐用年数に応じて計上する際に使用します。償却資産の例は、パソコンやオフィス家具、ソフトウェアなどです。耐用年数は資産ごとに異なるため、国税庁の耐用年数表などを確認しましょう。
減価償却の計算方法や注意点について理解を深めたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:減価償却費とは何かわかりやすく解説!資産となる・ならない例と計算方法
諸会費
業務上発生する、団体や同業組合への支払費用は諸会費で仕訳を行います。
商店会・町内会など地域の自治会、医師会・税理士会などの職能団体、商工会議所などの業界団体への会費などが該当します。また、所属する業界団体への協賛金も、諸会費で計上可能です。
会費や協賛金について、詳しくは以下の記事で解説しています。
関連記事:会費の勘定科目は?入会費や年会費などの仕訳例と消費税の扱い方
関連記事:協賛金の勘定科目は何費?仕訳の見本と領収書の但し書き・記入例を紹介
仮払金
仮払金とは、支出の段階で用途や金額が確定しない場合に、一時的に支払う概算費用のことです。
たとえば、海外出張などで高額な交通費や宿泊費の支払いが見込まれる場合、会社が概算費用を従業員に渡します。このときの立て替え費用が、仮払金に該当します。
なお、仮払金は、用途や金額が確定した時点で相殺処理が必要です。詳しい精算手順や仕訳例は、以下の記事にまとめています。
関連記事:勘定科目「仮払金」とは?立替金や前払金との違い、仕訳例などを解説
売掛金
売掛金は、商品・サービスの代金を後日受け取る場合に計上する費用のことです。ツケや仮取引を指し、手形などの証書が発行されない信用取引に該当します。
売掛金は、取引の発生時ではなく、商品を引き渡す時点で計上するのが一般的です。売掛金を計上する具体的な流れについては、以下の記事で解説しています。
関連記事:売掛金とはどのような勘定科目?間違えやすい仕訳方法と具体例を解説
迷いがちな勘定科目を判断するポイント
勘定科目には類似するものが多く、仕訳の際に迷うこともあるでしょう。本章では、迷いやすい勘定科目を判断するポイントを解説します。
「福利厚生費」「接待交際費」「会議費」の違い
福利厚生費と混同しやすい勘定科目に、接待交際費や会議費があります。いずれも飲食代が関わる点で共通していますが、支出の目的や金額が異なるため、迷った場合は以下を参考に判断しましょう。
- 福利厚生費:従業員全員が対象で、現物支給ではない場合
- 接待交際費:接待に関わる費用で、1人あたりの金額が5,000円以上の場合
- 会議費:会議に関わる費用で、1人あたりの金額が5,000円以下の場合
会議費について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:勘定科目「会議費」とは?定義・接待交際費との違いや上限額・仕訳例を解説
「交通費」と「旅費交通費」の違い
交通費と旅費交通費はいずれも移動費を計上する点で類似していますが、移動の目的が異なります。
通勤や取引先営業などの日常的な移動にかかる費用は交通費、出張の際に発生する費用は旅費交通費で仕訳を行うのが望ましいでしょう。
「広告宣伝費」と「販売促進費」の違い
販売促進費は、会社の商品・サービスの販売業務をスムーズに進めるための費用です。広告宣伝費と販売促進費は、いずれも損益計算書の「販売費および一般管理費」に分類されます。
両者の違いは、費用を支払う目的です。販売促進費は商品・サービスの販売促進、広告宣伝費は広告や宣伝活動を目的とした支出を指します。
「雑費」と「消耗品費」の違い
雑費と消耗品費も、混同しやすい勘定科目といえます。勘定科目の決め方に税法上のルールはありませんが、一般的な定義は以下のとおりです。
- 雑費:ほかの具体的な勘定科目への分類が難しい、少額かつ一時的な支出
- 消耗品費:使用寿命が1年未満または取得価額が10万円未満の物品購入費用
雑費は消耗品に限らず少額のイレギュラーな支出、消耗品費は上記の耐用年数・取得価額を満たす消耗品の購入に使用する点が主な違いです。ボールペンや洗剤などを購入した場合は、消耗品費として計上するのが望ましいでしょう。
「仮払金」「前払金」「前払費用」の違い
仮払金と類似する勘定科目に、前払金や前払費用があります。
前払金は、商品・サービスの引渡し前に代金の一部または全額を支払う場合に使用する勘定科目です。たとえば、外注加工業で作業依頼をする際、納品前や作業前の手付金として支払う費用などが該当します。
前払費用は、継続的に購入する物品・サービスの代金を事前に支払う場合に使用する勘定科目です。たとえば、生命保険や火災保険などの保険料、翌月以降の家賃、年間契約した場合のサブスクリプション利用料金などが該当します。
いずれも事前に代金を支払う点は共通していますが、継続性の有無が異なります。商品を継続的に購入しない場合は前払金、続けて購入する場合は前払費用で仕訳を行うのが適切です。
なお、商品・サービスの購入費用を事前に受け取る側の場合は、前払金ではなく前受金での処理が必要です。前受金について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:前受金の仕訳方法は?借方・貸方の例と間違えやすい勘定科目との違いなどを解説
前払費用の仕訳例や計上のタイミングについては、以下の記事で解説しています。
関連記事:前払費用の勘定科目は?仕訳例・計上タイミングと特例を解説
「売掛金」「未収収益」「未収入金」の違い
売掛金と混同しやすいのが、未収収益や未収入金です。
未収収益は、一定の契約に基づいて継続的にサービスを提供する場合、提供済みのサービスに対する未回収の代金を計上する際に使用します。未収収益の具体例は、定期預金の受取利息や家賃の未収金などです。
未収入金は、固定資産の売却や有価証券の譲渡など、営業活動以外の取引における未回収金を計上する際に使用します。
いずれも未回収の収益を計上する点で共通していますが、取引の継続性に違いがあります。継続的な取引の場合は未収収益、非継続的であれば未収入金で仕訳を行うのが望ましいでしょう。
未収入金の仕訳方法や注意点について理解を深めたい方は、以下の記事をご覧ください。
経費精算の仕訳例
続いては、経費精算の仕訳例を紹介します。2回に分けて計上が必要なケースもあるため、仕訳漏れがないようにポイントを押さえておきましょう。
従業員が立て替えた経費を精算する場合
従業員が立て替えた経費を精算する場合は、立替経費の申請時と精算時にそれぞれ仕訳が必要です。ただし、小口現金払いなどで申請と精算が同日の場合、仕訳は一度で問題ありません。
たとえば、従業員が出張時に宿泊費8,000円を立て替えた場合の仕訳例は、以下のとおりです。
〈従業員が立替経費を申請したとき〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 旅費交通費 | 8,000円 | 未払金 | 8,000円 |
〈従業員の口座に精算金を振り込んだとき〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払金 | 8,000円 | 普通預金 | 8,000円 |
立替経費精算の手順や注意点などは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:立替精算とは?立替経費の精算手順や仕訳、注意点、負担軽減方法を解説
従業員に仮払金として支給し、あとで精算する場合
従業員に仮払金を支給して後日精算する場合も、仕訳を2回行う必要があります。仕訳のタイミングは、仮払金の支給時と精算時です。
たとえば、出張費用として現金50,000円を従業員にあらかじめ支給し、出張で35,000円使用した場合の仕訳方法は以下のとおりです。
〈従業員に仮払金を支給したとき〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 仮払金 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
〈仮払金を精算したとき(相殺処理)〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 旅費交通費 | 35,000円 | 仮払金 | 50,000円 |
| 現金 | 15,000円 | ||
買掛金を支払うときに振込手数料を自社負担する場合
支払手数料は、原則として課税取引に該当します。そのため、税抜経理方式を採用している場合は、消費税分を仮払消費税等の項目で別途計上しなければなりません。税込経理方式の場合は、消費税を含めて支払手数料で仕訳を行います。
たとえば、買掛金50,000円の支払い時に振込手数料880円を自社負担した場合は、以下のように仕訳を行いましょう。
〈税抜経理方式の場合〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 買掛金 | 50,000円 | 現金 | 50,880円 |
| 支払手数料 | 800円 | ||
| 仮払消費税等 | 80円 | ||
〈税込経理方式の場合〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 買掛金 | 50,000円 | 現金 | 50,880円 |
| 支払手数料 | 880円 | ||
支払手数料の具体例や注意点などは、以下の記事で解説していますのでご覧ください。
経費精算の勘定科目を選ぶ際の注意点
勘定科目の定義に法的な決まりはなく、事業や業種に合わせて任意で設定できます。経費精算の勘定科目を設定する際は、以下の2点に注意しましょう。
勘定科目はわかりやすい名前を設定する
会計ソフトなどに適切な勘定科目が見当たらず、雑費で計上できない場合は新たに設定できます。追加する際は専門用語や業界用語の使用を避け、第三者が判別しやすい名称を設定しましょう。
ただし、勘定科目が増えすぎると会計処理が複雑化する恐れがあります。まずは社内で追加の必要性を検討し、適切な判断をしましょう。
勘定科目のルールを企業内で統一する
勘定科目のルールを社内で統一し、一貫性を維持することが重要です。担当者によって使用する勘定科目が異なると、会計情報の信頼性が低下するため注意が必要です。
現時点でルールが不明瞭な企業は、以下のような対策を講じて会計の一貫性を保ちましょう。
- 過去の仕訳例を基にマニュアルを作成する
- 自動仕訳が可能なシステム・ツールを導入する
勘定科目がわからないときや間違えたときは?
使用すべき勘定科目がわからないときは、社内ルールを確認または会計ソフトのヘルプ機能を活用しましょう。そのほか、経費が使用された用途を確認する、過去の仕訳例から同様のケースを探すといった方法もあります。
選択した勘定科目が誤っていた場合、少額かつ同様の経費科目であれば問題視する必要はありません。勘定科目の役割は経費の内訳を示すことであり、経費科目の計算結果には影響しないためです。
ただし、交際費など、一部の勘定科目は税金の計算に影響する可能性があります。また、多額の経費を誤って計上すると、適切な経営判断や財務状況の把握が困難になるため注意しましょう。
自動仕訳機能が搭載されている経費精算システム「バクラク経費精算」
経営判断や財務状況の把握を正しく行うには、社内のルールに則った一貫性のある仕訳が必要です。経費精算システムなどを活用して、経費精算業務の正確性を向上しましょう。
バクラク経費精算は、利用中の会計ソフトに合わせた自動仕訳が可能です。領収書のAI-OCR自動読み取りや使い回し自動判定など、申請者・承認者・経理担当者のミスを防ぐ多彩な機能が搭載されている点もポイントです。
バクラク経費精算について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。