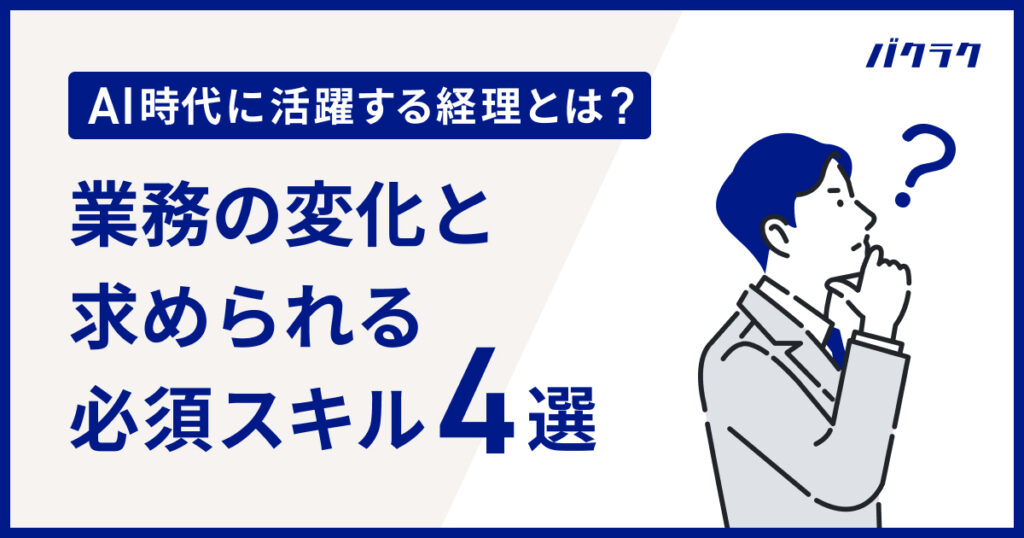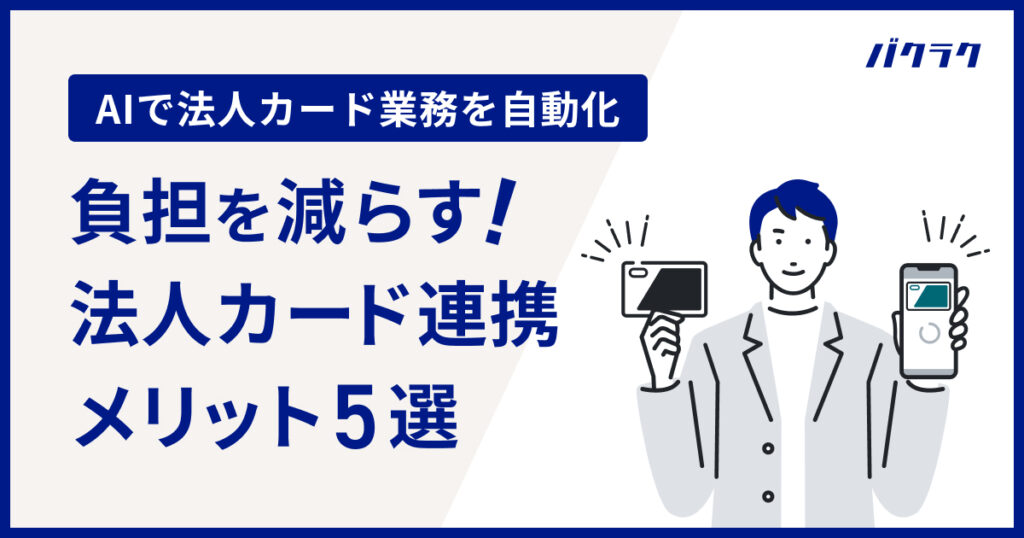「新聞図書費」とはどんな勘定科目?経費計上できるもの・仕訳のポイント
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 新聞図書費とは、会社や事業に関連する新聞・書籍などの経費を仕訳するための勘定科目である
- 目的や使用場所により勘定科目は異なり、事業に直接関係ない書籍は福利厚生費か雑費で計上する
- 10万円以上の書籍などを購入したときは、固定資産として計上する
事業に必要な書籍や新聞などの費用は「新聞図書費」として経費計上します。ただし、全ての書籍や新聞の費用を新聞図書費として計上できるわけではありません。
本記事では新聞図書費の対象範囲や仕訳例、福利厚生費や雑費との使い分けを解説します。10万円以上の書籍を固定資産として計上する際のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
「新聞図書費」とはどんな勘定科目?経費計上できるもの・仕訳のポイント
新聞図書費とは?
新聞図書費とは、会社や事業に関わる情報収集や知識の獲得のために購入する書籍や新聞、雑誌などの経費を仕訳するための勘定科目です。
新聞図書費は新聞や書籍の購入が多い場合に、会社の判断で任意に追加できる勘定科目で決算書には元々存在しません。会社の成長に必要な情報を得るための費用として、処理できます。
紙媒体だけでなく、電子書籍やオンラインで提供されるメールマガジンの購読料も、事業に関連するものであれば新聞図書費として経費計上可能です。
ただし、全ての書籍や新聞が新聞図書費として計上できるわけではありません。事業に直接関係する内容で、事業の進展や従業員の知識向上に貢献するものに限られます。
どこまで経費にできる?新聞図書費に該当するもの
新聞図書費に該当する経費の具体例は、以下のとおりです。
- 新聞の購読料
- 雑誌代
- 専門書・業界紙や情報誌の購入費
- 官報
- 地図や路線価図・統計資料の購入費
- メールマガジンや有料サイトの定期購読料 など
上記のような情報源は、従業員が業務に必要な知識を得たり、事業に関連する最新情報を把握したりするために使用されるので、新聞図書費として計上可能です。
通信費と混同しやすい電子書籍やメールマガジンの購読料も、事業に関連している場合は新聞図書費に該当するため、計上時は注意しましょう。
新聞図書費・福利厚生費・雑費の使い分け
新聞や雑誌などの書籍をどの勘定科目で計上するかは、目的や使用場所によって異なります。
たとえば、オフィスの休憩室に従業員のリフレッシュを目的として新聞や雑誌を備え付ける場合、事業に直接関係がないため「新聞図書費」ではなく「福利厚生費」として計上します。福利厚生費は、従業員の福利厚生に関連する費用を処理する勘定科目です。
また投資を事業としていない場合の投資関連書籍や、事業に直接関わらないビジネス書、経営ノウハウ本なども新聞図書費には該当しません。
一般的には、事業に必要な書籍を一時的に購入する場合かつ金額も少額であれば「雑費」として計上します。雑費は、他の勘定科目に当てはまらない少額の一時的な支出を処理するための項目です。
ただし頻繁に購入する場合は、より適切な勘定科目として「新聞図書費」の使用が望ましいでしょう。一度雑費で計上した費用が今後も継続的に発生するなら、経理処理の統一のため、同じ勘定科目を使うほうが管理しやすくなります。
福利厚生や雑費について詳しくは以下の記事で解説しているため、ぜひご覧ください。
新聞図書費の仕訳例
新聞図書費を仕訳する際には、書籍や新聞、雑誌の購入が一時的なものか、それとも定期購読かによって処理が異なります。新聞の定期購読では軽減税率が適用される場合があるため、税率にも注意が必要です。
ここからは新聞図書費として仕訳する際の具体的な例を、一時的な購入と定期購読のケースに分けて解説します。
一時的に購入する場合
一時的に書籍や新聞、地図などを購入する場合、購入した金額はそのまま新聞図書費として計上します。
たとえば会社の調査目的で参考書を1万6千円で購入し、現金にて支払いをしたときは、以下のように仕訳を行います。
参考書籍代1万6千円を現金で支払った場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
| 新聞図書費 | 16,000円 | 現金 | 16,000円 |
また商圏分析のためにエリアマーケティング用の地図を現金1万円で購入した場合なども、同様に仕訳します。
定期購読する場合
業界紙や雑誌を定期購読する場合、購読料は新聞図書費として計上できます。1年間の月刊誌購読料2万4千円を現金で前払いした場合、12月決算での仕訳は以下のとおりです。
11月から年間購読料2万4千円を現金で支払った場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
| 新聞図書費 | 2,000円 | 現金 | 24,000円 |
| 前払金 | 22,000円 | ||
年間購読料を「新聞図書費」と「前払金」に分ける理由は、費用を実際に発生する期間に対応させるためです。年間分の購読料を一括で支払っても、その支出は複数月で利用されるため、支払った月に全額を新聞図書費として計上するのは適切ではありません。
当期に該当する分のみを新聞図書費として、残りの分は前払金として資産に計上し、次期以降の会計期間で費用として振り替えます。
また週2回以上発行される新聞を定期購読する場合、軽減税率8%が適用されます。ただしコンビニなどで単発購入する場合や、電子版の新聞購読料は軽減税率の対象外となるため、注意しましょう。
消費税の軽減税率対象品目に関しては、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。
10万円以上の書籍などを購入した場合は固定資産として計上
事業に必要な書籍のうち、取得価額が10万円以上のものについては、新聞図書費としてではなく固定資産として計上します。
金額の大きい書籍や百科事典などのセットは長期間にわたり事業に利用されることが多いため、支出を一度に計上するのではなく、減価償却によって少しずつ費用化するためです。
固定資産として計上する際は、勘定科目に「工具器具備品」を使用し、減価償却時には「減価償却費」で処理します。取得価額は購入金額に加え、送料なども含める点に注意しましょう。
青色申告者は「少額減価償却資産の特例」を利用して、一括で30万円未満の資産の経費計上が可能です。たとえば全巻セットの百科事典が30万円未満であれば、この特例を適用して経費計上ができます。
取得価額が10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」として扱い、通常の減価償却とは異なり、3年間で均等に償却する方法も選択可能です。期の途中で取得した場合でも、月割計算を行わずに年間を通して均等償却ができます。
少額減価償却資産や一括償却資産を活用すれば、資産管理や税務の負担軽減が期待できます。詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
簡単で正確な経費精算を実現する「バクラク経費精算」
新聞図書費とは、事業に関連した情報収集のために購入する書籍や新聞、雑誌の経費です。事業に直接関係するもののみが対象で、休憩室用の雑誌や個人的な目的の書籍は対象外となります。
10万円以上の書籍などを購入した場合は固定資産とし、工具器具備品で計上、減価償却費で減価償却する点にも注意しなければなりません。このような新聞図書費をはじめ、多くの経費を正確に管理するには、経費精算ツールの導入もおすすめです。
「バクラク経費精算」であれば、複数枚の領収書や請求書を一括で読み取れるAI-OCR自動読み取りがあるほか、インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しています。
経費精算の手間を省いて正確に処理をしたいと考えている方は、ぜひ以下のページより資料を取り寄せてください。