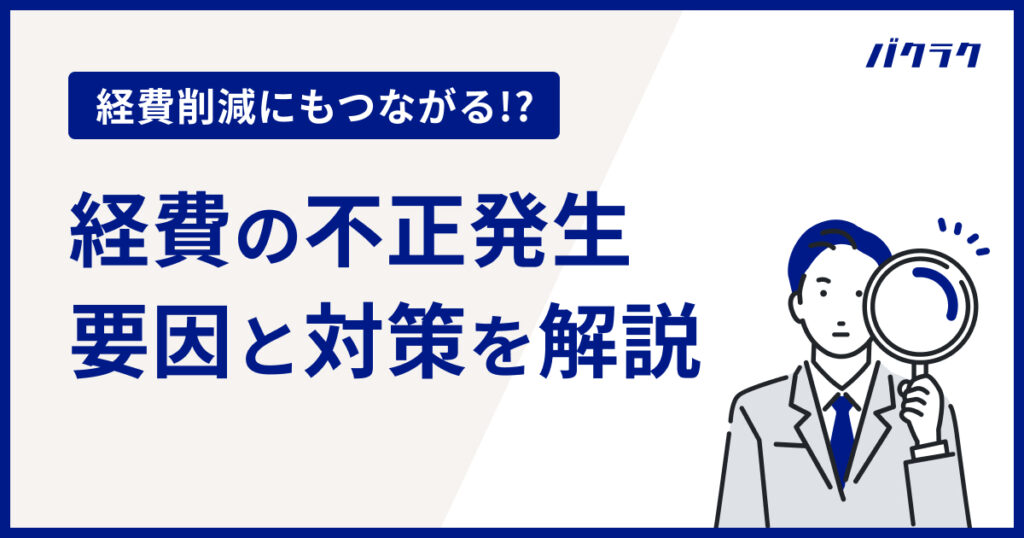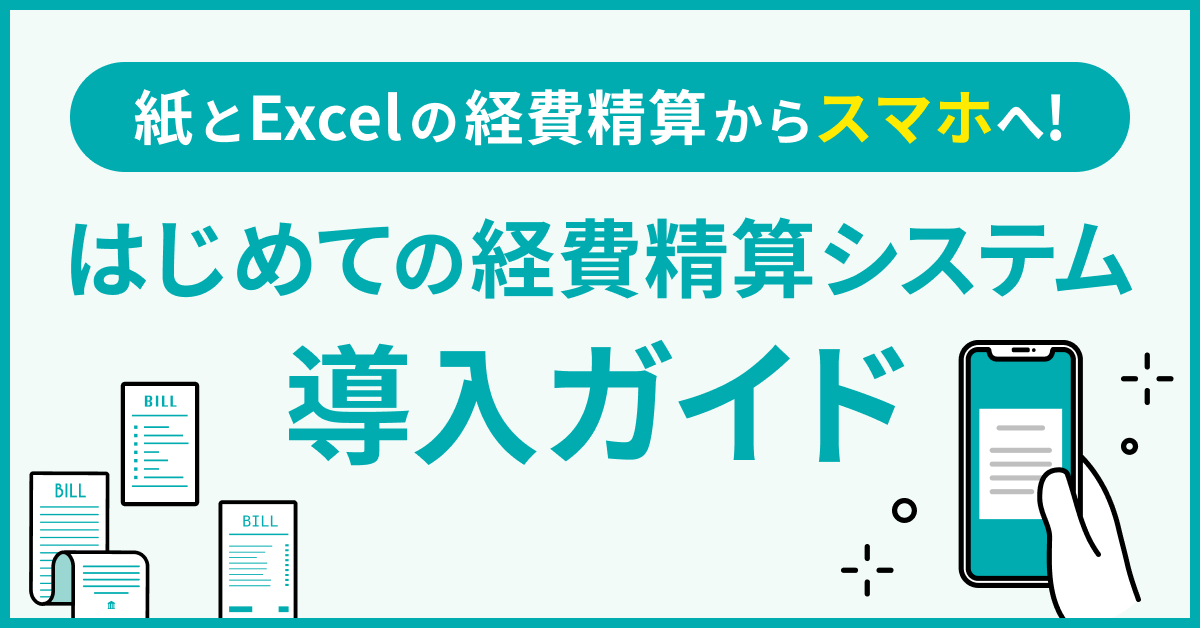一括償却資産とは?少額減価償却資産との違い、仕訳方法を解説
- この記事の3つのポイント
- 一括償却資産は、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等償却できる
- 一括償却資産と少額減価償却資産は、適用条件や償却方法が異なり、節税効果や資産管理に影響する
- 一括償却資産は申告調整方式と決算調整方式があり、どちらを選ぶかで会計処理の流れが変わる
一括償却資産は、企業や個人事業主が固定資産の減価償却を行う際に活用できる方法です。一括償却資産を利用することで、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に費用計上できます。
本記事では、一括償却資産の概念や少額減価償却資産との違い、具体的な仕訳方法までを詳しく解説します。
一括償却資産とは?
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を、耐用年数に関係なく取得した年から3年間で均等に償却する方法です。
具体的には、取得価額の3分の1ずつを毎年費用として計上します。この方法を選択することで、複雑な耐用年数の計算を省略し会計処理を簡素化できます。また一括償却資産は、法人だけでなく個人事業主でも適用可能です。
一括償却資産を利用するための条件は、以下のとおりです。
- 取得価額が10万円以上20万円未満であること
- 減価償却資産であること(棚卸資産や繰延資産は対象外)
- 国外リース資産や特定のリース資産でないこと
上記の条件を満たす資産であれば、一括償却資産として処理できます。ただし一度選択すると、途中で他の減価償却方法に変更することはできないため慎重な判断が必要です。
固定資産・一括償却資産・少額減価償却資産の取扱いの違い
固定資産の減価償却方法は、資産の使用可能期間(耐用年数)と取得価額に応じて異なります。取得価額が高額な資産は通常の減価償却を行い、少額な資産については特例を適用できます。
固定資産の取扱いは、下表のとおりです。
| 使用可能期間 | 取得価額 | 取扱い |
| 1年以上 | 30万円以上 | 固定資産計上 |
| 20万円以上30万円未満 | 固定資産計上、少額減価償却資産 | |
| 10万円以上20万円未満 | 固定資産計上、一括償却資産、少額減価償却資産 | |
| 1年以上 | 10万円未満 | 費用計上 |
| 1年未満 | 10万円以上 | |
| 10万円未満 |
中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産については、取得年度に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の特例」という制度を利用できます。
この特例を利用するためには「青色申告を行っている中小企業者等が対象」「年間の合計取得価額は300万円が限度」といった条件があります。
なお少額減価償却資産の特例は、2025年度末(2026年3月31日)が期限です。30万円未満の減価償却資産がある中小企業で、節税を検討している場合は期限に注意しましょう。
一括償却資産として取り扱うメリット・デメリット
| 項目 | 内容 |
| メリット |
|
| デメリット |
|
一括償却資産の仕訳方法
一括償却資産の仕訳方法には、決算調整方式と申告調整方式の2つがあります。それぞれの方法について、具体的な仕訳例を示します。
申告調整方式
申告調整方式は、資産の購入時に全額を経費として処理し、税務申告時に損金不算入の調整を行う方法です。たとえば、取得金額が15万円のデスクトップパソコンを「一括償却資産」として処理する場合は、以下の仕訳となります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 消耗品 | 150,000円 | 現金 | 150,000円 |
申告調整方式は上記のみで仕訳が終わりではなく、法人税申告書で調整を行わなければなりません。
まずは別表一六(八)「一括償却資産の損金算入に関する明細書」にて、一括償却資産対象額150,000円を記入します。次に、損金算入限度額として、取得金額である150,000円を3年で割った50,000円を記入しましょう。
最後に、翌年以降に繰り越しする金額となる100,000円を記入すれば完了です。
申告調整方式は、会計上の処理と税務上の処理が異なるため、将来的な税務調査対策として記録を残しておく必要があるため、注意が必要です。
決算調整方式
決算調整方式は、資産の購入時に「一括償却資産」として資産計上し、決算時に減価償却費を計上する方法です。仕訳内容がシンプルなので、一般的には決算調整方式による処理がおすすめです。
取得金額が15万円のデスクトップパソコンを「一括償却資産」として処理する場合は、以下の仕訳となります。
購入時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
| 一括償却資産 | 150,000円 | 現金 | 150,000円 |
決算時の仕訳(毎期)
| 借方 | 貸方 | ||
| 減価償却費 | 50,000円 | 一括償却資産 | 50,000円 |
なお、3年目までで全額を償却するため、4年目以降の仕訳は不要です。簿価はゼロとなりますが、資産が引き続き使用されていても減価償却は行いません。
固定資産に関わる経費の管理なら「バクラク経費精算」
固定資産の購入や維持管理に関連する経費の管理は、経理業務において重要です。特に、取得価額が10万円未満の資産や、固定資産の購入に伴う運送費や設置費、修理費や保守費用などは、経費として全額損金算入できます。
これらの経費を正確かつ効率的に管理するためには、経費精算システムの活用が効果的です。バクラク経費精算は、経費の申請から承認、支払いまでを一元管理できるクラウドサービスで、経費精算を効率化できます。
経費データを自動で仕訳が可能で、会計ソフトと連携させることで入力ミスや二重入力を防ぐことができます。システム上で経費の申請・承認ができるようになるので、オンラインで処理が完結するだけでなく、ペーパーレス化を進めることも可能です。
また、経費情報は常に即時更新で、最新の資金状況の確認が可能です。未入金・未払いを防げるだけでなく、上場に向けた内部統制の強化や経費管理の業務削減につなげられます。
固定資産に関連する経費の管理を効率化し、経理業務の負担を軽減したい方は、ぜひ「バクラク経費精算」の導入をご検討ください。