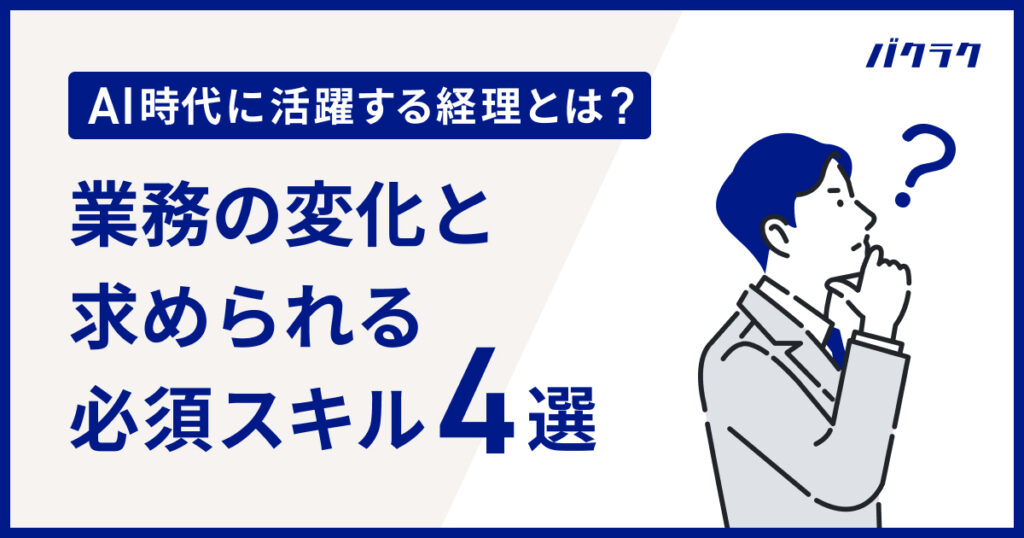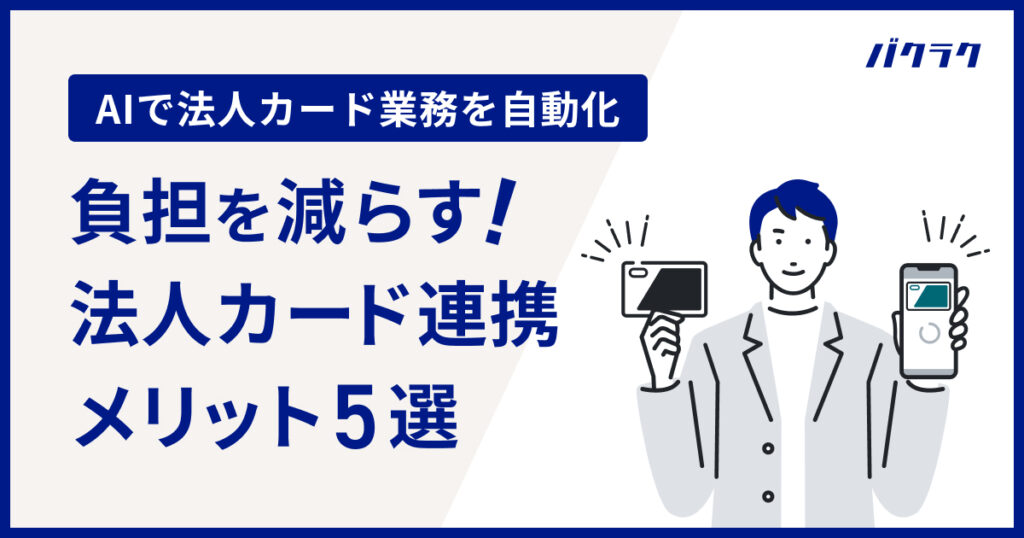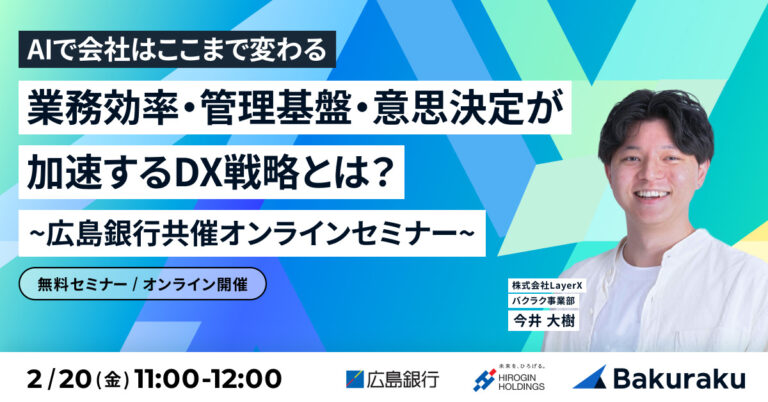受領書と領収書の違いは?代わりにできる場合や取り扱いのポイントを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-08-05
- この記事の3つのポイント
- 受領書は商品やサービスを受け取った事実、領収書は代金受け取りの事実を証明する目的で発行する
- 受領書が金銭の受け取り事実を証明できる内容の場合は、領収書の代わりに利用できる
- 受領書は商品を受け取ったら速やかに発行し、原本または控えを原則7年間保管する

受領書と領収書の違いについて、お悩みの方もいるでしょう。両者は発行の目的やタイミングが異なりますが、受領書を領収書の代わりに利用できるケースもあります。
本記事では、受領書と領収書の違いや受領書を取り扱う際のポイントなどを詳しく解説します。
受領書と領収書の違いは?代わりにできる場合や取り扱いのポイントを解説
受領書と領収書の違いとは?
受領書と領収書はいずれも受け取りを証明する書類ですが、発行の目的やタイミングが異なるため注意が必要です。まずは、受領書と領収書の違いについて詳しく見ていきましょう。
商品やサービスの受け取りを証明する「受領書」
受領書は、発注者が商品やサービスの受け取りを証明する目的で発行します。受領書の発行は法律で義務付けられていませんが、取引の状況を明らかにできることから、トラブル発生時に役立つ書類の一つです。
受領書の記載内容は、以下のとおりです。
- 発行日
- 取引先の名称
- 発行元の名称・住所
- 担当者印
- 受領した物品の名称・単価・数量・合計金額
- 受領日
受領書の書き方や保存方法について理解を深めたい方は、以下の記事をご参照ください。
商品やサービスの代金を受け取ったことを証明する「領収書」
領収書は、商品やサービスの代金を受け取った事実を証明する書類です。
領収書には、同じ内容の請求書を二度送る二重請求や、情報の改ざんといった経理のミス・不正を防ぐ役割があります。領収書がない場合、支払いが完了していることを客観的に示すのは困難です。
領収書の発行も法律で義務付けられていませんが、商品やサービスを受け取った相手に発行を求められた場合は応じる必要があります。
領収書の記載内容は以下のとおりです。
- 取引年月日
- 取引先の名称
- 取引金額
- 取引内容
- 発行元の名称・住所
必要な項目が記載されていれば、手書きや印刷、電子的方法など、様式は自由です。
なお、領収書は税法上の「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、印紙税が課されます。取引代金が5万円以上の場合は、収入印紙の貼付が必要な点に注意しましょう。
参考:e-Gov法令検索「民法第486条」
参考:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
以下の記事では収入印紙の基本知識を解説していますので参考にしてください。
受領書は領収書の代わりにできる場合がある
受領書に以下の項目が記載されている場合は、領収書の代わりに利用できます。
- 発行日
- 取引先の名称
- 取引金額
- 発行元の情報
- 担当者印
金銭の受け取り事実を証明できる内容であれば、経費精算に受領書が利用できることを理解しておきましょう。
受領書を発行する目的・メリット

本章では、受領書を発行する目的・メリットを紹介します。受領書の重要性を理解して、今後の実務にお役立てください。
納品完了の証明ができる
受領書には、商品やサービスの納品が完了したことを受注者に通知する役割があります。
運送業者から受注者に配達完了の通知が届くケースもありますが、発注者へ確実に商品が届いたかは確認できません。受注者が請求書を送付するタイミングを判断できず、取引の停滞を招く可能性もあるでしょう。
発注者が受領書を発行することで「いつ」「誰が」「何を受け取ったか」を証明できます。商品が届いた旨を受注者に伝達でき、その後の取引を円滑に進められる点もメリットの一つです。
トラブルが発生した際の証拠になる
取引中にトラブルが発生した際、受領書があれば状況を円滑に確認できます。
たとえば、納品された商品の数量が不足していた場合に、受領書を発行していなければ事実確認が困難です。口頭のやり取りのみでは、どちらの主張が正しいかを客観的に判断できず、不足分の発送を断られる可能性もあるでしょう。
しかし、受領書を発行していれば、届いた商品の名称や数量を示す証拠として機能します。受領書がトラブルの解決に役立ち、取引を円滑に進められるでしょう。
取引状況がわかりやすくなる
商品やサービスの取引においては、発送や納品以外にもさまざまな工程があります。そのため、取引の状況をスムーズに把握するには、発注書や納品書などの取引関係書類が欠かせません。
受領書も、取引関係書類の一つとして重要な役割を果たします。納品が完了した旨を証明できるため、次のフローである請求・支払い業務に移行できることを双方が認識できます。
取引状況を可視化できる点は、受領書を発行する大きなメリットといえるでしょう。
受領書と納品書・検収書の違い

受領書と混同しやすい書類に、納品書や検収書があります。
納品書は、納品する商品の名称や数量を記載した書類です。発注内容と納品物に相違がないことを、発注者に証明する目的で発行します。
受領書と納品書の主な違いは、発行者と発行のタイミングです。納品書は受注者が発行し、商品に同梱する形で送付するのが一般的です。一方受領書は、発注者が納品書の記載内容と納品物を照合した後に、受け取りの事実を証明する目的で発行します。
検収書は、受け取った商品の数量や品質、納期などに問題がなかった旨を通知する書類です。
受領書と検収書はいずれも発注者が商品を受け取った後に発行しますが、目的が異なります。受領書は商品を受け取った事実を証明するために発行し、検収書は納品された商品が注文通りであったことを伝えるために発行します。
納品書と検収書について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。納品書の必須項目や書き方、納品から検収処理までの流れなどを解説しています。
受領書を取り扱う際のポイント
本章では、受領書を取り扱う際に注意すべき3つのポイントを紹介します。取引を円滑に進めるために、要点を押さえた上で受領書の作成を行いましょう。
商品やサービスを受け取ったら迅速に発行する
受領書に発行期限はありませんが、商品やサービスを受け取ったら速やかに発行する必要があります。受領書の発行が遅れると、書類の信用性が担保されにくくなるほか、取引の停滞を招いて取引先に迷惑をかける可能性があります。
また、記載ミス・漏れをしないことも重要なポイントです。取引先の名称や受領した物品の情報を誤って記載すると、取引先に不信感を抱かれて、今後の取引に影響を及ぼしかねません。取引先名は正式名称で記載し、敬称も忘れず記載しましょう。
受領書には保管義務がある
受領書には、発行・受領のいずれにおいても、一定期間の保管義務があります。保管期間は、原則として、取引が発生した事業年度の確定申告期限日翌日から7年間です。
発行者は受領書の控え、受領者は受領書の原本を適切な方法で保管し、いつでも確認できる状態にしておくことが大切です。税務調査で受領書の提示を求められた際は、速やかに対応しましょう。
参考:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
参考:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
なお、電子的方法で受領した書類は、法律で電子保存が義務付けられています。電子帳簿保存法の対象書類や保存要件などは以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:電子帳簿保存法とは?対象書類・保存要件・改正内容・対応策を一挙に紹介
書類の電子化も検討する
紙で発行した受領書は、記載内容の確認や保管に手間がかかり、経理処理におけるミスが発生しやすい懸念点があります。
受領書を電子化すれば、紙代やインク代などのコストを削減できるほか、保管の手間やスペースも減らせます。書類の検索性が向上して複数の部署で共有しやすくなる点や、劣化・紛失の防止に役立つ点もメリットです。
なお、2022年1月に施行された電子帳簿保存法改正では、決算・国税関係書類の電子化が認められています。また、2024年1月以降は、電子データで完結する取引の関係書類を、すべて電子データで保存することが義務付けられています。
法改正への対応はもちろんのこと、ペーパーレス化を進めるためにも、書類の電子化を検討しましょう。
参考:国税庁「パンフレット(過去の主な改正を含む)」
領収書の代わりにできる6つの書類
受領書以外にも、領収書の代わりとして利用できる書類がいくつかあります。本章では、領収書の代わりにできる以下6点の書類について、特徴や注意点を解説します。
- クレジットカードの利用明細書
- レシート
- 銀行の振込金受取書(振込明細書)・預金通帳
- 出金伝票
- オンライン販売の支払い完了メール
- ご祝儀袋や香典袋などのコピー
クレジットカードの利用明細書
領収書は金銭の授受を証明する証憑のため、クレジットカードで決済した場合は原則発行されません。クレジットカード決済の場合、レシートと一緒に発行される利用明細書(お客様控え)を、領収書の代わりに利用できます。
ただし、利用明細書を領収書の代わりとする場合は、利用明細書に以下5点の記載が必要です。
- クレジットカードの決済日
- 発行元の名称
- 受領者の名称
- 金額
- 取引内容
クレジットカード会社から定期的に送付される請求明細書は、領収書の代わりにならないため注意しましょう。
出典:国税庁「クレジットカード会社からの請求明細書」
レシート
レシートは、領収書と同様、税法上の「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。そのため、発行元の名称や発行日、取引内容、取引金額などが記載されていれば、領収書の代わりとして経費精算に利用できます。
ただし、企業によっては、レシートを領収書の代わりとして認めないケースもあるため注意が必要です。代用の可否を、経理担当者へ事前に確認しましょう。
出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
銀行の振込金受取書(振込明細書)・預金通帳
銀行振込を経費精算する場合は、銀行の振込金受取書(振込明細書)や預金通帳の記帳内容を領収書の代わりに利用できます。
ただし、長期間記帳をしていない場合、未記帳分の出入金情報をまとめて記帳されることがあるため注意が必要です。取引の内容を把握しにくくなり、税務処理の根拠として利用できなくなる可能性があります。
通帳は定期的に記帳して、取引の内容をこまめに確認することが重要です。
なお、銀行振込で領収書が必要な場合は、送金先に領収書の発行を依頼すれば発行してもらえます。領収書の発行を依頼した場合は、振込金受取書などの代替書類と領収書の両方を使うことで、経費の二重計上が発生しないように注意しましょう。
出金伝票
出金伝票は、現金を支出した際に作成する伝票です。たとえば、交通費や慶弔費の精算時、自動販売機の利用時に作成します。
出金伝票に、日付・出金先・摘要・金額・作成者が記載されていれば、領収書の代わりとして経費精算に利用可能です。
ただし、出金伝票は自社で作成するため、多用すると税務調査で不正を疑われる可能性があります。領収書が発行されないなど、やむを得ない場合のみ出金伝票を利用しましょう。
オンライン販売の支払い完了メール
オンライン販売を利用した際に受け取る支払い完了メールも、領収書の代わりに利用可能です。
ただし、メールは電子取引データに該当するため、税務署類として利用する場合は電子帳簿保存法に基づいた保存が必要です。
電子帳簿保存法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:電子帳簿保存法とは?対象書類・保存要件・改正内容・対応策を一挙に紹介
ご祝儀袋や香典袋などのコピー
ご祝儀や香典などの慶弔金を出した場合は、ご祝儀袋や香典袋のコピーを領収書の代わりに利用できます。事前にコピーができなかった場合は、以下を保管する方法でも問題ありません。
- 支出の日付・金額・内容を記したメモ
- 慶弔案内状
- 招待状・席次表(結婚式の場合)
- 会葬礼状(葬儀の場合)
「バクラク請求書発行」「バクラク請求書受取」なら書類発行の手間を削減
受領書と領収書はいずれも受け取りを証明する書類ですが、発行の目的やタイミングが異なります。受領書は商品やサービスの受け取りを証明する書類、領収書は商品やサービスの代金を受け取った事実を証明する書類です。
経費精算では、領収書を証憑書類として利用するのが一般的ですが、金銭の受け取りが証明できる記載内容であれば、受領書を代用しても問題ありません。法律で定められた書類の保管期間や保存方法に注意し、適切に取り扱いましょう。
書類の作成・管理業務を効率化したい方には、バクラク請求書発行がおすすめです。請求書や納品書など、あらゆる書類の作成・送付・保存をシステム上で完結できます。
自社のフォーマットに合わせた柔軟なレイアウト設定が可能で、取引先に合わせて個別・一括作成できる点もポイントです。また、電子帳簿保存法やインボイス制度などの各種法令にも対応しています。
バクラク請求書発行のサービス内容や導入事例について知りたい方は、以下のページをご覧ください。詳しい資料も無料でダウンロードいただけます。