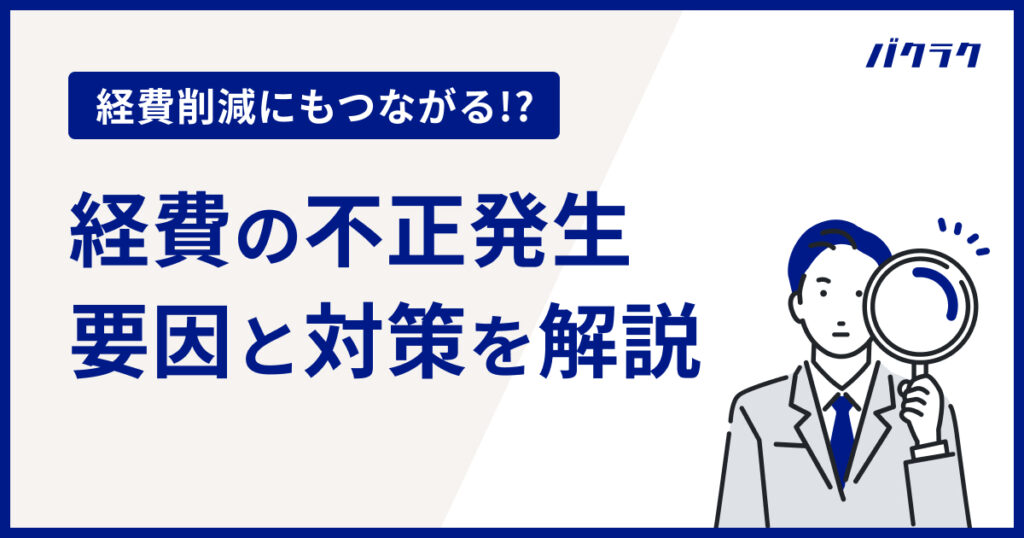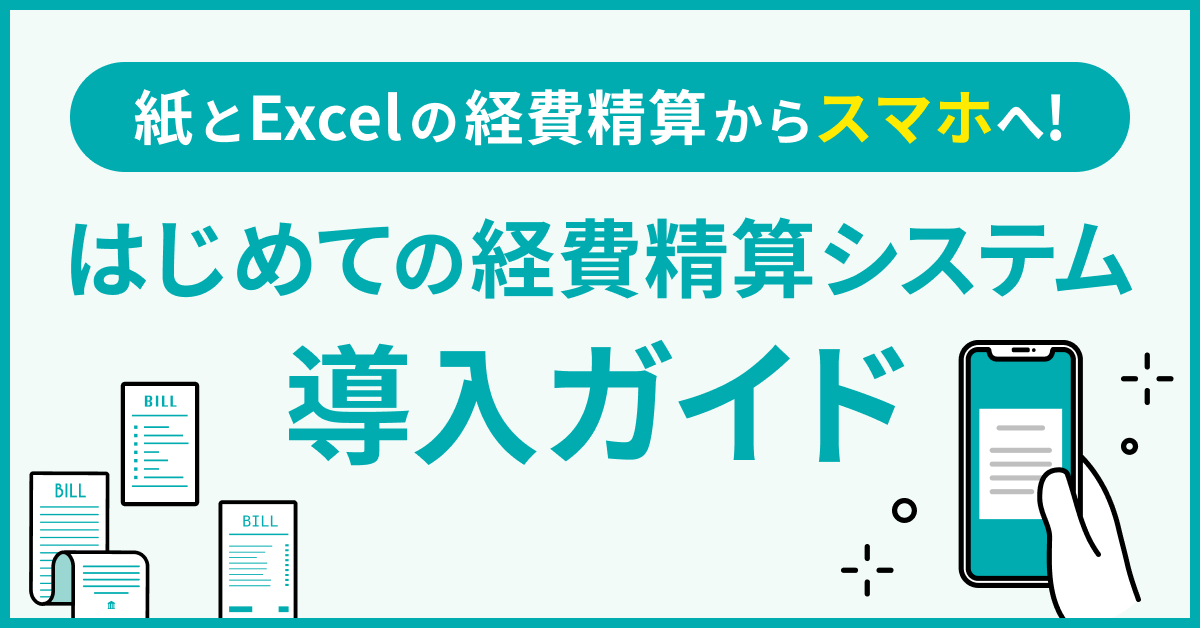収入印紙の税額一覧と金額の種類|購入方法や貼り方まで解説
- この記事の3つのポイント
- 収入印紙は税金や手数料などを徴収するために国が発行する証票で、課税文書への貼付が必要
- 収入印紙の税額は文書の種類ごとに異なるものの、いずれも5万円未満の場合は非課税となる
- 収入印紙を貼らなかった場合は故意か否かに関わらず、発行人に過怠税が課せられる
記載金額が5万円以上の課税文書には、収入印紙の貼付が必要です。貼付すべき収入印紙の金額は、文書の種類や記載金額ごとに異なるため、事前に理解を深めておくことが重要です。
本記事では、文書の種類ごとにまとめた収入印紙の税額一覧を紹介します。収入印紙の購入方法や貼り方、貼らなかった場合の罰則なども詳しく解説しますので、今後の実務にお役立てください。
収入印紙の税額一覧
収入印紙とは、税金や手数料などの収納金を徴収する目的で国が発行する証票です。印紙税法で定められた金額分の収入印紙を、課税文書に貼り付けることで納税の証明ができます。
課税文書に該当するか否かは、文書の名称ではなく、記載内容で判断します。たとえば、文書の名称が「覚書」「合意書」であっても、内容が企業間取引の契約であれば、収入印紙の貼付が必要です。
本章では、課税文書の種類ごとにまとめた収入印紙の税額一覧を紹介します。収入印紙の基本知識について理解を深めたい方は、以下の記事もご一読ください。
関連記事:収入印紙とは?必要性や金額、購入方法、貼り方などを徹底解説
領収書に貼る印紙の金額
領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当する文書で、印紙税の課税対象です。支払者に領収書を交付することにより、金銭の受領事実を証明できます。
第17号文書には、領収書のほかに受取書やレシート、預かり書などが該当するほか、「代済」「相殺」「了」と記入した、請求書や納品書も含まれます。
第17号文書に貼る収入印紙の金額は、以下のとおりです。
記載受取金額 | 収入印紙の金額 |
5万円未満 | 不要(非課税) |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 2万円 |
1億円超2億円以下 | 4万円 |
2億円超3億円以下 | 6万円 |
3億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
受取金額の記載がないもの | 200円 |
記載受取金額は、原則として消費税を含まない額を指します。消費税額の記載がある場合は、税抜金額で判断しましょう。
なお、記載受取金額が5万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は不要です。受け取った金銭などが受取人の営業に関与しない場合も、非課税となる点に注意しましょう。
不動産売買契約書や金銭借用証書などに貼る印紙の金額
不動産売買契約書や金銭借用証書は、第1号文書に該当します。契約金額に応じた第1号文書とは「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書」や「消費貸借に関する契約書」のことで、以下のものも該当します。
- 不動産交換契約書
- 不動産売渡証書
- 土地賃貸借契約書
- 土地賃料変更契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 運送契約書
- 貨物運送引受書 など
記載契約金額が5万円以上の第1号文書には、収入印紙が必要です。具体的な金額は、以下をご覧ください。
記載契約金額 | 収入印紙の金額 |
1万円未満 | 不要(非課税) |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
不動産の譲渡に関する契約書(土地建物売買契約書など)のうち、契約金額が10万円を超えるものには、印紙税が半額になるなどの軽減措置が適用されることを知っておきましょう。
工事請負契約書や工事注文請書などに貼る印紙の金額
工事請負契約書や工事注文請書は第2号文書に該当し、記載契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。第2号文書には、ほかに以下のものがあります。
- 物品加工注文請書
- 広告契約書
- 映画俳優専属契約書
- 請負金額変更契約書 など
第2号文書に貼る収入印紙の金額は、以下のとおりです。
記載契約金額 | 収入印紙の金額 |
1万円未満 | 不要(非課税) |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 1,000円 |
300万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
建物建築工事請負契約書など、建設工事の請負に関する契約書で、記載契約金額が100万円を超えるものには軽減措置が設けられています。該当の契約書を発行する際は、軽減措置の詳しい内容を確認しましょう。
売買取引基本契約書や業務委託契約書などに貼る印紙の金額
売買取引基本契約書や業務委託契約書などは、第7号文書に該当します。第7号文書には、ほかに以下のものも含まれます。
- 特約店契約書
- 代理店契約書
- 銀行取引約定書 など
第7号文書の印紙税額は一律4,000円ですが、契約期間が3カ月以内かつ更新の定めがないものは非課税です。
収入印紙の金額別の種類と組み合わせ例
収入印紙の額面には、1円から10万円までの全31種類があります。
- 1円、2円、5円
- 10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円
- 100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円
- 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円
- 10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円
- 100,000円
印紙税を納める際は、上記から額面を組み合わせて使用します。たとえば、貼付金額が1,500円の場合は、1,000円と500円の収入印紙を1枚ずつ貼るのが一般的です。手元の収入印紙を組み合わせて、1,000円×1枚、200円×2枚、100円×1枚としても問題ありません。
収入印紙の購入方法
収入印紙は、以下の場所で購入できます。
- 法務局
- 役所
- 郵便局
- コンビニエンスストア
- たばこ屋
- 金券ショップ など
法務局や役所では、基本的に31種類すべての収入印紙を購入できます。郵便局は、窓口の規模が小さいと、全種類の在庫がないこともあるため注意が必要です。額面の大きい収入印紙を購入する場合は、事前に確認するとよいでしょう。
コンビニエンスストアでは、利用頻度の高い200円のみを取り扱うケースが多いです。個人経営や駅構内のコンビニエンスストアでは、取り扱い自体がないこともあるため注意しましょう。
収入印紙はたばこ屋でも購入できますが、販売するのは「印紙売りさばき所」の登録を受けた店舗に限られます。
金券ショップは額面より安い金額で購入できるものの、在庫によっては収入印紙の種類や枚数が希望と一致しないこともあります。消費税の課税ルールや仕訳時の勘定科目も異なるため、注意が必要です。
収入印紙代を経費として計上する方法について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
収入印紙の貼り方
収入印紙の貼り方に、法的なルールはありません。文書内に貼り付け欄が設けられている場合は、その部分に貼り付けましょう。
貼り付け欄がないときは、文書タイトルの左右の空白に貼付するのが一般的です。複数枚の場合は、上下または左右に並べて貼るとよいでしょう。
収入印紙を貼り付けた後は、消印が必要です。文書と収入印紙をまたぐ形で印鑑を押すことにより、印紙の貼付者を証明できます。また、印紙が使用済みであることを示す役割も果たします。
消印には、契約書に押印した印鑑や角印を使用するのが一般的です。会社名または担当者名がわかれば、ゴム印やシヤチハタでも問題ありません。
収入印紙の消印について、正しい押印方法や割印がない場合の罰則を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
収入印紙を貼らなかった場合の罰則
課税文書に収入印紙を貼らなかった場合、文書を受け取る側に罰則はありません。収入印紙を貼ることが義務付けられている発行者に対して、過怠税が課せられます。過怠税は、貼付すべき収入印紙の金額と、印紙税額の2倍の合計です。
たとえば、10万円の領収書に200円の収入印紙を貼り忘れて発行した場合、200円と400円の合計で600円の過怠税を納める義務が生じます。
ただし、収入印紙を貼らなかった旨を自ら税務署に申告した場合は、課せられる過怠税が減額されます。この場合に発生する過怠税は、納付すべき印紙税の金額と印紙税額に、それぞれ10%を掛けた合計です。
たとえば、200円分の貼り忘れを自己申告した場合、200円と20円の合計で220円の過怠税を納めなければなりません。
過怠税は、収入印紙の貼り漏れが故意か否かに関わらず発生します。貼り忘れに気付いた場合は、税務署へ速やかに申告して過怠税を支払いましょう。
電子決済や電子データ取引の場合は収入印紙不要
クレジットカード決済などの電子決済、FAXやPDFなどの電子データ取引に、収入印紙は不要です。クレジット決済の場合、購入時点で受取人は金銭を授受しておらず、印紙税法上の受取書に該当しないためです。
印紙税は文書に課せられる税金のため、電子化された契約書にも収入印紙を貼り付ける必要はありません。ただし、パソコンなどで作成した領収書や契約書を紙に出力した場合は、収入印紙が必要となるため注意しましょう。
クレジットカードの領収書や電子化した領収書への収入印紙の必要性については、以下の記事でさらに詳しく解説していますのでご覧ください。
収入印紙不要の電子化した書類を発行するならバクラク請求書発行
収入印紙は、税金や手数料を徴収するために国が発行する証票です。文書の種類や記載金額によって金額が異なるため、貼り間違えないようにあらかじめ理解を深めておくことが重要です。
収入印紙を貼り忘れた場合は、発行者に過怠税が課せられます。貼り忘れをなくすには、領収書や契約書を電子発行できる専用システムを導入するのがおすすめです。
バクラク請求書発行は、請求書や領収書などのさまざまな書類をシステム上で一括・個別作成できます。自社のフォーマットに合わせた柔軟なカスタマイズのほか、送付方法や宛先などを取引先ごとに設定でき、書類発行業務全体の効率化を図れます。
電子帳簿保存法やインボイス制度などの、各種法令に対応している点も強みです。収入印紙の管理やコストについてお悩みの方は、バクラク請求書発行の導入をご検討ください。詳しいサービス内容は、以下のページからご確認いただけます。