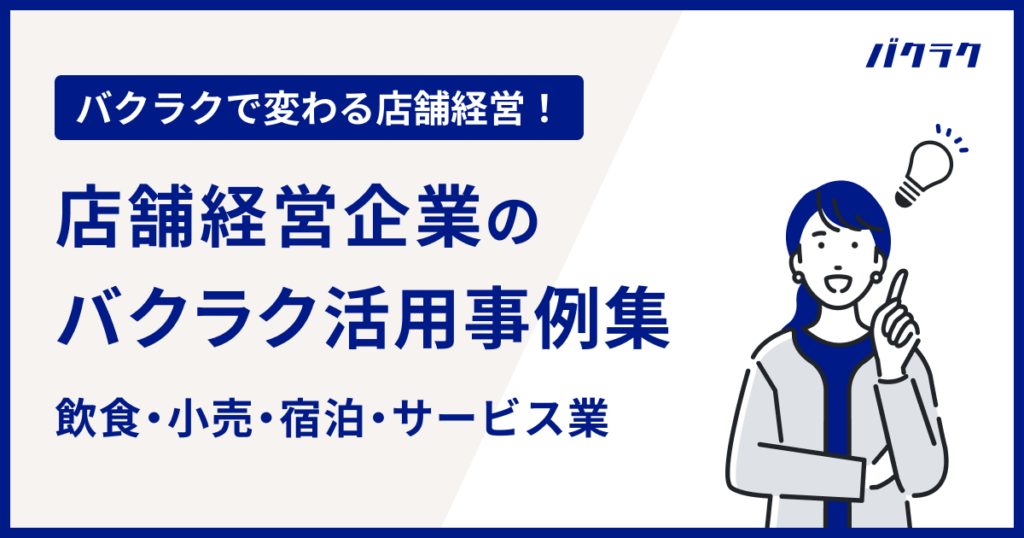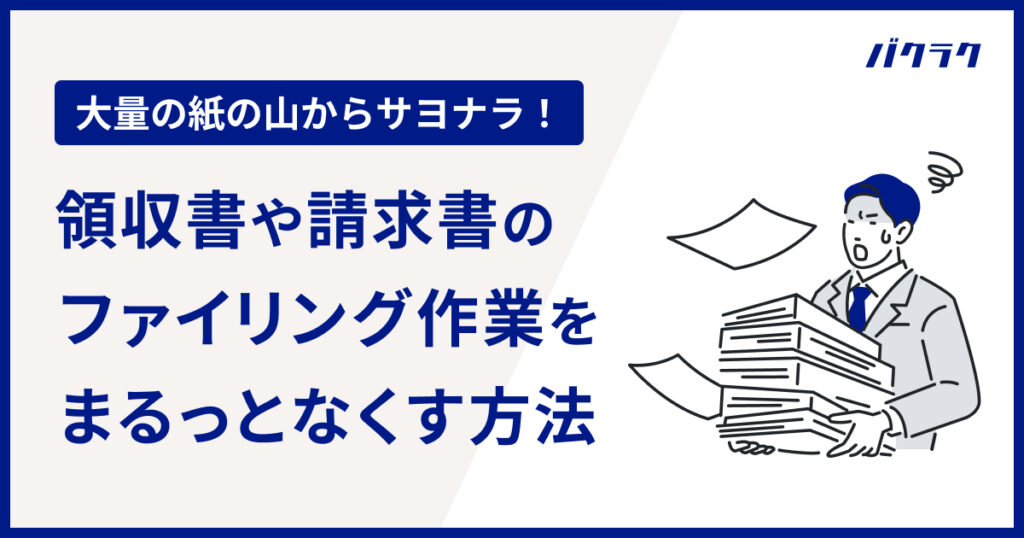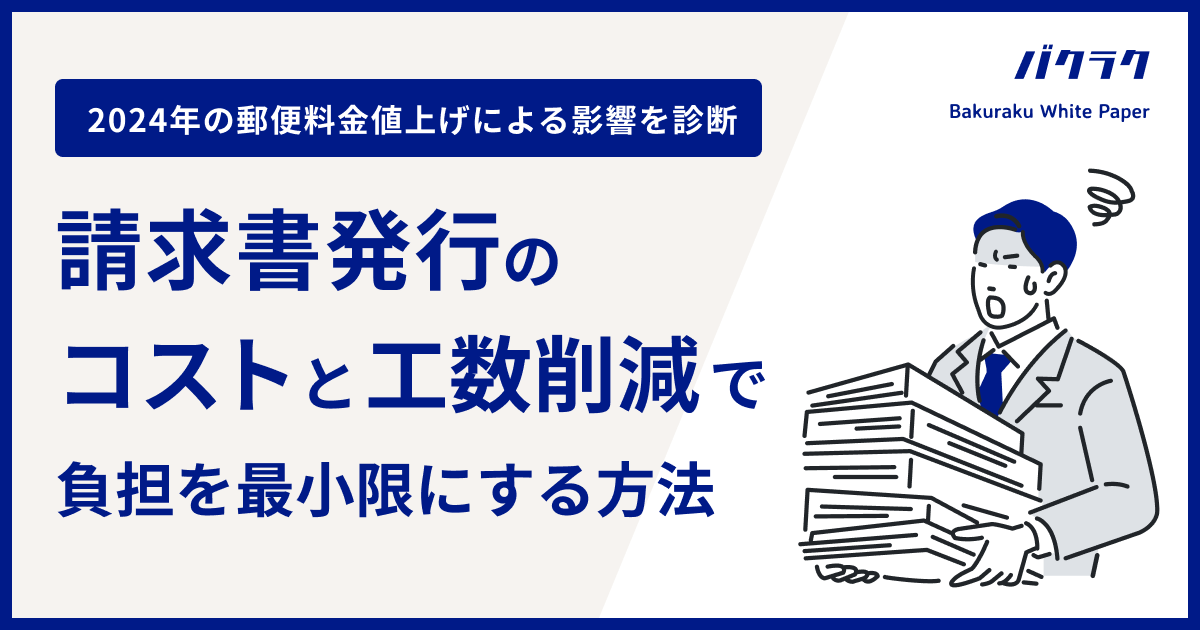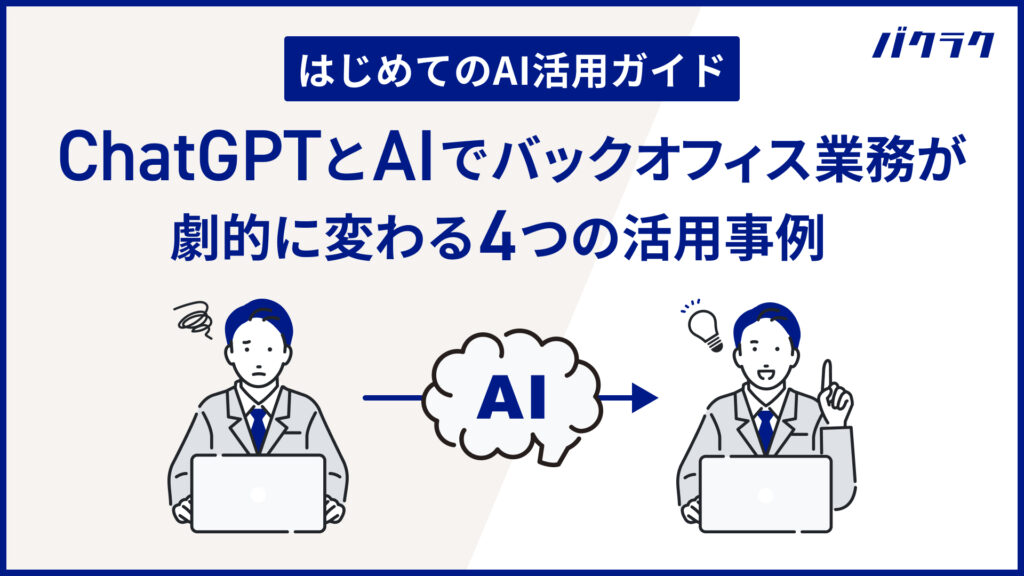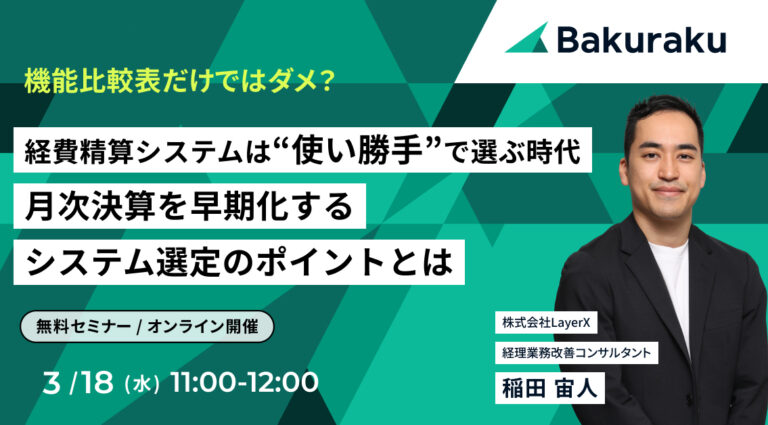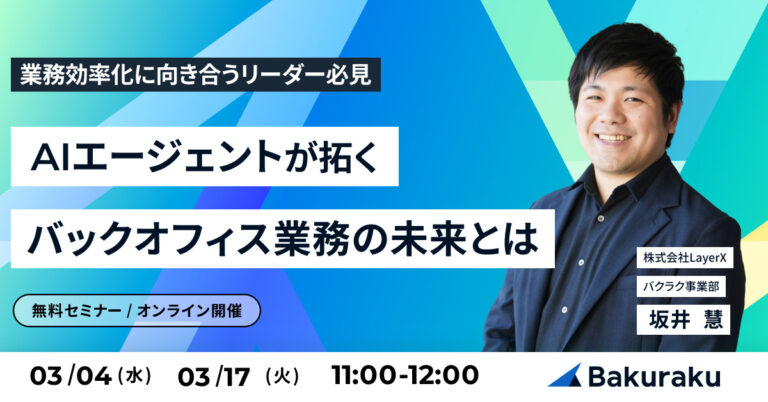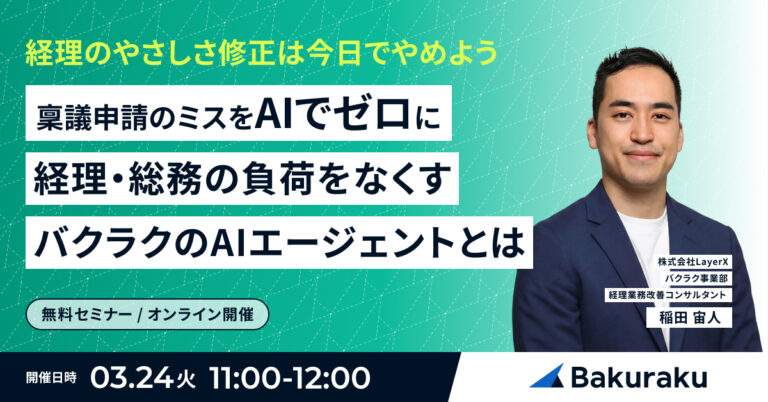
請求書の管理方法とは?保管年数やデータ化、管理システムの選び方について解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 受領する側でも発行する側でも、請求書は段階ごとに分けて適切な管理が求められる
- Excelで管理する方法もあるが、一元管理や検索性向上のために請求書管理システム導入を推奨
- 請求書管理システムの選び方を把握して、自社に合ったツールを選ぶことが重要である
請求書は、取引の確認や財務の正確な把握のために重要な書類ですが、Excelで管理すればデータが重たくなったり、属人化しやすかったりといったデメリットがあります。
本記事では、請求書の管理方法や保管年数、管理システムの選び方について解説します。
請求書の管理方法とは?保管年数やデータ化、管理システムの選び方について解説
請求書をまとめて管理する主な方法
請求書をまとめる方法としては、月ごとにまとめる方法と取引先ごとにまとめる方法があります。ここでは、それぞれの方法について解説します。
月ごとに管理
まずは、請求書を発行月ごとに整理・保管する方法です。たとえば、2024年1月1日〜1月31日までに発行された請求書をまとめて保管します。
月ごとに整理したり保管したりすれば、各月の支出や収入の把握が可能です。また、月次の会計処理や決算時にも月ごとに整理されているとわかりやすく、経理業務の効率化につながります。
ただし、特定の会社の請求書を探したいという場合には時間がかかります。
取引先ごとに管理
取引先ごとに請求書を整理・保管する方法もあります。取引先ごとに請求書をまとめることで、特定の取引先の請求書を見たいという場合にも、迅速に探せるようになります。
また、取引先ごとの取引状況も把握しやすくなるため、顧客管理の効率化にも役立つでしょう。固定の取引先が多い場合にも管理しやすくなります。
ただし、取引先が多いと分類が多くなり、まとめるのが大変になる、1事業年度が終わらないと全体を締められない、といったデメリットもあります。
請求書を受領する側の管理方法
受領した請求書は、支払状況を管理する重要な書類です。適切に管理しなければ、支払い漏れや二重払いといったトラブルにつながる可能性があるため、明確なルールを設けて整理しましょう。
具体的には以下のように、未払い分と支払い済み分の2つのステップに分けて管理します。
- 受領したら内容を確認し、未払い分として支払期日が早い順に保管する
- 支払が完了したら支払い済み分へ移動し、支払い証明書とあわせて保管する
請求書を受領したら、まず内容を確認しましょう。請求金額や支払期日など、誤りがあれば速やかに取引先に問い合わせます。
問題がなければ未払い分として「未払い」と明記されたフォルダや専用ケースを支払期日が早い順に並べて整理します。必要に応じて支払い承認用フォルダを作成して、決済プロセスを明確にしましょう。
支払いが完了した請求書は「支払い済み」として分類し、支払い証明書と共に保管します。請求書に「済」スタンプや「支払い済み」記入ですぐに確認できるようにしておくことがポイントです。
支払い済みの請求書は、未払いのものと混同しないよう専用フォルダに月ごとや取引先ごとに分類し、支払い証明書を添付して保管しましょう。電子帳簿保存法に対応するため、スキャンしてデータ保存することも有効です。
請求書処理のフローについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
請求書を発行する側の管理方法
請求書を発行した場合、適切な管理方法の確立は、未収金の把握や資金繰りの安定に直結します。請求書を発行した後は入金状況に応じて分類し、効率的な管理を心掛けましょう。
- 発行後は控えを未入金分として、支払期日が早い順に保管する
- 取引先からの入金が確認できれば入金済み分へ移動し保管する
請求書を発行したら「未入金請求書控えファイル」を用意し、発行した請求を保管しましょう。支払期日順に整理して、確認しやすい状態の維持を徹底すれば、資金管理の精度を向上させられます。
取引先からの入金が確認できた請求書は「済」スタンプや記入をして「入金済み」で分類し、保管します。請求書は保管期間が定められているため、月ごともしくは取引先ごとにまとめて整理・保管しておきましょう。
請求書の発行方法については、以下の記事で詳しくまとめているのでぜひご覧ください。
請求書の保管年数
請求書の保管期間は、法人・個人事業主のどちらであるかによって異なります。法人の場合は7年間(繰越欠損金が発生した場合は10年間)、個人事業主は5年間の保存義務を順守しなければなりません。
適格請求書発行事業者(インボイス制度対応)は、法人・個人を問わず、適格請求書を7年間保存する義務があります。発行・受領した請求書ともに該当する場合は、同じ期間保存することが必要です。
また、紙の請求書をスキャンして電子データとして保存することも可能です。ただし、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があり、改ざん防止措置を講じたうえで適切に管理しなければなりません。
請求書の保管や電子帳簿保存方法のルールについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
請求書の管理が重要な理由
請求書は企業や個人事業主が適切に取引を記録し、財務を正確に管理するための重要な会計書類です。確定申告時に作成する決算書や申告書の根拠となるため、適切な方法で管理する必要があります。
また2023年10月から開始したインボイス制度によると、適格請求書発行事業者は、法令に従った適格請求書の保存が義務付けられています。さらに、2024年1月1日以降、電子帳簿保存法に基づき、電子取引の請求書は電子データとして保存することが完全義務化されました。
請求書は取引の証拠となるだけでなく、税務申告の際に必要な会計帳簿の一部です。適切な管理を怠ると、税務調査で指摘を受ける可能性があるため、ルールに則った管理を行いましょう。
Excelで請求書を管理するデメリット
Excelは手軽に利用できる表計算ソフトであり、請求書管理にも活用できます。しかし、長期間にわたって大量のデータを管理する際には、複数の課題が生じます。
まず一つ目のデメリットとして挙げられるのは、データ量が増えるにつれて処理速度が低下し、ファイルが重くなる点です。たとえば、5年分や7年分のデータを1つのExcelブックで管理すると動作が遅くなり、作業効率が悪化します。
また、Excelは手入力が基本となるため、入力ミスが発生しやすいこともデメリットです。関数やマクロを活用すれば、ある程度のミスを防ぐことはできますが、マクロを使用すると、その設定や修正ができる担当者がいない場合、業務が滞るリスクが発生します。
さらにExcelは複数人での共有が難しく、リアルタイムでのデータ更新が困難です。ファイルが属人的になり、担当者が異動や退職した際に、引き継ぎがスムーズに行えないケースもあります。
請求書管理システムを導入するメリット
請求書の管理をExcelで行う方法は一般的ですが、デメリットも存在します。Excelの課題を解決する手段として挙げられるのが、請求書管理システムの導入です。
システムを活用すれば一元管理や業務効率化が可能になり、企業の生産性向上も期待できます。システムのメリットについて順番に解説します。
一元管理ができ業務効率化につながる
請求書管理システムを導入して得られるメリットは、請求書の管理から承認、送付、入金確認までを一元管理できる点です。Excelのように手作業で入力したり、管理したりする必要がなくなるため、入力ミスも防げます。
また、テンプレートに社印を登録すれば、印刷や押印の手間を省けるため、業務の負担が軽減されます。
さらに、請求書の社内承認や入金管理も自動化でき、手作業によるチェックの手間も減らせる点も、メリットといえるでしょう。
入金状況をリアルタイムで確認できる
請求書管理システムを導入すれば、入金状況などをリアルタイムで確認できるようになるため、迅速な対応が可能です。また支払い期日の追跡やリマインダーの送信なども行えるため、支払い漏れを防ぎやすくなります。
未払いの状況をリアルタイムで把握でき、必要な対応を迅速に行えるようになることも、メリットの一つです。未収金の管理なども可能で、財務管理の精度が向上して透明性の高い財務を実現できます。
特定の請求書を簡単に検索できる
請求書管理システムによって、特定の請求書を簡単に検索できるようになります。紙の請求書をファイリングしている場合、発行日順に並べることはできますが、目的の請求書を探すのには時間がかかってしまいます。
しかし、請求書管理システムには検索機能が搭載されており、過去の取引や支払い状況をすぐに確認できるようになるため、業務効率の向上が期待できるでしょう。
データ管理がより効果的かつ効率的に行えるようになるため、担当者の負担軽減にもつながります。
コストの削減も期待できる
請求書管理システムを導入すると、紙やインク、封筒、郵送費といったコストの削減が可能です。電子データとして請求書を発行・送付できるため、印刷や封入、郵送の作業が不要になり、紙ベースでの管理に比べて大幅なコストカットが期待できます。
また、請求業務の負担が軽減されれば作業時間の短縮につながり、結果として残業が減少します。
従業員の労働時間が効率化されることで人件費の削減にも寄与し、長期的なコスト削減につながるでしょう。
請求書管理システムの選び方
請求書管理システムを選ぶ際には、さまざまな面に焦点を当てて選ぶことが重要です。選び方のポイントを5つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。
機能や法制度への対応
請求書管理システムを選ぶ際は、提供される機能と法制度への対応状況を確認することが重要です。請求書の作成や送付だけでなく、以下のような業務効率を向上させる機能が揃っているかチェックしましょう。
- 請求・入金ステータスの管理
- 自動作成予約
- CSVデータの活用など
また、インボイス制度や電子帳簿保存法など、法改正への対応も必須です。適格請求書の発行や電子データでの証憑管理が可能かどうか確認しましょう。さらに、導入後も継続的にアップデートされるクラウド型システムかどうかも考慮すると安心です。
さらに操作性もポイントとなるため、画面の見やすさや直感的な操作ができるかも確認が必要です。
料金
請求書管理システムの導入には、費用がかかります。そのため、ツールの月額費用やオプションサービスの有無・費用などをよく検討したうえで、自社の予算に合ったものを選ぶことがポイントです。
初期費用だけでなく追加機能のコスト、維持管理に必要なランニングコストなどの総合的なコストを把握し、コストパフォーマンスが優れているか評価しましょう。
請求書管理システムは継続的に利用するツールのため、コスト管理がしやすいものがおすすめです。
セキュリティ
請求書管理システムには企業の機密情報が含まれるため、セキュリティ対策が万全であるかの確認が不可欠です。特に、データの暗号化やアクセス制限、不正アクセス防止策などが講じられているかを確認してください。
さらに、データのバックアップ体制も重要です。システム障害やサイバー攻撃が発生した際に、迅速に復旧できるような仕組みが整っているかを確認しておきましょう。
セキュリティ対策が不十分なシステムでは、データ流出や改ざんのリスクが高まるため、慎重に選ぶことが重要です。
既存システムとの連携
請求書管理システムを導入する際は、既存の会計ソフトや既存システムとの連携が可能かどうかの確認も重要です。
請求データが会計ソフトと自動で連携できれば、記帳作業の手間が削減され、入力ミスの防止にもつながります。
また、請求情報がリアルタイムで仕訳に反映されれば、経理業務の効率化が実現します。決算業務の簡素化や記帳漏れの防止といったメリットもあるため、自社の業務フローに適したシステムかどうか、事前に確認しておくとよいでしょう。
サポート体制
システム導入後にトラブルが発生した際、適切なサポートを受けられるかどうかも重要なポイントです。電話やメール、チャットなど、どのような方法で問い合わせが可能か、また、サポートの対応時間が自社の業務時間に適しているかを確認しましょう。
さらに、オペレーターとの画面共有によるサポートや、導入後のトレーニングサポートが提供されているかもチェックしておくと安心です。
特に初めて導入する場合は、設定や運用面でのフォローが充実しているシステムを選ぶと、スムーズに活用できます。
「バクラク請求書受取」なら請求書の管理も手間なくできる
請求書は、財務の正確な管理のために企業や個人事業主が適切に取引を記録する重要な書類です。管理には月や取引先ごとの方法がありますが、適切に管理しなければ税務調査で指摘されてしまう可能性もあるため注意しましょう。
管理はExcelでもできますが、請求書管理システムの導入がおすすめです。「バクラク経費精算」では請求書の受領から処理、保管までを自動化し、業務の効率化を実現します。
電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しているため、法令遵守の面でも安心です。経理業務の最適化が可能になる「バクラク経費精算」について気になる方は、以下のページをご覧ください。