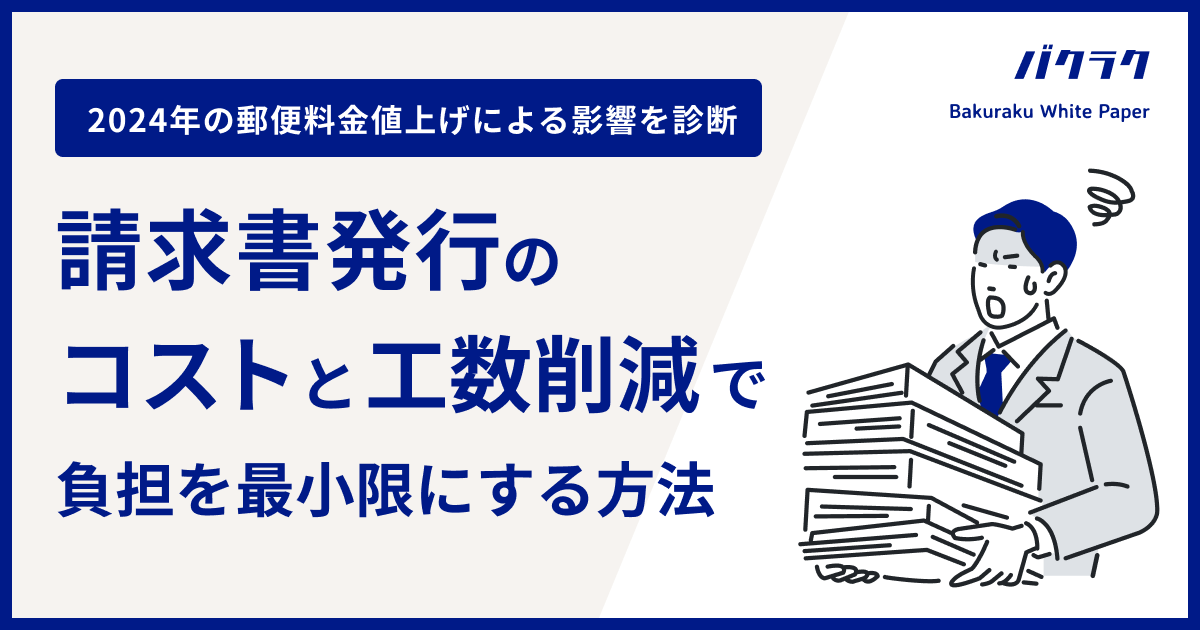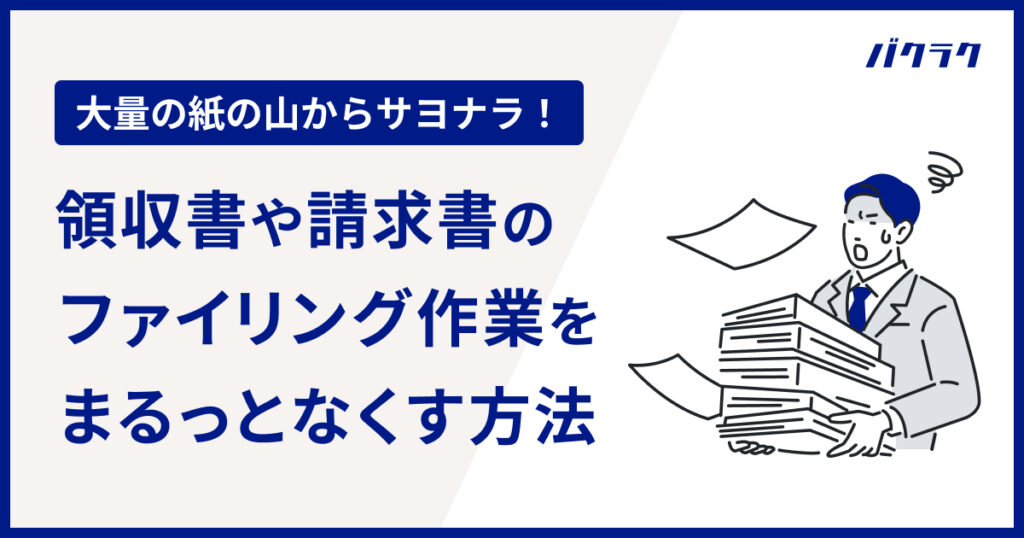請求書は必須?保管など法律上の各種義務の有無や必要な理由を解説
- この記事の3つのポイント
- 請求書は法律上、必須ではないが、トラブルの防止や日本の商習慣において発行が求められる
- インボイス制度の実施により、交付を求められた際には発行義務が生じるなどの変化があった
- 発行した請求書は法人の場合は7年、個人事業主の場合は5年の保管義務がある
請求書の発行は法律上の義務ではないものの、トラブル防止や商習慣上ほぼ必須の書類です。
本記事では、請求書を発行しなければいけない理由や記載すべき項目、インボイス制度の影響、発行した請求書の保管義務について解説します。
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
請求書の発行は義務?
請求書の発行は、法律上の義務ではありません。発行の形式も決められていないため、紙やデジタルなどの媒体も自由です。また商品やサービスの購入者側も、請求書が必ずしも必要とは限らず、契約書や領収書など、他の証拠書類があれば支障はありません。
ただし、企業の経費計上では請求書の提出が求められることが多く、税務調査時のトラブル回避のためにも、発行を依頼するのが一般的です。日本の商慣習では請求書の発行が通例とされており、取引の証拠や信頼関係の維持に効果的です。
さらに請求書には法的効力があり、支払いトラブル時に取引の証拠となります。なお請求書の有効期限は民法166条に基づき5年とされており、2020年3月以前の取引は旧民法により2年の時効が適用されます。
請求書がもらえない場合について詳しくは、以下の記事で解説しているのでぜひ参考にしてください。
請求書の発行が必要な理由
請求書の発行は、トラブルの防止、取引の事実証明、正確な経理業務の3つの理由から、ビジネスの常識といえるでしょう。それぞれについて詳しく解説します。
トラブルを防止するため
請求書を発行すると、取引金額とその内訳、振込先、支払い期限などを相手先に明確に伝えられます。「事前に取り決めた金額と違う」などの認識違いからトラブルに発展する可能性を減らせるでしょう。口頭での契約のような問題も生じません。
また、自社で請求書のフォーマットを作成しておけば、請求業務を標準化できるのもメリットです。口頭や電子メールなどでの請求では、担当者のやり方の違いにより無用なトラブルを招く恐れがありますが、請求書なら自社ルールに従って請求できます。
取引が行われた事実の証明になるため
請求書は税法上において、取引があった事実を客観的に証明できる証憑書類の一つです。このため、金額や支払い時期などのトラブルがあった際に、裁判の証拠書類となります。
また、税務調査が入って説明を求められた際に、取引の事実を証明する資料としても提出可能です。
正確な経理業務を行うため
請求書を発行すると正確な経理業務ができます。請求書には入金額と支払い期日が記入されているため、お金の流れを明確に管理できるようになるからです。
特に、経理業務システムを用いてデジタル文書で管理している場合は、請求書発行と同時にリアルタイムでお金の流れを把握できます。
このメリットは、対価を支払う側も同様です。期日に遅れることなく支払いを完了させたり、計上月に合わせて入金ができたりします。
請求書に記載すべき項目
請求書には法律上の決まった形式はなく、紙文書でもデジタル文書でも自由に作成できます。しかし税務上の証憑としての役割があるため、以下のように一定の記載項目が求められます。
- 発行者の氏名または名称(会社名・個人名)
- 発行年月日(請求書の作成日)
- 取引年月日(実際に取引が行われた日)
- 取引内容(提供した商品やサービスの詳細)
- 取引金額(小計・消費税・合計金額)
- 発行相手の氏名または名称(取引先の会社名・個人名)
- 振込先(銀行口座情報など)
加えて取引管理のため「請求書番号」や「支払い期限」を記載するのが一般的です。また取引先の締め日に合わせて発行日を調整すれば、スムーズな支払い処理につながります。
請求書の書き方とルールについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
関連記事:請求書の書き方とルールを具体例付きで解説(テンプレートあり)
また請求書の支払期限については、以下の記事で詳しく解説しています。
インボイス制度の実施で請求書の発行はどう変わった?
2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、請求書の発行に関するルールが変更されました。この章では、インボイス制度による具体的な変更点を解説します。
適格請求書の交付を求められたときは発行義務が生じる
インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者は、課税事業者である取引先から求められた場合、適格請求書(インボイス)の交付が義務となりました。これは仕入税額控除を適用するために、適格請求書の保存が必要であるためです。
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引先(課税事業者)から請求書の発行を求められると、原則として適格請求書を交付する義務があります。
適格請求書を発行しない場合、取引先が仕入税額控除を受けられず、取引上の不利益につながる可能性があるため、適格請求書発行事業者は適切な対応が重要です。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
4-2.請求書の記載方法に変化が生じる
インボイス制度の導入により、請求書の記載方法に変更が生じました。適格請求書として認められるためには、以下の6つの記載事項が必要です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日(いつ売買が行われたか)
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合、その旨を記載)
- 税率ごとに分類した金額(税抜または税込)とそれぞれの税率
- 税率別に計算した消費税の額
- 請求書を受け取る側の会社名や氏名
今までの請求書との大きな違いは「登録番号」と「税率ごとに区分した金額」、「税率別の消費税額」を記載する必要がある点です。
また適格請求書発行事業者として登録すると、免税事業者であっても課税事業者となるため、制度の適用を検討する際は注意しましょう。
関連記事:適格請求書とは?概要や書き方(見本付き)をわかりやすく解説
発行した請求書は保管義務がある
送付した請求書の控えをとっている場合には、保管が義務付けられています。請求書の控え(写し、コピー)は証憑書類という文書区分に該当するため、法人は7年間、個人事業主は5年間保管しなければなりません。
取引先からの入金の有無を確かめるために、自社で請求書の控えを発行しているといった場合は、忘れずに保管しておきましょう。
詳細については以下で解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事:請求書の保管期間は?法人・個人事業主ごとの年数やインボイスの影響を解説
請求書の発行・保存なら法制度に対応している「バクラク請求書発行」
請求書の発行はビジネス上必須ですが、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が求められ、業務の負担が増えています。「バクラク請求書発行」は、従来の業務フローを大きく変えずに、取引先に合わせた発行方法を選べるのが特徴です。
バクラク請求書発行は適格請求書の自動作成や税率ごとの金額計算、電子帳簿保存法に則ったデータ管理など、法制度対応を自動化しています。さらに帳票の作成・稟議・送付・保存をデジタルで一元管理できるため、経理業務の負担軽減が可能です。
業務の効率化と法制度対応を両立したい人は、ぜひ以下のページをご覧ください。