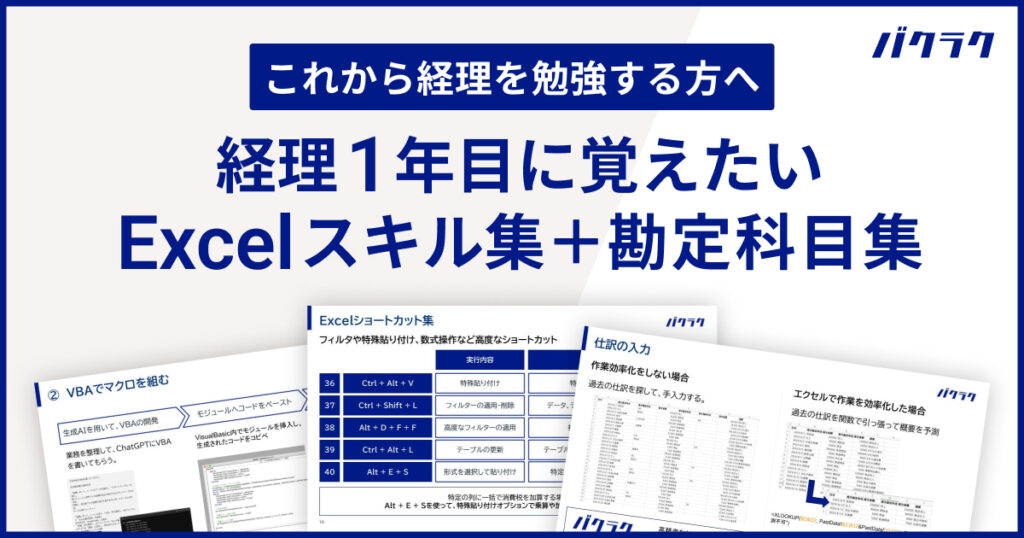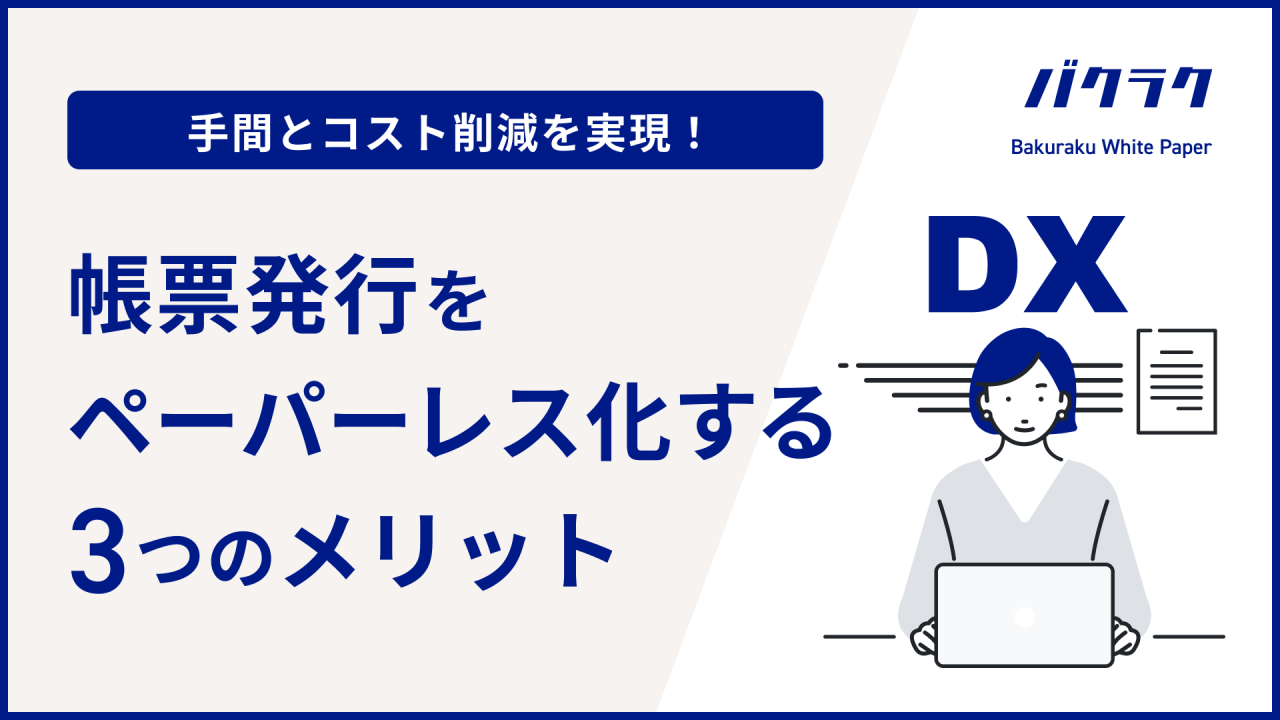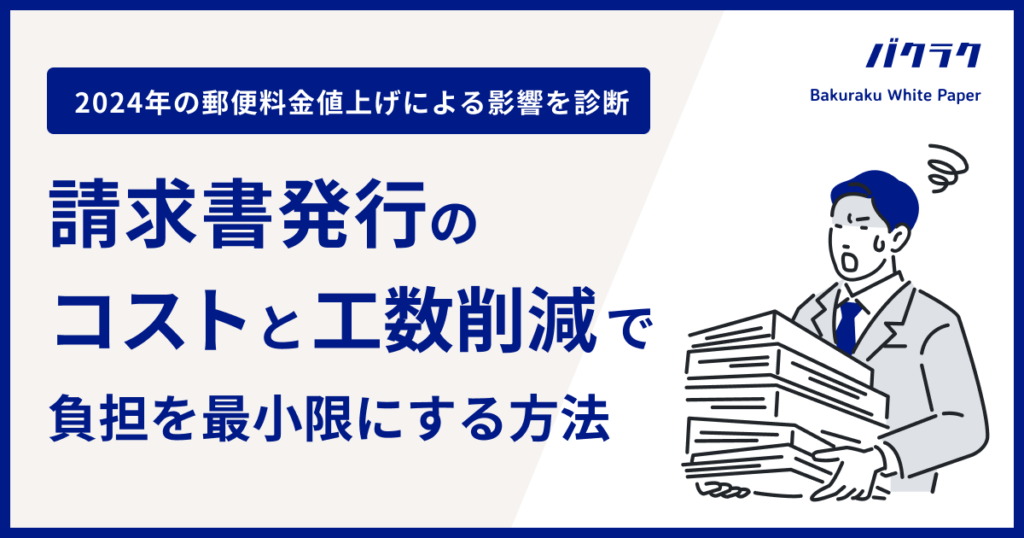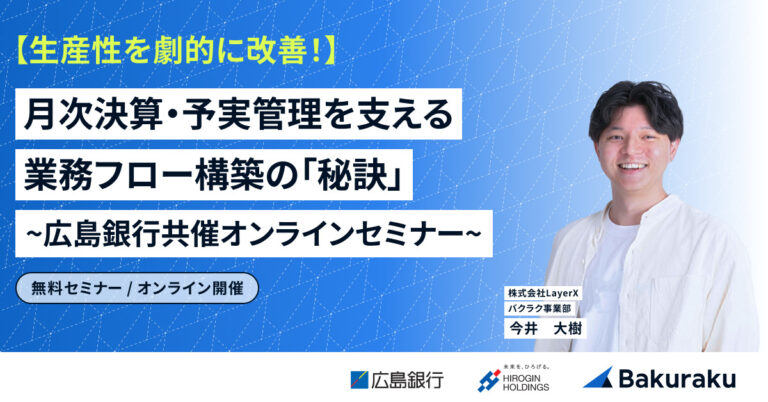請求書の消費税の端数処理方法は?インボイスでの扱い・1円ずれる場合の対処法
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 請求書に記載する消費税で1円未満の端数が出た場合、事業者の判断で端数処理を行う
- 端数処理は適格請求書1枚につき1度までで、1品目ごとの処理は認められない
- インボイス制度以降積上げ計算方式も可能で、納税時に出た100円未満は端数処理をする
従来の区分記載請求書では、税率ごとの対価を記載する決まりでした。しかし、2023年10月1日以降はインボイス制度導入により、適格請求書等保存方式での請求書発行・保管が必要となりました。
適格請求書では、記載項目やルールがこれまでよりも細かくなっています。本記事では、インボイス制度下において、消費税の算出時に小数点以下の端数が発生した際の対処法や端数処理のポイントを詳しく解説します。
納税額の端数処理についても解説していますので、ぜひお役立てください。
請求書の消費税の端数処理方法は?インボイスでの扱い・1円ずれる場合の対処法
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
請求書に記載する消費税に端数が発生した場合の処理方法
請求書の作成時、消費税の計算で1円未満の端数が生じることがあります。具体的には、商品本体価格に消費税率を乗じて請求額を求める際に発生するケースが多いでしょう。
端数の処理方法としては「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」の3つが一般的です。どの方法を選択するかは事業者の任意で良いとの見解が財務省で示されてはいるものの、一般的には切り捨てを採用する企業が多いとされています。
ただし、選択した端数処理方法によって請求書の金額が変わる点には注意が必要です。
たとえば、商品代金が1,780円で消費税率が10%の場合、税額は178.0円となり、1円未満の端数は出ません。しかし、1,783円のケースでは税額は178.3円となり端数が発生します。この端数をそれぞれの方法で処理すると、以下の結果となります。
- 切り捨て:178円
- 切り上げ:179円
- 四捨五入:178円
上記のとおり、処理方法により1円の差が生じているとわかるでしょう。1円とはいえ、取引件数が増えれば合計金額にも大きな影響を与えるため、端数処理のルールは明確に定め、一貫して運用することが重要です。
参考:財務省「総額表示に関する主な質問」
消費税を内税表示する際のポイントについては、以下をご確認ください。
インボイス制度導入による消費税の端数処理の変更点
インボイス制度開始以降、仕入税額控除を受けるには、適格請求書を用いた取引をすることが原則です。そして端数処理についても、インボイス制度に合わせて新たにルールが設けられています。
ここでは、インボイス制度による端数処理の変更点を解説します。
適格請求書1枚につき端数処理は1回まで
2023年9月末までの区分記載請求書等保存方式では、端数処理の回数に関するルールは定められていませんでした。しかし、2023年10月より導入されたインボイス制度では、適格請求書1枚につき端数処理は1回までのルールが設けられています。
ただし、標準税率10%と軽減税率8%が混在する場合は、それぞれの税率ごとに端数処理をしてから合算金額を記載してかまいません。端数処理の方法は事業者の裁量に委ねられており、切り上げ、切り捨て、四捨五入のうち任意の方法を選択できます。
軽減税率の対象品目については、以下の記事で詳細をご確認ください。
関連記事:消費税の軽減税率の対象品目は?8%課税がされる商品の具体例と対応方法
請求書内の商品ごとの端数処理はできない
適格請求書等保存方式に基づき、従来の請求書には以下の項目を追加する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 軽減税率の対象品目である旨(※印などをつけることにより明記)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分して合計した消費税額など(消費税額および地方消費税額の合計額)
国税庁によると、税率ごとに区分した消費税額等で生じた1円未満の端数処理については、1枚の請求書あたり、税率ごとに1回ずつ端数処理を行うルールがあります。
そのため、商品ごとに1円未満の端数処理を行って算出した消費税額を合算して、合計消費税額を求める方法は認められていません。ただし、税込の商品額を求めるために1商品ずつ消費税額の端数処理を行うことは可能です。
その場合は、合算した税込対価に対して、税率ごとに端数処理を行い消費税額の合計を求める必要があります。
参考:国税庁「適格請求書等保存方法の概要(p.8)」
関連記事:適格請求書とは?概要や書き方(見本付き)をわかりやすく解説
請求書の消費税を端数処理するときのポイント・注意点
請求書における端数処理のポイントは、次の2つです。
端数処理方法は社内で統一する
消費税の端数処理方法は事業者の判断に委ねられているため、社内で統一したルールを設けることが重要です。ルールが統一されていないと、同一の商品・サービスでも担当者によって消費税額が異なり、取引先ともトラブルに発展するリスクがあります。
無用な混乱を避けるため、端数処理に関する社内ルールを明確に定めておき、全従業員に周知・徹底しましょう。
取引先に端数処理方法を事前に確認する
取引先との間で、端数処理の方法の認識を合わせておくことも重要です。それぞれの端数処理が異なっていると、請求時の金額に誤差が生じてしまい、トラブルになる可能性があります。そのため、事前に端数処理の方法について話し合っておくと安心です。
もし、作成時に消費税額が1円ずれてしまった場合には、確認を取りながら調整します。交付後であれば請求書の修正・再発行を行い、互いの認識が食い違わないよう努めましょう。
請求書を再発行する際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
納税する消費税額の端数処理方法
請求書発行における消費税額の端数処理と、納税額算出時の端数処理方法はルールが異なります。混同しないよう、ポイントを把握しておきましょう。
納税額は「割り戻し方式」もしくは「積上げ方式」で計算する
消費税の納税額は「割り戻し方式」と「積上げ方式」のどちらかで計算できます。インボイス制度の導入により、これまでの割り戻し方式に加えて積上げ方式も選択可能になりました。なお、売上税額では割り戻し方式、仕入れ税額では積上げ方式が原則となっています。
割り戻し方式は、課税期間中の課税(売上)仕入れ総額をもとに消費税額を一括計算する方法で、計算式は以下のとおりです。
課税(売上)仕入れ総額×7.8/110(軽減税率の場合は6.24/110)=納税額
課税仕入れ総額が66,000円(10%税率対象)だった場合は、以下のように納税消費税額を求めます。
66,000円×7.8/110=4,680円
一方、積上げ方式は取引ごとに消費税額を計算し、これを積み上げて算出したものを納税額とする方法で、以下の計算式で求めます。
取引額×7.8/110(軽減税率の場合は6.24/110)=1取引ごとの消費税額
1回の課税仕入れ額3,300円の取引が10回あった場合には、以下のとおりです。
3,300円×7.8/110=234円
234円×10=2,340円
積上げ方式では取引ごとに計算するため、計算の正確性が向上します。一方、割り戻し方式は計算が簡略である代わりに、1円のズレが生じやすいのがデメリットです。
参考:国税庁「適格請求書等保存方式の下での税額計算」
納税の際には100円未満を端数処理する
請求書では1円未満を端数処理するルールでしたが、納税時には100円未満を端数処理をして、端数は切り捨てとします。たとえば、消費税額が8,540円と算出された場合には、8,500円としてかまいません。
参考:国税庁「No.6371 端数計算」
請求業務を効率化するなら「バクラク請求書発行」
消費税に小数点以下の端数が発生した場合には、インボイス制度による変更点も踏まえながら端数処理を行うことが必要です。
端数処理方法については事前に取引先と認識を合わせておくことで、トラブル防止につながります。今一度ルールをよく確認し、金額のズレが生じないよう心がけましょう。
バクラク請求書発行は、インボイス制度・電子帳簿保存法に対応した経理システムです。取引先に応じた形式でスムーズに請求書を作成できます。また、請求書交付や管理も一括して行え、経費精算や法人カードをスマートに連携し、経理作業の大幅な効率化が実現できます。請求書業務に不安をおもちなら、ぜひバクラク請求書発行のご利用をご検討ください。