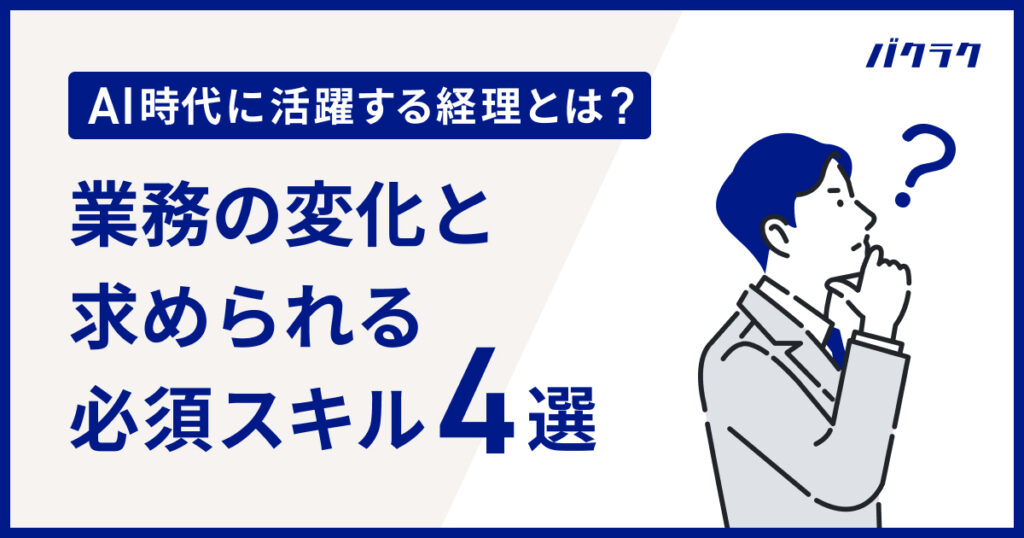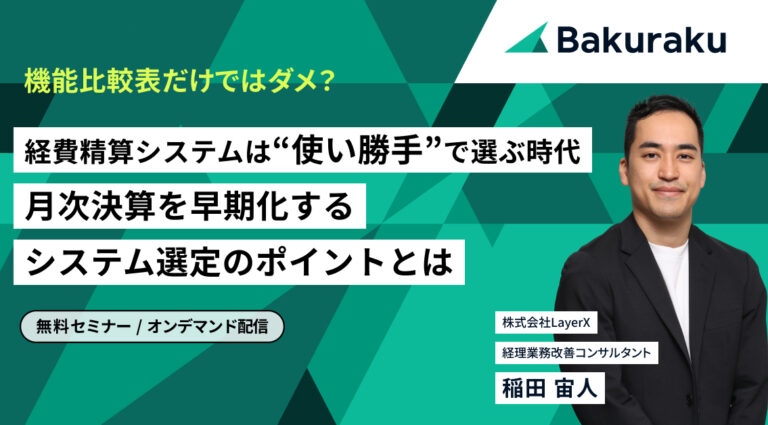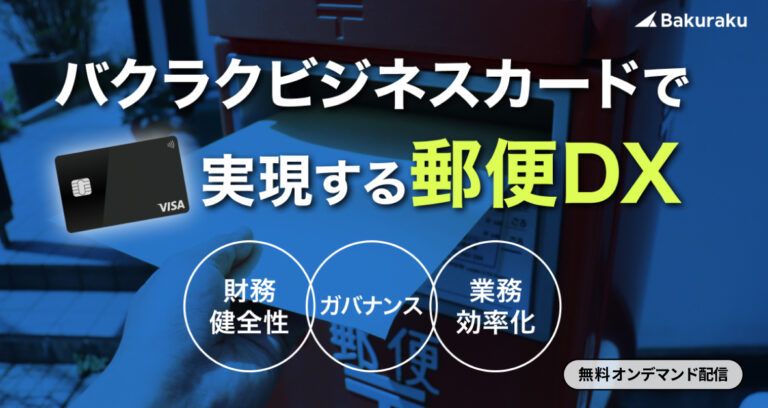スマホで撮影した領収書の写真でも経費精算は可能!保存要件や原本の取扱いを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-08-18
- この記事の3つのポイント
- 領収書は、電子帳簿保存法の改正によりスマートフォンの写真をデータ保存し、経費申請できる
- 領収書を写真で保存する際は、スキャナ保存制度の要件を満たす必要がある
- 電子帳簿保存法の要件を正しく満たせば、写真で保存した領収書の原本は破棄しても問題ない
スマートフォンで撮影した写真は、電子帳簿保存法の要件を満たせば、領収書として認められます。
本記事では、写真データで領収書保存が認められる根拠や具体的な手順、さらに原本の取り扱いまで解説します。領収書の管理をより効率的かつ適切に行いたい方は、ぜひ最後までお読みください。
領収書はスマホで撮影した写真で保存しても問題ない
領収書はスマートフォンの撮影データで保存でき、経費申請にも利用可能です。2016年の電子帳簿保存法の改正により、スキャナ保存の一種として、スマートフォンの撮影データの使用が認められました。
ただし、経費精算などに撮影データを使用するには、電子帳簿保存法で定められているスキャナ保存要件を満たすことが必要です。
電子帳簿保存法については、以下の記事で詳しく解説しています。
領収書を写真で保存するときに満たすべき要件
領収書を写真データで保存するには、電子帳簿保存法のスキャナ保存制度に適用する必要があります。スキャナ保存には一定のルールがあり、守らなければ法的に有効な書類とは見なされません。
領収書は「重要書類」に該当し、以下の表の要件を満たす必要があります。
| 書類の区分 ルール | 重要書類 (資金や物の流れに直結・連動する書類) | 一般書類 (資金や物の流れに直結・連動しない書類) | ||||
| 書類の例 | 契約書、納品書、請求書、領収書 など | 見積書、注文書、検収書 など | ||||
| 入力期間の制限 | 次のどちらかの入力期間内に入力すること ① 書類を作成または受領してから、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する(早期入力方式) ② それぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間(最長2か⽉以内)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する(業務処理サイクル方式) ※ ②の業務処理サイクル方式は、企業において書類を作成または受領してからスキャナ保存するまでの各事務の処理規 | |||||
| 程を定めている場合のみ採用できます | 一般書類の場合は、入力期間の制限なく入力することもできます(注) | |||||
| 一定の解像度による読み取り | 解像度200dpi相当以上で読み取ること | |||||
| カラー画像による読み取り | 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取ること | |||||
| 一般書類の場合は、白黒階調(グレースケール)で読み取ることもできます(注) | ||||||
| タイムスタンプの付与 | 入力期間内に、総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプ(※1)を、一の入力単位ごとのスキャナデータに付すこと ※1 スキャナデータが変更されていないことについて、保存期間を通じて確認することができ、課税期間中の任意の期間 を指定し、一括して検証することができるものに限ります ※2 入力期間内にスキャナ保存したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができます | |||||
| ヴァージョン管理 | スキャナデータについて訂正・削除の事実やその内容を確認することができるシステム等又は訂正・削除を行うことができないシステム等を使用すること | |||||
| 帳簿との相互関連性の確保 | スキャナデータとそのデータに関連する帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと | (不要) | ||||
| 見読可能装置等の備付け | 14インチ(映像面の最大径が35cm)以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びに操作説明書を備え付けること | |||||
| 白黒階調(グレースケール)で読み取った一般書類は、カラー対応でないディスプレイ及びプリンタでの出力で問題ありません(注) | ||||||
| 速やかに出力すること | スキャナデータについて、次の①~➃の状態で速やかに出力することができるようにすること ①整然とした形式 ②書類と同程度に明瞭 ③拡大又は縮小して出力することができる ➃4ポイントの大きさの文字を認識できる | |||||
| システム概要書等の備付け | スキャナ保存するシステム等のシステム概要書、システム仕様書、操作説明書、スキャナ保存する手順や担当部署などを明らかにした書類を備え付けること | |||||
| 検索機能の確保 | スキャナデータについて、次の要件による検索ができるようにすること ① 取引年⽉日その他の日付、取引金額及び取引先での検索 ② 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索 ③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索 ※ 税務職員による質問検査権に基づくスキャナデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②及び③の要件は不要 | |||||
引用:国税庁「はじめませんか、書類のスキャナ保存」
スキャナ保存制度を活用して領収書を写真で保存する際は、速やかに入力する必要があります。具体的には、以下のいずれかの方式を選択し、定められた期間内に入力しなければなりません。
- 早期入力方式:領収書の受領後、おおむね7営業日以内に入力
- 業務サイクル方式:業務処理サイクル(最長2カ月)+おおむね7営業日以内に入力
保存するデータには、改ざん防止のため「タイムスタンプ」の付与が必要です。タイムスタンプの付与は、税務署が認める方法で行う必要があるため、対応している会計ソフトやクラウドサービスを利用するのがよいでしょう。
タイムスタンプの付与については、以下の記事で解説しています。
関連記事:電子帳簿保存法のタイムスタンプとは|仕組みや改正の変更点、不要なケースなど解説
領収書を電子データで保存する場合、必要な領収書を迅速に検索できる仕組みを整えておく必要があります。具体的には「取引年月日」「取引金額」「取引先の名称」などの検索条件でデータを管理することが、業務効率化につながるでしょう。
電子帳簿保存法に則した領収書の保存方法は、以下の記事を参考にしてください。
領収書を写真で保存すれば原本は破棄しても良い?
領収書を写真で保存した場合、電子帳簿保存法の要件を正しく満たしていれば、原本を破棄しても問題ありません。スキャナ保存された電子データは、電子帳簿保存法により原本と同等の法的証拠力をもつと認められています。
電子データの保存期間は、紙の領収書と同様で7年間です。期間中は電子データを確実に保管し、税務調査などで求められた際に速やかに提示できるようにしておきましょう。
領収書原本の保管方法について、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
領収書を写真で保存するメリット
スマートフォンで領収書を撮影すれば、以下のようなメリットがあります。
コストを減らせる
紙で保存する場合、保管場所、キャビネット、ファイルなどの用意が必要になったり、書類を管理する担当者の人件費もかかったりします。そこで、スマートフォンで撮影した領収書の電子データを活用すれば、コストの削減につながるでしょう。
なお法人税法により、領収書には7年間の保存義務があります。
以下は、領収書の保管方法について紹介した記事です。ぜひ参考にしてください。
関連記事:領収書の保管・管理方法は?手間と時間を削減するおすすめの方法を法人・個人事業主向けに紹介
長期にわたって保存ができる
電子データなら、長期にわたって一定の質を保ちながら保存できます。紙の領収書の場合、時間の経過とともに劣化やインクの滲みなどが発生し、汚れがつく恐れもあるでしょう。
そのため、保存義務が定められている7年が経過する前に、内容を確認できなくなるリスクもあります。一方で電子データで保存すれば、そのような心配はありません。
領収書を電子データで保存するメリットは、以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:領収書の保存期間は何年?保管方法や領収書を電子データ化するメリットも紹介
検索がしやすくなる
電子データは、キーワードや条件の指定による検索ですぐに見つけられます。紙の領収書をそのまま保管している場合、膨大な書類の中から必要なものを見つけ出すためには多くの労力と時間が必要です。
電子データ化により、そのような無駄を省きましょう。
写真で保存した領収書を使用した経費精算の手順
スマートフォンで撮影した領収書の電子データを使用して経費精算する場合の手順は、以下のとおりです。
- 申請者が領収書を撮影して電子データにする
- 申請者が経費精算の申請をする
- 上長が承認する
- 経理担当者が申請内容を確認する
- 会計ソフトにより自動仕訳を行う
- 電子帳簿保存法に対応したシステムで保存する
各手順において、すでに説明した要件を満たし、電子データによる経費精算を適切に進めましょう。
領収書を写真で保存するときの注意点
領収書を写真で保存する方法はメリットがある一方、いくつかの注意点があります。そのうち2つの注意点を解説しましょう。
保存要件に違反すると罰則が科せられる
電子帳簿保存法では、領収書を電子データで保存する際の要件や保存期間が定められています。ルールに違反した場合、罰則が科せられる可能性もあるので注意してください。
たとえば、青色申告の承認が取り消されたり、推計課税を支払わなければならなくなったりする可能性があります。悪質な場合は会社法違反として、罰則金100万円以下が科されることもあるでしょう。
参考:e-Gov法令検索「会社法」
電子帳簿保存法に関連した罰則については、以下の記事をお読みください。
関連記事:電子帳簿保存をやらない場合の懸念は?罰則・リスクとシステム導入の必要性を解説
電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を検討する必要がある
領収書を電子データ化する場合、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件に沿った形で行わなければなりません。手作業で要件を満たすことも可能ですが、手間がかかりミスも発生しやすくなります。そこでおすすめなのが、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入です。
システム導入によって、タイムスタンプの付与や検索機能の確保が自動化され、業務効率を向上できます。導入にはコストがかかりますが、長期的な視点で見ると、業務効率化やコンプライアンス強化によるメリットの方が大きいといえるでしょう。
経費精算システムのメリットや選び方は、下の記事を参考にしてください。
領収書の写真で経費精算をするなら、電子帳簿保存法に対応している「バクラク経費精算」
領収書は、電子帳簿保存法の要件を満たせば、スマートフォンで撮影して保存し、経費精算に活用できます。
ただし、要件を満たさない場合は罰則の対象となる可能性があります。法令遵守と業務効率化の両立を目指すなら、ぜひバクラク経費精算をお試しください。
バクラク経費精算は、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しており、申請時に要件を満たさない証憑を自動で検知できます。経理担当者の負担を軽減し、スムーズな経費精算をサポートしてくれるでしょう。
法対応の手間を減らし経費管理を効率化したい方は、ぜひバクラク経費精算の導入をご検討ください。

以下の内容がわかるバクラクビジネスカードの資料をプレゼントします。
①バクラクビジネスカードの製品概要/主な機能紹介
②バクラクビジネスカードによる経理業務の改善事例
③小口現金や立替精算の削減を実現する方法
\簡単30秒!資料だけの情報が盛りだくさん/
実際の経費精算の運用はどのように行っている?
企業における経費精算の実運用については、なかなか公開されることがなく、それぞれが独自にフローやシステムを構築していることが多いと思われますが、「バクラク経費精算」を提供するLayerXは、実際の経費精算運用をまとめた資料を公開しております。
電子帳簿保存法への対応などの法改正にどのように対応したのか、経費精算の承認ステップはどのように構築したのかなどが記載されておりますので、ぜひご一読ください。下記のボタンまたは画像よりダウンロード可能です。