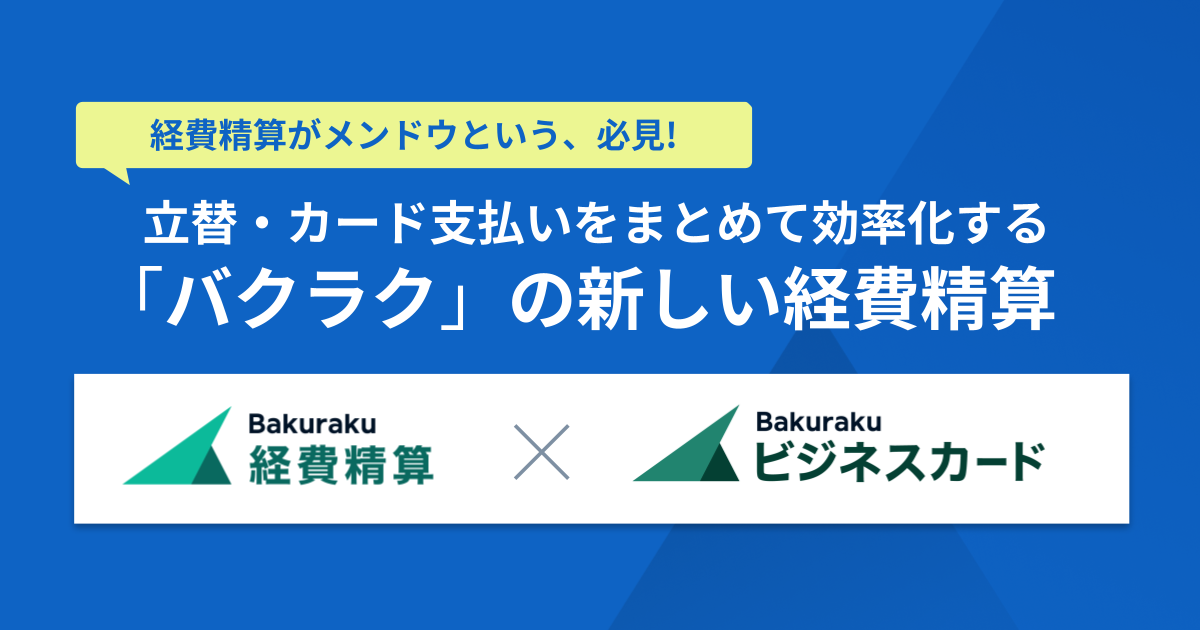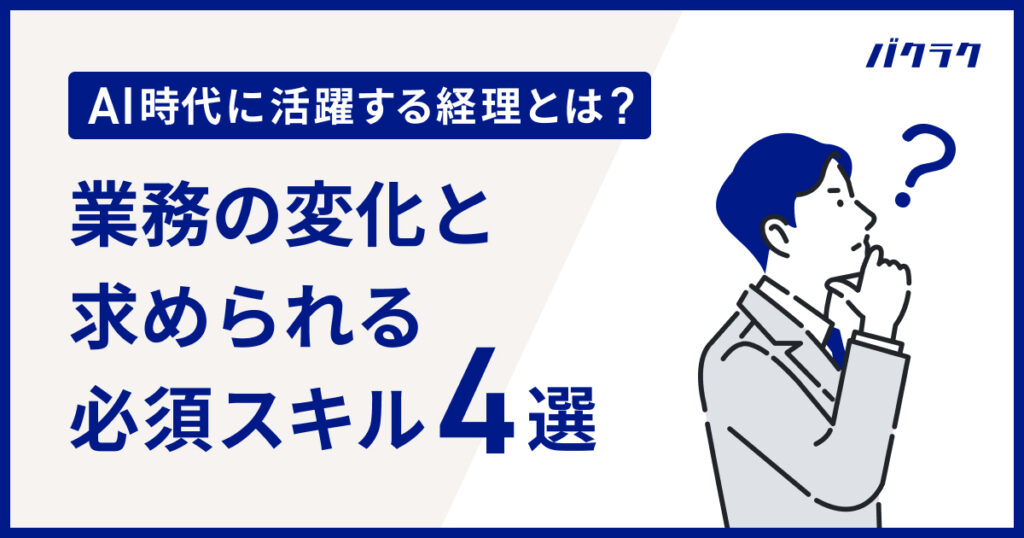経費精算業務を効率化する方法は?よくある課題と解決策を具体的に解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2026-02-12
- この記事の3つのポイント
- 経費精算では、ヒューマンエラーや手続きで発生する時間、管理の煩雑さが課題として挙げられる
- 実際に経費精算業務を効率化するためには、システムの導入などいくつかの方法がある
- システムを取り入れる際は、社内規定に合わせた設定や既存ツールとの連携など、注意点を意識する
経費精算とは、従業員が業務で発生した費用を申請し、会社が精算する手続きです。手作業での経費精算はミスや負担が発生しやすいため、効率化が求められます。
本記事では、経費精算の流れや課題、具体的な効率化の方法について詳しく解説します。
立替・カード支払いをまとめて効率化
本資料では、立替精算と法人カードの運用をシームレスに統合し、経理業務の圧倒的な効率化とガバナンス強化を同時に実現する新しい経費精算の仕組みを解説します。
経費精算とは?
経費精算とは、従業員が業務のために支払った費用を会社が払い戻す手続きです。経費精算は「実費精算」「仮払精算」の2種類があります。
経費精算は単なる払い戻し手続きではなく、会社の財務管理やコスト削減にも影響を及ぼす重要な業務です。適切に管理すれば、不正利用の防止や予算管理の精度向上につながります。
経費精算のやり方については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:経費精算のやり方を徹底解説!経費の定義や種類、精算の流れなど
小口精算
小口精算とは、会社の業務において発生する少額の経費を、スムーズに処理するための仕組みです。たとえば以下のように頻繁に発生する経費が、小口精算の対象になります。
- 交通費
- 会議費
- 消耗品費など
これらの支払いには「小口現金」と呼ばれる一定額の現金を社内で管理し、そこから経費を精算する方法が一般的です。
小口現金を利用する場合、企業は現金出納帳を用いて現金の出入りを管理し、正確な記録を残します。しかし小口現金の管理は手間がかかるため、最近では給与と合算して支給する方法や、電子マネーによる送金を導入する企業も増えています。
交通費精算
交通費精算とは、業務上の移動にかかった交通費を会社が負担し、精算する手続きのことを指します。たとえば以下のような交通費が対象です。
- 通勤
- 顧客訪問
- 営業活動の際に利用した電車やバス、タクシーなど
交通費を精算する際は単に金額を申請するだけでなく、移動ルートや利用した交通手段の明記が求められます。移動の多い企業や営業の多い職場では交通費の申請が頻繁に発生するため、経費精算業務の負担が大きくなることが課題です。
近年ではICカードの履歴を活用した精算システムの導入や、交通費精算アプリの活用など、より効率的な方法を取り入れる企業も増えています。
旅費精算
旅費精算とは、遠方への出張時に発生した費用を精算する手続きです。一般的な交通費精算とは異なり、比較的高額な経費が対象となるため、現金手渡しではなく振込での精算が行われることも多いです。
旅費精算は、以下が対象に含まれます。
- 宿泊費
- 出張日当
- 飲食費
- 出張先での移動にかかる交通費など
企業によっては上限額や精算ルールが決まっており、事前に申請して承認を得なければいけない場合もあります。
経費精算の流れ
経費精算の実際の流れについて、実費精算と仮払精算のそれぞれの方法を解説します。
実費精算の流れ
実費精算は、従業員が業務で発生した費用をいったん立て替え、後から会社に精算申請をして払い戻してもらう方法です。経費精算のなかで一般的な方法であり、多くの企業で採用されています。
実費精算の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 従業員が業務で必要な経費を立て替える
- 経費を証明するレシートや領収書を保管する
- 社内ルールに従い経費精算書を作成する
- 上司や承認者に経費精算書を提出し承認を受ける
- 経理部門が精算書を確認し会計処理を行う
- 承認後従業員に立て替えた経費が払い戻される
この方法は企業側が無駄な仮払いを防ぎ、経費の管理をシンプルにできる点がメリットです。一方で従業員にとっては、一時的に個人で費用を立て替えるため、負担が大きくなるケースもあります。
従業員が一時的に立て替える「立替経費」について詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:立替経費とは何?精算手順や注意点、負担軽減方法を解説
仮払精算の流れ
仮払精算とは業務に必要な経費を事前に概算で支給し、後から実際の支出額を調整して精算する方法です。主に出張や高額な経費が発生する業務において利用されます。
仮払精算の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 従業員が業務で必要な経費の概算を算出して仮払申請書を作成・提出する
- 承認後、従業員へ仮払い金が支給される
- 従業員は仮払い金を使って必要な経費を支払い領収書やレシートを保管する
- 業務終了後実際にかかった費用の仮払精算書を作成し領収書とともに提出する
- 経理部門が確認後、会計処理を行う
- 実際の支出額と仮払い額の差額を調整する
仮払精算のメリットは、従業員の金銭的負担を軽減できる点です。ただし、仮払申請と精算の手続きが必要なので、手間が増えることがデメリットとして挙げられます。
仮払精算について詳しくは、以下のページで解説しています。
経費精算業務のよくある課題
経費精算業務は、企業のコスト管理や、財務の透明性確保に欠かせないプロセスですが、多くの企業で非効率な作業やヒューマンエラーが発生しやすいという課題があります。
ここでは経費精算業務でよく見られる課題と、それが業務に与える影響について詳しく解説します。
経費精算の課題については、以下の記事を参考にしてください。
計算ミスや入力ミスなどが起こりやすい
手作業で精算書を作成する場合、以下のミスが発生しやすくなります。
- 金額の入力ミス
- 計算間違い
- 仕訳ミス など
またミスが起こるのは、経理担当者だけではありません。従業員側でも領収書の添付忘れや経費精算書との金額の相違、日当の計算ミスなどが発生することがあります。
さらに経費精算書がExcelで管理されている場合、フォーマットが統一されていなかったり、誤って関数を削除したりするリスクもあるでしょう。
こうしたミスが発生すると、修正作業が発生して経費精算の処理が遅れるだけでなく、最終的な財務データの正確性にも影響を与える可能性があります。
申請書類の差し戻しで時間がかかる
以下のような不備があると、経理担当者は確認後申請者へ差し戻しをしなければならず業務の遅延につながります。
- 記入漏れ
- 誤字脱字
- 必要な領収書の添付忘れ など
このやり取りが何度も発生すると経理担当者・申請者双方にとって業務の負担が増大し、処理の遅延が発生します。
従業員に払い戻すまでに時間がかかる
手作業で経費精算を行う企業では、経費精算書の作成をオフィスに戻ってから処理をしなければならず、時間がかかるでしょう。
承認者が不在だった場合は書類の承認が滞り、払い戻しの処理が遅れてしまうこともあります。払い戻しに時間がかかると、業務負担の増加や会計処理の遅れなどのリスクが発生します。
領収書や小口現金の管理が煩雑になりやすい
領収書の管理が煩雑になりやすいことも、経費精算業務の課題の一つです。日本の法人税法では領収書は最低7年間、場合によっては10年間の保管が義務付けられているため、企業が管理しなければならない領収書の量は年々増えていきます。
また単に保存するだけでなく、必要なときにすぐに取り出せる状態にしておかなければなりません。紙の領収書が多い企業では保管スペースの確保も必要で、経理担当者の負担も増大します。
小口現金の管理も同様に、頻繁な出入りが発生するため、現金の出納帳管理や領収書の整理が煩雑になりがちです。
経費精算業務を自動化・効率化すべき理由
この章では、経費精算業務を自動化・効率化すべき理由を解説します。
働き方改革を推進できる
経費精算業務を自動化・効率化すべき理由として、働き方改革の推進が挙げられます。労働環境の改善をはじめとした働き方改革の実現に向けて、企業にはさまざまな部門・業務における効率化が求められているのが現状です。
そのなかでバックオフィス業務のアナログからの脱却・改善施策の一つとして、経費精算業務の自動化・効率化に取り組む企業が増えています。
企業全体の業務効率化につながる
営業部や労務部では、経費の立て替えが頻繁に発生しており、経費精算にもある程度以上の時間や手間が割かれているケースがあります。
そこで経費精算システムなどの自動化により経費精算を効率化すると、経費の立て替えをしている各部署の負担軽減も実現できます。
また、手作業によるミスが減ることで修正や再申請にかかる時間も減らすこともできるでしょう。
本業務に時間やリソースを割きやすくなる
経費精算にかかる時間を削減できれば、従業員は本業務に時間やリソースを割きやすくなります。経費精算のための書類作成やデータの入力などは、各部署の本業務とは基本的に関係ありません。経費精算に時間が多くかかっている場合、その分だけ本業務にかけられる時間が少なくなります。
コア業務へ集中できるようになると、生産性の向上や業績アップも目指しやすくなるでしょう。最終的には、従業員の満足度を高めることにもつながります。
経費精算業務を効率化する方法
効率化の方法は複数あるため、自社の状況に応じて取り入れることが不可欠です。ここでは経費精算業務を効率化する施策について、具体的に解説します。
ルールをマニュアル化して従業員へ周知する
経費精算のルールを明確にし、マニュアル化して周知することは、業務の効率化に欠かせません。ルールを統一すれば、どの経費が認められるのか、どのような手続きが必要なのかを従業員が理解しやすくなり、申請ミスや差し戻しを減らせます。
ルールを決めることは最初は手間がかかるものの、一度マニュアル化してしまえば長期的に業務の効率化が期待できます。また定期的に見直しを行い、業務の変化に合わせてアップデートすることも重要です。
書類を電子化してペーパーレス化する
経費精算業務を効率化するためには、書類を電子化し、ペーパーレス化を進める方法も有効です。紙の書類は作成や管理に手間がかかり、申請や承認の遅れ、紛失のリスクが生じやすいですが、電子化すればスムーズな処理が可能です。
経費申請をシステム上で完結できるようにすれば、入力ミスの削減や承認フローの迅速化が実現でき、業務負担を軽減できます。また電子帳簿保存法の要件を満たせば、領収書や申請書を電子データとして管理できるため、紙の保管も不要です。
ただし紙と電子が混在すると二重管理の手間が発生し、かえって業務が煩雑になることがあります。そのため経費精算の流れ全体を電子化し、一貫してペーパーレス化を進めることが重要です。
経費精算のペーパーレス化については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:経費精算のペーパーレス化で経理業務の負担軽減!実施する方法や期待できる効果とは?
法人カードを導入する
経費精算業務を効率化する方法としては、法人カードの導入も挙げられます。経費精算に法人カードを利用すると、従業員がお金を立て替える負担や、経理担当者が費用を払い戻す手間が削減できます。
法人カードを使った経費精算の効率化については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:法人カードで経費精算するメリット・デメリットとは?流れや注意点も解説
経路検索やICカードで交通費を自動計算
経路検索やICカードなどを活用して交通費を自動計算すれば、交通費の精算もスムーズになります。
交通費の精算は多くの手間がかかるうえに、頻度も高い業務です。しかし、確認を怠ると金額が水増しされたり「カラ出張」の申請が行われたりするリスクがあります。
交通費の自動計算を実現できれば、手間や時間をかけずに正しい交通費の金額を計算できます。各従業員や経理担当者にかかる負担を大幅に削減できる可能性が高いでしょう。
Suica®やPASMO®を利用した経費精算の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:Suica®やPASMO®を利用した経費精算の流れ!注意点や効率化の方法も解説
経費精算システムを導入する
経費精算の効率化には、経費精算システムの導入が効果的です。経費精算システムには、経費精算の作業を簡略化するために役立つ便利な機能が多く搭載されています。
たとえば、領収書を撮影してデータを取り込むOCR機能、交通費の計算を自動化する機能、システム上で承認や申請状況の確認などができる機能などがあります。
また、会計ソフトや給与システム、勤怠管理システムなどと連携させれば、経費精算システムの経費データへの反映が可能です。反映作業が不要となり、経理担当者の負担が軽減されます。
経費精算システムについて知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
経費精算システムを導入する際の注意点
経費精算業務の効率化には、経費精算システムの導入をはじめとしたシステム化・自動化がおすすめです。ただし、社内規定に合わせた設定や既存システムとの連携可否、入力精度についてよく確認しておく必要があります。
ここでは、経費精算システムを導入する際の注意点を解説します。
社内規定に合わせた設定が必要
経費精算システムを導入した場合、あらかじめ社内規定に関する設定を行うと、社内規定に反した申請を自動的にチェックできます。具体的には、問題がある申請に対してアラートを表示したり、申請を拒否したりすることが可能です。
特に交通費は計算が複雑ですが、社内規定に合わせた設定をしておけば、ガイドの役割や誤った申請の防止に役立ちます。
一方で、設定が不適切な場合、経費精算の申請に混乱をきたしたり、従業員が使いにくいと不満を感じたりする可能性があります。適切に設定を行うよう、十分注意しましょう。
経費精算規定への記載項目などについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:経費精算規定(ルール)への記載項目や作成のポイントなどを解説
既存ツールとの連携可否を確認する
経費精算業務のために新しいシステムを導入するうえでは、経費精算と親和性のある業務で使用している既存ツールやシステムに関する確認も必要です。導入を希望する新しいシステムと既存ツールの相性を確認し、連携できるかチェックしましょう。
具体的には、会計ソフト、給与システム、勤怠管理システム、交通経路の検索ソフトなどが対象です。
入力精度を把握する
OCRなどの自動入力が可能なシステムを導入する場合、入力精度もチェックしましょう。どの程度正確にデータを読み取れるかは、システムによって大きな差があります。
自動入力が可能でも、入力精度が低ければ手直しが必要になり、余計に業務の負担になってしまう場合もあります。システムを選ぶ際は、なるべく入力精度が高いものを選びましょう。
スマホで申請・承認が可能な「バクラク経費精算」で効率化
経費精算業務を効率化するには、スマホから簡単に申請・承認ができるシステムの導入が有効です。「バクラク経費精算」は、スマホアプリを活用して複数枚の領収書を自動で読み取り、一括アップロードできるため、手作業による入力の手間を削減できます。
高精度のAI-OCRを搭載し、軽減税率の自動判定にも対応しているため、経理担当者の確認作業を大幅に軽減できます。
さらに領収書の使いまわしを自動判定するなど、申請者・承認者・経理担当者を支援するミス防止機能を備えており、正確でスムーズな経費精算が可能です。
手間のかかる経費精算業務を効率化し、業務負担を大幅に削減したい方は、ぜひ「バクラク経費精算」の導入を検討してください。