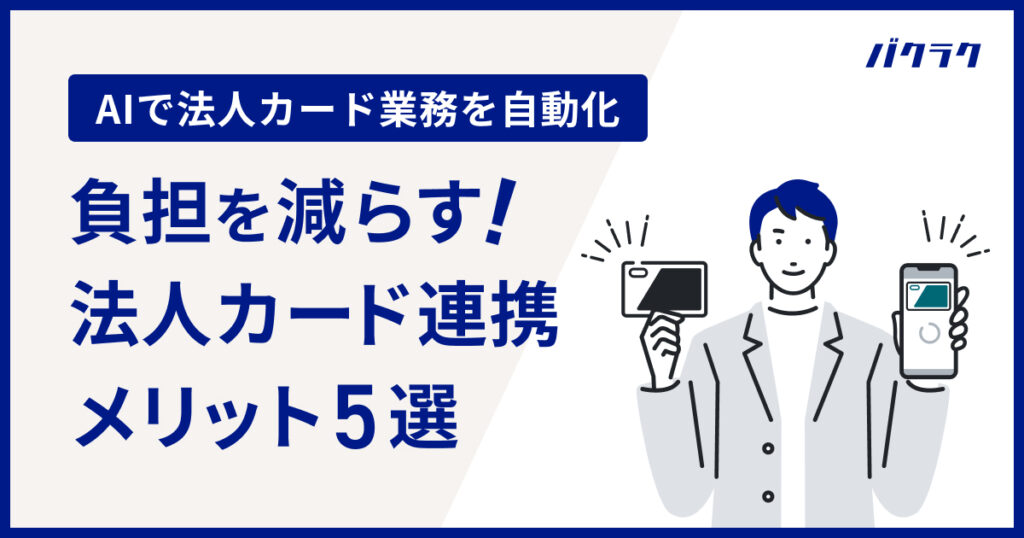請求書をペーパーレス化するメリット・デメリット|進め方も紹介
- この記事の3つのポイント
- ペーパーレス化で書類の保管スペース削減・請求業務の効率化・リモートワークの促進が期待できる
- 難点は電子帳簿保存法の対応やセキュリティ対策が必要で、システム導入や運営にコストがかかる点
- 社内の運用体制・セキュリティ体制を整備してから社内外へ通達するのが、一般的な流れ
近年、書類や帳票類をデジタルで管理する「ペーパーレス化」が注目を集めています。ペーパーレス化には多くのメリットがある一方でデメリットも存在するため、理解を深めた上で導入を検討することが重要です。
本記事では、請求書をペーパーレス化するメリット・デメリットを詳しく紹介します。導入の具体的な流れも解説しますので、ペーパーレス化を検討中の方はぜひ参考にしてください。
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
請求書のペーパーレス化が促進された背景
請求書のペーパーレス化が進む背景に、コロナ禍のリモートワーク推進があります。出社頻度の減少に伴って郵送やファックスでの請求書送付・受領が難しくなり、クラウドシステムやメールでのやり取りが普及しました。
紙ベースのやり取りは以前から効率面が問題視されており、コロナ禍を機に業務効率化を図る目的でペーパーレス化が進んだ側面もあるでしょう。
なお、請求書のペーパーレス化に伴い「電子請求書」の導入も進んでいます。電子請求書の導入方法やメリット・デメリットについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
請求書をペーパーレス化するメリット
請求書をペーパーレス化する主なメリットは、以下の3点です。
- 書類の保管スペースが不要
- 請求業務を効率化できる
- リモートワークの促進につながる
紙を使わず請求書をやり取りすると、日々の経理業務がどのように変化するのか詳しく見ていきましょう。
書類の保管スペースが不要
請求書をペーパーレス化した場合、書類の保管スペースが不要です。請求書の発行だけでなく控えの保管も紙で行う場合、7年間の保管が義務付けられていることから大幅なスペースの削減が期待できます。
事業年度や取引先ごとに請求書をフォルダ分けしておけば、過去の請求書を探す際にキーワード検索を活用しながら容易に見つけられるメリットも持ち合わせています。
参考:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
請求業務を効率化できる
請求書をペーパーレス化すると、以下のように請求業務を効率化できるのもメリットの一つです。
- 社内外を問わず請求書のやり取りがスムーズになる
- 請求書の印刷や封入、発送作業が不要になる
- 請求書発行システムを導入した場合は請求書の受取や入金を自動化できる
請求書を紙で発行した場合、最終承認までに複数の部署や担当者間をやり取りしなければなりません。記載ミスなどが発覚して修正が必要になると、より多くの手間と時間がかかります。
発行のたびに印刷・封入・発送という煩雑な業務が生じ、ほかの経理業務に支障をきたす可能性もあるでしょう。
ペーパーレス化をすれば、こうした問題を解消しやすくなります。なお、請求書発行システムを導入すると請求書の受取や入金も自動化でき、さらなる業務効率の向上が期待できます。
リモートワークの促進につながる
ペーパーレス化することで、リモートワークがしやすい環境になります。パソコンと通信環境さえあれば請求書の発行ができるため、作成した請求書の印刷や押印などのために出社する必要がありません。
自宅はもちろんのこと、移動中や出張先などのあらゆる場面で仕事ができるのはペーパーレス化の強みといえます。ペーパーレス化でリモートワークがしやすくなれば、会社から離れた地域に住む人を積極的に採用できるメリットも得られるでしょう。
請求書をペーパーレス化するデメリット
利便性だけに着目して請求書をペーパーレス化すると、失敗や後悔を招く可能性があります。メリットだけでなくデメリットも理解した上で、ペーパーレス化の必要性を慎重に検討しましょう。
電子帳簿保存法に対応する必要がある
ペーパーレス化をする際に避けて通れないのが、電子帳簿保存法への対応です。電子帳簿保存法は、所得税法や法人税法に関わる帳簿・書類に関して電子データでの保存も認められるという法律ですが、一定の要件を満たさなければなりません。
一定の要件とは「真実性と可視性の確保」です。具体的には社内規定の整備や、タイムスタンプの付与が可能なシステムの導入などが求められるでしょう。
電子帳簿保存法については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
関連記事:電子帳簿保存法とは?2024年義務化の内容や注意点などわかりやすく解説
システム導入や運用体制の構築にコストがかかる
請求書の完全なペーパーレス化には専用システムの導入が効果的ですが、導入・運用にコストがかかるという懸念点があります。
月額の維持費用が経営状況を圧迫する可能性があるほか、システム導入の比較検討や新たな運用体制の構築に人的コストも発生する点を理解しておきましょう。
結果的には人件費削減や業務効率化などにつながるケースが多いものの、費用対効果を見極めた上でペーパーレス化の必要性やシステム導入を検討することが重要です。
ITリテラシー教育・セキュリティ対策が必要
請求書のペーパーレス化には、従業員へのITリテラシー教育やセキュリティ対策が必要不可欠です。
従業員のITリテラシー不足やサイバー攻撃によってデータの漏洩・消失が発生すると、会社の信頼を失いかねません。社員研修を実施するほか、セキュリティ対策として万全のシステム構築を行って、健全な経営体制の維持に努めましょう。
請求書をペーパーレス化する流れ
ここからは、請求書をペーパーレス化する流れについて解説します。紙の請求書からスムーズに移行できるよう、大切なポイントを押さえておきましょう。
1.社内の運用体制を整える
ペーパーレス化が決定したら、まずは自社の運用体制を見直して継続運用できる仕組みを整える必要があります。自社完結とシステム導入のどちらにするか検討しつつ、請求書の作成・確認・承認フローの電子化に向けて仕組みを構築しましょう。
自社完結は運用コストを削減できるメリットがありますが、取り扱う件数が多かったり多彩な機能を求めたりする場合はシステムの導入がおすすめです。移行後にスムーズな運用ができるよう、人員配置の調整やマニュアル作成なども忘れず行いましょう。
ただし自社がペーパーレス化しても、すべての取引先が対応可能とは限りません。取引先の意向を整理し、紙でのやり取りを希望する相手にはどのように対応するか決めておくことも重要です。
2.セキュリティ体制を整備する
ペーパーレス化には、セキュリティ体制の整備も欠かせません。
セキュリティ性を高めるためには専用システムの導入が効果的で、タイムスタンプの付与や受領・保存の履歴保管、電子署名機能などが搭載されたものがおすすめです。加えて、電子帳簿保存法対応のシステムであれば運用がよりスムーズになるでしょう。
万が一情報漏洩やデータ改ざんが発生した場合、どのように対応するかもあわせて検討しておいてください。
3.社内外へ通達する
運用可能な体制が整ったら、社内外へ通達を行います。自社の従業員に対しては事前に決めた運用ルールを共有し、必要に応じてシステムの運用方法やITリテラシーに関する研修などを実施してください。
取引先にはペーパーレス化に至った経緯を説明しつつ、今後の取引についての意向を確認しましょう。相手がペーパーレス化に難色を示す場合は、受領側のメリットを伝えることで理解を得られるケースもあります。
無理にペーパーレス化を押し付けると関係悪化につながる可能性もあるため、紙でのやり取りを強く希望する取引先には今まで通り対応しましょう。
請求書をペーパーレス化するなら「バクラク請求発行」がおすすめ
請求書のペーパーレス化は、書類の保管スペースが不要になるほか、業務効率化を促進できリモートワークとの相性が良いといったメリットがあります。
一方で、セキュリティ対策やITリテラシー教育が必要なほか、電子帳簿保存法などの法律に対応しなければならず、システム導入も視野に入れる必要があるでしょう。
請求書をペーパーレス化するシステム導入を検討する際は、請求書の作成から発行までを一元管理できる「バクラク請求書発行」の導入がおすすめです。電子帳簿保存法にも追加の負担なく対応できるほか、取引先が紙でのやり取りを希望する場合は郵送代行サービスを利用できます。
請求書のペーパーレス化を予定している方は、バクラク請求書発行の導入をぜひご検討ください。サービス内容については、以下のページで詳しく解説しています。