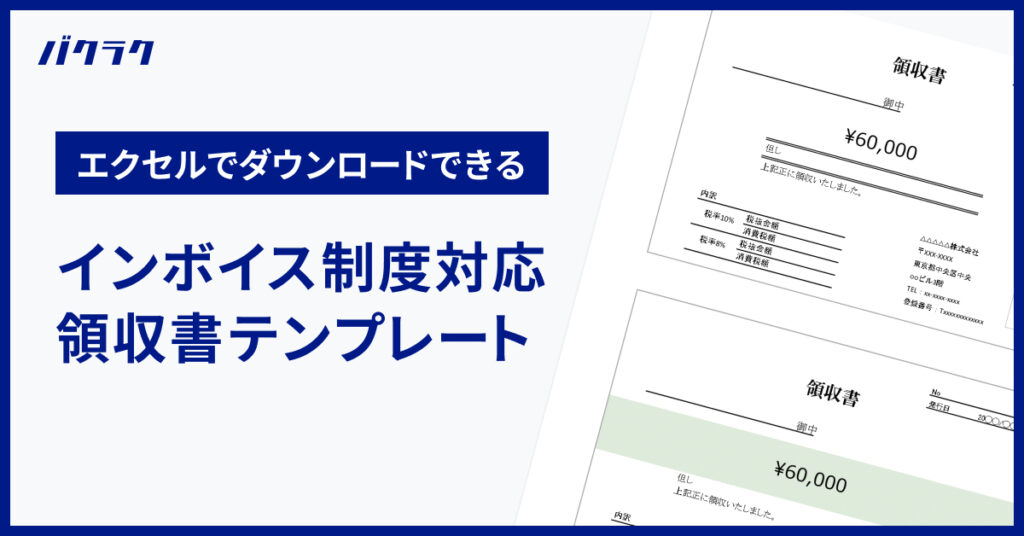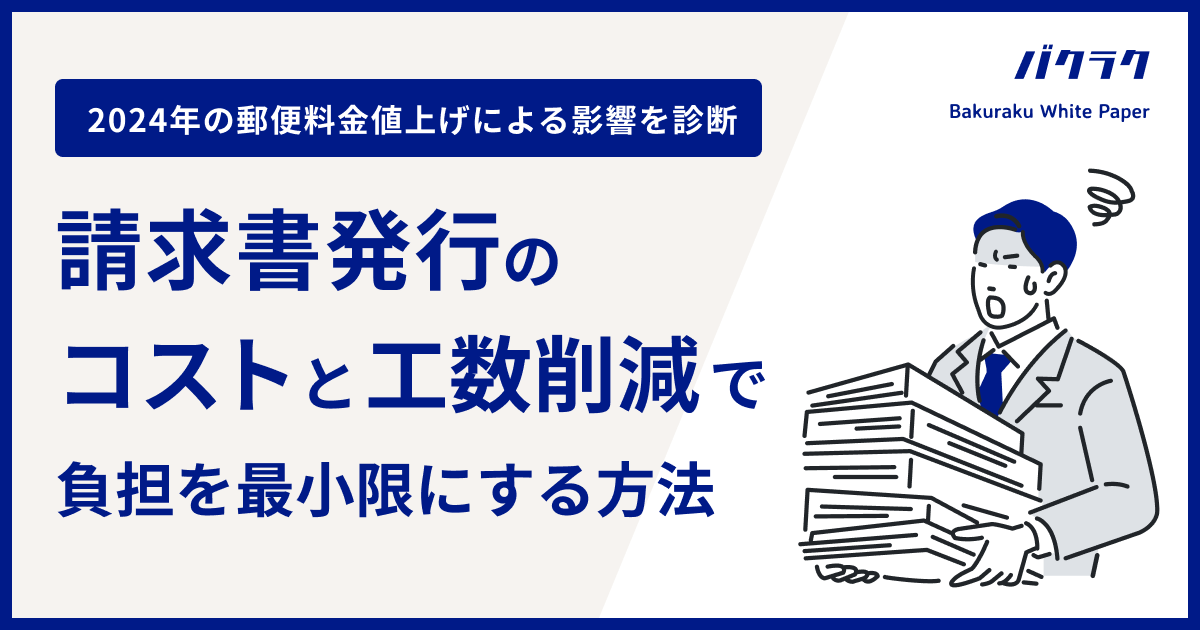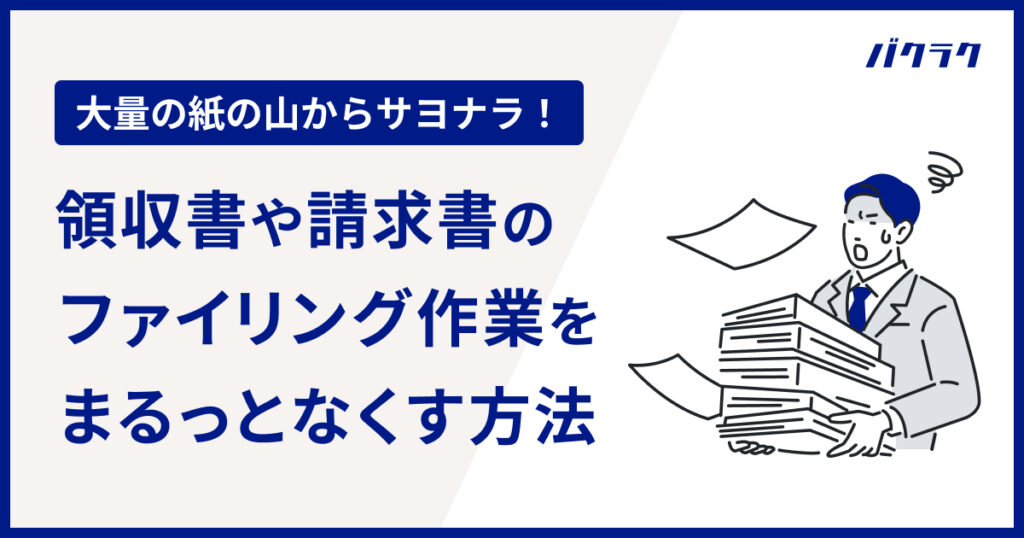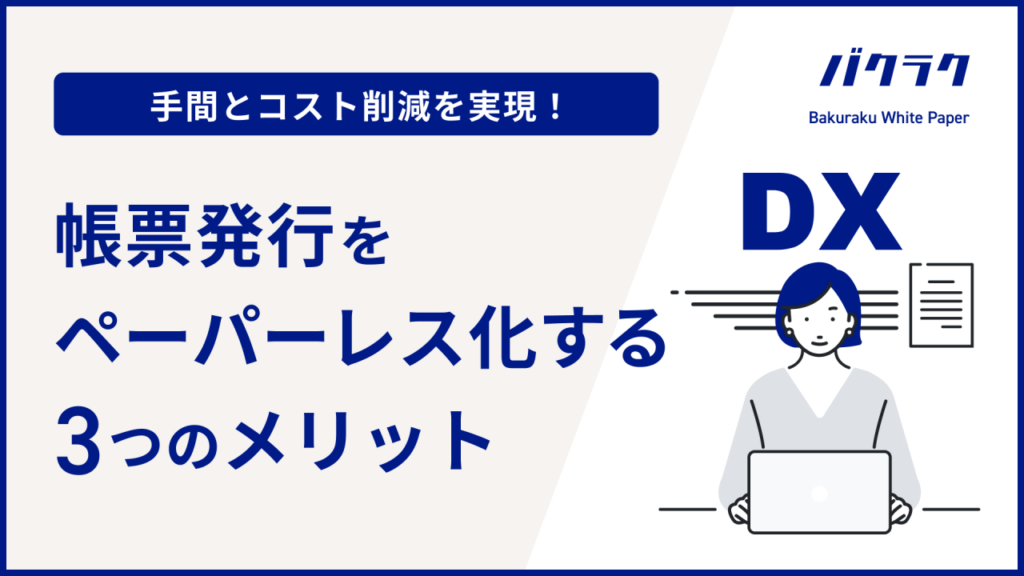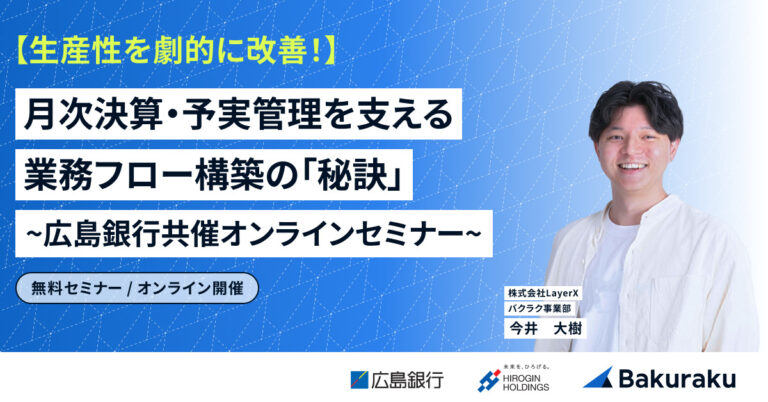
領収書の宛名や金額に間違いがある場合の訂正方法は?項目別に解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-04-25
- この記事の3つのポイント
- 領収書は訂正しても問題ないが、不正防止のためには極力再発行をするのが望ましい
- 訂正の際は誤った箇所に二重線を引き、上から訂正印を押した付近に正しい内容を記載する
- 取引先の名刺を参考に下書きを作成する、領収書にミスがないか細部まで確認することが重要
領収書の発行後に宛名や金額の間違いが発覚し、訂正が必要になるケースもあるでしょう。領収書は原則訂正が認められていますが、不正のリスクがあることから適切な対応が求められます。
本記事では、領収書の訂正方法や注意点について詳しく解説します。間違いを防ぐ方法も紹介しますので、今後の業務にお役立てください。
インボイス制度への対応方法も解説 !そのまま使える領収書テンプレートのご紹介
インボイス制度の要件を満たした領収書のテンプレート3点セット(明細あり、明細なし)をダウンロードいただけます。
インボイス制度対応の留意点と対応のポイントについても記載しています。
領収書の宛名や金額に間違いがある場合の訂正方法は?項目別に解説
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
領収書は訂正しても問題ない?
領収書にはさまざまな記載項目があるため、宛名や金額、但し書きなどに間違いが生じることもあるでしょう。領収書の発行者は、記載内容の訂正が原則可能です。
まずは、領収書の訂正に関する2点の基本ルールを紹介します。
訂正するときは二重線と訂正印を使う
領収書を訂正する際は、二重線と訂正印を使用するのが一般的なルールです。記載を誤った箇所に二重線を引き、上から訂正印を押します。
社内の書類であれば担当者の印鑑を訂正印としても問題ありませんが、取引先宛ての場合は角印などの社印を使用するのが適切です。正しい文字や数字は、訂正箇所の付近にわかりやすく記載しましょう。
特別な事情がない限り再発行が望ましい
間違いのある領収書は、特別な事情がない限り再発行をするのが望ましいといえます。特に、以下のいずれかに該当する場合は、訂正ではなく再発行で対応しましょう。
- 発行した領収書に「訂正したものは無効」と記載している場合
- 取引先の社内規定により、書類の訂正が認められない場合
領収書は確定申告に欠かせない書類であり、不備があると取引先に迷惑をかける恐れがあります。税務調査などで、不適切な訂正との指摘を受けることもあるでしょう。その場合、発行者が私文書偽造等の罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
参考:e-Gov法令検索「刑法第159条」
領収書の不正事例や対策について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【項目別】領収書に間違いがある場合の対処法
領収書の日付・宛名・金額のいずれかに間違いがある場合は、訂正ではなく再発行で対応するのが適切です。本章では、それぞれの具体的な対処法について詳しく解説します。
宛名の間違い
領収書が法的効力を発揮するには、宛名が必須です。領収書の宛名に誤りがあると、税務署に正式な書類として認めてもらえない可能性があります。
宛名のミスは取引先にネガティブな印象を与えかねないことからも、謝罪の上で再発行をするのが望ましいでしょう。
金額の間違い
金額は、領収書において特に重要な項目の一つです。金額の間違いは取引先から不信感をもたれる原因となりうるため、誤りが発覚した場合は迅速な対応が求められます。
対応の遅れは双方に損失が生じる可能性があることを踏まえて、極力早めに領収書を再発行しましょう。
日付の間違い
領収書の日付を変更すると、納税額に影響する可能性があります。そのため、日付の誤りは原則として再発行で対応するのが適切です。
たとえば、実際の取引とは異なる日付を記載して特定期間の支出を増やした場合、意図的に納税額を下げる不正行為とみなされます。取引先から日付の訂正を依頼された場合は、事実確認の上で適切に対応しましょう。
領収書を訂正する際の注意点
やむを得ない事情で領収書の再発行ができず、訂正で対応することもあるでしょう。訂正が違法行為とみなされないために、注意すべき4つのポイントを紹介します。
修正テープや修正ペンを使わない
領収書の訂正には、修正テープや修正ペンを使用すべきではありません。領収書の信頼性を担保するには、誤った箇所に二重線を引いて訂正印を押すのが基本です。訂正前後の状況を確認できれば、不正を疑われにくくなります。
摩擦熱でインクが消えるタイプのペンも同様の理由から、領収書の訂正には使用を避けましょう。
訂正印はシヤチハタ以外にする
領収書を訂正する際の印鑑に、明確な決まりはありません。しかし、容易に入手できるシヤチハタなどの浸透印は、訂正には不向きです。
発行者が訂正したことを証明できるように、角印などの社印を使用しましょう。
訂正の下書きをする
領収書を訂正する際は、記載を誤らないように下書きをするのがおすすめです。
訂正で書き損じをすると、二重線や訂正印が増えて領収書の視認性が低下します。訂正の際に記載を誤った場合は、再発行で対応しましょう。
発行者のみが訂正できる
領収書の訂正が認められるのは、発行者のみです。受領者が間違いに気付いても、発行者でなければ訂正できないため注意してください。
記載事項の抜け漏れがあった場合に、受領者が記入することも認められません。双方がやり取りを行い、適切に対応することで信頼関係も深まりやすくなるでしょう。
領収書の訂正・再発行のポイント
領収書を訂正・再発行した際は、その旨を書面上に残すことが重要です。
訂正の場合は、二重線と訂正印によって証明できます。再発行であれば、以下のいずれかの対応により、再発行文書であることを明確にしましょう。
- 赤字で「再発行」と記載する
- 専用の印鑑を押印する
- 枝番を振る
間違いのある領収書は破棄せず、適切に保存する必要があります。取り違え防止のため、見やすい箇所に×印などを記載しておきましょう。
なお、領収書の再発行に法的な義務はありません。紛失を理由に再発行を依頼された場合は、不正の可能性を考慮して対応を見送るのも賢明といえるでしょう。
領収書の再発行を依頼された場合の対処法や、紛失のリスクを下げる方法について知りたい方は以下の記事をご参照ください。
領収書の間違いを防ぐ方法
領収書の訂正・再発行は、経理担当者の負担が増えるだけでなく取引先に迷惑をかける可能性もあります。本章では、領収書の間違いを防ぐ3つのポイントを紹介しますので、参考にしてください。
取引先の名刺をもらう
取引先の名刺を事前に受け取っておくと、ミスのない領収書の作成に役立ちます。作成時に名刺を確認し、会社名や個人名を正しく記載しましょう。
漢字やアルファベット、前株・後株など、細部にも注意を払いつつ記載することが重要です。
領収書の下書きを作成する
領収書の記載ミスを防ぐには、下書きの作成がおすすめです。取引金額が大きい場合は、下書きを取引先にあらかじめ確認してもらうのも効果的といえるでしょう。
下書きの作成や確認のやり取りには手間がかかりますが、トラブルのリスクを軽減できるメリットがあります。また、取引先との信頼関係も築きやすくなるでしょう。
細部まで確認する
領収書を取引先へ渡す前に、間違いがないか細部まで確認しましょう。特に確認すべき項目は日付・宛名・金額の3点で、抜け漏れの有無をチェックすることもポイントです。
重要な取引における領収書は、複数の担当者で確認作業を行うと、訂正・再発行が生じるリスクを減らせておすすめです。
関連記事:領収書とは?書き方や発行・受領時のポイント(無料テンプレートあり)
領収書のミスを防ぐために!効率的に正確な作成ができる「バクラク請求書発行」
領収書の記載内容に間違いがある場合は、発行者のみ訂正が認められます。しかし不正のリスクを考慮すると、特別な事情がない限りは再発行をするのが適切です。
領収書のミスは自社と取引先の両者に迷惑がかかることを理解した上で、誤りのない正確な作成を心がけましょう。
領収書作成のミスを減らして業務を効率化するには、請求書発行システムの導入がおすすめです。バクラク請求書発行は、領収書を含むあらゆる帳票類の作成から送付までを一気通貫でシステム化できます。
個別の作成・修正や複製が可能なほか、送付方法や宛先、添付書類の有無を取引先ごとに設定できる機能も搭載されています。
バクラク請求書発行に興味をおもちの方は、以下のページから詳しいサービスや導入事例をご覧ください。無料の資料もダウンロードいただけます。