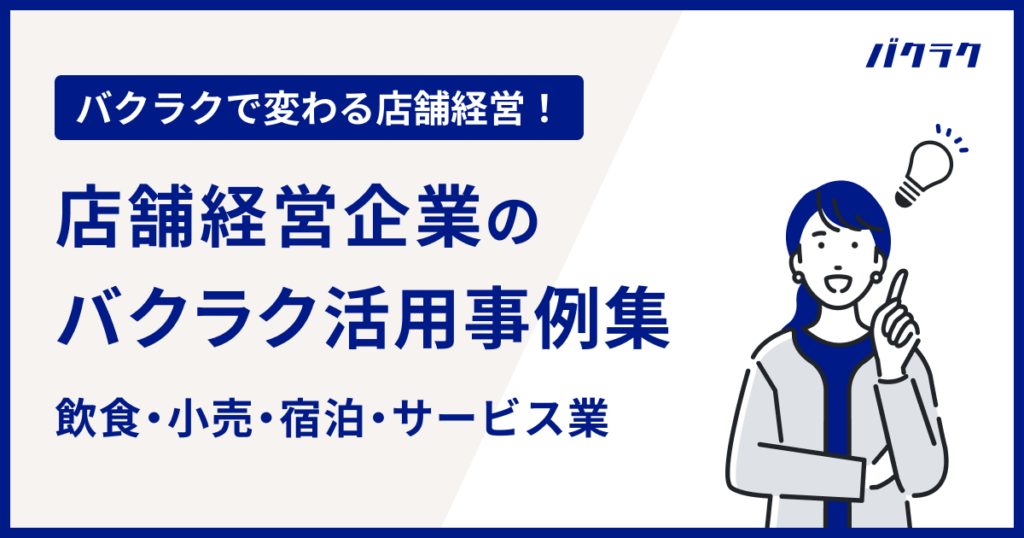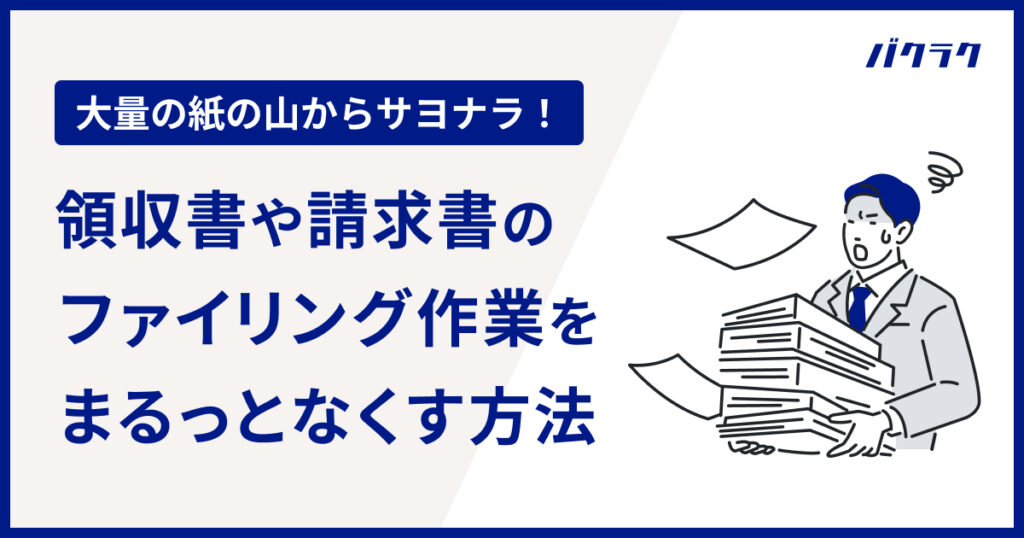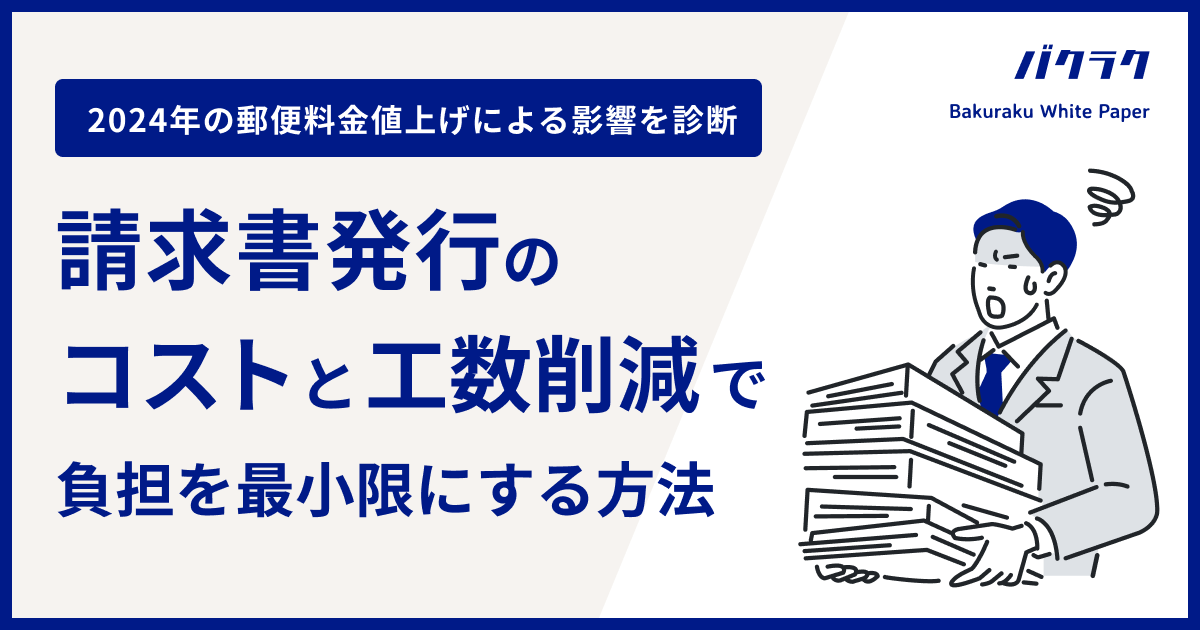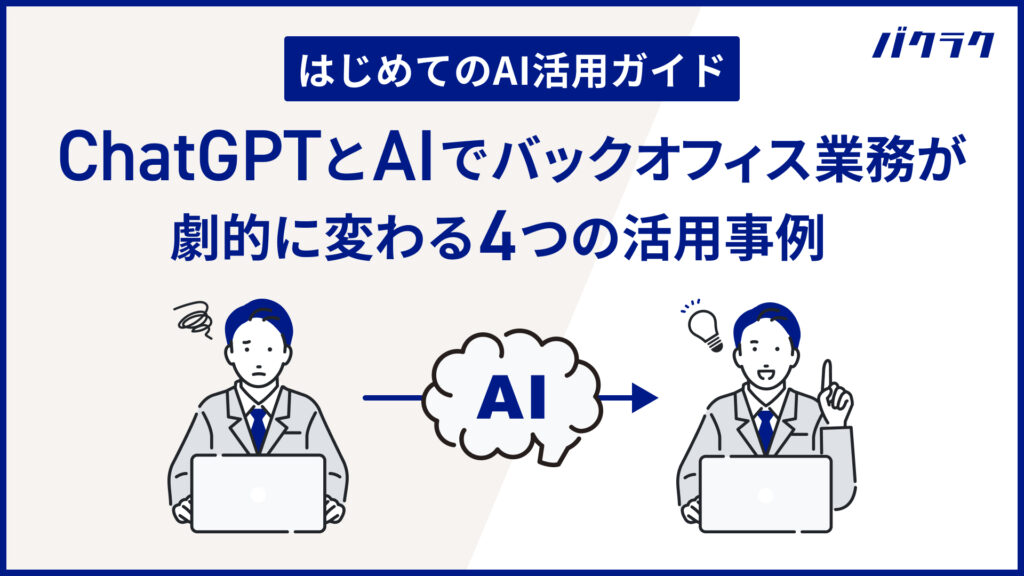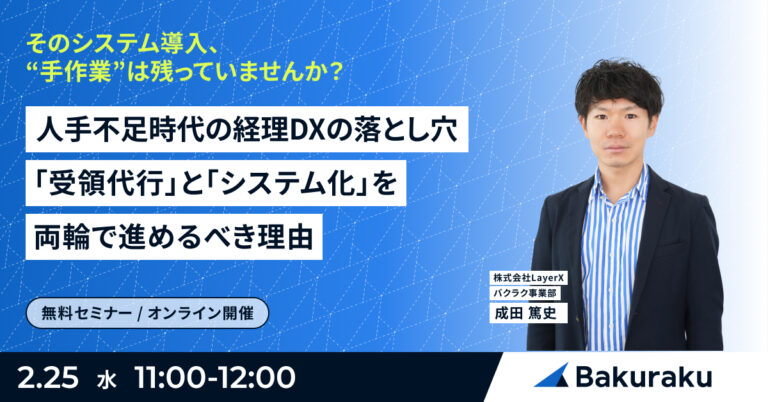
インボイス制度は飲食店にどんな影響がある?対応すべきこと・特例を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 飲食店は課税事業者か免税事業者かで、インボイス制度による影響が異なる
- 飲食店は適格請求書発行事業者への登録検討など、対策を講じる必要がある
- 消費税負担を軽減する「2割特例」や「経過措置」といった特例が存在する
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関する仕組みです。インボイス制度の開始により、経理業務の負担が増加している飲食店は少なくないでしょう。
本記事では、インボイス制度が飲食店経営に与える影響をわかりやすく解説するとともに、飲食店が取るべき具体的な対策を詳しく紹介します。経理業務の負担軽減と確実な法対応のために、ぜひ最後までお読みください。
インボイス制度は飲食店にどんな影響がある?対応すべきこと・特例を解説
知っておきたいインボイス制度の概要
インボイス制度について理解を深めるのは、日々の食材仕入れや顧客への請求方法にも関わるため重要です。
そもそもインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を正確に行うための仕組みです。インボイス制度の目的は、正確な消費税額を把握し、適正な申告・納税を促すことにあります。
特に軽減税率(8%)と標準税率(10%)が混在する飲食店の取引においては、知っておかなければなりません。
なお、仕入税額控除が適用されるのは、仕入先からの請求書や、発行するレシート・領収書が「適格請求書(インボイス)」または「適格簡易請求書」の要件を満たしている場合のみです。
インボイス制度を理解する上で「課税事業者」と「免税事業者」の違いを知っておく必要があります。課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者、免税事業者とは納税義務が免除されている事業者です。
インボイスを発行できるのは課税事業者のみです。飲食店経営者が課税事業者、免税事業者のどちらを選択するかによって、仕入税額控除の可否や経理業務、取引先との関係が変わる可能性があります。
課税事業者に登録しない場合のデメリットや免税事業者の違いについては、以下の記事を参考にしてください。
インボイス制度が飲食店に与える影響とは?
インボイス制度の導入は、飲食店経営にもさまざまな影響を及ぼします。また「課税事業者」なのか「免税事業者」なのかによって、受ける影響の内容は異なります。
どのような影響が想定されるのかを詳しく見ていきましょう。
課税事業者の場合
課税事業者の飲食店において、インボイス制度は主に「仕入税額控除」と「経理業務」の2つの面で影響を及ぼします。
原則として適格請求書(インボイス)の保存がなければ、仕入れにかかった消費税の控除が受けられなくなります。たとえば、免税事業者の農家や個人経営の卸売業者が取引先の場合、インボイスを発行してもらえません。
免税事業者からの食材や備品の仕入れについては消費税分の控除ができず、結果的に自店の納税負担が増加してしまう可能性があります。経過措置はありますが、恒久的なものではありません。
経理業務では受け取った請求書がインボイスの要件を満たしているか毎回確認し、区分して保存する必要があり、負担増加も避けられないでしょう。また、顧客に発行するレシートや領収書も、適格簡易請求書の要件を満たす形式に変更しなければなりません。
変更に伴い、レジシステムの改修や、手書き領収書の記載項目の変更・追加といった対応が必要です。適用税率ごとに消費税額を正確に計算し記帳しなければならず、経理プロセスの複雑化が見込まれます。
免税事業者の場合
免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できません。免税事業者の飲食店にとって、インボイス制度は取引や事業継続の判断にまで影響を与えます。
顧客が法人などの課税事業者であった場合、当該飲食店における飲食代について、消費税の仕入税額控除を適用できなくなります。
顧客側から消費税相当額の値引きを要求されたり、インボイスを発行できる他の飲食店が選択されたりするリスクが生じる可能性も否定できません。
特に、平日のランチタイムや夜間の宴会などで法人顧客の利用が多い飲食店にとっては、売上減少に直結しかねない深刻な問題です。また、新規の法人顧客獲得においても不利になる可能性があるでしょう。
状況への対応策として、適格請求書発行事業者として登録する選択肢が考えられます。しかし、課税事業者へ移行すると、これまで免除されていた消費税の申告・納付義務を負うことになります。
売上に応じた消費税を納める必要が生じるため、手取り収入が減少する可能性も出てくるでしょう。さらに、消費税申告に伴う経理業務の負担が増加したり、税理士への依頼費用やインボイス対応レジへの変更費用が発生したりする点も考慮するべきです。
飲食店がインボイス制度に対応するためにすべきこと
インボイス制度の開始に伴い、飲食店経営者が取るべき対応は以下の3つが考えられます。
- 適格請求書発行事業者への登録手続きを検討
- 適格簡易請求書の様式に対応したレシート発行
- インボイス制度に対応したレジ・システムの導入
具体的な内容について、順を追って解説していきます。
適格請求書発行事業者への登録手続きを検討する
はじめに検討すべきは、適格請求書発行事業者への登録です。インボイスを発行するには、税務署へ申請し、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、課税事業者のみです。免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書を提出し、まずは課税事業者になる必要があります。
すでに課税事業者であっても、自動的にインボイス発行事業者になるわけではなく、適格請求書発行事業者への登録申請が求められます。
適格請求書発行事業者の手続きや消費税納付義務については、以下の記事で解説しています。
関連記事:「適格請求書発行事業者」とは?税務署への登録手続きと消費税納付の義務を解説
レシートを適格簡易請求書の様式にする
飲食店は、通常のインボイスに代えて、記載項目を簡易にした「適格簡易請求書」の交付が認められています。日常的に使用しているレシートも、必要な記載要件を満たせば適格簡易請求書として扱うことが可能です。
インボイス制度に対応するには、現在使用しているレシートのフォーマットを見直し、必要な項目が正しく記載されるように、様式を変更する必要があるでしょう。適格請求書の具体的な記載項目については、この後の章で詳しく解説します。
インボイス制度に対応したレジ・システムを導入する
飲食店がインボイス制度に対応すると、経理業務の負担が増加します。また、取引先が一般の消費者ではなく、課税事業者である場合はインボイス発行が必要です。
インボイス制度に対応したレジ・システムの導入によって、忙しくなりがちな飲食店の業務負担を軽減できます。
たとえば、適格簡易請求書やインボイスを効率的に発行するには、発行機能が搭載されたPOSレジの導入が役立つでしょう。他には、会計システムや請求書発行システムを取り入れれば、経理業務を効率化できます。
インボイス制度に対応したレシート・領収書の書き方
飲食店のような、不特定多数の顧客と取引を行う業種は、通常の適格請求書(インボイス)よりも記載項目が一部省略された「適格簡易請求書」の発行が認められています。
適格簡易請求書は、レシートや領収書に以下の項目の記載が必要です。
- 発行事業者の氏名または名称
- インボイス登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨 ※印などで示すことも可)
- 税率ごとに区分して合計した金額(税抜または税込)
- 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
たとえば「取引内容」には、軽減税率(8%)対象のテイクアウト品目と、標準税率(10%)対象の店内飲食を区別して記載する必要があります。
記載項目の詳細については、以下の記事も参考にしてください。
飲食店経営者が知っておきたいインボイス制度の特例
インボイス制度には、いくつかの特例が設けられています。飲食店を経営する上で、「2割特例」と「仕入税額控除の特例」を押さえておきましょう。下記にて、それぞれの特例を解説します。
2割特例
2割特例では、事業者の消費税負担を売上税額の2割に軽減できます。適用対象は免税事業者から課税転換し、インボイス発行事業者になった事業者です。2割特例の適用時における消費税額の計算は、下記のとおりです。
【条件】
- 簡易課税・2割特例の適用
- 年間売上額600万円(消費税60万円)
- 仕入れ200万円(消費税20万円)
- 仕入れ率60%
【消費税額の計算】
- 通常時の消費税額 = 消費税60万円 – 60万円×60% =24万円
- 2割特例による消費税額 = 消費税60万円×20% =12万円
2割特例が適用されると、消費税の負担を大きく軽減できることがわかります。
参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
仕入税額控除の特例
仕入税額控除の特例によって、インボイス制度では6年間の経過措置が設けられています。経過措置の期間中はインボイスがない取引でも、一定の割合で仕入税額控除が適用可能です。経過措置による控除の割合は、下記のとおりになります。
【経過措置による控除割合】
- 2023年10月1日〜2026年9月30日:80%
- 2026年10月1日〜2029年9月30日:50%
現在は免税事業者であっても、仕入税額控除の特例が終了する前に、インボイス制度への対応を検討するのもよいでしょう。
参考:国税庁「経過措置(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)」
飲食店が適格簡易請求書を発行する際の書き方
不特定多数の顧客と取引があるなら、取引の都度インボイスを発行しようとすると手間がかかり現実的ではありません。飲食店は大勢の消費者に対して営業するため、業務負担の軽減を目的に適格簡易請求書(簡易インボイス)の発行が認められています。適格簡易請求書は通常のインボイスと比較し、簡略化した記載で済ませられます。適格簡易請求書の記載事項は下記のとおりです。
(1)簡易インボイス発行事業者の氏名(または名称)
(2)登録番号
(3)取引年月日
(4)取引内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨)
(5)税抜取引価額または税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
(6)(5)に対する消費税額等または適用税率
適格簡易請求書について詳しくは、下記の記事も参考にしてください。
飲食店のインボイスに関するQ&A
飲食店のインボイスに関して、よくある質問と回答を紹介します。
手書きの領収書でもインボイスとして認められる?
手書きの領収書であっても、必要事項が記載されていればインボイスとして認められます。しかし、インボイスには事業者の登録番号を記す必要があり、発行の度に手動で書き込んでいると手間が増えてしまうでしょう。
また、ヒューマンエラーによる登録番号の記載ミスも考えられます。登録番号が印字されたスタンプを用意しておけば、手書きインボイスの発行を効率化できます。
免税事業者・課税事業者どちらを選択すればいい?
飲食店が免税事業者・課税事業者のどちらを選択すべきかは、条件や状況によって異なるため検討が必要です。検討する上で、それぞれのメリット・デメリットを把握しておきましょう。
免税事業者の飲食店で顧客に法人が多いケースだと、インボイスが発行できなければ顧客が離れてしまう可能性があります。
一方、顧客として一般消費者の割合が高く、仕入先も免税事業者が多いケースは、インボイスを求められる機会が少ないと考えられます。そのため、適格請求書発行事業者として登録する必要性は薄いといえるでしょう。
経理業務の負担を最小限にするなら「バクラク請求書発行」
インボイス制度への対応は、飲食店にとって経理業務の複雑化を招く可能性があります。適格簡易請求書の要件を満たすレシート発行や、仕入税額控除のための請求書管理など、新たな作業が増えるでしょう。
飲食店の経理負担を最小限に抑え、効率的に対応するためには、制度に適したシステムの導入が有効です。そこでおすすめしたいのが、バクラク請求書発行です。
バクラク請求書発行は、インボイス制度はもちろん電子帳簿保存法などの法制度にもしっかりと対応しています。日々のレシート発行から、取引先への請求書発行まで、あらゆる帳票をシステム上で簡単に作成可能です。
さらに飲食店の業態や運用に合わせて、帳票のレイアウトや記載項目を柔軟にカスタマイズできる点も、大きな特徴といえるでしょう。ぜひバクラク請求書発行の導入をご検討ください。