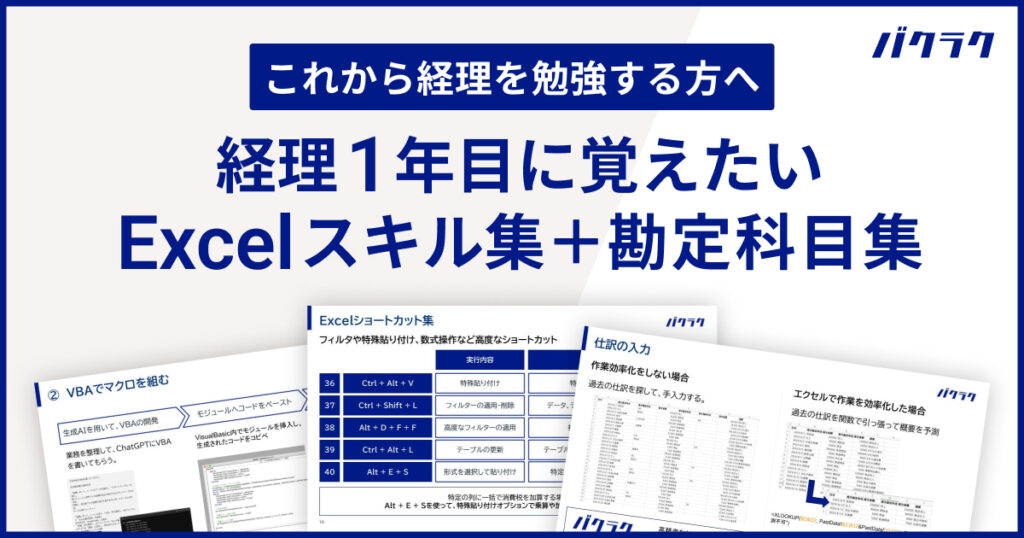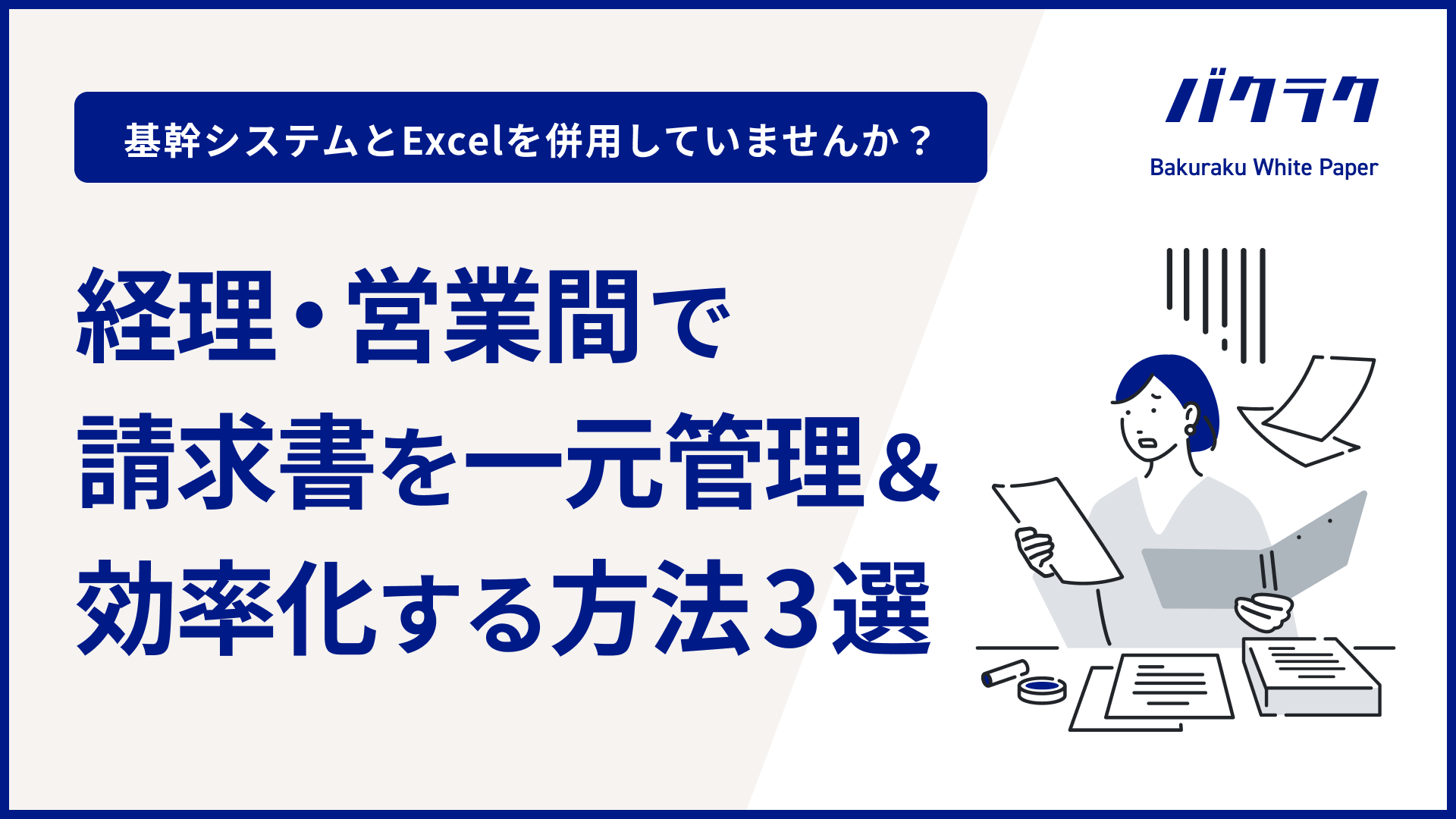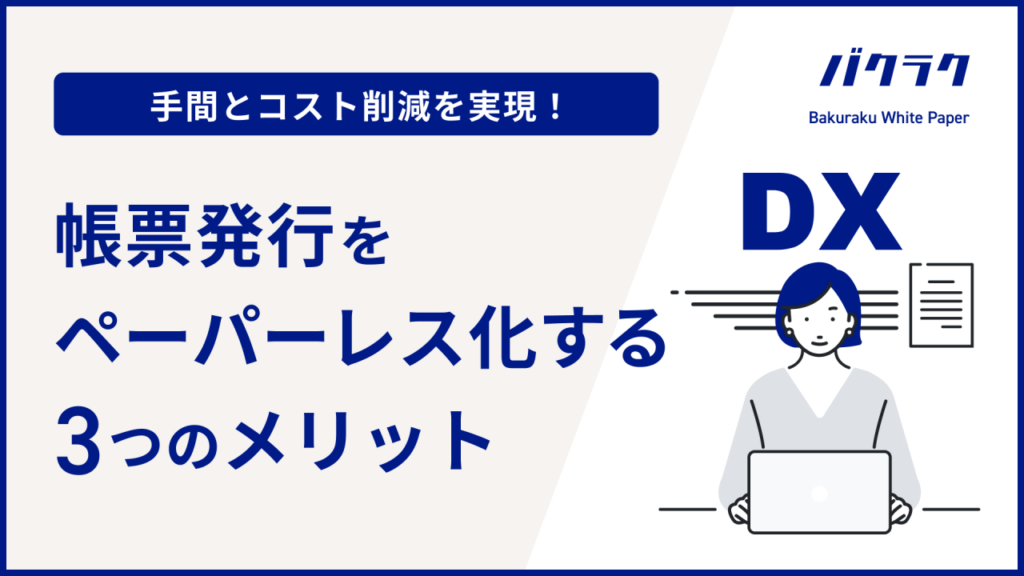収入印紙とは?必要性や金額、購入方法、貼り方などを徹底解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-04-25
- この記事の3つのポイント
- 収入印紙とは、印紙税を納付するために使用される証票のこと
- 収入印紙の金額は文書の内容によって異なり、文書の内容と金額の確認が重要
- 貼り忘れや消印がない場合、ペナルティとして過怠税が課せられる
収入印紙とは、契約書や領収書などの文書には印紙税が課せられ、その印紙税を納付するために使用される証票です。
本記事では収入印紙とはなにか、必要性や金額について解説します。また収入印紙が購入できる場所や貼り方についても解説しているので、ぜひご覧ください。
収入印紙とは?必要性や金額、購入方法、貼り方などを徹底解説
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
収入印紙とは
収入印紙とは、国が発行する証票のことです。契約書や領収書などの文書には印紙税が課せられ、その印紙税を納付するために使用されます。
日本では印紙税法に基づき、取引時に必要となる作成文書に印紙税が課せられる仕組みが設けられています。
文書の作成者は必要な金額の収入印紙を購入し、該当文書に貼り付けて印紙税を納める義務があるため、必要なときにスムーズに対応できるようにしておきましょう。
なお、収入印紙は見た目が似ている収入証紙や普通切手と混同されることが多いですが、それぞれ用途や発行元が異なります。
| 証票の種類 | 発行元 | 用途 |
| 収入印紙 | 国 | 税金や行政関係への手数料の支払い |
| 収入証紙 | 地方公共団体 | 地方税や手数料の支払い |
| 普通切手 | 日本郵便株式会社 | 郵便料金の支払い |
それぞれの違いを正しく理解して、適切に使い分けることが重要です。
収入印紙が必要な文書
印紙税が課せられる文書を、課税文書といいます。この課税文書を作成すると、作成者は取引金額に応じた印紙税を納付しなければなりません。このとき、収入印紙を購入し課税文書に貼付すると、印紙税を納付したと見なされます。
印紙税法によって以下のとおり、第1号文書から第20号文書まで20種類が定められています。
- 額面が5万円以上の領収書
- 不動産の譲渡に関する契約書
- 土地の賃借権設定に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 請負に関する契約書
- 営業に関する受取書(領収書)など
- 約束手形や為替手形
- 業務委託契約書
- 物品加工注文請書
- 専属契約書
- 運送契約書
- 代理店契約書
- 借用証書
- 株券
- 社債
- 投資信託などの証券
なお、印紙税は各文書の契約内容や契約金額、領収書の金額によって、納付すべき収入印紙の金額(印紙税額)が異なります。過不足なく収入印紙を貼る必要があるため、印紙税額についてしっかりと理解しておきましょう。
収入印紙の金額
収入印紙の金額(印紙税額)は、文書の内容によって異なります。ここでは、収入印紙にかかる費用について解説します。
領収書に貼る収入印紙の金額
商品やサービスの金銭または有価証券の受取を証明する領収書には、収入印紙を貼付する必要があります。収入印紙の貼付が必要な領収書は、受取金額が5万円以上の場合に限られます。
| 記載された受取金額 | 収入印紙の金額 |
| 5万円未満 | 不要(非課税) |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
出典:国税庁「No.7105 金銭または有価証券の受取書、領収書」
不動産売買契約書や金銭借用証書などに貼る印紙の金額
不動産売買契約書、不動産交換契約書などの契約書を交わす際に貼り付ける収入印紙の金額は、以下のとおりです。
| 記載された契約金額 | 収入印紙の金額 |
| 1万円未満 | 不要(非課税) |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
工事請負契約書や工事注文請書などに貼る印紙の金額や、売買取引基本契約書や業務委託契約書などに貼る印紙の金額については、以下の記事で詳しく解説しています。
収入印紙の購入方法
収入印紙は郵便局や法務局などで購入できますが、場所によっては取り扱いの収入印紙の種類が限られてしまうこともあるため注意しましょう。収入印紙の購入場所と種類については、以下のとおりです。
- 郵便局・法務局ではすべての額面を購入できる
- 役所では一部の額面を購入できる
- コンビニでは基本的に200円で購入できる
- 金券ショップでは額面より安く購入できるものの、在庫がない場合は購入できない
収入印紙は税金や手数料を納めるという性質上、原則非課税です。しかし金券ショップで販売している収入印紙を購入する場合は消費税がかかります。
また、購入した場所により仕訳方法も異なります。なお、課税対象となる収入印紙は仕入税額控除の適用となり消費税の負担を軽減できるため、忘れずに経理処理をすることも重要です。
収入印紙の経費計上方法について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
収入印紙の貼り方と注意点
収入印紙を購入したものの、取り扱い方がわからないという方もいるでしょう。ここからは、収入印紙の貼り方と注意点について解説します。
基本的な貼り方
収入印紙を貼る基本的な方法は、切手と同じです。日本の法律においては、貼り方について決まった方法を定めてはいません。
ただし、契約書に貼る場合には左右いずれかの余白に貼るのが一般的です。また、領収書には貼り付け欄が用意されていることもあります。収入印紙を貼り付けただけでは印紙税の納付にはならず、消印が必要である点には注意が必要です。
2枚以上の収入印紙を貼る場合も貼り方に決まりはありませんが、上下左右に並べて貼るとわかりやすくてよいでしょう。この場合、すべての収入印紙に消印が必要となります。複数の収入印紙にまたがるように消印を押すことも可能です。
収入印紙の正しい押印方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:収入印紙に割印は必要?正しい押印方法や割印がない場合のペナルティを解説
間違えて貼ってしまった場合の対処法
収入印紙は、印紙税など税金を納めるためのものです。そのため、間違えて貼ってしまった場合は、印紙税の過誤納金として還付を受けられる可能性があります。
還付の対象となるのは、次のようなケースです。
- 非課税の文書に誤って収入印紙を貼った場合
- 収入印紙を貼ったが使用予定がなくなった場合
- 課税文書に過大な金額の収入印紙を貼った場合
なお、還付請求権は請求可能日から5年間です。貼り間違えた収入印紙がある場合には、早めに還付の手続きをしましょう。
ただし、還付の対象となるのは印紙税に関する場合です。登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼った場合は、貼り間違えても還付の対象外である点に注意をしてください。
参考:国税庁「No.7130 誤って納付した印紙税の還付」
貼り忘れや消印がない場合のペナルティ
課税文書の作成者が収入印紙を貼り忘れたり、消印がなかったりした場合、ペナルティが課せられます。ペナルティは過怠税で、未納の印税額とその2倍に相当する金額の合計額(本来納付すべき収入印紙税額の3倍)です。
ただし、貼り忘れを自主的に所轄税務署長に申し出た場合、過怠税は1.1倍に軽減されます。未納に気付いた場合、早めに申し出るようにしましょう。
収入印紙が不要な場面
収入印紙が不要になる主なケースは、以下のとおりです。
- 電子データ取引の場合
- クレジットカード決済の場合
- 債権と相殺した場合
- リース契約の場合 など
あらかじめ不要となるケースを知っておけば、誤って収入印紙を購入するおそれが軽減されるでしょう。ここからは上記の項目について、具体的に解説します。
電子データ取引の場合
電子データ取引の場合、収入印紙は貼る必要がありません。
印紙税は紙の書類を発行する際に課せられる税金のため、電子発行の領収書や契約書では紙の書類が不要です。収入印紙の貼付や印紙税の納税も必要ない点を把握しておきましょう。
2023年10月からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されており、2024年12月31日には電子帳簿保存法の電子データ保存義務化の猶予期間が終了します。
この影響もあり、今後はビジネス文書の電子化がますます進展し、紙の書類を使用せずに文書を管理する傾向が加速すると考えられています。
電子化した領収書における収入印紙の取り扱いについては、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。
関連記事:電子化した領収書に収入印紙は不要?電子化方法や注意点を解説
クレジットカード決済の場合
クレジットカード決済における領収書も、印紙税法の課税文書に該当せず収入印紙を貼る必要がありません。直接的な現金のやり取りを伴わないクレジットカード決済は、信用取引と見なされるためです。
ただし、領収書には必ず「クレジットカード決済」であることを明記しておきましょう。明記がないと「課税文書にもかかわらず収入印紙を貼り忘れた」と見なされる可能性があるため、注意が必要です。
クレジットカードの領収書に収入印紙は必要かどうかは、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。
債権と相殺した場合
お互いに債権と債務がある企業間では、取引のなかで債権を相殺するケースがあります。この場合、相殺できた金額部分は非課税となり、収入印紙は不要です。しかし、相殺しきれなかった金額部分は印紙税の対象となるため、金額によっては収入印紙が必要となります。
たとえば、企業Aが企業Bから20万円の商品を現金で購入するケースを考えてみましょう。企業Aが企業Bに対して5万円の債権をもっている場合、債権5万円と今回の取引の20万円を相殺し、企業Aが企業Bに15万円を支払うことで商品を購入できます。
そしてこのケースの場合、相殺した5万円分が非課税となります。ですが、相殺しきれなかった15万円分については課税対象となるため、収入印紙を用意しなければなりません。
仮に、取引で相殺できなかった金額が5万円未満であれば収入印紙は不要となります。
リース契約の場合
リース契約とは、リース会社が機器や設備などを業者から購入し、ユーザーに貸し出すことで毎月一定の料金を受け取る仕組みです。このリース契約における収入印紙の要否は、貸し出す対象物や、契約の種類により異なります。
たとえば、リース会社と業者間の契約は売買契約になります。そしてコピー機や自動車などの動産(不動産以外の財産)の売買契約書は非課税文書とされるため、収入印紙は不要です。
また、リース会社とユーザー間の契約は賃貸借契約です。こちらも対象が動産の場合、収入印紙は必要ありません。ただし、不動産リースでは契約書の内容によっては収入印紙が必要になる場合があります。
なお、上述のとおり動産のリース契約書自体には収入印紙は不要ですが、リース契約にともない保守契約を締結する場合は、収入印紙が必要となる可能性があります。請負に関する契約書(第2号文書)、あるいは継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)として印紙税が課されるためです。
リース契約の対象となる機器や設備、契約書の内容を確認のうえ、収入印紙の要否を判断しましょう。
請求業務の効率化ならペーパーレスな「バクラク請求書発行」
収入印紙が必要な場面においては、対象となる金額に対して適切な額の収入印紙を貼らなければなりません。あらかじめ収入印紙に関わる基礎知識を十分に押さえておきましょう。
バクラク請求書発行は、請求書・納品書・見積書などあらゆる書類をWeb上で発行できるシステムです。
請求書発行・処理などの作業を電子化できるため、収入印紙が不要となります。貼り間違いなどのミスや管理の手間を軽減できるでしょう。
また、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応可能です。申請者がミスなく申請できる機能も搭載されており、経理担当者の業務負担も削減できます。
経費申請全体を効率化したいと考えている人は、ぜひお問い合わせください。