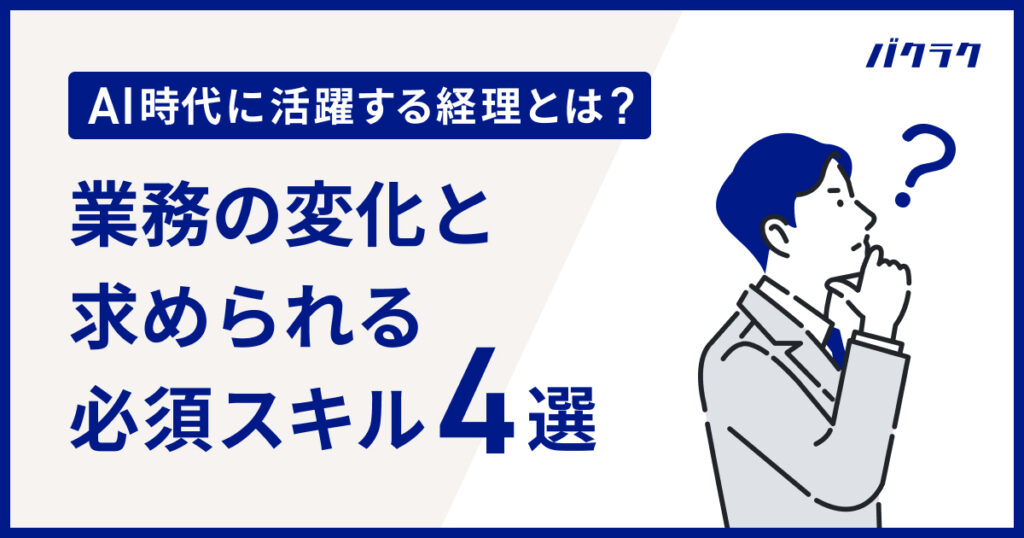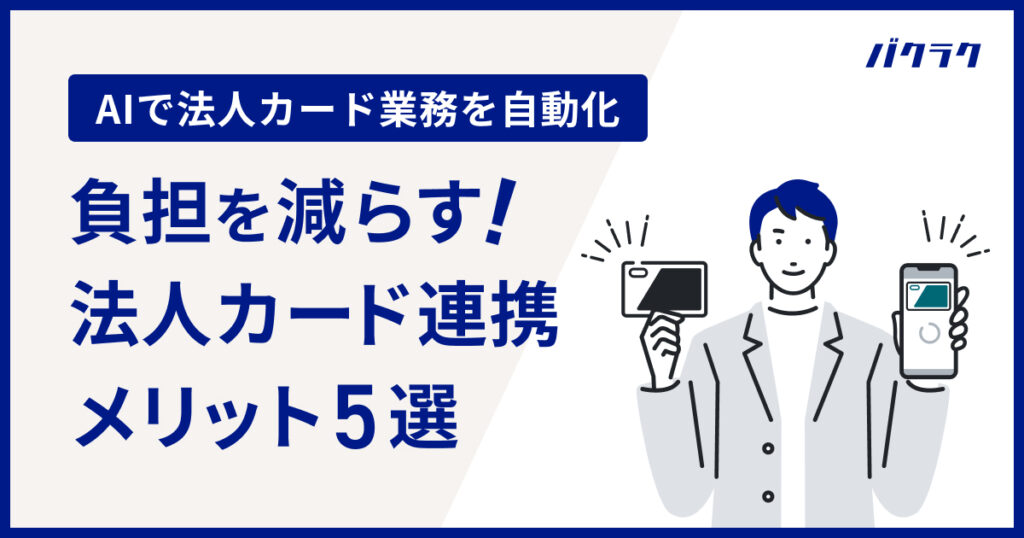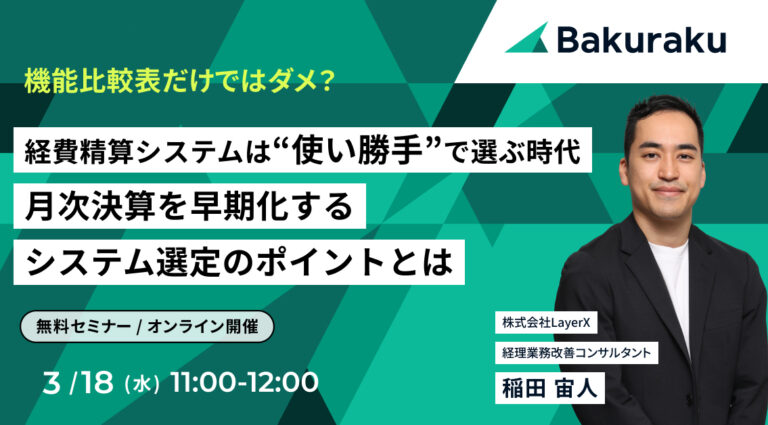Suica®やPASMO®で経費精算する方法|履歴印字・領収書発行も解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-10-20
- この記事の3つのポイント
- 券売機・ICカードリーダー・モバイルアプリ・経費精算システムを利用して経費精算を行う
- 経費精算時は、券売機の印字・カードリーダーの履歴上限、モバイルアプリの対応機種に注意する
- 経費精算システムと交通系ICの支払いを連携させると、不正防止や大幅な業務効率化が期待できる
経費の決済手段として交通系ICを利用する場面は珍しくありません。しかし、Suica®やPASMO®などを使用した際の経費精算方法がわからない方もいるでしょう。
本記事では、Suica®やPASMO®を利用した際の領収書の出し方や経費精算手順、注意点について解説します。交通系ICの支払いを経費精算システムと連携した場合のメリットも紹介していますので、経費精算を効率化したい方は、ぜひ参考にしてください。
Suica®やPASMO®で経費精算する方法|履歴印字・領収書発行も解説
Suica®やPASMO®で経費精算する4つの方法
Suica®やPASMO®を利用すると、利用履歴をデータで確認できるため、スムーズな経費精算が可能です。利用履歴を活用した経費精算の方法は、以下の4つです。
券売機の履歴表示機能の利用
Suica®など交通系ICカードの利用履歴は、駅構内に設置された「IC」マーク付きの券売機から印刷できます。具体的には、自動券売機、チャージ専用機、多機能券売機の3種類です。
印字をするには、券売機にカードを入れ「利用履歴を確認」もしくは「チャージ・残額履歴」のボタンを選択します。利用日、利用駅、乗降の別、残高が記載されるため、そのまま経費精算書に書き写せば問題ありません。
ただし、場所によっては駅名の代わりに事業者名が印字されるケースもあるため、正確な印字でない場合は社内の経理担当者に相談しましょう。可能であればカードを利用したエリアで印字しておくと安心です。
履歴表示件数の上限を超えて利用した場合や、カードが正しく読み取られない場合は、情報が正確に印字されないことがあるため注意しましょう。
ICカードリーダーの利用
専用のICカードリーダーを利用すると、Suica®やPASMO®の利用履歴がデータ上で確認できます。データはExcelと連携させて処理することも可能です。
ただし、利用するにはパソコンに対応アプリをインストールする必要があります。
モバイルアプリの利用
スマートフォン専用アプリのモバイルSuica®やモバイルPASMO®を使って、利用履歴を確認することも可能です。
アプリの画面を開き「SF利用履歴」「残額履歴」を選択すると、履歴が表示されます。表示された履歴は、プリンターと接続して印刷することで確認できます。パソコンから操作する場合は、モバイル会員メニュー内の「SF利用履歴」から履歴を確認してください。
経費精算システムと連携している場合は、印刷不要でそのまま申請できます。
ただし、印字の対象となるのは、クレジットカードでチャージした場合(オートチャージは対象外)や、切符の購入履歴のみです。領収書を表示する際には「クレジットカードご利用分」と印字されます。
なお、履歴表示は最大100件です。
経費精算システムの利用
経費精算システムは、経費の申請から承認、支払いまでの一連の流れを電子化するシステムです。ICカードリーダーやモバイルSuica®・モバイルPASMO®と連携できる製品もあります。
経費精算システムとICカードリーダーやモバイルSuica®・モバイルPASMO®を連携することで、読み取ったデータをそのまま利用して交通費申請が行えます。精算業務の正確性や効率の向上にもつながるでしょう。
経費精算システムの概要やシステムの選び方は、以下の記事でご確認ください。
Suica®やPASMO®で交通費の経費精算をする流れ
Suica®やPASMO®で交通費の経費精算をする際の流れは、以下のとおりです。
- 精算書類の作成
- 上司の確認・承認
- 経理部の確認・承認
- 交通費の受取
精算書類を作成したら、上司の確認・承認を得て、経理部に提出します。経理部で確認して問題がなければ、交通費が支給されます。
交通費の精算書類を作成する際は、基本的に社内で用意されている所定のフォーマットを利用すれば問題ありません。フォーマットがない場合は、以下のような項目の記載が必要です。
- 日時
- 交通機関名
- 経路
- 運賃
- 訪問先
- 訪問目的
交通費の精算方法や交通費精算書の書き方、注意点については、以下の記事で解説しています。
Suica®やPASMO®で経費精算する際の3つの注意点
Suica®やPASMO®で経費精算するとスムーズに手続きできるものの、注意しなければならない点がいくつかあります。特に、以下の3つに留意しましょう。
券売機の印字できる上限に注意
券売機の履歴表示機能を利用する際、表示できる履歴は最大20件まで、印字できる履歴は直近の100件までという制限があることを理解しておきましょう。
なお、利用から26週間を過ぎると過去の履歴を印字することはできません。また、1日の利用回数が21回以上になると利用履歴が印刷されない場合があります。
ICカードリーダーの履歴を確認できる上限に注意
ICカードリーダーで確認できる履歴は、直近の20件のみです。新たに利用するたびに、より古い履歴は順番に表示されなくなります。そのため、利用回数が多い場合は、履歴の確認や保管を頻繁に行うようにしましょう。
出張などでICカードリーダーがないときは、券売機やモバイルSuica®と併用して履歴を確認する必要があります。
モバイルアプリの対応機種の制限に注意
モバイルSuica®やモバイルPASMO®を利用するには、対応するスマートフォンが必要です。Android端末であれば、キャリアごとに対応機種が異なります。古い機種だと対応していないケースもあるため注意が必要です。
また、券売機の履歴表示機能と同様に、26週間を過ぎると履歴は表示されなくなり、表示できる件数も前日分までの最大100件に限られます。
経費精算システムと連携することで得られるメリット
Suica®やPASMO®を経費精算システムと連携することで、正確性が向上し、経費精算フローも大幅に効率化できます。
本章では、連携による主なメリットを詳しく見ていきましょう。
手書きや手入力が不要
経費精算システムには、交通系ICをカードリーダーにかざしたり、モバイルアプリと連携したりするだけで、利用履歴を自動で読み込める機能を備えたものがあります。
データをそのまま交通費申請に使えるため、印字した利用履歴を申請書に転記する手間が省けます。自動で正しい情報が入力されるため、計算ミスや入力ミスもありません。
いつでもどこでも精算可能
クラウド型の経費精算システムであれば、スマートフォンやパソコンからいつでもアクセス可能です。
手書きや手入力による申請では、出先や出張で経費精算が行えず、帰社してから作業する必要があります。しかし、クラウド型の経費精算システムの連携により、場所や時間を問わず交通費申請が可能です。
定期区間は自動控除
経費精算システムは、定期区間控除に対応しているものもあります。自動で控除される機能を搭載していれば、金額計算をやり直す必要がありません。申請者本人のみならず、経理担当者の確認の手間も省け、経費精算の過払いや二重請求の防止にもつながります。
経理業務の効率化
交通系ICを経費精算システムと連携すると、必要なデータが自動で読み込まれ、承認や仕訳もスムーズになります。計算ミスや記載漏れを防ぐことで、申請内容の正確性も高まり、金額や駅名を確認する手間や、不備があった際の修正業務も軽減するでしょう。
申請内容にミスがあった場合でも、申請者へ自動で差し戻しが行われるため、経理担当者は最終確認だけで済み、他の業務に注力できるようになります。
データの一元管理が可能
経費精算書類や領収書を郵送でやり取りしている企業は、経費精算システムの連携により、郵便費用を削減できるだけでなく、申請から承認までの時間も大幅に短縮可能です。従業員も外出先や出張先から経費精算ができるため、利便性が向上します。
不正の防止
交通費精算は、不正が発生しやすい項目です。
しかし、交通系IC対応の経費精算システムを活用することで、履歴が残るだけでなく自動でデータが読み込まれるため、不正申告を防止できます。定期区間の自動控除機能がついた経費精算システムであれば、過払いや二重請求の対策も可能です。
モバイルSuica®の履歴印字・領収書の発行方法
モバイルSuica®やモバイルPASMO®の履歴確認や領収書発行は、会員メニューサイトやアプリからできます。利用履歴の確認も可能です。領収書の発行は、会員メニューサイトにアクセスし、プリンターと接続して印字します。
なお、モバイルSuica®の場合、領収書の発行が可能なのはクレジットチャージ(オートチャージは不可)のみです。
交通系ICでの経費精算を効率化できる「バクラク経費精算」
Suica®やPASMO®など交通系ICを利用した経費精算は、現在では一般的です。経費精算時には、券売機による利用履歴の印字や、ICカードリーダーやモバイルアプリを用いたデータ出力が可能です。
経費精算システムと連携させることで、印刷せずにデータをそのまま利用して精算できるため、不正防止や業務負担軽減につながります。交通費精算の効率化を図りたい方は、経費精算システムの導入を検討するとよいでしょう。
バクラク経費精算なら交通系ICの乗降履歴を取得し、経費精算にそのまま利用できます。また、申請から承認、仕訳までの一連の流れを自動化できるため、大幅な効率化が実現します。
紙の領収書で精算する場合も、領収書を撮影するとAIが自動で読み取り、仕訳まで行うため、手作業でデータを転記する必要がありません。不正やミスを防止できるよう、二重申請、領収書の重複を検知する機能も備えています。
経費精算のフローを見直すのであれば、ぜひバクラク経費精算の活用をご検討ください。
※「Suica」・「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「PASMO」・「モバイルPASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。