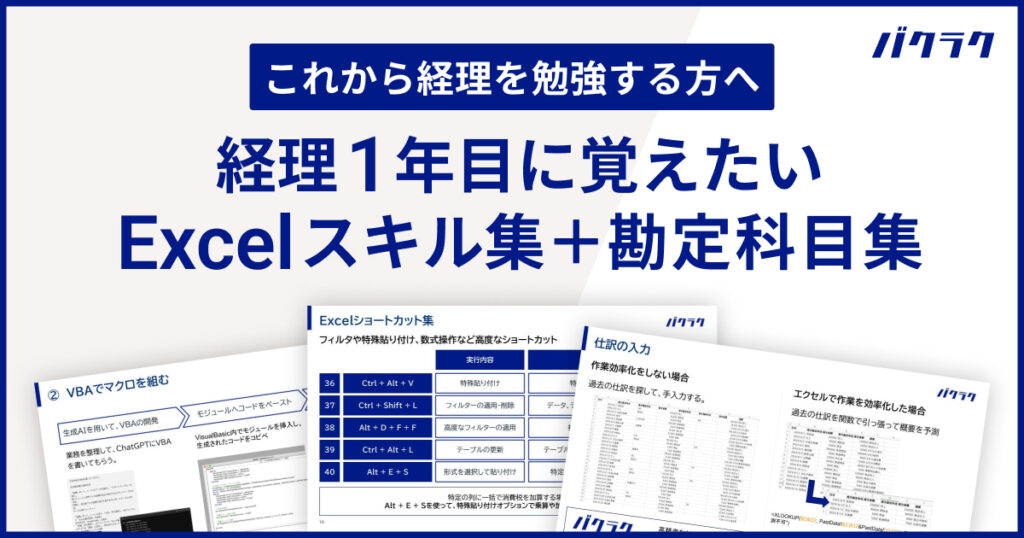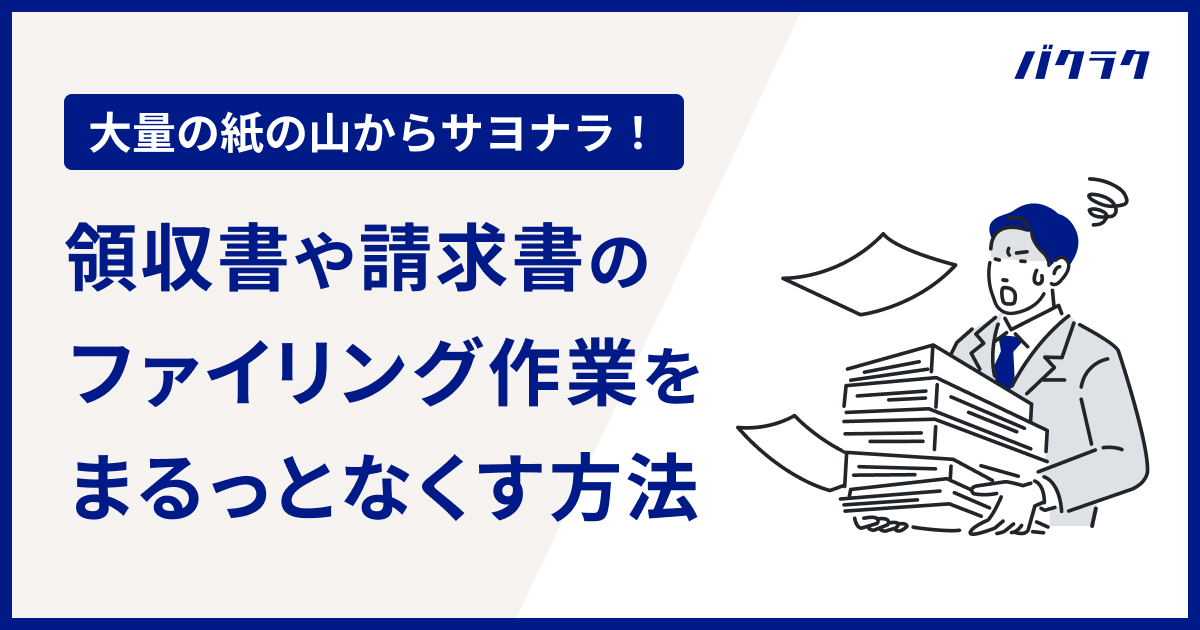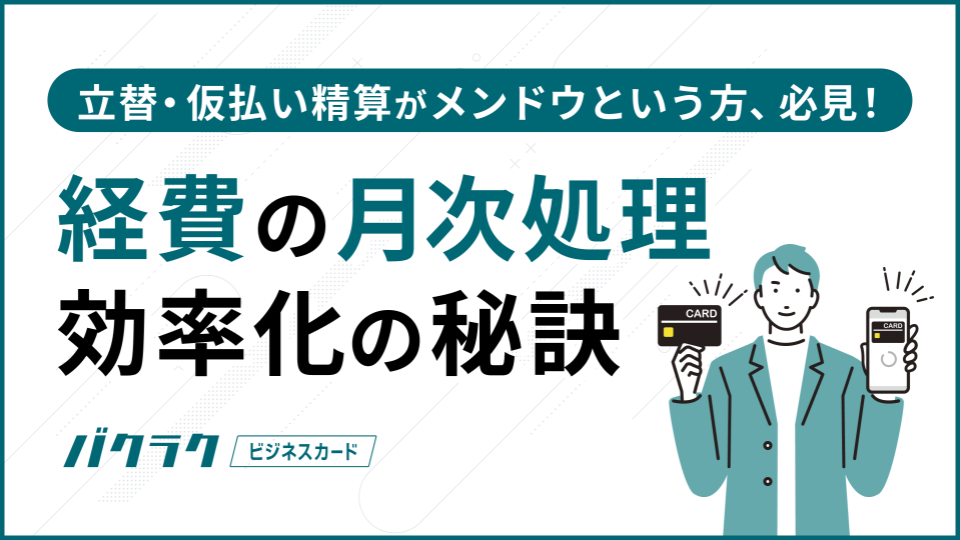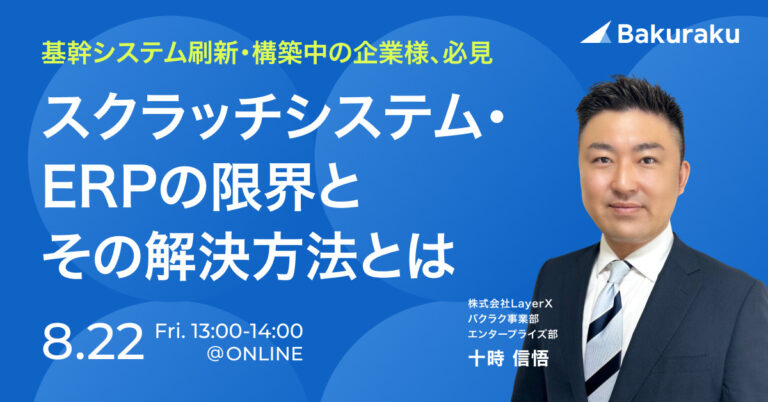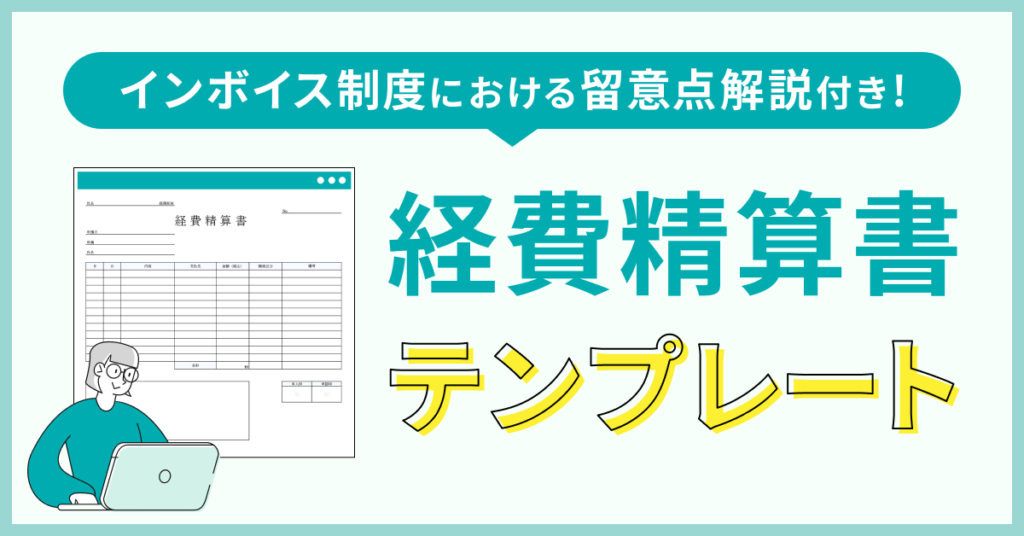月またぎや年度またぎの経費精算は可能?注意点や会計処理の例を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-04-07
- この記事の3つのポイント
- 経費の発生から5年間は企業への請求が認められているため、月・年度またぎでも経費精算は可能
- 決算月や年度またぎの精算では企業会計・法人税法を考慮し、後追い修正できないことに注意する
- 月またぎ・年度またぎの経費精算を防ぐには、経費精算システムや法人カードの導入がおすすめ
長期の出張や、月末に急遽発生した経費などにより、月や年度をまたいで経費精算が発生する場合もあります。
この記事では、そもそも月またぎや年度またぎの経費精算は可能なのかについて触れたうえで、月や年度をまたぐ理由と正しい会計処理の方法などを解説します。
月・年度またぎの経費精算を発生させない方法も紹介しているので、毎月の手続きに課題を感じている方はぜひ参考にしてください。
【結論】月またぎ・年度またぎの経費精算は可能
月や年度をまたいでいても、経費精算はできます。民法は「従業員の権利」として、経費が発生してから5年間は企業への支払いの請求を認めているからです。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
なお、月またぎとはある月に発生した経費や収益を翌月に精算または計上することです。年度またぎとは、事業年度内に発生した経費や収益を翌事業年度に精算または計上することです。
事業年度の区切りは会社によって異なりますが、3・9・12月を決算時期に設定している会社が多い傾向にあります。たとえば3月決算の会社では、3月に発生した経費を4月分として精算すると年度またぎになります。
ただし基本的に、経費精算は就業規則や社内規程によって定められた締切日までに処理しなくてはなりません。締切日が定められている理由は、自社の経費がいつどれくらい発生しているか正確に把握し、会計の歪みを防止するためです。
企業会計には「発生主義の原則」という考え方があり、現金が動いたかどうかは関係なく、取引が発生した時点で費用と収益を計上します。経費に関しても発生主義を徹底することで、収支を正確に確認しやすくなります。このように企業会計では、発生主義に基づいて月またぎや年度またぎを発生させないことが重要です。
しかし、実際には経費精算の手続きが締切日を守れていないケースも少なくありません。たとえば長期の出張があったり、月末に急遽の経費が発生したりすると、締切日に間に合わず月またぎ・年度またぎにつながります。
月またぎの経費精算が発生すると通常の会計処理と異なる対応が求められ、頻繁に起きると企業の信用が低下するなどの悪影響を及ぼす可能性があります。当然、経理担当者の負担も増加するでしょう。
経費精算の仕訳日付や仕訳例について詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
月またぎ・年度またぎが起きるケース
月またぎや年度またぎの経費精算が発生するケースはさまざまです。以下で詳しく解説します。
月・年度をまたぐ経費が発生する
月や年度をまたいで経費が発生した結果、経費精算も月・年度をまたぐケースがあります。たとえば、泊まりがけの月や年度をまたぐ出張が挙げられるでしょう。
交通手段として新幹線を利用し、3月31日に出発して4月1日に戻ってきた場合、往路については前月分、復路については当月分として処理する必要があります。3月が決算で年度またぎになる場合も、同じ考え方で問題ありません。
出張が多い従業員は、月またぎや年度またぎの経費精算が発生する可能性が高いでしょう。
月末や年度末の締め日に経費精算が間に合わない
月末や年度末に発生した経費は、精算の申請が期限に間に合わないケースもあります。たとえば、月の最終日に経費が発生した場合、急いで経費精算を行っても夕方以降になる可能性があるでしょう。
提出時に経理担当者がすでに退社していれば、当日中には処理されません。その結果、月またぎや年度またぎの経費精算が発生します。
経費の申請方法が複雑・面倒なため後回しになる
紙の経費精算書による申請方法が複雑で、申請に時間がかかった結果、月や年度またぎの経費精算が発生するケースもあります。経費精算は規定が多く、経費精算書にさまざまな項目を記載しなければなりません。
また、申請や決裁の際は押印が必要であり、手続きが完了するまでの手順が長くて面倒です。従業員が「経費申請に手間や時間がかかる」と認識すると、本来の業務を優先し、手続きを後回しにしがちです。
特に、外出や出張が多い場合には期日が迫ってからまとめて申請しようと考える従業員も多く、抜け漏れや遅れが生じやすくなります。繁忙期なら負担はさらに大きくなるため、月・年度またぎの経費精算がさらに発生しやすくなります。
経費の申請・提出忘れによる遅延が発生する
経費が発生しても、従業員が経費精算書の提出を忘れて月や年度をまたぐパターンも少なくありません。このような場合、経費精算のルールや期日がわかりにくい、周知不足、厳守する文化や風土がないといったことも原因として考えられます。
また、経費が発生しても、経費精算書の提出を忘れて月をまたぐパターンも少なくありません。従業員が多忙だと経費精算が後回しになり、数カ月後に申請される場合もあります。
期日までに申請しない従業員が多い場合は、ルールの見直しや周知徹底が必要かもしれません。新入社員向けに経費精算の講習を行ったり、定期的にガイドラインを配布したりすることで、組織全体の意識改革につながります。
【注意】決算月や年度またぎの精算は後追い修正できない
前述した経費精算の月またぎと同様、民法上の時効の範疇においては年度またぎの経費精算も可能です。ただし、以下の「企業会計」と「法人税法」の2つを考慮し、基本的に後追いの修正ができないことに注意しましょう。
企業会計における年度またぎ
企業会計とは、企業の経済活動に関する収入や支出について、一定のルールに基づいて記録・測定したものです。企業会計では、一度締めている期末決算は修正できません。決算で確定済みの数値は変えられないため、過年度の経費精算は「前期損益修正損」として、翌期への計上が一般的です。
また、年度またぎの経費精算が多いと決算の遅れにもつながるため、会社の繁忙期を避けて決算月を決める企業も少なくありません。
法人税法における年度またぎ
法人税法とは、企業の経済活動にかかる税金について定めた法律です。税務上は、確定申告の期限までは経費精算の年度またぎが認められています。たとえば3月決算の会社なら、5月末までは前年度の経費として精算が可能です。
ただし6月に入り確定申告の期限を過ぎてしまうと、原則として損金計上できなくなるため注意しましょう。
月またぎ・年度またぎが発生する際の会計処理の例
経費精算が月や年度をまたぐ場合は、どのように会計処理をするのでしょうか。先払いか後払いかによって、勘定科目が変わる点にも注意が必要です。
料金を先払いした際の会計処理
料金を先払いしたときは「前払金」という勘定科目を使用します。年度またぎの出張などの場合は、領収書の日付に基づいた経費処理が必要です。
たとえば2万円の往復切符を従業員が立て替えた場合、次のように会計処理を行います。
| 借方(資産) | 貸方(負債・純資産) | |||
| 3月31日 | 旅費 | 10,000円 | 現金 | 20,000円 |
| 前払金 | 10,000円 | |||
| 4月1日 | 旅費 | 10,000円 | 前払金 | 10,000円 |
料金を後払いした際の会計処理
料金を先払いしたときは「未払金」という勘定科目を使用します。たとえば、2万円の往復切符を代理店経由の後払いで購入した場合は、次のように会計処理を行います。
| 借方(資産) | 貸方(負債・純資産) | |||
| 3月31日 | 旅費 | 10,000円 | 未払金 | 10,000円 |
| 4月1日 | 旅費 | 10,000円 | 現金 | 20,000円 |
| 未払金 | 10,000円 | |||
経費精算の仕訳日付や仕訳例について詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
月またぎ・年度またぎで経費精算する際の3つの問題点
月またぎ・年度またぎでの経費精算は可能なものの、問題点もあります。以下で内容を詳しく解説します。
社外からの信用低下を招く恐れがある
月またぎの経費精算は経理担当者の負担が増えるだけでなく、社外からの信用を低下させる原因にもなるでしょう。
特に年度をまたいで経費精算が発生すれば、決算の修正が必要です。決算を正確に申告できない企業だと判断され、投資家や取引先などからのイメージダウンにつながります。ルールを守れない企業だとみなされた結果、取引を見直される恐れもあります。
また、経費の額は税額の計算に使用する所得にも影響するため、税務調査での印象も悪化する可能性が高いでしょう。
企業と従業員の信頼関係への悪影響が起こる
社内のルールを守らない従業員が増えた場合、社内全体の雰囲気もルーズになります。ルールを守らなくても問題にならないという認識が広まれば、従業員の不正行為が発生しやすくなります。
また、ルールを守って適切に対応している従業員の不満もたまりやすくなるでしょう。企業と従業員や従業員同士の信頼関係にも悪影響が生じます。
信頼関係を維持するには、経費精算の明確な締切日を設定し、厳格に管理する必要があります。
経理担当のコストと余分な業務が発生する
月またぎや年度またぎの経費精算が発生すれば、経理担当者は余計な業務に対応する必要があります。月や年度をまたいで経費精算する従業員が多ければ、その分だけ経理担当者の負担も増えます。
民法上は5年以内なら従業員の経費精算が認められるため、仮に1年以上前の経費精算が行われても対応が必要です。その場合、通常の業務とは別に対応しなければならず、余計な人的リソースが割かれて企業の生産性が低下します。
月またぎ・年度またぎの経費精算を防ぐ4つの方法
月またぎや年度またぎの経費精算を防ぐには、どうすればよいのでしょうか。具体的な対策について解説します。
ルールや締切日を定め周知する
就業規則や社内規定で経費精算の締切日を定め、従業員へ周知しましょう。「毎月〇日まで」「領収書の受領後〇日以内」のように、締切日は具体的に定める必要があります。
ルールや締切日があれば、従業員の意識にも変化を与えられるでしょう。月末より少し前に締切日を設定すると、月またぎの経費精算の発生を防げます。ルールの遵守が当たり前だという共通認識をもたせることが大切です。
ただし、出張や急な経費発生により、やむを得ず月またぎの経費精算が発生するパターンもあります。経費の発生から5年間は支払いの請求が可能なため、状況を考慮した柔軟な対応も必要です。
経費精算規定への記載項目や作成のポイントについて詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
関連記事:経費精算規定(ルール)への記載項目や作成のポイントなどを解説
経費の申請方法を明確にする
経費の申請方法を明確にすることで、期日までに申請する従業員が増えるでしょう。そのためには、経費精算のガイドラインを作成するのがおすすめです。ガイドラインは定期的に見直して、修正が発生した際は、社内全体に周知することで文化・風土として定着しやすくなります。
経費精算のやり方については以下の記事で詳しく説明していますので、あわせてご参照ください。
関連記事:経費精算のやり方を徹底解説!経費の定義や種類、精算の流れなど
経費精算システムを導入して手続きをスムーズにする
従業員が経費精算を手間に感じていて手続きが遅れがちなケースも多いため、スムーズに対応できる環境の整備も重要です。
紙の経費申請書に内訳を書いたり、上司の承認を得たうえで経理担当者へ提出したりする作業には、多くの手間や時間がかかります。特に、泊まりがけの出張では記載すべき項目も多く、負担はさらに大きくなります。
経費精算の負担を減らすには、経費精算システムの導入がおすすめです。安価で導入できるサービスもあり、経費精算申請の効率化とペーパーレス化を実現できます。
また、インターネット上で利用できるクラウド型なら、外出先でもスマートフォンやタブレットで申請が可能です。経費が発生したタイミングで素早く経費精算ができるため、間に合わない、後回しにするといった問題の改善につながります。
経費精算システムの機能や選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事もお読みください。
関連記事:経費精算システムとは?導入するメリット・デメリットや機能、選び方を解説
法人カードを導入する
従業員からの経費の報告と、経理担当者の対応にタイムラグが起きなければ、経費精算の遅れや漏れの防止につながります。特に、経費の利用が多い従業員には、専用の法人カードを持たせておくのも1つの手段です。
以下の記事では法人カードの種類や特徴を詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:法人カードとは?種類別の特徴や違いを解説
月またぎ・年度またぎを防ぐためにスムーズな経費精算をするなら「バクラク経費精算」
経費精算の月・年度またぎは、自社の信頼低下につながるリスクもあるため、発生しないよう対策を講じる必要があります。まずは明確なルールを定めたり、簡単に経費精算の申請を出せる環境を整えたりすることが大切です。
スムーズな経費精算を目指すなら、電子帳簿保存法に対応している経費精算システム「バクラク経費精算」の導入がおすすめです。
申請者や経理担当者の入力ミスを防ぐ機能で、経費精算の流れを効率化できます。稟議申請と支払い申請を簡単に紐づけられ、一気通貫で管理可能です。また、領収書の使い回しや月またぎの領収書の自動検知機能があり、手戻りも少なくなります。
月・年度またぎの経費精算をなくして適切に処理するために、ぜひご検討ください。