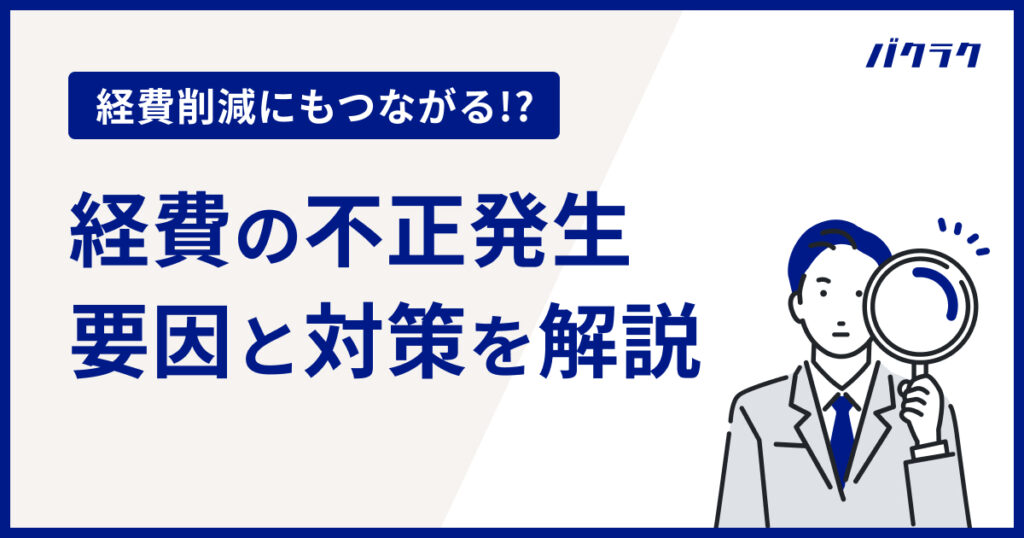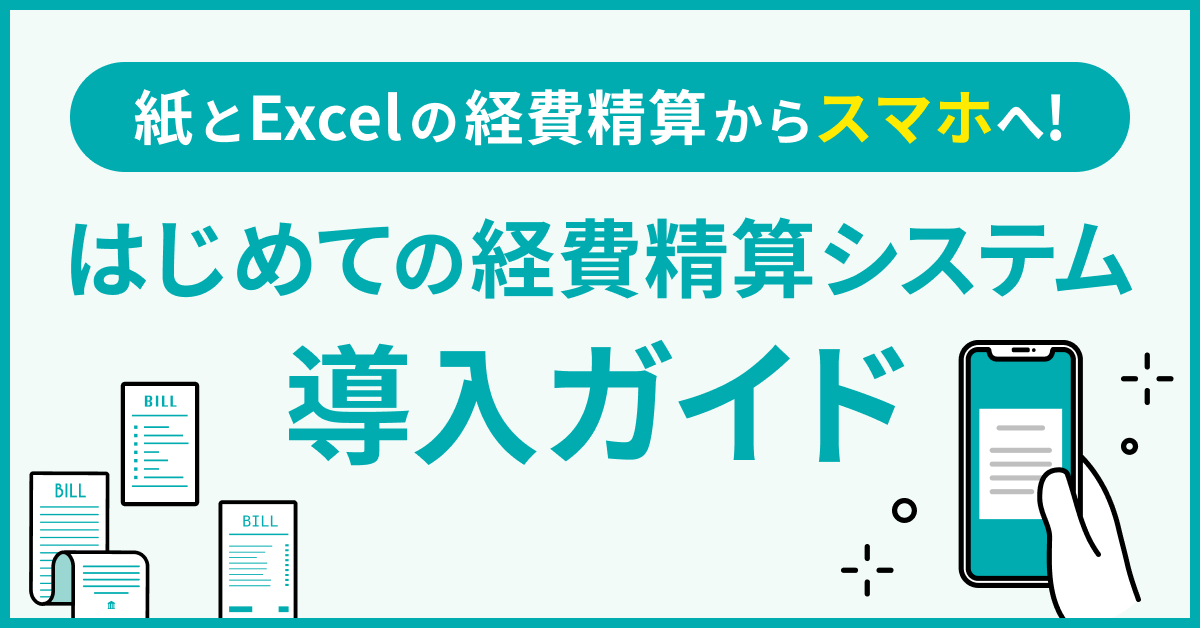決算期とは?一般的な設定時期・決め方のポイント、変更手続きなど
- この記事の3つのポイント
- 決算期とは事業年度の最終月のことで、法人の場合は任意の時期を設定できる
- 一般的な設定時期は3月だが、自社の都合で9月や12月を決算期にしている法人も多くある
- 決算期は自社の繁忙期や会社設立月、消費税の免税期間を考慮したうえで設定することが重要である
決算期は会社設立時に決めなければならないことの一つであり、決め方を誤ると経理部門の負担が増大したり税金で損をしたりする可能性があるため注意が必要です。
本記事では決算期の一般的な設定時期や決め方のポイント、変更手続きについて詳しく解説します。これから会社を設立する予定の方や、変更の流れについて知りたい方はぜひ参考にしてください。
決算期とは?
「決算期」とは、事業年度の最終月のことで「決算月」ともいいます。
事業年度は決算のために区切った1年以内の任意の期間であり、事業年度を決めると決算期も必然的に確定します。たとえば事業年度を「10月1日から9月30日まで」とした場合は、9月が決算期ということです。
決算期を迎えた法人は、事業年度の収益をまとめる「決算業務」を行わなければなりません。決算書を作成し、株主総会を開催したり申告納税を行ったりするのが決算期の一般的な流れです。
決算期はいつにするのが一般的?
決算期は、法人と個人事業主とで根本的に考え方が異なります。それぞれ何月に設定するのが一般的なのか、詳しく見ていきましょう。
法人
法人の場合は設立の時点で決算期を設定する必要があり、時期については任意です。3月を決算期とする法人が多く見られるものの、自社の都合で9月や12月に設定しているケースも少なくありません。
決算期を3月にする法人が多い背景として考えられるのが、国・地方公共団体が会計年度や予算期間、学校年度などを4月始まりにしているという実情です。特に行政機関との関わりが深い法人は、事業計画や予算策定のしやすさを考慮して3月を決算期に設定する傾向があります。
しかしながら近年は、海外企業に合わせて12月を決算期とする法人も多く見られます。グローバルな事業展開などの理由で海外企業との取引が多い法人は、決算期を12月にすることで決算業務をスムーズに進められるでしょう。
参考:国税庁「決算期別の普通法人数」
個人事業主
個人事業主の事業期間は1月1日から12月31日で、決算期は12月と一律に決まっています。法人と違い、任意で期間を設定できない点に注意が必要です。
決算期が忙しくなる理由
決算期に忙しくなるのは主に経理部門で、理由は日次業務や月次業務と並行して決算業務を進めなければならないためです。
決算報告は決算日の翌日から2カ月以内と決まっており、それまでに経理担当者は以下の業務をこなさなければなりません。
- 棚卸および在庫表の作成
- 決算整理仕訳
- 決算書作成
- 法人税・消費税の申告書作成と税務署への提出
たとえば3月が決算期の法人は、3月〜6月が繁忙期です。3月から徐々に決算の準備を始めて4月〜5月に決算業務を済ませます。その後、決算報告を目的として6月頃に開催される株主総会を終えるまでが決算期の大まかな流れです。
決算期は単純に仕事量が増えるだけでなく、一つひとつの業務に期限があることから、経理担当者に負担がかかりやすい時期といえます。
こうした課題の解決に効果的なのが、経費精算システムの導入です。経費精算システムを活用することで、煩雑な経理業務を効率的に進められるでしょう。
経理業務の作業量を75%削減できる「バクラク経費精算」について、詳しいサービス内容を知りたい方は以下のページをぜひご覧ください。資料配布も無料で行っています。
決算期を決めるときのポイント
決算期の適切な設定時期は法人ごとに異なり、判断を誤ると設立後の業務や資金繰りに支障をきたす可能性があります。
決算期を決めるときに考慮するとよい3つのポイントを紹介しますので、設定時期を迷っている方はぜひ参考にしてください。
自社の繁忙期を考慮して決める
まず欠かせないのが、自社の繁忙期を考慮することです。閑散期と繁忙期がはっきりしている法人は、繁忙期を避けることによって決算業務に集中して臨めます。仕事量の増加による、経理担当者のミスなども起こりにくくなるでしょう。
また繁忙期は、想定外の利益や損失が出やすい時期でもあります。決算間近のタイミングで起こると対策を講じるのが難しいため、余裕をもって業務を進めるには繁忙期以外を決算期に設定するのが効果的です。
一方で、繁忙期は大きな利益が出やすい点に着目し、あえて決算期を重ねる考え方もあります。資金面に余裕が生じることで、決算後の納税をスムーズに行えるでしょう。特に顧問税理士を雇っている法人の場合、3月を避けることでお互い時間に余裕をもってやり取りできるメリットもあります。
決算業務は決算期以降も2カ月程度は業務が立て込むことを理解したうえで、自社の繁忙期を考慮しつつ設定してください。
会社設立月に合わせて決める
決算期を、会社設立月から1年後に設定するのも有効な選択肢です。設立直後はさまざまな手続きに追われることも多く、決算期をすぐに迎えると社内に混乱を招く可能性があるためです。
1年間で着実に売上を積み上げつつ、決算業務に必要な費用や人的リソースを確保しましょう。たとえば会社設立日が7月1日の場合、6月を決算期にすることで最大の期間を空けられます。
ただし、無理に1年後とする必要はありません。会社設立後の第1期(事業年度)は設立日から1年以内の期間であればいつでも構わないので、自社の経営状況や経理部門の状況を見通しつつ最適な時期を検討してください。
消費税の免税期間を考慮して決める
免税期間の恩恵を最大限受けるために、会社設立月からもっとも遠い時期を決算期とする方法もあります。資本金が1,000万円未満の会社は、原則として設立から2期目まで消費税の納税が免除されるためです。免税期間が長いほど、資金繰りに余裕が生じやすくなります。
たとえば4月1日に会社を設立した場合は翌年3月、10月1日設立であれば翌年9月を決算期に設定しましょう。
決算期の変更に必要な手続き
決算期は、以下の手続きを順に行うことで変更が可能です。
- 定款の変更
- 税務署などへの書類の提出
決算期の変更は事業年度が変わることを意味しているため、まずは定款に記載された事業年度の変更手続きを行わなければなりません。
定款の変更には、普通決議より重要度が高いとされる特別決議での承認が必要です。特別決議とは議決権の過半数に該当する株主が出席する株主総会で、議決権の2/3以上の賛成を必要とする決議のことです。
定款の変更が認められたら、速やかに所轄税務署・都道府県税事務所・市役所へ届出を行います。変更後の定款や株主総会の議事録の写しとともに、異動届出書を提出して手続きは完了です。
なお、決算期の変更には資金繰りや経理業務の効率を改善する効果が期待できる一方で、イレギュラーな時期に決算業務が発生するという懸念点もあります。
決算期の変更に伴い1年以内に決算・確定申告・納税を行う義務が生じ、経理部門が多忙になったり納税が前倒しになったりすることを留意しておきましょう。
スムーズな決算業務を実現する経費精算システム「バクラク経費精算」
法人は決算期を任意で設定でき、一般的には3月を決算期とするケースが多い傾向です。しかしながら、自社の繁忙期や会社設立月、消費税の免税期間などを考慮したうえで適切な時期を検討することが重要です。
経費精算は通常、決算期間内に発生した経費のすべてを事業年度内に計上しなければなりません。そのため、年度末に経費精算が立て込むと、経理部門は大きな負担を強いられるでしょう。
「バクラク経費精算」は、決算業務を支援する経費精算システムです。稟議申請と支払申請の紐づけによって一気通貫の管理が可能となり、経費の申請から承認、支払いまでの流れがスムーズになります。
また、通常は手入力や目視での確認が必要な作業も自動化されているため、ミスを減らしやすい点もメリットの一つです。
さらに、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法令にも対応しており、あらゆる書類の保管もシステム上で一本化できます。結果的に財務データの正確性が向上し、決算業務をスムーズに進められるでしょう。
煩雑な決算業務を効率的に行いたいと考えている方は、バクラク経費精算の導入をぜひ検討してください。