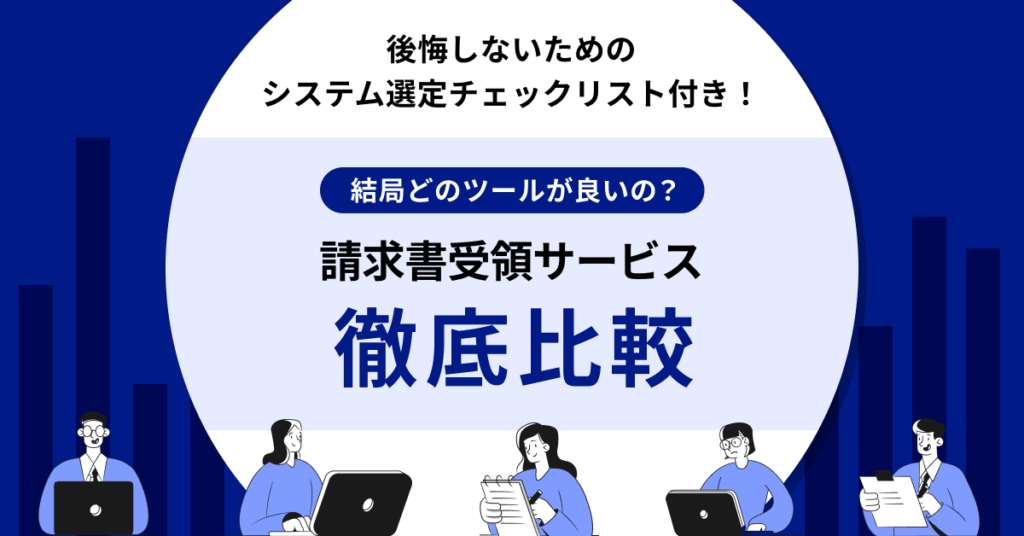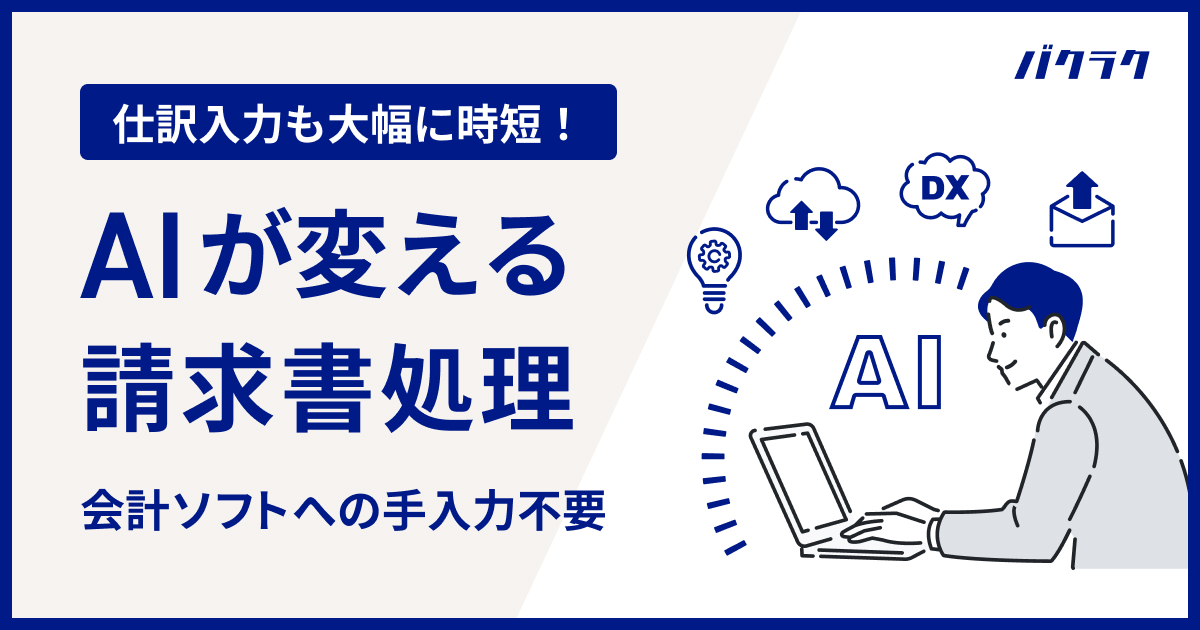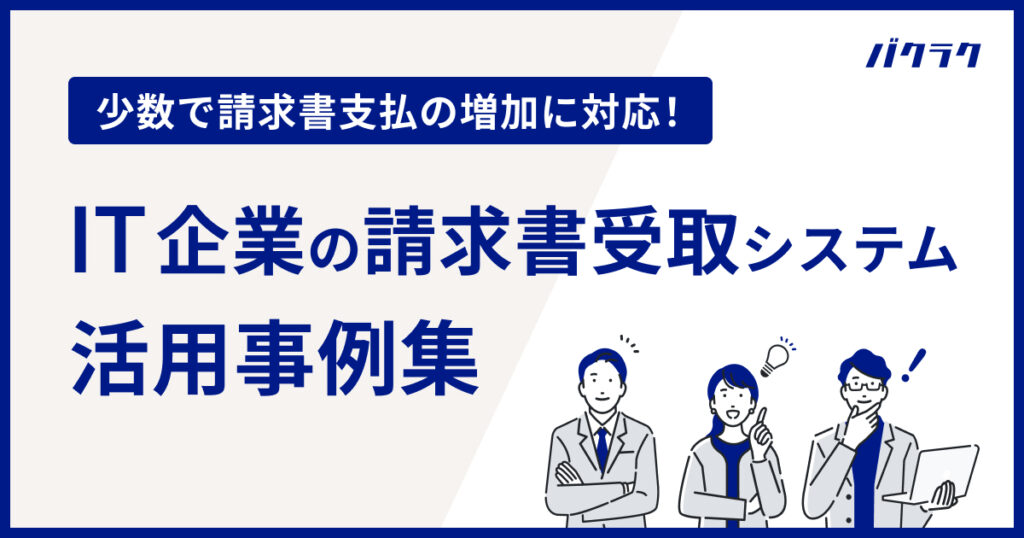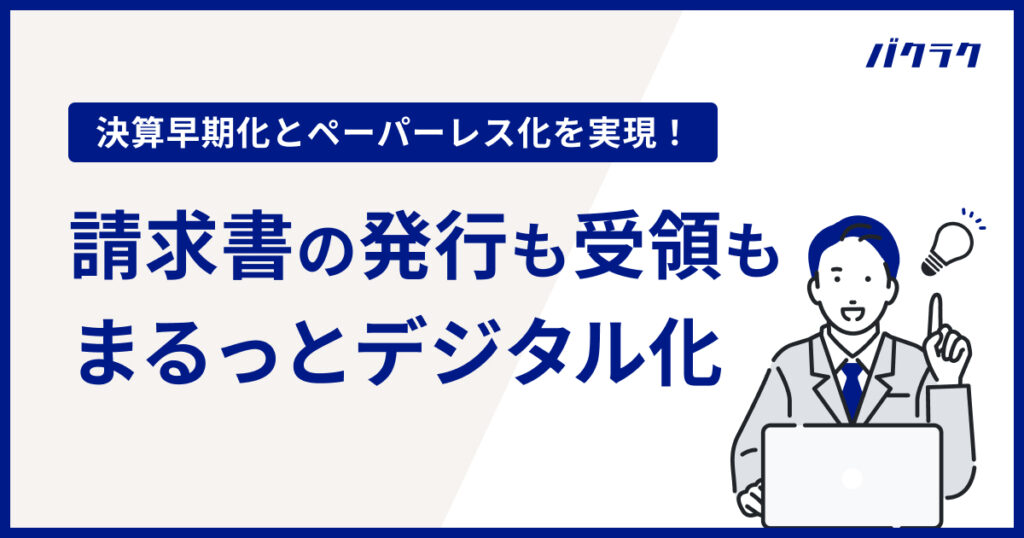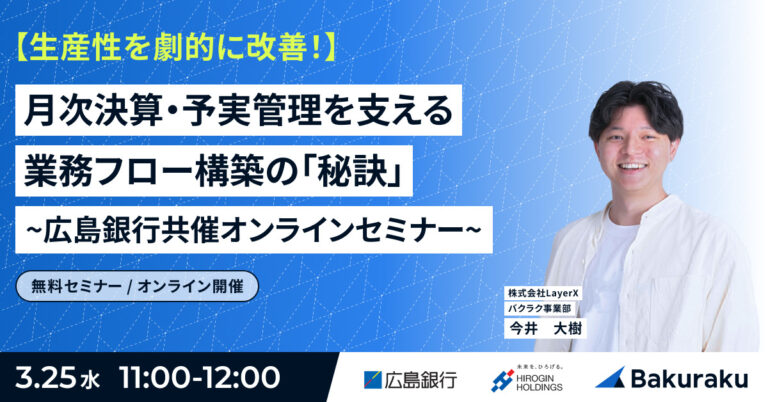請求書チェックを効率化するポイントとは?発行時・受領時に分けて解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 請求書発行前には支払期日や送付方法、請求金額などを確認する必要がある
- 請求書のチェック業務には、確認事項が多い・整理に手間と時間がかかるなどの課題がある
- 自社に必要な機能がある請求書システムを導入することで、請求書チェックを効率化できる
請求書を作成する際には、事前のチェック業務が欠かせません。取引先との信頼関係を保つためにも、適切かつ、わかりやすい内容の請求書を発行する必要があります。
しかし、請求書は確認すべき項目が多く、整理に時間や手間がかかってしまいがちです。手作業での請求書チェックに煩わしさを感じている方も多いでしょう。
そこで本記事では、請求書チェックを効率化するポイントを紹介します。発行時・受領時に分けて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
請求書受領サービス比較資料のご紹介
受領した請求書の受取〜仕訳、支払といった諸業務を効率化するために重要な役割を担う請求書受領サービスの比較表や選定のポイントを紹介した資料が以下のリンクからダウンロードできます。
全6社のサービスの機能や値段の違いを記載した比較表に加え、サービスのトライアル時などに確認しておきたいチェックリスト付きです。システム選定時の参考にぜひお役立てください。
請求書チェックを効率化するポイントとは?発行時・受領時に分けて解説
請求書発行前のチェックポイント
請求書発行前のチェックポイントを紹介します。必須事項の記載漏れがあると、正しく入金されなかったり、消費税の仕入税額控除を受けられなかったりする可能性があるため、しっかり押さえておきましょう。
請求日と支払期日
請求書を発行する際は、請求日と支払期日が明記されているかを確認する必要があります。
請求日によって入金日は変化するため、取引先の締め日や支払日に合わせて日付を記載しなければいけません。あらかじめ支払期日が決まっている場合も、請求書に必ず記載しておきましょう。
ただし、請求日と請求書を送付すべき日が異なるケースもあるため注意が必要です。なかには送付の期限を定めていたり、請求日を統一したりしている企業もあります。
また、振込先の情報が記載されているかの確認も必須です。請求書は発行のタイミングなど、相手に配慮すべき点が複数あるため、事前に確認しておきましょう。
送付方法・送付先・送付期日
請求書を発行する際は、送付方法や送付先、送付期日を確認する必要があります。
送付方法は郵送やFAX、メール、電子システムにアップロードなどがあり、企業によって対応が異なります。「原本の郵送必須」「メールでのPDF送付のみでOK」など、企業ごとに送付方法を確認しておきましょう。
また、請求書発行時には送付先(宛先)と送付期日の確認も必須です。企業名や住所またはメールアドレス、部署および担当者の役職などを把握し、間違いがないように記載しましょう。
送付期日に関しても「締め日の翌5営業日以内」など企業ごとで扱いが異なります。送付期日に間に合うよう余裕をもって対応することが大切です。
なお、請求書の形式は特に決まりがなく、必要な項目が記載されたものであれば、ExcelやWord、手書きやシステム利用など、いずれの方法で作成しても問題ありません。
請求金額の書き方
請求書を発行する際は、請求金額の書き方にも注意が必要です。1円未満の端数が発生した場合はどう処理するかを事前に確認しておくことで、請求金額の記載ミスや修正による手間を防げます。
消費税額によっては、請求書に1円未満の端数が生まれる場合もあるでしょう。財務省では、端数処理の方法は「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」などは任意、かつ企業の判断で端数処理の方法を決めて構わないとしています。
そのため、請求書を発行する際は、事前に取引先と端数処理の方法に関する認識をすり合わせておき、社内でも対応を統一しておかなければいけません。
参考:財務省「総額表示に関する主な質問」
掛売方式と都度方式のどちらか
請求書作成時には、掛売方式と都度方式のどちらかで発行するのかも確認しておく必要があります。「掛売方式」「都度方式」の概要は、以下のとおりです。
| 方式 | 掛売方式 | 都度方式 |
| 概要 |
|
|
| メリット | 請求書発行の手間を削減できる | 代金を早く回収できる |
| デメリット | 資金繰りや取引相手との信頼性に注意が必要 | 請求書の作成・発行回数が増えるため手間がかかる |
どちらの方式をとるかは取引先との取り決めによって異なるため、必ず事前に把握しておきましょう。
請求書発行時にチェックすべき記載項目
請求書に記載すべき項目に明確なルールはありません。ただし、請求業務を正しく行うためには、いくつか記載しておくべき項目があります。
請求書発行時にチェックすべき記載項目は、以下のとおりです。
- 宛名
- 発行年月日
- 発行者の氏名または名称
- 請求書番号
- 請求金額
- 振込先
- 支払期日
- 取引年月日
- 取引内容
宛名や発行者の氏名、請求金額をはじめ、発行年月日や取引内容、振込先情報の記載も必須です。請求書に記載する日付は、請求書の発行日もしくは事前に確認した締め日を記載します。
取引内容の項目には、商品名・単価・数量・合計金額などを具体的に記載する必要があります。なお、請求書への押印は必要ありません。
送付先の企業が支払い時に困らないよう、上記すべての項目を記載した請求書を発行しましょう。
請求書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。項目ごとの書き方や請求書作成時の注意点も紹介しているので、気になる方はぜひ読んでみてください。
請求書チェック業務における課題
請求書チェックにおいては、さまざまな課題があります。ここでは、具体的にどのような課題があるか解説します。
請求書の整理に手間や時間がかかる
請求書の形態は紙、電子データ、専用Webサイトのサービスなどがあり、取引先によって取扱いがさまざまです。そのため、請求書の整理には手間と時間がかかります。
特に紙の請求書は原本をファイリングしなければならず、担当者の業務負担も大きくなります。また、請求書が経理担当者に直接届いた場合には、請求内容について担当者へ個別に確認しなければなりません。
請求書の確認事項が多くややこしい
請求書には、宛名、発行日、取引内容などの確認事項が多く記載されています。また、取引先によってフォーマットが異なるため、確認の作業は煩雑になりがちです。2023年10月に導入されたインボイス制度によって、適格請求書に関する確認の手間がより増えています。
請求書処理のフローが増えミスが発生しやすくなる
請求書処理のフローが多いとミスが発生しやすくなり、未払いを招く原因になります。
特に紙の請求書の場合、発送する際に宛名ラベルを貼り間違えたり封入のミスが生じたりする可能性も否定できません。情報漏えいの問題に発展するだけでなく、取引先企業との関係性の悪化を招く危険性もあります。
また、請求書の管理においては、原本と入力データの照合も必要です。取引先が増えると人的ミスが増える確率がより高まります。
紙と電子データを二重に保管しなければならない
請求書の形式は、主に紙と電子データの2種類です。2024年以降、紙での請求書の保存が禁止されたことで、スキャナやデータ整理など経理担当者の業務負担が追加されています。
ペーパーレス化が進んでいない企業は、紙と電子データを二重に保管する必要があります。管理がより煩雑になりやすく注意が必要です。
請求書チェックを効率化する方法
請求書チェックを効率化するには、どうすればよいのでしょうか。ここでは、具体的な方法について解説します。
請求書のデジタル化
請求書をデジタル化すれば、保管と管理が簡単になります。請求書をデジタル化するための環境を整えつつ、紙の請求書を受領した際は要件を満たしてスキャナ保存しましょう。
スキャナ保存については以下で詳しく解説しています。
※参考:電子帳簿保存法とは?2024年義務化の内容や注意点などわかりやすく解説
請求書受領のシステム化
請求書受領システムや会計システムなどを導入すれば、請求書業務を効率化できます。場所を選ばず作業を進められるため、テレワークも導入可能です。会計システムは会計業務の一連の流れに対応している場合が多く、請求書受領業務の改善に適しています。
※参考:請求書受領をツールで自動化する方法 導入メリットとツール選定のポイントを解説
入金確認・消込の自動化
効率化には入金確認や消込の自動化が効果的であり、自動消込ツールの導入が選択肢の1つとなります。制度変更への対応も自動で行われ、経理担当者の負担を軽減可能です。ただし、コストがかかるため、ExcelやGoogleスプレッドシートを活用する簡易的な効率化も視野に入れましょう。
請求書処理の効率化
請求書の入力や消込作業に加え、支払予定表の作成や仕訳起票なども自動で行うとさらなる効率化につながります。繰り返し行う入力作業について手間を削減できます。また、紙の請求書の印刷、封入、宛名のラベル貼りといった一連の流れをデジタル化し、手作業を減らすことも大切です。
ヒューマンエラーの削減
システム化に取り組むと担当者同士のやり取りが少なくなり、ヒューマンエラーも減らせます。たとえば、請求書を紛失するリスクが低くなります。支払予定表の自動作成と消込により、支払いの漏れやミスも防止可能です。セキュリティを高め、より安全な管理体制を確立できます。
リモートワークの導入
システムを導入して場所を問わず必要なデータにアクセスできるようにすれば、リモートワークを実現できます。リモートワークに対応できる環境なら、支店に届いた請求書を本社でリアルタイムに処理することも可能です。
請求書チェックを効率化!請求書システムを導入するメリット
請求書の作成やチェックには、手間がかかります。また、手作業による請求書のチェック業務にはさまざまな課題があるため、業務の正確性や効率化を目指すならシステムの導入がおすすめです。
ここでは、請求書システムを導入するメリットを紹介します。
手間を省いて業務効率化できる
請求書システムを導入するメリットは、手間を省いて業務効率化ができることです。
2024年に電子帳簿保存法が改正されたことで、請求書は電子データでの保管が義務付けられています。請求書をデジタル化すれば、法律に遵守しつつ、保管や管理も容易になります。
自動消込ツールの導入によって、入金確認や消込を自動化することも可能です。繰り返し行う入力作業においても手間を削減できるほか、紙の請求書の印刷や封入、宛名のラベル貼りといった一連の流れもデジタル化できます。
また、請求書システムは会計システムと連携できるものが多く、請求書受領業務の一元管理が可能です。システム操作は場所を選ばないため、テレワークにも対応できます。
法改正にも対応しているシステムなら、会計処理や保管時の手間も省けます。請求書システムを導入することで、発行側・受領側ともに手作業を減らし、業務効率化につながるでしょう。
ヒューマンエラーを減らせる
システム化に取り組むと担当者同士のやり取りが少なくなり、請求書の紛失などのヒューマンエラーを減らせます。
支払予定表の自動作成と消込により、支払いの漏れやミスも防止可能です。セキュリティを高め、より安全な管理体制を確立できます。
リモートワークが可能になる
リモートワークが可能になる点も請求書システムを導入するメリットの一つです。請求書システムの導入により、請求書の発行や受領を紙から電子データに移行すれば、出社せずとも業務が進められるようになります。
リモートワークに対応できる環境なら、支店に届いた請求書を本社でリアルタイムに処理することも可能です。多様な働き方に対応でき、従業員の負担軽減につながります。
法改正にも柔軟に対応できる
請求書システムを導入すれば、法改正にも柔軟に対応できるようになります。システムが自動的にアップデートされることで、今後法改正がある場合でも柔軟な対応が可能です。
法律に関する知識がなくても問題ありません。担当者の業務負担を最小限にしつつ、安全に請求書業務を行えます。
請求書発行システムについては以下の記事でも詳しく解説しているので、ご一読ください。
請求書システムの導入を成功させるポイント
請求書システムは数多く展開されていますが、業務効率化を実現するためには自社に合ったシステムを導入する必要があります。そこで以下では、請求書システムの導入を成功させるポイントを解説します。
解決したい課題を明確にする
請求書システムの導入を成功させるポイントは、解決したい課題を明確にすることです。自社の課題を把握せずにシステムを導入しても効果を実感できません。
システム導入を検討する際は「紙の請求書が多く、開封や保管に時間がかかる」「チェック時に人為的ミスが起こりがち」など、自社や部署が抱える課題を整理しましょう。
現在の業務フローや多発するミスを整理し「システム導入によって解決したい課題」を明確にすることが大切です。課題を明確にすると、自社の業務改善に必要な機能がわかるようになります。
以下の記事では、請求書をペーパーレス化するメリット・デメリットを詳しく解説しています。
関連記事:請求書をペーパーレス化するメリット・デメリット|進め方も紹介
自社に合うシステムを選定する
請求書処理に関してはさまざまな種類のシステムがありますが、自社に合うシステムを選定することが大切です。そのためには、自社が抱えている課題を可視化し、確実に改善できるシステムを導入する必要があります。
たとえば、どうしても紙の請求書が必要な場合、請求書の郵送代行機能がついているシステムを選ぶと手間を減らせます。自社特有の課題や既存システムの互換性を考慮すれば、システム導入による業務効率化を実感できるでしょう。
経理担当者の負担軽減を目指す
システムを導入する際は、通常業務と並行して対応する必要があります。経理担当者の負担を増やさないよう、請求書業務の流れに配慮したスケジュールを組みましょう。
なお、日頃使用する担当者が使いにくいシステムを導入してしまうと、うまく運用できません。そのため、経理担当者が実際に操作して業務のしやすさを確認することも大切です。
「バクラク請求書受取」なら毎月の請求書チェックがスムーズになる
請求書の処理には手間がかかりますが、システム化や自動化により作業の効率を高められます。ヒューマンエラーの防止やリモートワークの実現にもつながることから、請求書業務の効率化に取り組むために、請求書システムを導入する企業が増えています。
「バクラク請求書受取」は、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応している請求書受領システムです。請求書PDFをWeb・メールから自動で回収し、請求書業務を効率化できます。
手入力ゼロで請求書チェックにかかる工数を削減できるほか、入力ミスも防止できる点も魅力です。請求書業務の大幅な削減につながるため、ぜひ活用してください。