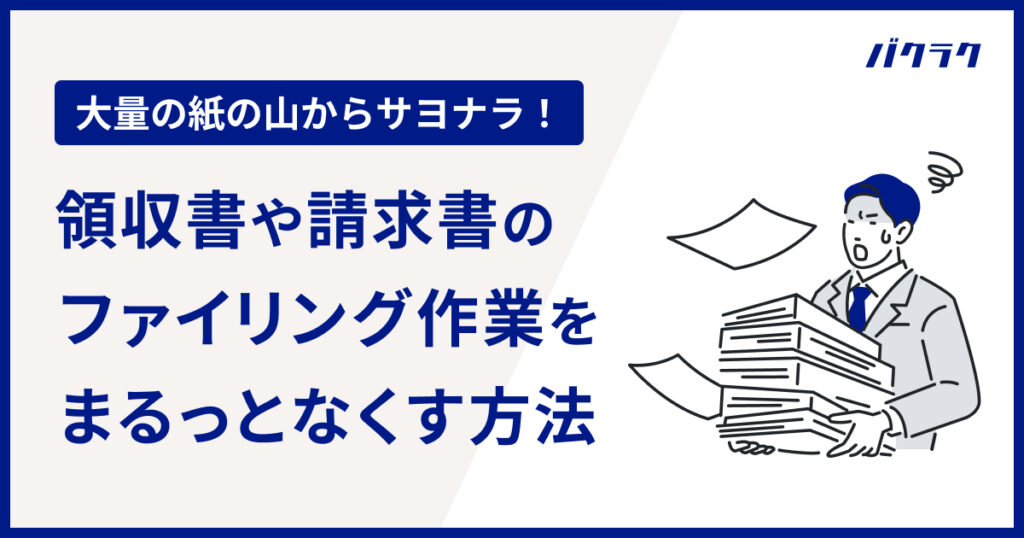領収書の保管・管理方法は?手間と時間を削減するおすすめの方法を法人・個人事業主向けに紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 法人は原則7年間、個人事業主は確定申告の方法に応じて7年間または5年間の領収書保管が必要
- 紙で保管する場合は、見た目の美しさより探しやすさを重視してまとめることが重要
- 電子取引の場合は電子データでの保存が必須で、真実性担保や不正防止のための取り組みも必要
経理担当者が抱える課題の一つに、領収書保管業務の煩雑さがあります。整理に手間と時間がかかり、お困りの方もいるでしょう。
本記事では領収書の保管期間や、効率的な保管方法を詳しく解説します。領収書の取り扱いについて理解を深め、今後の業務にお役立てください。
領収書や請求書のファイリング作業をまるっとなくす方法とは?
書類のファイリングや保管など、紙の書類管理に時間がかかっていませんか?アナログな管理方法だと、従業員からの申請や承認状況が分からないことによるコミュニケーションストレスも発生します。
こうした紙の書類の管理の手間をなくすときに押さえておきたいポイントをまとめた資料がダウンロードできます。自社のペーパーレス化状況がわかるチェックリスト付きです。ぜひご活用ください。
領収書の保管・管理方法は?手間と時間を削減するおすすめの方法を法人・個人事業主向けに紹介
領収書の保管期間は原則7年
領収書は保管方法に関わらず、一定期間の保管が法律で義務付けられています。
法人の場合は、原則として7年間の保管が必要です。個人事業主の場合、青色申告では7年間、白色申告では5年間と定められています。ただし、年度内に欠損金が発生した場合は10年間の保管が必要な点に注意しましょう。
領収書の保管について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
領収書を紙の状態で保管する方法
領収書を紙の状態で保管する場合の、具体的な方法を2つ紹介します。メリット・デメリットや注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
ファイルや封筒で保管
業務効率を重視する場合は、ファイルや封筒での保管がおすすめです。領収書をファイリングすれば、複数枚の領収書も見やすく整理できます。領収書が少ない会社であれば、封筒に入れて保管するのも一つの方法です。
しかしファイルや封筒での保管には、過去の領収書を見つけにくい難点があります。そのため、膨大な領収書の管理には不向きです。紛失のリスクを避けるために、ファイルや封筒からの落下を防ぐ工夫も検討しましょう。
ノートや用紙に貼り付けて保管
わかりやすさを重視する場合は、ノートや用紙に貼り付けて保管する方法が効果的です。領収書を時系列にまとめることで、過去の領収書も比較的容易に探せます。糊やテープで確実に貼り付ければ、紛失の心配もないでしょう。
デメリットは、貼付作業に手間と時間がかかる点です。見た目の美しさより、探しやすさに重きを置いてまとめることが重要です。領収書を単に貼り付けるのではなく、1日ごとにページを変える、種類ごとに貼付するなどのルールを決めて運用しましょう。
領収書を効率的に保管するためのステップ
領収書の保管は、基本的に3つのステップで行います。効率良く整理できるように、手順を押さえておきましょう。
保管用のアイテムを用意する
まずは、領収書の整理に必要なアイテムを用意します。
ファイルで保管する場合は、内容物を確認しやすいクリアファイルや、領収書の保管に特化した専用のファイルなどがおすすめです。封筒で保管する場合は、必要に応じてクリップやホチキスも用意しましょう。
ノートや用紙に貼り付ける場合は、分類ごとに透明のチャック付きポリ袋に入れると紛失のリスクを軽減できます。作業中に不足しないよう、保管用のアイテムは多めに準備しましょう。
分類の項目を決定する
月別・科目別・取引先別など、領収書の分類項目を決めます。月別は期間ごとのお金の流れを把握しやすい一方で、取引先が多いと必要な領収書を探す際に時間を要します。
確定申告をスムーズに行いたい場合は、科目別での保管がおすすめです。ただし、毎月のお金の流れや取引先ごとの金額を把握しにくい難点があります。取引先の数が少ない場合は、取引先別に分類するのも一つの選択肢です。
帳簿や会計ソフトに入力する
分類項目に従って領収書を整理し、記載内容を帳簿に記録または会計ソフトに入力します。入力が完了した領収書から順に保管することで、入力の重複を防止できます。分類した領収書の乱雑化を防ぐためにも、入力済みの領収書は適宜収納しましょう。
領収書を電子データとして保管する方法
本章では、領収書を電子データとして保管する2つの方法をお伝えします。それぞれの特徴を理解して、最適な方法で領収書を保管しましょう。
スキャナで読み取ってデータとして保存
電子帳簿保存法の改正に伴い、紙の領収書も一定の要件を満たせば電子データ化して保存可能です。電子データが原本とみなされるには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 領収書発行から2カ月+7営業日以内の入力である
- 解像度が200dpi以上である
- カラー画像でのスキャンまたは撮影である
- 検索機能が搭載されている
- 見読可能性が確保されている
- 入力者情報が確認できる
- タイムスタンプが付与されている など
電子データ化は、紙の領収書をスキャナで読み取るほか、スマートフォンやデジタルカメラで撮影しても問題ありません。読み取り後、紙とデータの内容不一致や折れ曲がりがなければ原本は破棄できます。
紙の領収書を電子データ化することで、書類整理や保管場所の確保に必要な手間と時間を削減可能です。経年劣化しやすい感熱紙の領収書などを、良好な状態で保存できるメリットもあります。
スキャナ保存が認められる要件やメリットは、以下の記事に詳しくまとめていますので参考にしてください。
関連記事:経費精算で領収書の原本はどう保管する?メリットの多い電子保存の方法や注意点を解説
電子取引したデータのまま保存
電子データで受け取った領収書は、印刷せず電子データのまま保存することが義務付けられています。たとえばオンラインショップで商品を購入した際、メールにPDFファイルとして添付された領収書は電子データに該当します。
電子取引のメリットは、領収書の経年劣化や紛失のリスクがなく、万が一データが消失しても復旧できうる点です。保管場所が不要なほか、システム上で過去のデータを容易に検索できるため業務効率化も期待できます。
ただし、電子データを保存する際は、真実性・可視性確保のための取り組みが欠かせません。また、領収書の受領方法によって保存要件が異なる点にも注意が必要です。電子帳簿保存法に則り、適切な方法で領収書を保存しましょう。
タイムスタンプの仕組みや領収書の保存方法について理解を深めたい方は、以下の記事を参考にしてください。
「バクラク経費精算」は電子帳簿保存法にも対応
領収書は、法律により一定期間の保管が義務付けられています。紙と電子データのどちらで保存するかは、事業規模や領収書の量を考慮しつつ検討するのがおすすめです。電子取引の場合は、印刷せず電子データのまま保存が必要な点に注意しましょう。
領収書や請求書に関わる業務の効率化には、バクラク経費精算の導入がおすすめです。バクラク経費精算は、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法令に対応しています。タイムスタンプが付与されるため、証憑類の原本保存は不要です。
また申請・承認時に、書類がスキャナ保存要件に適しているか自動判定する機能も搭載されています。手戻りの手間が減り、経理担当者の業務効率化につながるでしょう。
バクラク経費精算について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。無料の資料ダウンロードやトライアルもご利用いただけます。