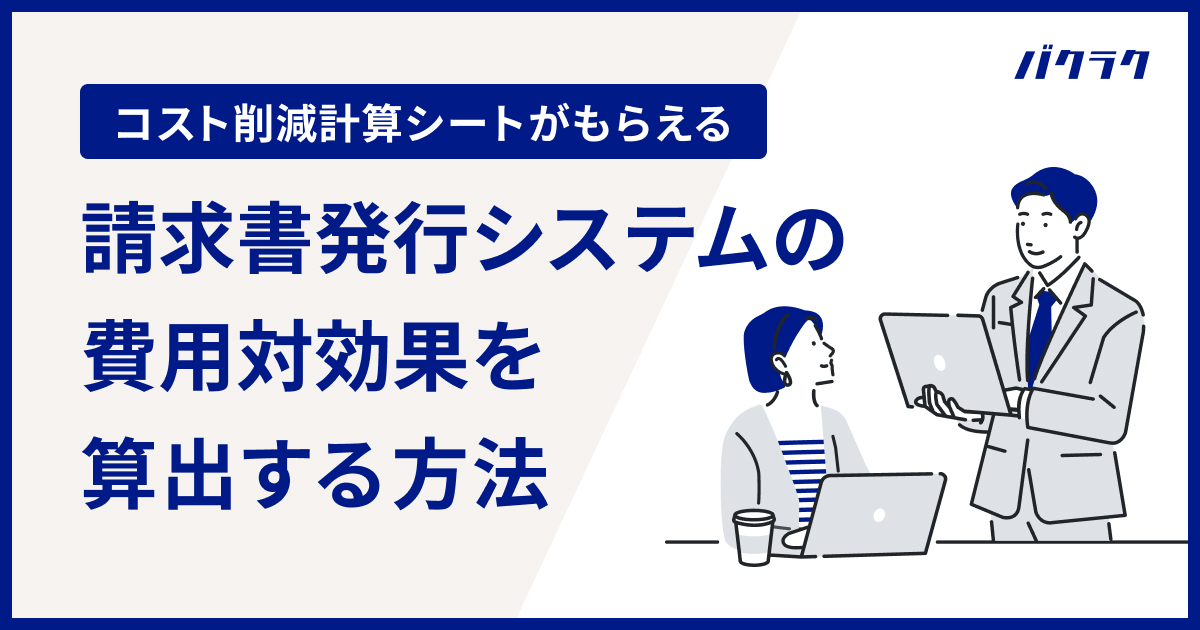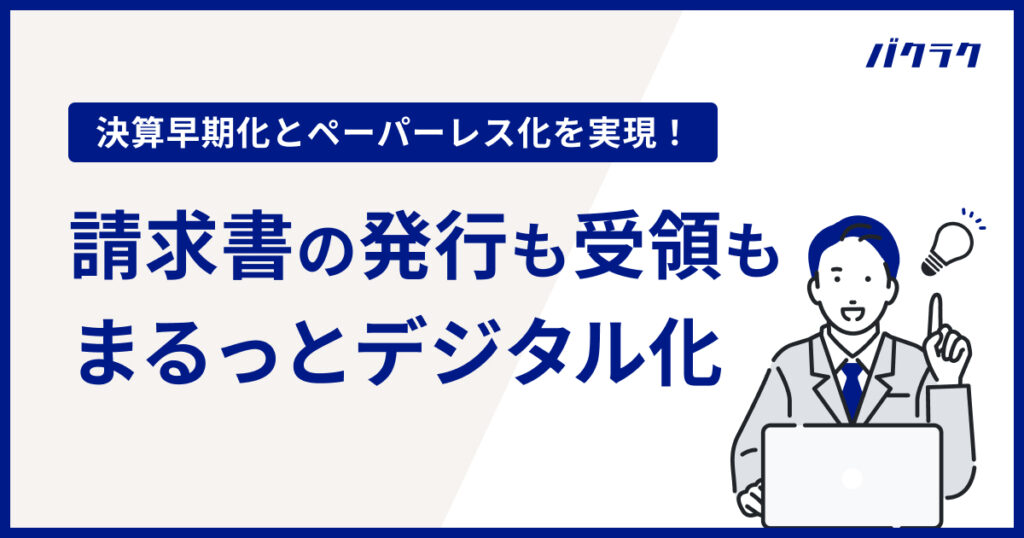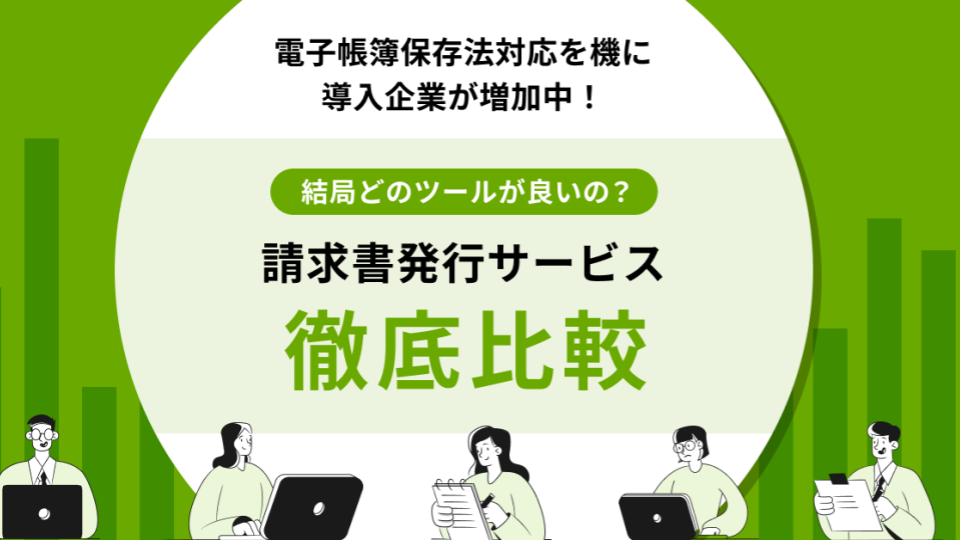請求書をメールで送付/受領するときの例文と注意点を解説
- 最終更新日:2025-03-21
- この記事の3つのポイント
- 請求書をファイルにしてメールで送ることは法的に問題なく、紙の請求書と同じ有効性をもつ
- 請求書は確定後の編集や変更ができないよう、PDFファイル変換にしてからメールに添付する
- 請求書送付を郵送からメール送付に変更する際は、取引先へ理由を説明し了承を得た上で変更する
請求書を送付する方法は、郵送とメールの2つに分けられます。しかし最近では、電子帳簿保存法に対応するために請求書をメールで送るケースが増えています。そのため、メールで送る場合のルールやビジネスマナーについて、正しく理解しておく必要があるでしょう。
本記事では請求書をメールで送付する場合の例文、確認事項やルールについて、詳しく解説します。
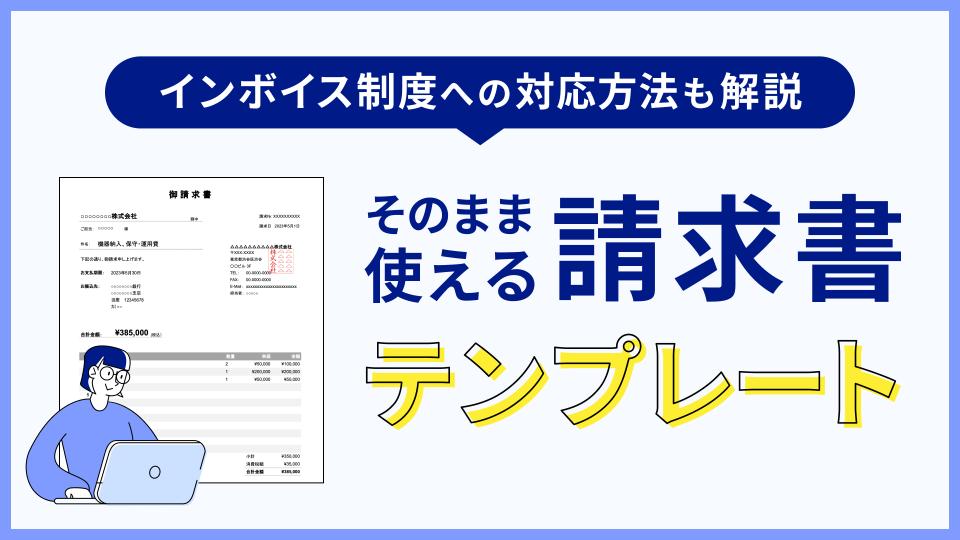
インボイス制度への対応方法も解説 !そのまま使える請求書テンプレートのご紹介
請求書テンプレート5点セット(複数税率、単一税率10%、単一税率8%、源泉徴収あり、源泉徴収なし)をダウンロードいただけます。
インボイス制度対応の留意点と対応のポイントについても記載しています。
請求書をメールで送付/受領するときの例文と注意点を解説
請求書はメールで送付してもいいの?
「請求書をメールで送ることは法的に大丈夫なのか」と、疑問に感じる方もいるでしょう。
取引の証明となる請求書をメールで送るのは法的に問題なく、紙の請求書と同じ有効性をもちます。
そもそも、請求書の発行そのものは、法律的に義務付けられているわけではありません。しかし、企業として「請求書の存在は不可欠なもの」という考えが多く、請求書を発行するケースが多いでしょう。
請求書をメールで送付/受領する場合の例文
請求書をメールで送付/受領する場合の例文を、複数のパターンに分けて紹介します。
例1)請求書をメールで送付し、原本は郵送しない場合
請求書をメールで送付する場合、請求書はPDFファイルにしてメールに添付しましょう。
請求書をメールで送付し、原本は郵送しない場合の本文の文例は以下のとおりです。
件名:10月分請求書送付 株式会社〇〇 担当〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の✕✕です。 日ごろより弊社のサービスをご利用いただき、心より感謝申し上げます。 「◇◇◇」の件につきまして、10月分の請求書を送付させていただきます。 内容をご確認いただき、期日までにお支払いいただけますようよろしくお願い申し上げます。 添付ファイル【abcd_efg_2025.02.02.pdf】 ご請求金額:¥〇〇〇 お支払期日:〇〇年〇〇月〇〇日 ご不明な点や、添付ファイルが見られない等の不都合がございましたら、お手数ですが〇〇までお問い合わせください。 また、請求書の原本郵送が必要でしたらお気軽にご連絡ください。 Tel:〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇〇〇 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 株式会社△△ ✕✕ |
例2)請求書をメールで送付し、原本も郵送する場合
取引先から請求書の原本が求められた場合は、請求書をメールで送付した上で原本も郵送しましょう。
請求書をメールで送付し、原本も郵送する場合の本文の文例は以下のとおりです。
件名:10月分請求書送付 株式会社〇〇 いつもお世話になっております。株式会社△△の✕✕です。 日ごろより弊社のサービスをご利用いただき、心より感謝申し上げます。 「◇◇◇」の件につきまして、10月分の請求書を送付させていただきます。 内容をご確認いただき、期日までにお支払いいただけますようよろしくお願い申し上げます。 添付ファイル【abcd_efg_2025.02.02.pdf】 ご請求金額:¥〇〇〇 お支払期日:〇〇年〇〇月〇〇日 ご不明な点や、添付ファイルが見られない等の不都合がございましたら、お手数ですが〇〇までお問い合わせください。 請求書原本も郵送させていただきました。 Tel:〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇〇〇 mail:〇〇〇@〇〇.com 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 株式会社△△ ✕✕ |
例3)請求書を受領した場合
請求書を受領したら、取引先にメールで連絡しましょう。
請求書番号やファイル名だけでなく、いつまでに振り込むかを明記すると丁寧です。万が一振り込みが遅れる場合は、その旨を一言添えるとよいでしょう。
請求書を受領した場合の、本文の文例は以下のとおりです。
件名:請求書受領のご連絡 株式会社〇〇 担当〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の✕✕です。 本日、貴社より下記の請求書を確かに受領いたしましたので、ご連絡申し上げます。 請求書番号:INV-2025-002 ファイル名:abcd_efg_2025.02.02.pdf 発行日:〇〇年〇〇月〇〇日 請求金額:¥〇〇〇 内容を確認の上、支払い手続きを進めさせていただきます。 支払いは請求書記載の期日までに完了する予定です。 ご不明な点がございましたら、お手数ですがご連絡ください。 今後とも、よろしくお願い申し上げます。 株式会社△△ ✕✕ |
例4)請求書の送付を催促する場合
請求書の催促はセンシティブな連絡であるため、メールの書き方には十分な配慮が必要です。
請求書が未着の場合、締日に余裕がある場合でも、できるだけ早くメール連絡をしましょう。相手のミスだと決めつけず、郵便トラブルなどさまざまな可能性を想定し、配慮ある文面を心がけてください。
件名は簡潔でわかりやすいものにし、必要に応じて表題の先頭に【重要】や【至急】などを付けることも検討しましょう。
また、期日と入金が遅れるリスクを明確に伝えることも大切です。具体的な日付を示し、請求書が未着の場合のリスクを簡潔に説明することで、相手の迅速な対応を促すことができます。
請求書の送付を催促する場合の、文例は以下のとおりです。
件名:〇月分請求書・送付確認のお願い 株式会社〇〇 担当〇〇様 いつも大変お世話になっております。株式会社△△の✕✕です。 恐れ入りますが、御社の〇月分の請求書につきまして、弊社での受領をまだ確認できていないようです。 お手数をおかけしますが、請求書の発行および送付状況のご確認をお願いできますでしょうか。 請求書は、請求者の名前、取引年月日、取引内容、金額、事業者名、請求書番号などを記入の上、電子印鑑や署名などでご対応いただければPDF送付のみで構いません。 〇月〇日までに送付お願いできますと幸いです。 本メールと行き違いで請求書をご送付いただいている場合は、ご放念くださいませ。 何かご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。 どうぞよろしくお願いいたします。 株式会社△△ ✕✕ |
上記のポイントの詳細や催促メールの書き方・例文については関連記事をご参照ください。
請求書をメールで送付するときの注意点
請求書をメールで送付する場合には、いくつか注意点があります。本章で解説する注意点を把握し、取引先とのスムーズなやり取りが行えるよう徹底した準備をしておきましょう。
取引先の承諾を得る
請求書をメールで送る場合、自社の都合のみで送信を完結させて良いわけではありません。原本の存在を絶対としている企業もあるため、受け取る側の取引先の承諾を得ておきましょう。
取引先に確認した際、承諾を口頭で得ていても、関係者や担当者にその旨が正しく伝わっていないことも考えられます。
認識のすれ違いを防ぐため「今後請求書はデータ化してメールで送付を行うこと」や「原本の郵送は取りやめること」といった内容を明記した書面の作成を推奨します。
わかりやすい件名にする
請求書データが添付されたメールを受け取った担当者が、最初に見るのはメールの件名です。そのため、一目見てメールの内容を把握できるよう「10月分請求書送付」などわかりやすい件名にするように心がけてください。
件名で請求書の内容と判断できない場合、他のメールに埋もれてしまったり、確認を後回しにされたりすることもあります。また、件名をわかりやすくすることで、送った側も管理がしやすくなるというメリットがあります。
何に関する請求なのか、何月分の請求なのかなどを正しく記載するようにしましょう。
ファイル形式はPDFにする
セキュリティを強化するためにパスワードの設定を行い、ファイル形式をPDFにしてメール送付するという方法を推奨します。PDFはほとんどのパソコンで表示でき、修正がしにくいという特徴から、一番確実で安全な方法です。
Microsoft ExcelやMicrosoft Wordなどで請求書の作成を行う場合、そのまま送付すると、人的ミスにより数字を削除してしまう、なかには改ざんされてしまうというリスクがあります。
また、バージョンによってはファイルを閲覧できなかったり、レイアウトが崩れてしまったりすることもあります。
押印形式を確認する
請求書の印鑑は、必ずしも必要ではありません。
しかし、メールで請求書を送る場合であっても印鑑を必要としている企業もあるでしょう。取引先が印鑑のある書類のみしか受領しないというのであれば、送る側もそのルールに従わなければいけません。印鑑の必要性は取引先に事前に確認しておくようにしてください。
電子化した請求書に印鑑を押す場合、電子印鑑を利用、もしくは書面に押印した後、それをスキャンしてデータ化するという2つの方法があります。電子印鑑の場合、印影を画像化したものと、印影に作成者や使用者、タイムスタンプなどの情報を含むものに分けられます。
電子印鑑の導入をする場合は、単純に印影を画像化したものか、情報を付加したものか、それぞれの違いをよく理解し、管理体制についても事前に取り決めておくことが大切です。
適切な印鑑の種類や押印時のポイントについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:請求書に印鑑は必要か?適切な印鑑の種類や押印時のポイントを解説
請求書に記載漏れがないか確認する
請求書に記載すべき内容は、以下のとおりです。PDF形式など改変不可なファイル形式にして、必要事項を記載しましょう。
- 請求者の氏名
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書の交付を受ける事業者名
適格請求書については、上記の項目に加え以下の項目も追記します。
- インボイス発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 消費税額等
請求書の概要や書き方、ルールについて詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
関連記事:請求書の書き方とルールを具体例付きで解説(テンプレートあり)
関連記事:適格請求書とは?概要や書き方(見本付き)をわかりやすく解説
電子帳簿保存法に対応する
2022年1月1日に施行された電子帳簿保存法の改正により、電子データで交わされた請求書は、電子データのまま保存することになりました。2023年12月末までは移行期間として紙での保存が認められていましたが、2024年1月以降はデータ保存が義務化されています。
請求書の受信者側が、改ざん防止や検索機能を備えた状態で保存できるよう配慮することが大切です。タイムスタンプの付与や、検索可能な状態での保存など、真実性と可視性を確保する措置を講じましょう。
電子帳簿保存法は企業規模に関わらず適用されるため、個人事業主も含めたすべての事業者が対応を求められます。法律の要件を満たすシステムやクラウドサービスの利用を検討するなど、適切な対応策を講じることが重要です。
電子帳簿保存法について詳しくは、以下の記事で解説しています。
請求書をメールで送付するメリット
請求書のメール送付で得られるメリットは、以下のとおりです。
- 郵送より早く取引先へ届き、すぐに確認してもらえる
- 宛先の間違いや切手不足による返送などのミスを防ぐ
- 紙媒体として出力する手間や時間を短縮できる
- 請求書を電子化しておけば、再発行や修正が可能
上記のように、さまざまなメリットがあります。メリットを理解した上で、請求書をメールで送付するか検討するとよいでしょう。
請求書の送付をメールに変更するタイミング
請求書の送付をメールに変更するタイミングとして適しているのは、以下の3つのタイミングです。
- 料金の変更タイミング
- 消費税の増税タイミング
- ペーパーレス化推進やリモートワークへの切り替え
上記のように、どのようなタイミングであっても、メール送付に変更する理由を取引先へ明確に説明することが大切です。
「郵送費用の削減による値上げ幅の縮小」「ペーパーレス化による環境問題への配慮」「メールに変更することで得られるメリット」などを、丁寧に説明しましょう。取引先の理解を得た上で請求書をメール送付へ切り替えることで、スムーズな移行につながります。
請求書の作成から送付、管理まで行える「バクラク請求書発行」
請求書は、メールでの送付が可能です。改ざんが難しいPDFファイルにしてメールに添付しましょう。もし取引先から請求書の原本が求められたら、請求書をメールで送付した上で原本も郵送してください。
電子帳簿保存法の改正により、電子データで交わされた請求書は、電子データのまま保存する義務があります。
バクラク請求書発行は、会社が発行するあらゆる書類の電子発行をWeb上で簡単にできるシステムです。請求書のPDFファイルを取引先毎に自動分割する機能やCSVとの連携機能など、請求書送付に役立つ機能が搭載されています。
請求書送付の時間や手間を軽減されたい方は、ぜひ導入をご検討ください。