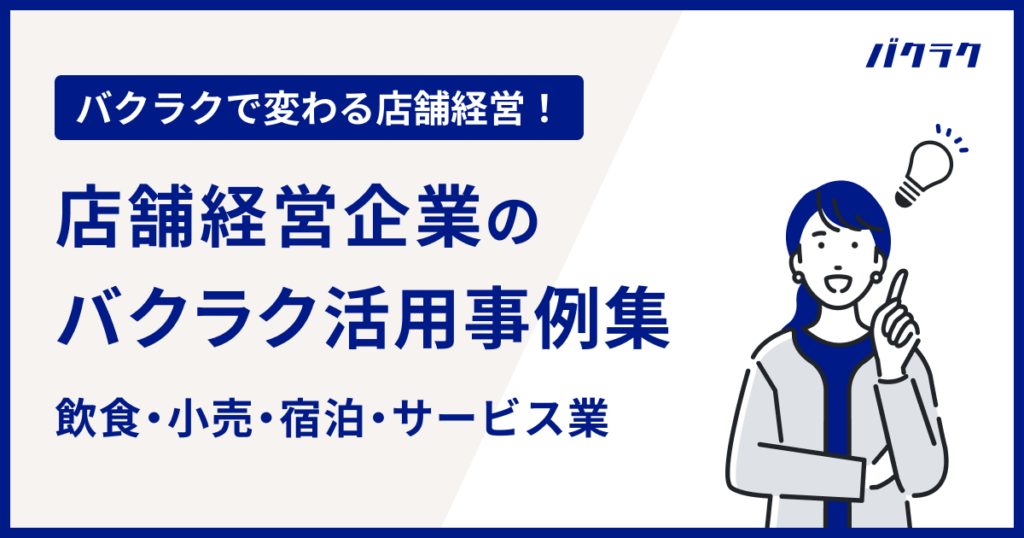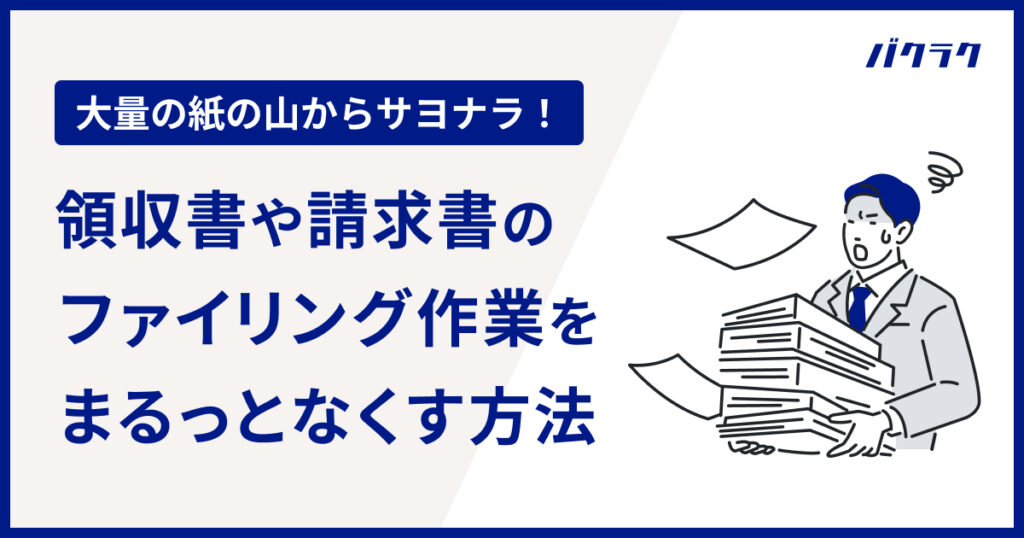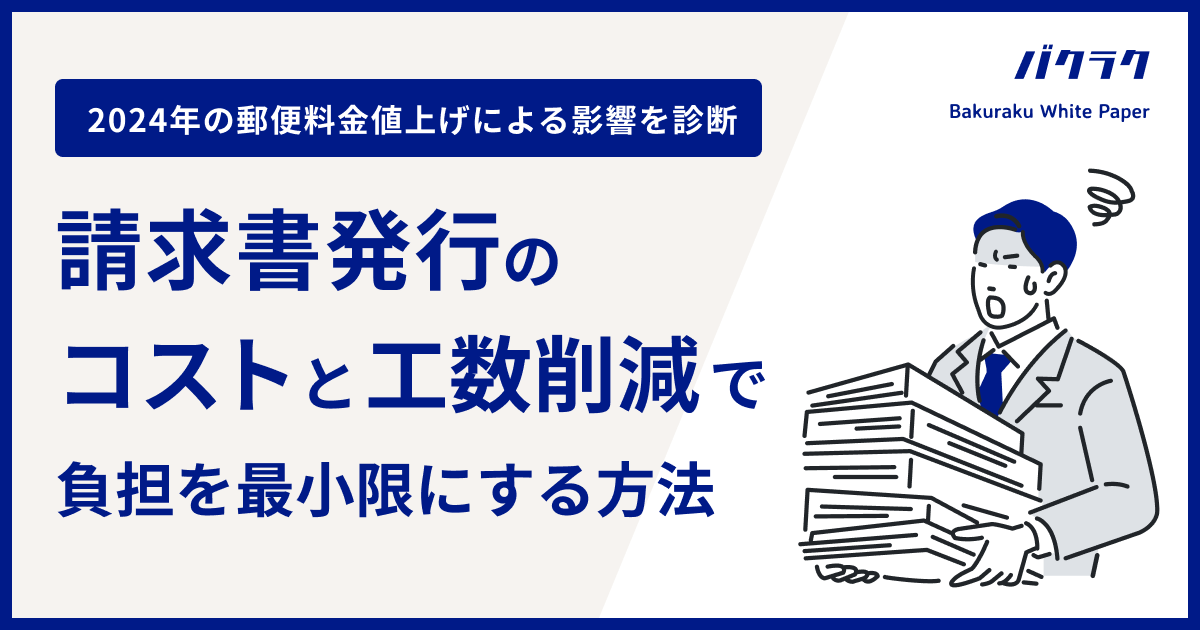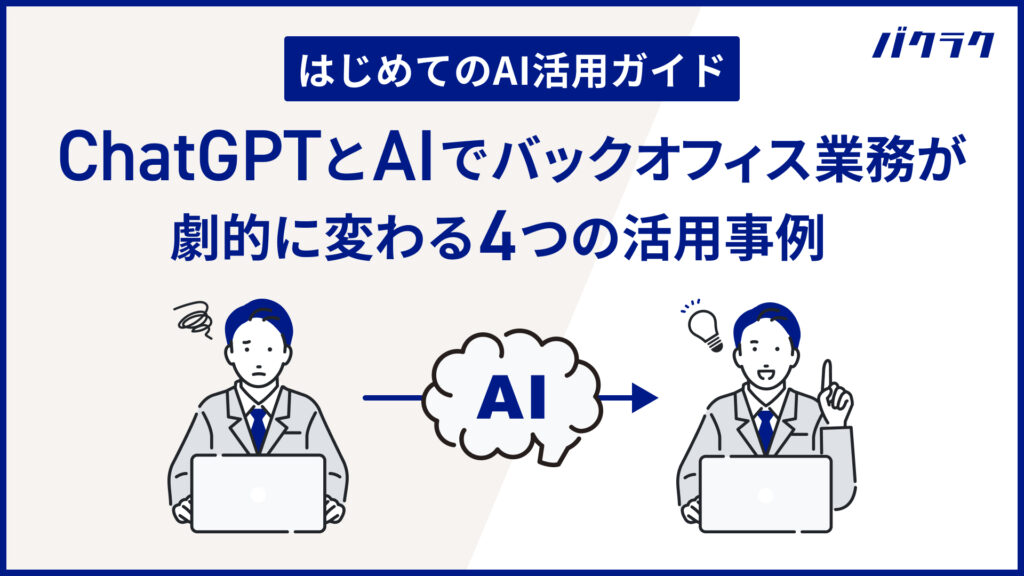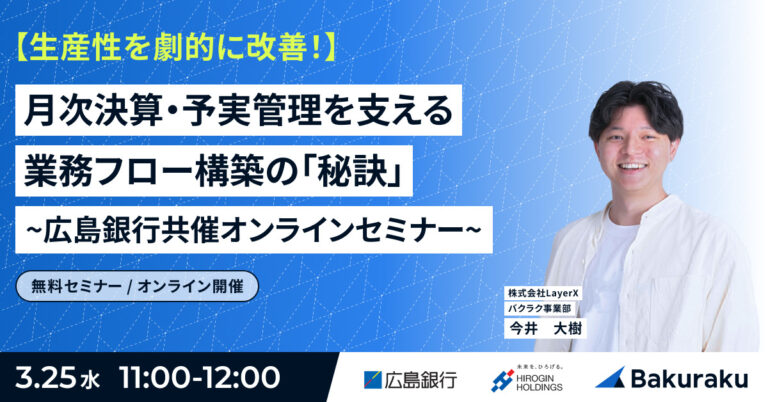インボイス制度が経理の会計処理業務に与える変化とは?仕訳方法についても解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式
- 買い手が仕入控除を受けるには、一定の事項を記載した適格請求書の発行が必要
- 免税事業者から仕入れを行った場合は、本体価格に上乗せするか雑損失として処理する
2023年10月1日にインボイス制度が施行されて以降、請求書の取り扱いや仕入取引に関するルールが変化しています。複雑化する会計処理に、お悩みの方もいるでしょう。
本記事では、インボイス制度が支払側に与える変化や会計処理上の注意点、免税事業者から仕入れを行った場合の仕訳方法などを詳しく解説します。
インボイス制度の概要を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
インボイス制度が経理の会計処理業務に与える変化とは?仕訳方法についても解説
インボイス制度の概要
インボイス制度はすでに施行されているものの、具体的にどのような制度か理解できていない方もいるでしょう。まずは、インボイス制度の概要を紹介します。
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
インボイス制度では、売り手が買い手に対して、一定の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行します。双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用される仕組みです。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
適格請求書とは?
適格請求書(インボイス)とは、一定の事項を記載した書類のことです。売り手が買い手に、正確な適用税率や消費税額を伝える目的で発行します。
証憑が適格請求書として認められるには、以下6点の記載が必要です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
1の登録番号は、適格請求書発行事業者の登録が完了した事業者に発行される番号です。法人番号の有無に応じて発行される「T+法人番号」または「T+13桁の固有番号」を記載します。
取引の内容に軽減税率の対象品目がある場合は、その旨を取引内容(3)に記載しましょう。その際に「※」などの記号を使用しても問題ありません。
参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
適格請求書の要件を満たさない場合は、仕入税額控除を受けられません。詳しくは、以下の記事をご参照ください。
関連記事:適格請求書の要件とは?記載事項や満たさない場合の対応について解説
インボイス制度による会計処理業務への影響
インボイス制度の施行により、支払側における会計処理業務の複雑化が懸念されます。特に影響が大きいのは、仕入税額控除の計算に関する会計処理です。
これまでは軽減税率と標準税率のいずれかによる会計処理が求められましたが、現在は事業者の税区分を判断した上で適切に処理しなければなりません。また、帳簿のみで仕入税額控除が受けられる条件なども変更されています。
ただし、会計処理への影響が生じるのは、本則課税で消費税を納める課税事業者(本則課税事業者)のみです。簡易課税事業者や免税事業者はインボイスの対象外のため、影響はないといえるでしょう。
支払側の会計処理業務で注意すべきポイント
支払側が会計処理をする際、注意すべきポイントが3つあります。インボイス制度に関する注意点を事前に理解して、正しい会計処理を行いましょう。
仕訳前にインボイスかどうかの判別を行う
仕訳前に、該当の証憑がインボイスか否かの判別が必要です。従来の請求書の記載事項に加えて、以下の記載がある場合はインボイスと判断できます。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
不正なインボイス発行や登録番号の記載ミスなどの可能性を考慮して、取引先が適格請求書発行事業者であるかを登録番号の正誤とともに確認することも重要です。適格請求書発行事業者の確認は国税庁のサイトでできますが、法人名で検索できない点に注意が必要です。
当サイトが提供するツールであれば、インボイス登録番号のほか、法人番号や法人名からも検索できます。取引先が適格請求書発行事業者か否かを判別する際に、ご活用ください。
参考:国税庁「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」
インボイス登録番号を検索(同時100件)法人番号や会社名で逆引き可
正しく消費税額が計算されているか確認
現行法では請求書の品目ごとに消費税額を算出でき、商品単位での端数処理も認められています。
しかし、インボイス制度ではルールが異なります。税率ごとに区分した消費税額等に1円未満の端数が生じる際、1枚の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理をしなければなりません。
従来の算出方法では消費税額が異なるため、受領した適格請求書の消費税額が正しく計算されているか確認する必要があります。
端数処理の計算に誤りがないかも確認し、ミスが発覚した場合は取引先に修正を依頼しましょう。自社が作成したインボイスの要件を満たす仕入明細書などを提示し、正しい税額を取引先に確認してもらう方法も認められています。
会計処理時に消費税区分を判断
インボイス制度の会計処理では、取引先の消費税区分が、以下4つの内いずれに該当するかを判断しなければなりません。
事業者区分 | 課税区分 |
適格請求書発行事業者 | 仕入税額控除対象の課税仕入10% |
仕入税額控除対象の課税仕入8% | |
適格請求書発行事業者以外 | 仕入税額控除対象外の課税仕入10% |
仕入税額控除対象外の課税仕入8% |
ただし、免税事業者からの課税仕入れには以下のような経過措置があります。2029年9月30日まで、段階的に仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる措置です。
期間 | 課税区分 | 税率 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 経過措置80%控除対象の課税仕入 | 10% |
8% | ||
2026年10月1日~2029年9月30日 | 経過措置50%控除対象の課税仕入 | 10% |
8% |
こうした経過措置の適用を考慮すると、インボイス制度の税区分はより複雑化するといえます。計6通りの税区分から、適切なものを判断した上で会計処理を行う必要があるでしょう。
免税事業者から仕入れた場合の仕訳方法
免税事業者から仕入れを行った場合は、以下のいずれかで仕訳を行います。
- 本体価格に上乗せする
- 雑損失として処理する
本章では、それぞれの仕訳方法を具体例とともに紹介します。
消費税の免税事業者について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:消費税の免税事業者とは?課税事業者との違い・インボイス制度による影響を解説
本体価格に上乗せする
消費税額を本体価格に上乗せすると、取引時(支払時)に仕訳を完結できます。経過措置期間中は、80%または50%の仕入税額控除を適用可能です。
たとえば免税事業者から、本体価格5万円・消費税率10%の商品を現金で仕入れたとします。5万円の課税仕入れにかかる消費税額は5,000円ですが、80%の仕入税額控除を適用した場合の仕入税額控除額は4,000円です。計算式は以下をご覧ください。
- 5,000円(消費税額)×80%(仕入税額控除の割合)=4,000円(仕入税額控除)
- 5,000円(消費税額)-4,000円(仕入税額控除)=1,000円(事業者負担額)
仕入税額控除額は仮払消費税額等で仕訳を行い、仕入税額控除を差し引いた1,000円は事業者負担として計上します。
以上を踏まえて、次のように仕訳を行いましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 51,000円 | 現金 | 55,000円 |
| 仮払消費税額等 | 4,000円 | ||
雑損失として処理
雑損失として処理する場合は、取引時(支払時)と決算時に仕訳が必要です。まず、取引時は現行のとおり仮払消費税額等で処理を行います。決算時は、雑損失として仕入税額控除を受けられない額(20%または50%)を仮払消費税等に計上します。
例として、80%の仕入税額控除適用期間に、免税事業者から本体価格5万円・消費税率10%の商品を現金で仕入れた場合の仕訳方法を見ていきましょう。
〈取引時〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 50,000円 | 現金 | 55,000円 |
| 仮払消費税等 | 5,000円 | ||
〈決算時〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 雑損失 | 1,000円 | 仮払消費税等 | 1,000円 |
経理の会計処理業務を効率化!インボイス制度対応の「バクラク請求書受取」がおすすめ
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度により、支払側は仕入税額控除の計算に関する会計処理業務に影響を受ける可能性があります。
インボイスの経過措置期間は、税区分がより複雑です。消費税区分の判断や記載された消費税額の正誤確認に時間を要して、会計処理の業務効率低下を招くことが懸念されるでしょう。
経理の会計処理業務を効率化するには、バクラク請求書受取の導入がおすすめです。インボイス制度に対応しており、証憑が適格請求書か否かを自動で判定します。
税区分の自動選択機能のほか、高精度のAI-OCRや不整合アラートも搭載されており、会計処理のミスを防止できる点もメリットです。
目視や税区分選択の手間を省いて会計処理業務の効率化を図りたい方は、バクラク請求書受取の導入をご検討ください。以下のページから、詳しい資料をダウンロードいただけます。