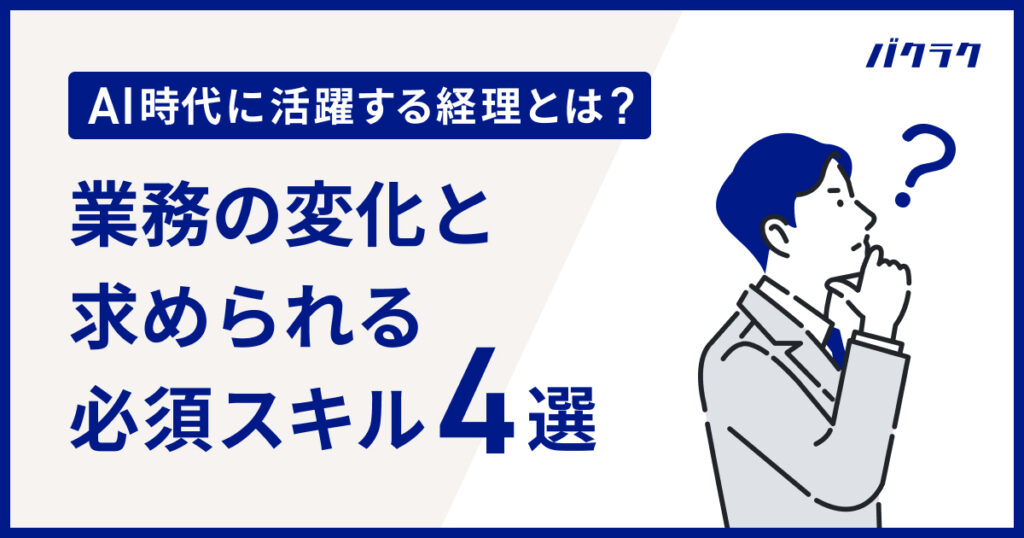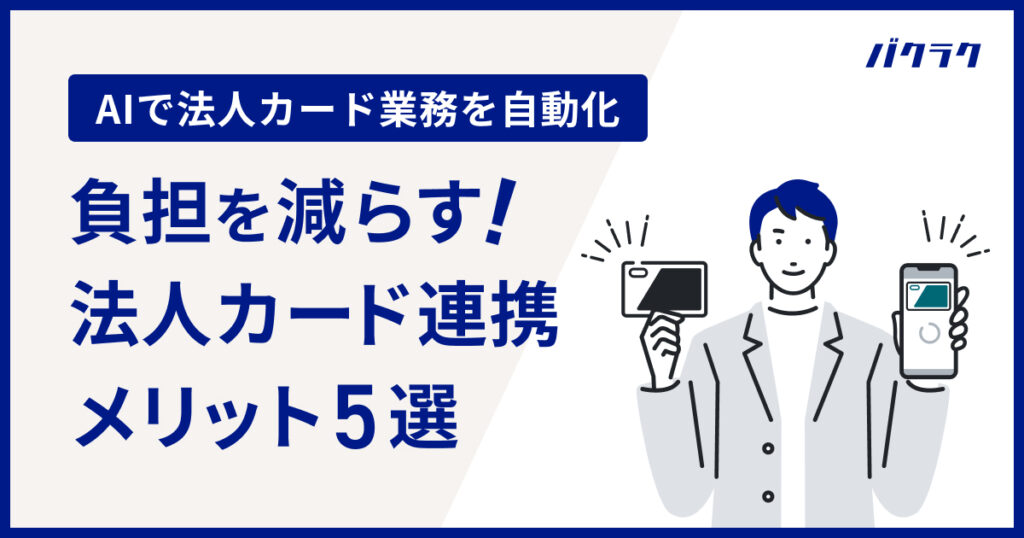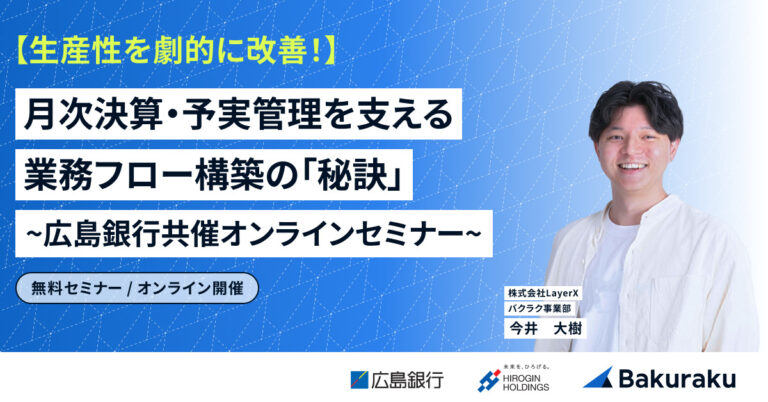注文書に収入印紙が不要な理由とは?例外で必要になるケースも解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-09-09
- この記事の3つのポイント
- 注文書のみでは基本的に契約が成立せず、課税文書に該当しないことから収入印紙は原則不要
- 注文書が領収書や契約書の役割をもつ場合は、文書の名称に関わらず収入印紙が必要
- 注文書が課税文書に該当する場合でも、電子化すれば収入印紙は必要ない
注文書に収入印紙を貼るべきか、お悩みの方もいるでしょう。注文書に収入印紙は原則不要ですが、一部のケースでは貼付が必要です。
本記事では、注文書に収入印紙が不要な理由や、貼付が必要なケースについて詳しく解説します。収入印紙の金額や貼り方などの基本知識も紹介しますので、今後の実務にお役立てください。
注文書に収入印紙が不要な理由とは?例外で必要になるケースも解説
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
注文書に収入印紙が原則不要な理由
注文書に、収入印紙は原則必要ありません。注文書はあくまで発注側が商品やサービスを発注する意思を示す文書であり、注文書のみでは契約が成立しないためです。
そもそも注文書は、印紙税法で定められている課税文書に該当しません。課税文書には契約書や領収書としての意味合いがあり、金銭の授受や経済行動が発生します。また、課税文書は、双方の同意が示されているのも特徴です。
注文書は発注者の意思を確認できる文書ですが、書面上に受注者の意思は示されません。発注者が注文を望む商品・サービスの数量や金額に同意しているとは限らず、金銭のやり取りも発生していないとみなされます。
以上のことから、注文書は課税文書でないとして、収入印紙は不要と判断できます。
収入印紙について理解を深めたい方は、以下の記事をご参照ください。収入印紙の必要性や金額、購入方法、貼り方などを詳しく解説しています。
関連記事:収入印紙とは?必要性や金額、購入方法、貼り方などを徹底解説
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
収入印紙が必要な書類
収入印紙が必要なのは、印紙税法で定められた課税文書です。課税文書に該当する書類の例は、以下のとおりです。
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書
- 工事請負契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 合併契約書
- 為替手形、約束手形
- 株式の受益証券
- 預貯金証書
- 領収書 など
課税文書には第1号文書から第20号文書まで20種類の分類があり、印紙税額がそれぞれ異なります。記載内容や金額によっては、非課税文書となり印紙税が不要のケースもあります。
たとえば領収書の場合は、記載された受取金額が5万円未満であれば、収入印紙は必要ありません。また、クレジットカード決済やキャッシュレス決済による取引の場合も、支払いの時点では金銭授受の事実がないとみなされるため、収入印紙は必要ありません。
課税文書とみなされる注文書には収入印紙が必要
課税文書とみなされる注文書には、収入印紙が必要です。文書が領収書や契約書としての役割・意味合いをもつ場合、文書の名称が「注文書」であっても、領収書や契約書とみなされるためです。
注文書が課税文書に該当するか否かは、文書のタイトルではなく内容に着目して判断する必要があります。発注書が課税文書とみなされないのは、発注側が注文意思を示す目的で発行する場合であることを理解しておきましょう。
課税文書に該当する発注書の具体例は、後ほど詳しく紹介します。
注文書が課税文書であっても収入印紙が不要な場合もある
注文書が課税文書としての役割や意味合いをもっていても、以下のいずれかに当てはまる場合は収入印紙が不要です。
- 注文請書の発行または発行の予定がある場合
- 契約金額が1万円未満の場合
- 物品の売買契約の場合
- 電子文書の場合
注文請書とは、受注者が注文の承諾を発注者に示す書類です。注文書が契約書としての役割をもっていても、注文請書の発行または発行の予定がある場合、収入印紙は注文請書に貼付する決まりです。
また、注文書の記載金額が1万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は必要ありません。注文書や注文請書の内容が、作業の請負契約ではなく物品の売買契約である場合も、収入印紙は不要です。
印紙税法は書面の文書を課税対象としているため、メール・FAXによる送付や電子署名を用いた注文書にも、収入印紙は不要であることを理解しておきましょう。
注文書に収入印紙が必要な例
注文書に収入印紙が必要か否かで判断を迷った際は、文書の発行目的や内容に着目することがポイントです。本章では、注文書に収入印紙が必要な6つの例を紹介します。
契約書の代わりとして注文書を発行する場合
注文書を契約書の代わりとして発行する場合は、収入印紙が必要です。契約書は、印紙税法の課税文書「第2号文書」に該当します。
注文書の交付が契約の成立を意味する旨の記載がある場合は、双方の合意があるとみなされ、契約書として扱われることを理解しておきましょう。
なお注文請書についても、交付によって契約が成立する旨が記載されている場合は、収入印紙が必要です。ただし、記載金額が5万円未満の場合は、非課税文書に該当するため収入印紙は必要ありません。
契約書への収入印紙について、さらに理解を深めたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:契約書に収入印紙は不要?貼られていない場合の有効性や必要なケースなど解説
見積書の承諾として注文書を使用する場合
受注側から受け取った見積書の内容に、承諾する意味合いで注文書を発行する場合も収入印紙が必要です。具体的には、見積書に対する発注である旨が注文書に記載されている場合です。
見積書を契約の申し込み、見積書に基づいて発行された注文書を承諾の意思表示とし、双方の合意があるとみなされます。
双方の署名や捺印がある場合
収入印紙が必要な例として、注文書に双方の署名や捺印があるケースも挙げられます。
注文書は本来、発注側が商品やサービスを申し込む意思表示をするための文書です。しかし受注側の署名や捺印がある場合は、双方の合意があるとみなされ、契約書として扱われます。契約書は課税文書に該当するため、収入印紙が必要です。
取付工事などの請負がオプションに含まれる場合
注文書の記載内容に、オプションとして以下のいずれかが含まれる場合も、収入印紙を貼らなければなりません。
- 工事の請負
- 物品の加工請負
- 請負金額の変更
例として、オフィスに設置するキャビネットを注文し、オプションとして金庫の取り付けを申し込むケースが挙げられます。
この場合、金庫の取付工事および工事料金が発生するため、取り付けを請け負う契約が必要です。注文書が印紙税法の第2文書「請負に関する契約書」とみなされ、収入印紙が必要な課税文書として扱われます。
手付金が発生する場合
手付金が含まれる注文書にも、収入印紙を貼らなければなりません。
手付金とは、取引代金の一部です。契約の成否に関わらず、手付金が発生する場合は金銭のやり取りがあるとみなされます。
注文書が売上代金の受取書の役割をもつとして、印紙税法の第17号文書「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に該当するため、収入印紙が必要です。
参考:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
リサイクル預託金を含めた注文書の場合
自動車などの注文書において、リサイクル預託金を含む場合も収入印紙が必要です。
リサイクル預託金とは、廃車の際に必要なエアバッグ類のリサイクル費用などを、事前に支払うものです。新車を注文する場合は、これまで所有していた自動車を売却し、リサイクル預託金相当額を含む売却代金を新車購入代金の一部に充てることもあるでしょう。
リサイクル預託金が含まれる注文書は、印紙税法の第15号文書「債権譲渡または債務引受けに関する契約書」とみなされます。
注文書に貼付する収入印紙の金額
課税文書には第1号文書から第20号文書までの分類があり、収入印紙の金額(印紙税額)は文書の種類ごとに異なります。
注文書に収入印紙を貼る場合は記載内容で金額を判断しますが、ここでは比較的多く見られる第2号文書「請負に関する契約書」について見ていきましょう。
第2号文書に貼付する収入印紙の金額は、以下のとおりです。
記載契約金額 | 収入印紙の金額 |
1万円未満 | 不要(非課税) |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 1,000円 |
300万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
参考:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
以下の記事では、収入印紙の金額を課税文書の種類ごとに紹介しています。領収書や各種契約書に貼る収入印紙の金額を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
収入印紙の貼り方と割り印の押し方
収入印紙を貼る場所に、法的な決まりはありません。左上に貼るのが一般的ですが、右上や右下のほか、あらかじめ設けられた貼り付け欄に貼るケースもあります。
収入印紙を貼り付けた後は、割り印(消印)を押します。注文書と収入印紙をまたぐ形で、印影が残るように印鑑を押しましょう。
割り印は収入印紙の再利用を防ぐために必要で、押印が義務付けられています。割り印がない場合は、印紙税法の規定で過怠税の対象となる可能性があるため注意しましょう。
収入印紙の割り印について、正しい押し方や失敗したときの対処法を知りたい方は以下の記事をご覧ください。割り印なしの収入印紙に課される、過怠税の額なども紹介しています。
注文書を電子化すれば収入印紙は不要
注文書が課税文書に該当する場合であっても、電子化すれば収入印紙は必要ありません。印紙税法の収入印紙に関する定めは、紙の文書が対象のためです。
電子化とは、電子データ化した文書のメールやFAXによる送付、電子署名を用いた契約などを指します。電子データ化した文書を印刷して受注者へ送付した場合は、課税文書とみなされ、収入印紙が必要となる点に注意しましょう。
注文を受けた後、スムーズに請求書を発行するなら「バクラク請求書発行」
注文書に、収入印紙は原則必要ありません。発注側が商品やサービスの発注意思を示す目的で発行した注文書は、課税文書に該当しないためです。
ただし、注文書の内容が領収書や契約書としての意味合いをもつ場合は、記載金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。見積書の承諾として注文書を使用する場合や双方の署名・捺印がある場合など、いくつかの例があることを理解しておきましょう。
印紙税法の煩雑なルールにお悩みの方には、請求書発行システムの導入がおすすめです。バクラク請求書発行では、請求書はもちろんのこと、注文書や見積書などのあらゆる帳票をシステム上で電子発行できます。
電子発行した文書は印紙税法の対象外であり、収入印紙の貼付や管理などの手間を省けることから、経理担当者にとってメリットが大きいといえるでしょう。
そのほか、帳票のレイアウトや項目を自由にカスタマイズできる点や、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法令に対応している点も特徴です。
注文書を含む帳票類の発行を電子化し、経理業務の負担軽減と効率化を実現したい方は、バクラク請求書発行の導入をご検討ください。以下のページから、詳しい資料を無料ダウンロードいただけます。