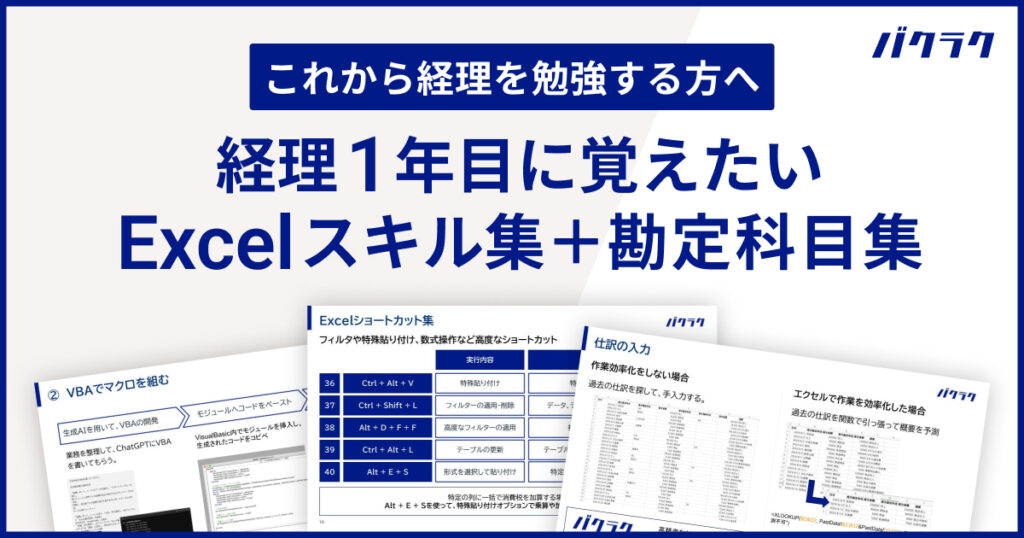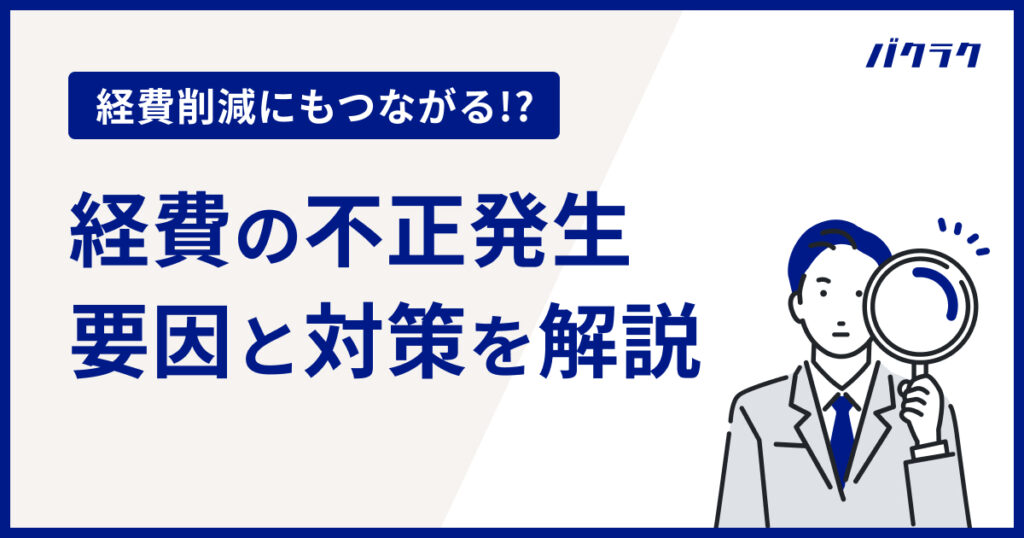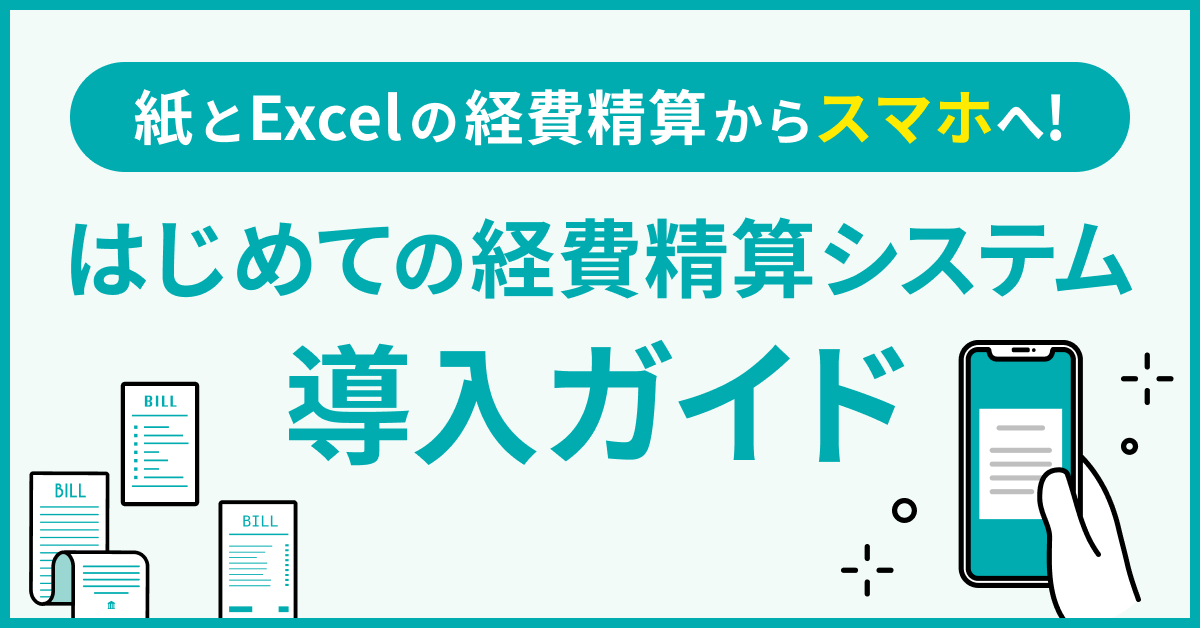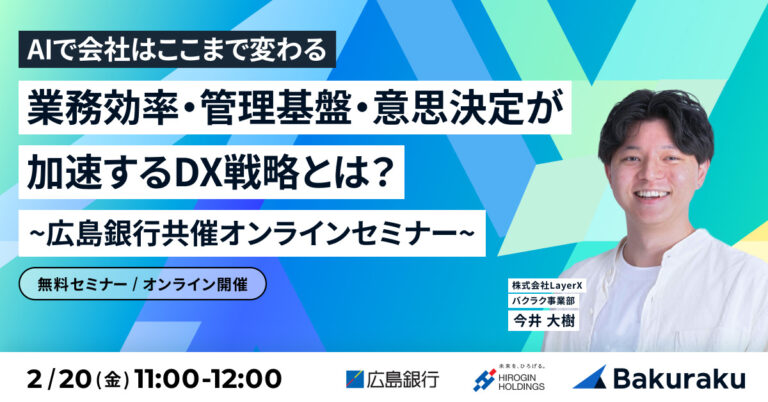「消耗品費」とはどんな勘定科目?具体例や雑費との違い・仕訳例を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 消耗品費にできるのは、取得価格10万円未満もしくは耐用年数1年未満の備品購入の費用のみ
- 消耗品費の内容としては、事務用品やパソコン用品、日用品、医療用品などが挙げられる
- 消耗品費を抑えるには、余計な在庫を持たないことや物品の再利用、まとめ購入が有効
消耗品費は、事務用品やパソコン用品などの消耗品の購入費用を仕訳する際に使用する勘定科目です。ただし消耗品であれば何でも計上できるわけではなく、要件が定められています。
本記事では、消耗品費として認められる費用の一覧や仕訳例、節約する方法を解説します。消耗品費とよく似た勘定科目の「雑費」や「消耗品」との違いも解説していますので、経理処理にお役立てください。
「消耗品費」とはどんな勘定科目?具体例や雑費との違い・仕訳例を解説
消耗品費とは?
消耗品費とは、事務用品などの備品購入にかかる費用を計上するための勘定科目です。詳しくは後述しますが、コピー用紙・文房具・名刺・USBメモリー・SDカード・洗剤といった消費サイクルの短いオフィス用品が含まれます。
なお国税庁では、取得価格10万円未満か耐用年数1年未満の什器備品を対象としています。そのため10万円未満であれば、物品購入代の全額を消耗品費として計上してかまいません。10万円以上となった場合には、減価償却費として処理します。
参考:国税庁「帳簿の記帳のしかた-事業所得者用」
消耗品費に仕訳される費用の一覧
消耗品費の多くは、オフィスで使用される事務関連用品の費用です。しかし、物によっては消耗品費として計上すべきか迷うこともあるでしょう。
そこで、消耗品費に仕分けされる費用の例を一覧にしましたので、ご活用ください。
| 内訳 | 具体例 |
| 事務用品 |
|
| パソコン用品 |
|
| 日用品 |
|
| 医療用品 |
|
多くの企業で利用されるコピー機について、コピー用紙代や印刷費は消耗品費以外の科目でも計上できます。詳しくは以下の記事で解説していますので、ご確認ください。
関連記事:コピー代や印刷費の勘定科目はどうする?使える9つの勘定科目を解説
また、10万円未満であればパソコン本体も消耗品費の対象です。本体価格に応じた経理処理の方法や仕訳例は、以下の記事で確認できます。
「消耗品」は未使用、「消耗品費」は使用中の場合に分けられる
消耗品費とよく似た名称の仕訳科目に、「消耗品」があります。「消耗品」と「消耗品費」は、物品の使用状況によって使い分けなければなりません。「消耗品」と同様に「貯蔵品」が使われることもあります。
基本的に繰り返し消費されるものは消耗品に該当しますが、消耗品でも決算時に未使用のものは貯蔵品として資産に計上しなければなりません。使用するタイミングで消耗品費に振り戻す必要があります。
未使用の「消耗品(貯蔵品)」は資産として扱われます。そもそも「企業の資産」とは、購入後まだ使われていない物品のことだからです。
一方、使用された物品は企業の運営コストとして認識されるため、物品の使用時に「消耗品(貯蔵品)」から「消耗品費」として費用計上され、損益計算書に記載されます。
取得価格が30万円未満のときに使える特例
消耗品費として認められるのは、使用期間1年未満もしくは購入価格10万円未満の物品購入費のみです。要件を満たさない消耗品については、減価償却費として複数の年度に分け計上しなくてはなりません。
ただし一定要件を満たした企業であれば、30万円未満の物品購入について、その全額を当該年度に計上してもよいとする特例が設けられています。
国税庁によれば、具体的な要件は以下のとおりです。
- 青色申告提出者
- 常時使用の従業員数が500人以下(特定法人は300人以下)
- 資本金もしくは出資金が1億円以下
- 発行済み株式の1/2以上を大規模法人に所有されていない
- 発行済み株式の2/3以上を複数の大規模法人に所有されていない
参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
参考:国税庁「No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者」
なお、この特例には期限があり、令和8年3月31日までに購入した事業用品にのみ適用されます。
雑費とはどのような勘定科目?消耗品費との違い
消耗品費と混同しやすい科目に「雑費」があります。雑費とは、他のどの勘定科目にも当てはまらない少額かつ一時的な支出です。法律で明確に定義付けられているわけではないため、何を雑費とすべきかは各企業に委ねられています。
雑費としてよく挙げられる項目は、以下のとおりです。
- 事務手数料、振込手数料
- サービスのキャンセル料
- 有料サービスの利用料や年会費
- クリーニング代や清掃費
- 粗大ごみ処理費用
- 引っ越し費用 など
消耗品費との使い分けが曖昧になりがちなため、使用頻度や購入金額、購入したものが物理的なものかどうか、などの観点でルールを定めておくのがよいでしょう。
たとえば、頻繁に買い替えや買い足しをする備品なら消耗品費、無形のサービス・商品で一時的な利用のために購入したものなら雑費とします。
なお損益計算書にて雑費の項目が多すぎると、税務調査で指摘を受ける可能性もあるため、科目の使用頻度にも注意しましょう。
雑費の具体的な仕訳例については、以下の記事をご確認ください。
「消耗品」は未使用、「消耗品費」は使用中の場合に分けられる
雑費と合わせて違いを押さえておきたい科目が「消耗品」です。消耗品費とよく似ていますが、意味は異なります。
消耗品とは、まだ使用していない物品のことで、会計上は資産の扱いです。貯蔵品として扱われることもあります。一方で消耗品費は、すでに使用状態にある消耗品の費用を計上するものです。
したがって、両者は購入したものを使用しているか否かに違いがあります。購入時点で未使用のものは消耗品で計上し、使用したら消耗品費として振り戻しましょう。
ただし消耗品費は少額であることから、実務上は購入時点で計上することも認められています。
消耗品費の仕訳例
消耗品費を仕訳する際には、購入時と決算時に分けて2回処理をする必要があります。
ここでは、1冊200円のノートを5冊(合計1,000円)現金で購入した場合の仕訳例を見てみましょう。
まず購入時点では借方に「消耗品費」、貸方に「現金」を入れて仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 消耗品費 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |
次に、決算時点で1冊だけ未使用だった場合の仕訳例です。
先に計上した5冊分の仕訳を修正するため、「消耗品(もしくは貯蔵品)」の科目を用いて消耗品費から未使用の分を除外します。消耗品か貯蔵品のどちらを採用するかは企業の自由です。
| 借方 | 貸方 | ||
| 消耗品(貯蔵品) | 200円 | 消耗品費 | 200円 |
補助科目と摘要欄で管理しやすくする方法
消耗品費に該当する費用は多岐にわたるため、管理も煩雑化しやすくなります。そこで管理上の工夫として、補助科目や摘要欄の活用がおすすめです。
補助科目は企業が任意に設定できるもので、内容別の集計や検索をしやすくなります。特にルールはありませんが、消耗品費に使える補助科目としては以下が挙げられます。
- 事務用品
- パソコン用品
- 作業用備品
- 梱包材
- 清掃用品 など
一方で摘要欄とは、取引内容を補足するメモのようなものです。勘定科目だけでは詳細を理解できない場合に摘要欄を入力すると、あとから見返したときに何に対しての費用なのかをすぐに把握できます。
補助科目と同様に決まったルールはありませんが、摘要欄には購入したものの品目や個数、支出の相手先、クーポンやポイントを利用したことなどを記載するのがよいでしょう。
消耗品費を節約する方法
消耗品費は一つひとつが少額であることも多いものの、積み重なることで大きな出費になる科目でもあります。消耗品費を節約する方法には、以下のようなものがあります。
必要な量だけを購入する
必要な量だけを購入し無駄なストックを減らすことで、不要なものを購入してしまったり、無駄遣いしてしまったりすることを防げます。多くのストックがあれば、誰しも無意識に「多くあるから」と使ってしまいがちです。購入量を絞ることで大切に使う意識をもてるでしょう。
したがって、定期的に在庫をチェックし、不足している分だけを補充することで、過剰な購入を防ぎます。また、購入リストを作成して計画的に購入することも効果的です。
使用済みの消耗品を再利用する
使用済みの消耗品を再利用することで、新しい購入を減らすことも可能です。たとえば、印刷はするものの用が済んだら不要になってしまう裏紙を、メモ用紙として使うなどの工夫が考えられます。自社の仕事内容に応じて、どのような工夫ができるかを全員で考えてみるのがおすすめです。
また、購入時にリサイクル可能な物品を選ぶことで、環境にも配慮しつつ節約ができます。
まとめ買い割引を利用する
複数の部署や他の営業所と共同で購入することで、まとめ買い割引を利用できる可能性があります。大口注文による割引を活用することで、単価を抑えられるでしょう。また、1カ所に配送してもらうと配送費も削減できるため、全体のコストの節約につながります。
一方、まとめ買いをする際は、購入量が使用量とかけ離れていないか、買い過ぎにならないかをチェックしましょう。
会計処理の効率化を目指すなら「バクラク請求書発行」「バクラク請求書受取」
消耗品費は、事務用品など少額の事業用品を購入した際に使用する勘定科目です。ただし消耗品費にできるのは、10万円未満であるものや、使用期間が1年未満であるものに限定されます。
また、消耗品費を計上する際には、雑費や消耗品など似た勘定科目との使い分けにも注意しましょう。
消耗品費をはじめ、企業の経費処理をスムーズにしたいなら「バクラク請求書発行」「バクラク請求書受取」がおすすめです。バクラク請求書発行は、作成や送付、発行までを一括してクラウド管理できるサービスで、大幅な作業時間短縮を実現できます。バクラク請求書受取は、受領した請求書をAIが瞬時にデータ化し、仕訳まで完了できるサービスです。
いずれもインボイス制度・電子帳簿保存法に対応しております。無料トライアルもございますので、お気軽にお試しください。