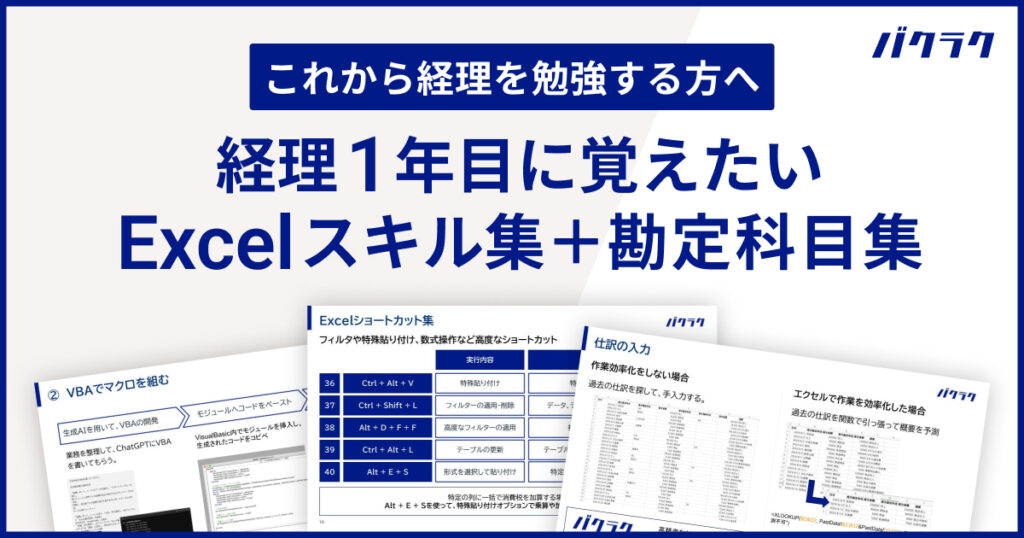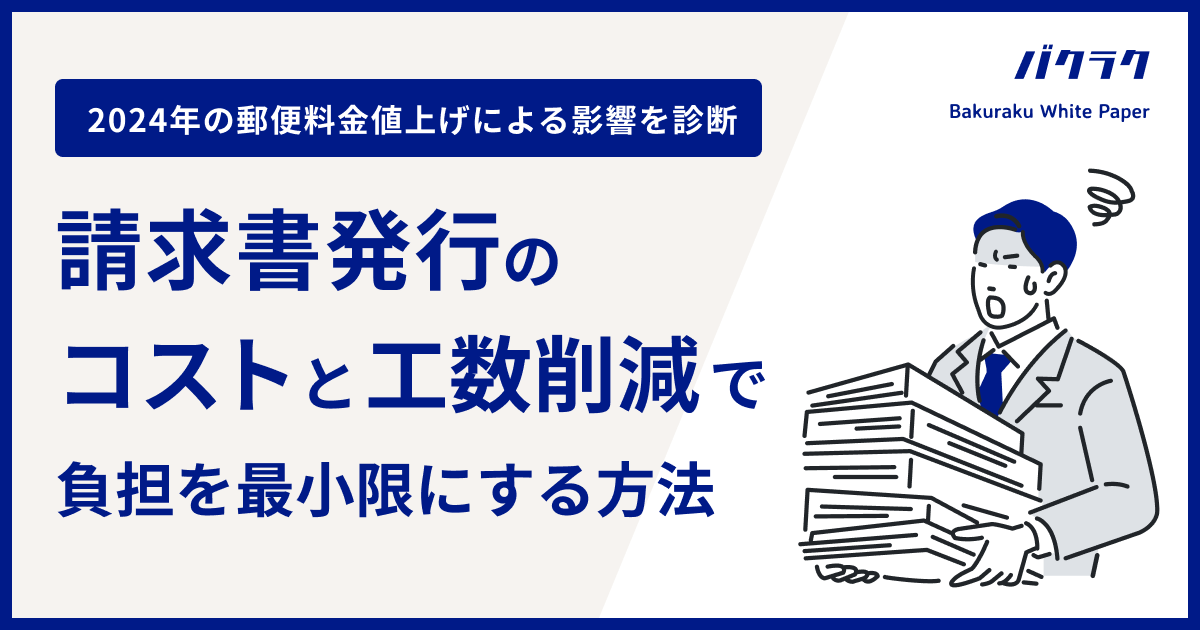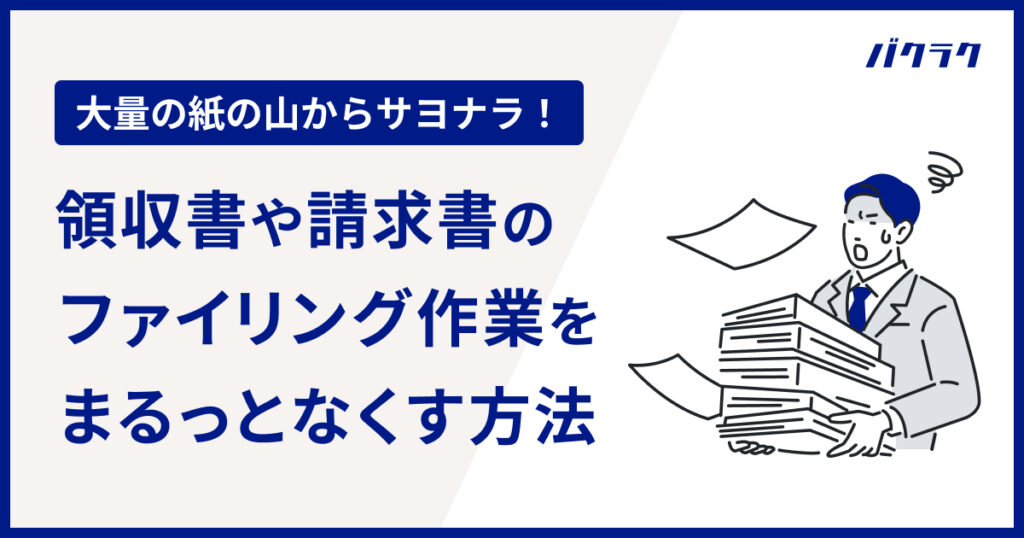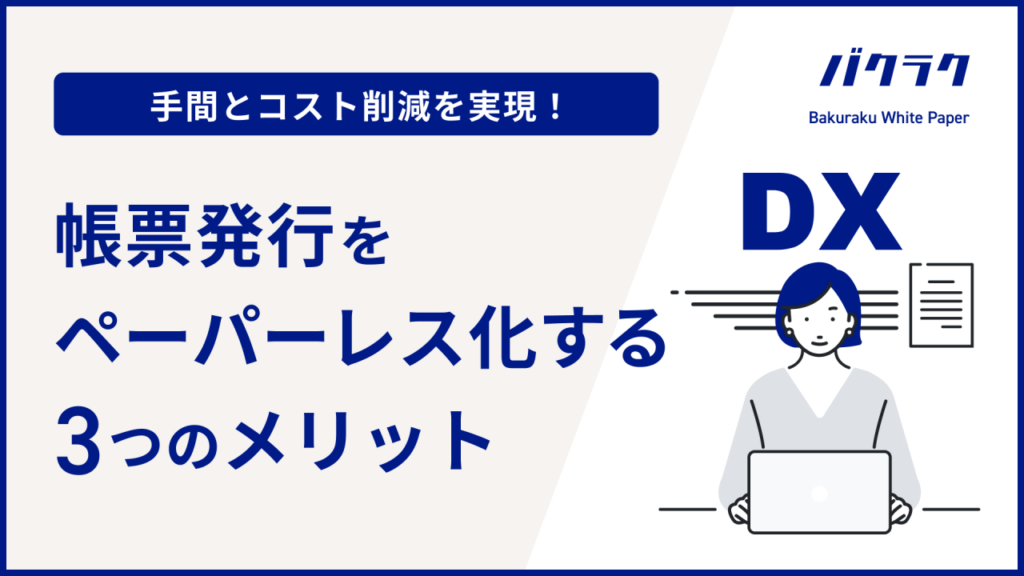インボイスにおける請求書と領収書の取り扱いは?対応はどちらかだけで良い?
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 請求書も領収書も必要事項が正しく記載されていれば、適格請求書として扱える
- インボイスに対応させるのは、請求書と領収書のどちらかだけでかまわない
- 請求書と領収書を合わせて1つの適格請求書とすることも可能
インボイス制度の開始に合わせて、請求書や領収書の書式を見直した事業者も多いでしょう。その際それぞれの書類の取り扱いについて、片方だけ見直せば良いのか、もしくは両方ともインボイス対応すべきなのか判断に迷うことも少なくありません。
本記事では、インボイス制度における請求書と領収書の取り扱いや、どちらか一方だけをインボイス対応すべきかについて解説します。各書類の保管期間も解説していますので、ぜひお役立てください。
インボイスにおける請求書と領収書の取り扱いは?対応はどちらかだけで良い?
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
インボイス制度における請求書と領収書の取り扱い
仕入税額控除を受けるためには、インボイス制度に沿って適格請求書を用いた取引を行わなくてはなりません。
適格請求書と認められないものが発行された場合や、発行できない事業者から仕入れを行った場合には、仕入税額控除を受けられず納税負担が増してしまうリスクもあります。
ではインボイス制度の要件を満たした請求書や領収書とは、どのようなものを指すのでしょうか。ここでは、各書類の記載要件と取り扱いについて解説します。
インボイス制度について改めて概要を確認したい方は、以下の記事をお読みください。関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
インボイス制度における請求書の取り扱い
インボイス制度では、請求書に以下6つの項目を記載することが義務付けられています。
- 請求書発行事業者の氏名や名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象の品目がある場合はその旨を記載)
- 税率ごとに区分記載した合計金額(税抜・税込どちらでも可)及び適用税率
- 税率ごとに区分記載した消費税額
- 請求書受領先者の氏名や名称
参考:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」
インボイスの要件を満たす請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録をすることが必須です。この際、登録番号「T + 13桁の(法人)番号」が付与されますので、その番号を記載します。
また、従来の区分記載請求書では、税率ごとに請求の合計金額が書かれていることが一般的でした。しかし、適格請求書ではこれに加えて、合計額それぞれの適用税率や消費税額を記載する点に注意しましょう。
適格請求書の書き方の例は、以下の記事でご確認ください。
関連記事:適格請求書とは?概要や書き方(見本付き)をわかりやすく解説
インボイス制度における領収書の取り扱い
インボイス制度では、領収書も適格請求書として扱えます。記載すべき項目は請求書と同様で、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの金額及び適用税率・消費税額や税率などが含まれます。
一方で、小売業や飲食店業など一部の事業者であれば「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を発行・交付することが可能です。簡易インボイスでは、受領者の氏名や名称の記載が不要で、消費税額または適用税率のいずれか一方を記載します。
通常の適格請求書と比較すると記載する項目が少なく、書類作成の負担が軽減されています。ただし、いずれも必須項目について記載が足りていないと、適格請求書として認められないため注意しましょう。
インボイス制度に則った領収書の詳しい書き方については、以下の記事をお読みください。
インボイスに対応させるのは請求書と領収書のどちらかだけで良い?
請求書と領収書を両方発行する場合、インボイスに対応させるのは請求書か領収書のどちらか一方だけで問題ありません。たとえば、請求書を適格請求書として発行した場合、領収書は通常の形式でよいでしょう。
反対に、従来どおりの区分記載請求書を発行し、領収書にインボイスの必要事項を記載することも可能です。また、同じ取引の請求書と領収書のそれぞれを適格請求書にしてもかまいません。
必要事項が記載されていると、両方を組み合わせて1つの適格請求書として認められます。ただし、1件の取引において複数の書類を扱う場合には、どれがインボイス対応のものなのか関連性を明確にし、取引先がスムーズに保存・管理できるよう配慮することが必要です。
請求書と領収書はどちらかの代わりに利用可能?
請求書と領収書はどちらもインボイスとして扱えますが、各書類の発行目的や役割は異なります。ここでは、それぞれの書類が各々の役割を代替できるかどうかについて解説します。
領収書が請求書の代わりになれるケース
領収書が請求書の代わりになるのは、領収書に取引内容が明確に記載されている場合です。具体的には、商品やサービスの名称、金額、消費税額とその税率区分が記載されている必要があります。合わせて、発行者および受領者の名称や住所も記載します。
また、領収書を適格請求書の代わりとするには、前述したとおりインボイス登録番号や税額内訳を含んで作成することが必要です。
請求書の詳しい書き方や注意点については、以下の記事で解説しています。
関連記事:請求書の書き方を重点的に解説!記載すべき項目や注意点とは
請求書が領収書の代わりになれるケース
請求書が領収書の代わりになるのは、支払い済みであることが明記されている場合です。「支払い済み」「受領済み」などの文言が記載されており、支払い日が確認できれば、領収書としての役割を果たします。
また、金額や消費税額が正確に記載されていることも重要です。インボイス制度に対応している場合には、適格請求書としての要件を満たすことで、領収書として利用されるケースもあります。
請求書兼領収書が発行されるケースも
請求書兼領収書とは、請求する金額と提供した商品やサービスの内容をまとめて記載した書類です。請求書と領収書が1枚にまとまっており、それぞれを同時に発行します。請求書兼領収書は、請求書の書面の一部に領収書の欄が設けられている書式が一般的です。
支払いが済んでいる事実がわかる内容であれば、任意の書式で作成した請求書でも領収書として認められます。使用される場面としては、病院がよく見受けられます。一方で、企業間取引において請求書兼領収書が使用されるケースは稀です。
請求書も領収書も保管義務があるため注意
請求書と領収書は、いずれも取引を証明するための証憑書類です。証憑書類には、一定期間の保管義務があります。法人の場合であれば、確定申告書の提出期限の翌日から7年間は、請求書と領収書を保管しなくてはなりません。
青色申告をしている個人事業主は、7年間の保管が必須です。支払総額が300万円以下もしくは白色申告であれば、保管の義務は5年間に短縮されます。
ただし、青色申告・白色申告の帳簿の保管期間は7年間と定められているため、実務上は税務に関するすべての書類をまとめて7年間保管するケースが多いでしょう。
インボイス制度に対応した請求書・領収書の発行なら「バクラク請求書発行」
請求書・領収書ともに記載要件を満たして作成していれば、適格請求書として使用できます。記載要件は、どちらも同じ項目でかまいません。また、取引においてどちらか一方だけをインボイス対応とすることも、反対に両方とも対応させることも可能です。
ただし、双方とも取引の証明となる証憑書類であるため、5〜7年間適切に保管しなくてはなりません。取引先にも考慮しながら、適切な方法で請求書や領収書をインボイスに対応させましょう。
「バクラク請求書発行」では、インボイス制度に則った請求書や領収書を発行できます。また、発行だけでなく送付や管理までの流れもワンストップで進められるため、大幅な業務効率化が期待できます。
電子取引・郵送取引の双方に対応しておりますので、請求書関連業務の見直しを検討しているのであれば、ぜひバクラク請求書発行にお任せください。