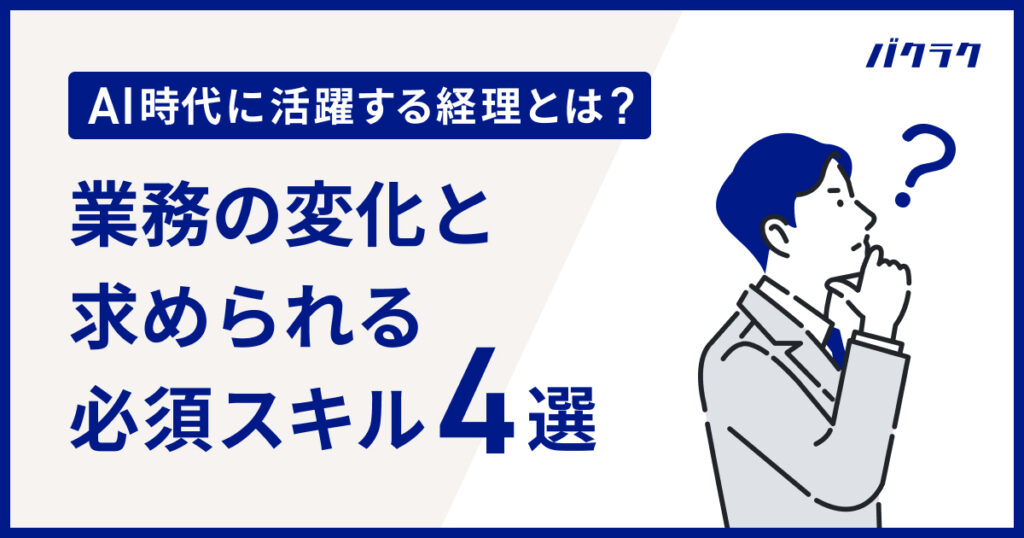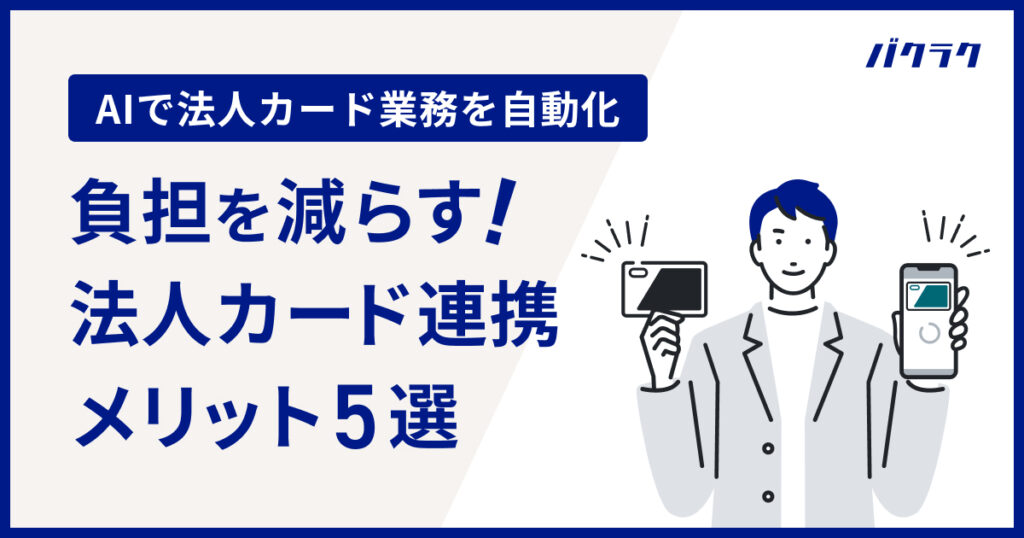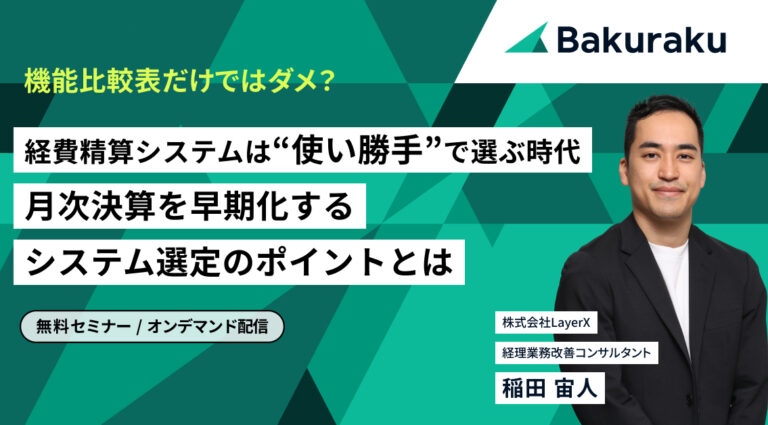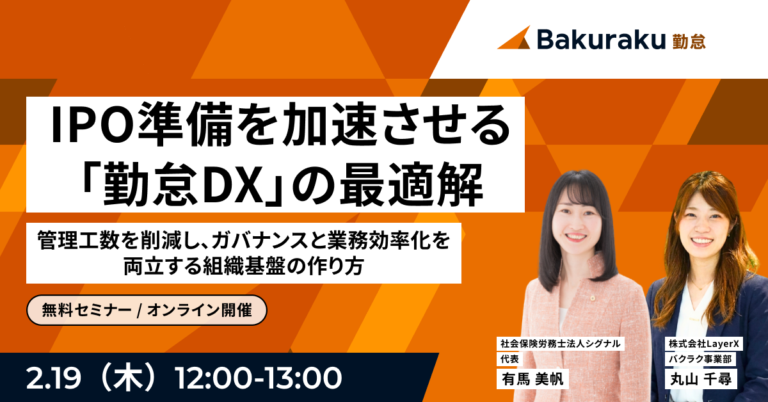通勤手当の全額課税はいつから?非課税限度額や計算方法についても紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-10-20
- この記事の3つのポイント
- 通勤手当は一定額まで非課税であり、現時点で全額課税対象になることは決定していない
- 現在の通勤手当の非課税限度額は、従業員の通勤手段によって異なる
- 通勤手当を支給する際は、支給要件を明記し、社会保険料の計算には注意が必要である
通勤手当の全額課税は、2025年8月時点で決定されていません。通勤手当は一定額まで非課税であり、通勤手段ごとに非課税限度額が定められています。
通勤手段によって計算方法が異なるほか「通勤手当が全額課税される」という噂もあることから、経理業務において混乱する方もいるでしょう。
当記事では、通勤手当の全額課税の真相を解説します。現在の非課税限度額や計算方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
通勤手当の全額課税はいつから?非課税限度額や計算方法についても紹介
通勤手当(通勤交通費)は一定額まで非課税
通勤手当(通勤交通費)は交通費の一種ではありますが、自宅から勤務地までの移動にかかる、日々の通勤費のみが対象です。たとえば電車やバスの定期代、自家用車のガソリン代などが含まれます。
通勤手当の支給義務はなく、福利厚生として導入するかどうかを会社側が決められる仕組みです。
通勤手当の支給額は、従業員が負担している実費の相当額を支給するケースが多いですが、交通費や旅費交通費とは異なり、全額が非課税とは認められません。一定額のみが非課税とされ、その範囲内で支給する会社がほとんどです。超過分は所得税の課税対象になります。
通勤手当が時給に含まれている場合には、通勤手当も給与所得の扱いとなり、全額が課税対象となる点に注意が必要です。
交通費は全額非課税
交通費は、業務目的で別の場所に移動した際にかかった費用のことです。たとえばクライアントへの訪問や商談、イベントや会議のための出張などが該当します。
交通費にはいくつか種類がありますが、単に「交通費」の勘定科目で処理する場合には、メインの勤務地から別の場所に移動した際の費用を指すことが多いでしょう。遠方に移動した場合には「旅費交通費」として処理する会社もあります。
交通費を支給する際には、先に従業員が費用を立て替え、後から会社がその費用を支給する流れが一般的です。「交通費」「旅費交通費」として支給すると、会社経営のための経費とみなされることから、従業員自身の所得税の対象にはならず、全額が非課税になります。
なお、交通費と旅費交通費の違いについては以下で解説していますので、ご確認ください。
関連記事:交通費精算とは?精算書の記載方法、ルールなど押さえるべきポイントを解説
旅費交通費の対象となる例については、以下の記事をお読みください。
通勤手当が全額課税対象になるのはいつから?
2023年に実施された政府の税制調査会の答申にて、通勤手当に対する課税の検討という文言が見られたことから「通勤手当が課税対象になる」という噂が広がっています。
答申を確認してみると、政府税制調査会は通勤手当と名指しはしていないものの「特に政策的に非課税なものは見直した方が良いのでは」という記述が見受けられます。
しかし、通勤手当に対する課税はあくまでも「検討中」の段階であり、2025年8月現在で決定した事実はありません。今後、通勤手当の全額課税について注視する必要はあるものの、現時点で具体的に必要とされる対応はないため、理解しておきましょう。
参考:内閣府 税制調査会「答申(案)について(2023年6月30日)」
現在の通勤手当の非課税限度額
通勤手当の非課税限度額は、従業員の通勤手段によって異なります。それぞれの限度額を確認しましょう。
電車・バスを利用する場合
電車やバスといった公共交通機関を利用している際は、1カ月15万円までであれば課税されません。以前の非課税限度額は10万円まででしたが、法改正により平成28年から5万円引き上げられています。
なお、通勤経路や手段が効率的だと判断されない場合には、課税対象となることもあります。たとえば新幹線のグリーン車を利用した場合や、他にルートがあるのに極端に乗り換え回数が多く、金額も高いルートを選定している場合などです。
参考:国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」
自家用車・自転車を利用する場合
自家用車や自転車を使って通勤している場合の限度額は、通勤距離に応じて変動します。具体的な金額は以下のとおりです。
片道の通勤距離 | 1ヵ月あたりの限度額 |
2km未満 | 全額課税対象 |
2km〜10km未満 | 4,200円 |
10km〜15km未満 | 7,100円 |
15km〜25km未満 | 12,900円 |
25km〜35km未満 | 18,700円 |
35km〜45km未満 | 24,400円 |
45km〜55km未満 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
参考:国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
交通機関と自家用車を併用する場合
交通機関と自家用車・自転車を併用している場合には、それぞれの限度額を合算したものが月15万円以内であれば非課税です。
具体的な例として、自宅最寄り駅から勤務先まで電車を利用し、最寄り駅から自宅までは自家用車を使って通勤しているケースを見てみましょう。
電車の定期代が月10,000円で、自宅から最寄り駅までの距離を片道8kmとすると「10,000円+4,200円(片道10km未満の限度額)=14,200円」となり、15万円に満たないため全額が非課税です。
ただし合理的なルートであると認められない場合は課税対象となることもあるため、注意しましょう。
自家用車の通勤手当の非課税限度額引き上げについて
政府は令和7年秋を目途に、マイカー(交通用具)通勤者に支給される通勤手当の非課税限度額を引き上げる方針を示しています。引き上げが実現されれば、平成28年の法改正から11年ぶりです。
この方針の背景には、近年のガソリン価格高騰によるマイカー通勤者の負担増加が挙げられます。一部報道では「距離区分ごとに数百円〜2,000円程度を上積みする案が検討されている」とされています。
課税となっていた一部が非課税となることで、所得税や住民税負担が軽減されるため、従業員側には手取り額が増加するという嬉しいニュースです。また、企業側としても負担増加なしで実質的な賃上げにもなるなど、双方にとってメリットがあります。
参考:日本経済新聞「マイカー通勤手当の非課税額、11年ぶり上げ 燃料高反映」
参考:自由民主党「令和7年度税制改正大綱」
通勤手当の計算方法
通勤手当を計算する方法は、従業員の通勤手段によって異なります。
電車・バスなどの交通機関を利用している場合は、定期券代を支給する会社が多いでしょう。
定期券がない場合には「片道運賃×2×月間労働日数」にて求めた額を支給します。支給は1カ月分とするのが一般的ではあるものの、定期券を3カ月や6カ月でまとめて購入している場合には、その期間分を一括で支給することも可能です。
自家用車の場合は、1kmあたりのガソリン代を会社ごとに定め、以下の計算式を用いて支給額を算出します。
1kmあたりのガソリン代(1Lあたりのガソリン単価÷平均燃費)×往復通勤距離×月間労働日数
ガソリン代をいくらに設定するかは会社の自由です。ガソリン単価の変動にも影響されますが、10円〜20円程度に設定する会社が多く見受けられます。また、駐車場料金を支給することも可能ですが、駐車場料金は非課税にならない点に注意しましょう。
自転車通勤の費用を支給する際は、駐輪場費用や保険費用、悪天候時に別の手段を利用する必要性などを加味して一律定額で支給することもあれば、電車・バス利用者の定期代相当額を支給するケースもあります。
また、通勤距離に応じて独自に算出方法を定めるケースもあるでしょう。つまり、自転車での通勤手当に関しては明確な計算ルールがなく、会社によって支給方法が異なる状況です。
ただし、非課税限度額は自家用車と同額のため、その範囲内で支給することが多いでしょう。駐輪場費用については、自家用車の駐車場料金と同様に課税対象となる点にも注意が必要です。
通勤手当の支給で注意したいポイント
ここからは、通勤手当を支給するときに気をつけるべきポイントを解説します。
支給の要件を明記する
通勤手当を支給するためには、要件を就業規則に前もって記載しておくことが必要です。たとえば、以下のような項目について明記します。
- どの通勤手段を使っている人が支給対象か
- 通勤手段ごとの支給額算出方法
- 支給上限額
- 支給時期
- 申請方法や手続きフロー
なお従業員の雇用形態によって、通勤手当の支給額や方法に差をつけることは認められません。アルバイトやパートの従業員であっても、正社員と同じように正当な算出方法で通勤手当を支給する必要があります。
また、通勤手当の支給は「月に◯回」と回数が定められているわけではないため、3カ月・6カ月分などまとまった期間分を一括で先払いしても問題はありません。実際、電車やバスの定期券は一括購入したほうが割引となるケースも多く、まとめて支給すれば支給時の業務負担軽減や支給額の節約につながります。
社会保険料の計算時に注意する
通勤手当は、社会保険料の計算に影響する点にも留意しましょう。
所得税の観点では非課税の範囲であっても、社会保険料を計算する際には、通勤手当など各種手当を含む月額報酬の全額が計算の対象とされます。そのため、誤って手当分を計算から除外しないよう気をつけましょう。
また、通勤手当を含んだ年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れる従業員も出てくるため、給与だけでなく各種手当の額も正確に把握しておく必要があります。
テレワークなら実費分を支給する
テレワークを推進している会社であれば従業員の出社回数が少ないため、実際の出勤日数に応じて従業員ごとに実費分を計算し、全額を支給するのがよいでしょう。
クライアント先へ訪問し、そのまま直帰して自宅でテレワークをするケースもあるかもしれません。その場合は通勤手当ではなく「交通費」として訪問時の費用を支給し、通勤手当にカウントしない対応も可能です。
「バクラク経費精算」で経費の処理がスムーズに
2025年8月時点で「通勤手当が全額課税対象になる」という事実はありません。政府の税制調査会の答申にて「通勤手当に対する課税の検討」という文言は見受けられるものの、あくまでも検討中の段階です。
マイカー通勤者の通勤手当に関しては、非課税限度額の引き上げ方針が検討されているなど、嬉しいニュースもあります。
一方、そもそも通勤手当の計算方法は従業員の通勤手段によって異なるほか、社会保険料の計算時にも注意が必要など、複雑な側面がある点は否定できません。計算時のミスは許されないため、慎重に進める必要があります。
通勤手当の計算をはじめ、経費精算を簡略化したい場合は「バクラク経費精算」の導入がおすすめです。経費の申請から承認、仕訳までを自動化できるため、一連の経理業務の自動化・効率化を実現できます。
また、走行距離に応じた手当など、社内の規定に合わせた手当の自動計算も可能です。利用する交通系ICカードの乗降履歴を取得して、経費精算時に利用することもできます。
複雑な通勤手当の処理を効率化したい場合は、ぜひ「バクラク経費精算」の導入をご検討ください。