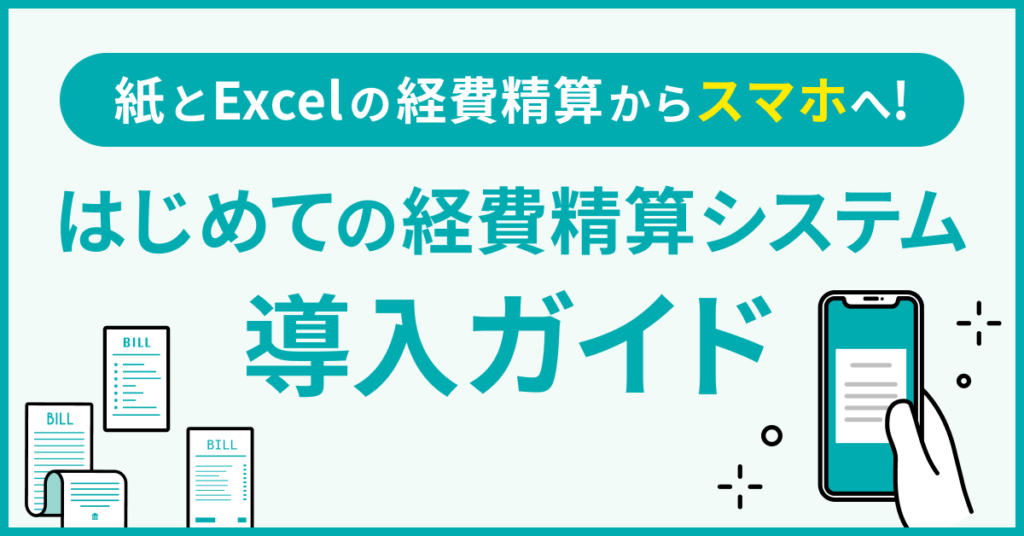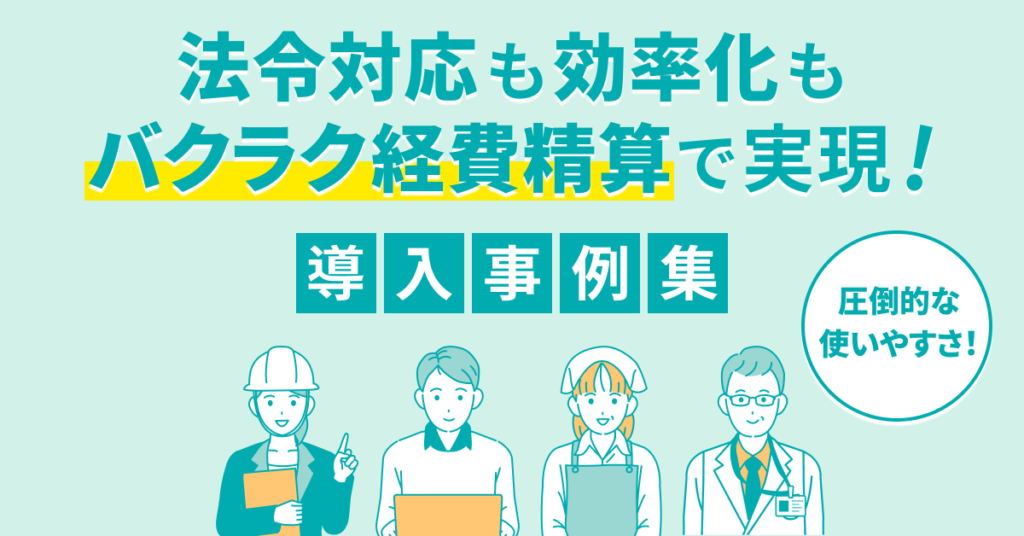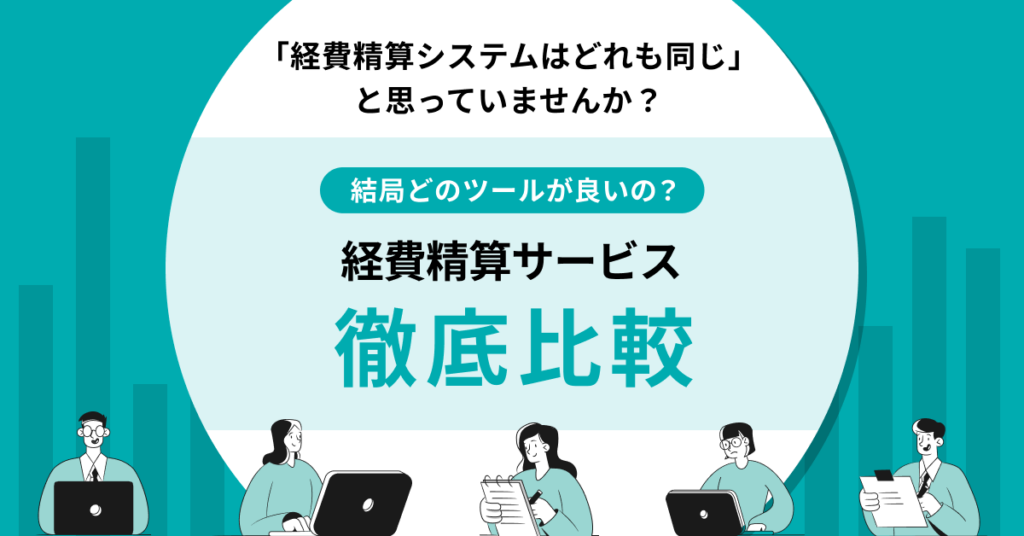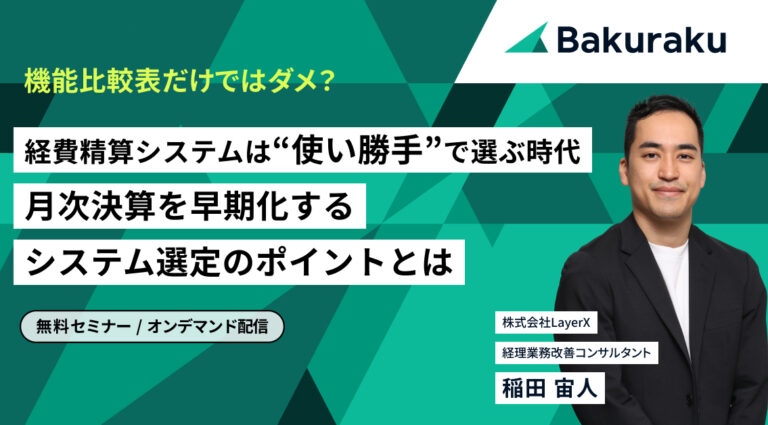経費精算システムとは?導入時のメリットやシステムの選び方を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 経費精算システムの導入は、申請者・承認者・経理担当者・経営者のそれぞれにメリットがある
- 導入・運用コストの問題、システム操作の取得が必要な点など、デメリットもいくつかある
- 運用のしやすさや機能の適合性、サポート体制などに着目し、自社に合うシステムを選ぶことが重要
経費精算システムの導入には、経費精算業務の効率化やペーパーレス化の推進、不正防止など多くのメリットがあります。しかし、経費精算システムには一定のコストがかかるため、導入の必要性を慎重に検討することが重要です。
本記事では、経費精算システムを導入するメリット・デメリットや選び方、導入の流れについて詳しく解説します。
経費精算システムとは
経費精算システムとは、経費の申請や承認、会計システムへのデータ入力など、経費精算に関わる業務を効率化するシステムのことです。
紙での経費精算には、申請・承認業務に時間と手間がかかる、入力ミスが発生しやすいなどの課題があります。経費精算システムを導入すると、経費精算に関する多くの業務を簡略化でき、ミスや不正も防げます。
経理部門だけでなく、企業全体に多くのメリットがもたらされるでしょう。
さらなる業務効率化を図るために、経費精算システムと会計システムを連携させるのも効果的です。会計システムのメリットや連携方法について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
経費精算システムの基本的な機能
経費精算システムには、さまざまな機能が搭載されています。基本的な機能を以下にまとめましたので、自社の課題と照らし合わせながらご確認ください。
| 機能 | 概要 |
| ワークフロー機能 | 経費精算の申請から承認までのプロセスを、システム上で完結できる機能 |
| 外部システムとの連携機能 | 会計システムや給与システム、勤怠管理システムなどと連携し、経費精算システムのデータを反映させる機能 |
| 自動仕訳機能 | 勘定科目や税区分などを選択すると、自動で仕訳が行われる機能 |
| 自動読み取り機能 | 領収書などに記載された文字や金額を、自動で読み取りデータ化する機能 |
| データ生成・分析機能 | 経費に関するデータを生成し、部門別・社員別・経費科目別などのさまざまな切り口から分析する機能 |
| 交通系ICカードとの連携・交通費の自動計算機能 | 交通系ICカードや乗換案内ソフトとの連携により、交通費を自動で計算できる機能 |
| 法人カードとの連携機能 | 法人カードを連携させると、クレジットカードの利用明細を経費精算システムに反映できる機能 |
| 証憑書類の管理機能 | 経費申請に使用した証憑類の電子データを、安全に管理する機能 |
| 振込データの自動作成機能 | 承認後の経費精算データを基に、振込データを自動で作成する機能 |
経費精算システム導入のメリット
申請者側のメリット
経費精算システムを導入する申請者側のメリットは、申請時の手作業を減らして業務効率化を図れる点です。記入漏れや計算間違いを防げることから、業務の正確性も向上するでしょう。申請書を記入する手間を省ける
経費精算システムの導入により、申請者は申請書に記入する手間を省けます。読み取り機能が搭載されている場合、スマートフォンで領収書を撮影してアップロードすると、申請書を容易に作成できます。 紙による経費精算の場合、申請者は領収書の記載内容を確認しながら申請書に記入しなければなりません。手間がかかるだけでなく、記入ミスや漏れが生じる可能性があります。簡単に承認依頼できる
経費精算システムを利用すると、申請書の承認依頼がシステム上で手軽にできます。申請書を直接提出しなくてよいため、事前に承認者のスケジュールを把握する必要がありません。 クラウド型のシステムの場合は、出先からも承認依頼ができるメリットもあります。外回りや出張が多い社員は、さらなる効率化を図れるでしょう。面倒な計算作業を自動化できる
交通系ICカードの読み取り機能や交通費の自動控除機能を活用すると、申請者は申請時の煩雑な計算を省略できます。 計算業務の自動化は、計算間違いの防止にも役立ちます。申請書の不備が減少し、差戻しによる再計算や修正の手間を省けるでしょう。承認者側のメリット
クラウド型の経費精算システムを導入した場合は、場所を問わず承認業務を進められます。ミスの防止にも役立つため、承認手続きの効率化を図れる点もメリットです。ボタン一つで承認・差戻しができる
経費精算システムを利用すると、申請書の内容を確認し、承認または否決を選択するのみで次の経費精算フローへと進みます。 承認者が申請書を持って、申請者や経理担当者を訪ねる必要はありません。出先でも承認作業ができる
クラウド型の経費精算システムであれば、出先で承認業務を進められます。移動中や出張中などの、すき間時間を有効活用できるのがメリットです。 テレワークを推進する企業にとって、魅力的なポイントの一つともいえるでしょう。承認し忘れを防げる
経費精算システムを導入すると、未承認の申請があった場合に承認者へ通知が届きます。承認忘れを防げるため、ほかの業務で多忙な人も安心です。 「未対応」「差戻し」などの申請状況をシステム上で確認し、自身が対応すべき申請を一目で把握できる点もメリットです。経理担当者側のメリット
経費精算システムの導入は、経理担当者にも多くのメリットがあります。いくつもの業務を省略できるほか、支払業務を終えた書類の保存・確認が容易になり、業務効率化を実現できます。申請内容のチェックを簡略化できる
経理担当者は申請内容を入念に確認し、不備があった場合は申請者へ差戻しをしなければなりません。経費精算システムでは、自動計算機能や自動読み取り機能があることによってチェックを簡略化できます。仕訳作業を効率化できる
経費精算システムを導入すると、勘定科目の確認や記帳の手間を省ける点もメリットです。 自動仕訳機能や会計システム連携機能の活用により、申請書の内容に応じた自動仕訳、会計ソフトへの反映が可能です。振込に必要なデータの作成を自動化できる
経費精算システムでは、精算後の振込に必要なFB(フォームバンキング)データが自動で作成されます。そのため、経理担当者は振込業務へスムーズに移行できます。 FBデータとは、複数の振込情報が集約されたデータのことです。紙による精算の場合、社員が立て替えた金銭を払い戻すために、FBデータを作成する手間が生じます。申請の催促や確認などがスムーズにできる
経費精算システムを導入すると、申請未提出者への催促や、不備がある書類の確認・差戻しなどがスムーズにできる点もメリットです。 未提出者をシステム上で抽出できるほか、申請期限が近付くと、メールやプッシュ通知での催促が自動で行われる機能が備わったシステムもあります。 差戻しをする場合も、システムを介して理由を簡潔に伝えられるため、再申請を促すまでの流れがスムーズです。申請者のもとに足を運んでやり取りする手間を省けるのは、経理担当者にとって大きなメリットといえるでしょう。紙での保管が不要になり管理や保管場所に困らない
経費精算システムを導入すると、申請書や領収書を自動で電子データ化できます。帳票類の整理や保管スペースの確保にかかる時間と手間を省けて、業務効率化を実現できるでしょう。 また、過去の電子データが必要になった際、ファイル名や日付で容易に見つけられるメリットもあります。膨大な量の中から、該当の書類を探し出す必要はありません。 経費精算のペーパーレス化による経理担当者のメリットは、以下の記事でも詳しく解説しています。実施の流れや注意点も紹介していますので、併せてご覧ください。 関連記事:経費精算のペーパーレス化で経理業務の負担軽減!実施する方法や期待できる効果とは?経営者側のメリット
企業経営において、社員の不正や人件費の問題に悩む経営者は少なくありません。経費精算システムの導入には、不正防止や人件費削減の効果も期待できます。経費精算の不正防止に効果がある
経費精算システムの導入は、経費精算の不正防止に役立ちます。 紙で経費精算をする場合は、申請書や領収書を1枚ずつ目視で確認する必要があるため、不正な経費を見逃す可能性もあるでしょう。しかし、経費精算システムの多くには、不正を防げる機能が搭載されています。 たとえば、交通系ICカードや法人クレジットカードと連携できるシステムの場合、正確な履歴を取り込めることから請求金額の水増しを防げます。最短の移動ルートと交通費を自動で算出できる機能を活用すれば、高額な交通費を故意に申請される心配もありません。 そのほか、交通費の二重申請を防げる定期区間の自動除外機能や、自動検知した不自然な経費の申請を知らせる自動アラート機能が備わったシステムもあります。 領収書や経費精算の不正事例について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。不正の原因や対策も、詳しく解説しています。 関連記事:領収書・経費精算の不正事例まとめ|原因や対策を解説人件費の削減が期待できる
経費精算システムの導入により、人件費の削減が見込めるのも経営者側のメリットです。 経費精算システムを導入すれば、紙の経費精算に必要なプロセスの多くを省略できます。これまで経費精算にかけていた業務時間をカットでき、結果として人件費の削減につながるでしょう。経費精算システム導入のデメリット
経費精算システムにはメリットだけでなくデメリットもあるため、どちらも把握しておきましょう。
導入や運用にコストがかかる
経費精算システムの導入、運用には費用がかかり、費用はオンプレミス型とクラウド型で異なります。
オンプレミス型は、初期費用としてライセンスやハードウェアを購入する必要があります。クラウド型の場合は利用ユーザー数に応じて毎月運用費がかかるのが一般的です。
経費精算システムの導入にあたっては、経理担当者の残業時間削減などの具体的な効果を検証し、費用対効果を考慮して導入するかどうかを考える必要があります。
システム操作の習得が必要になる
経費精算システムを導入すると、新しい進め方やシステムの操作を覚える必要があります。マニュアルを用意する、研修を開催するなどの対策を考えなければ、システムが浸透しない恐れがあります。
システム化できない作業がある
経費精算システムを導入しても、突合点検の作業や交際費の詳細を記載しなければならない場合など、システム化できない経費精算作業があります。
システム化できること・できないことをきちんと把握しておかないと、期待した成果が得られない場合もあります。システムの導入前に、自社の課題を経費精算システム導入で解決につなげられるかを検討しましょう。
導入前の周知・運用方法を検討する必要がある
経費精算システムを効果的に活用するためには、事前に従業員へ周知したり、運用方法をマニュアル・ルール化したりする必要があります。申請フローの確認・調整など、既存の運用方法を見直す手間も発生します。担当者を任命して、計画的にシステム導入を進めましょう。
経費精算システム導入のデメリット
経費精算システムの導入には多くのメリットがありますが、デメリットもあるため注意が必要です。
代表的な4つのデメリットを紹介しますので、メリット・デメリットの両方を理解した上で、導入の必要性を改めて検討しましょう。
導入や運用にコストがかかる
経費精算システムのデメリットの一つが、導入や運用にかかるコストです。経費精算システムにはオンプレミス型とクラウド型があり、それぞれ費用が異なります。
オンプレミス型は、導入時にライセンスやハードウェアの購入が必要なため、初期費用が高額になる傾向があります。クラウド型は、利用ユーザー数に応じた月額料金が発生するのが一般的です。
経費精算システムを導入する際は、費用対効果を考慮することが重要です。社員の人件費をどれくらい削減できるかなど、具体的な効果を検証した上で導入の必要性を検討しましょう。
システム操作の習得が必要になる
経費精算システムを導入する場合、これまでとは異なる業務フローで経費精算業務を進めなければなりません。システムの使用方法はもちろんのこと、場合によってはパソコンの基本操作から学ぶ必要のある社員もいるでしょう。
システムを有効活用するには、事前にマニュアルを整備し、必要に応じた研修を開催する必要があります。
システム化できない作業がある
経費精算システムを導入しても、突合点検や勘定科目の詳細入力など、一部の業務はシステム化できない可能性があります。
システムの導入で期待通りの効果を得るには、システム化できる業務を事前に把握しておかなければなりません。自社が求める機能の有無をシステムごとに確認し、最適なものを導入しましょう。
運用方法を検討し、導入前に周知する必要がある
導入前に運用方法を検討し、マニュアルを作成することも重要です。運用方法を決める際は、申請フローの確認や調整など、既存の運用方法を見直す手間が生じます。
マニュアルの作成後は、社員へ早めに周知して理解を得る必要もあるでしょう。スムーズな導入のためには、担当者を任命して計画的に準備を進めるのがおすすめです。
経費精算システム導入の流れ
経費精算システムの導入には、大きく分けて6つのステップがあります。
必要とする準備や具体的な動きをステップごとに紹介しますので、経費精算システムの導入を控えている方は理解を深めておきましょう。
システム導入の目的と解決したい課題を整理する
まずは経費精算システムを導入する目的と、解決したい課題を社内で整理します。
経費精算システムにはオンプレミス型とクラウド型の2種類があり、システムごとに特徴や機能性が異なります。導入の目的と課題を社内で明確化することにより、必要な機能が搭載された最適なシステムを選定できるでしょう。
経費精算に関する企業の課題として、代表的なものは以下のとおりです。
- 申請書の記載ミスや計算間違いが多い
- 電子帳簿保存法への対応が難しい
- 出張が続くと経費精算が締め日に間に合わない
- 交通費の二重申請や水増し申請が見受けられる
- 会計ソフトへのデータ入力や振込処理に手間がかかる
課題の洗い出しに難航する場合は、申請者・承認者・経理担当者・経営者のそれぞれから意見を聴取するとよいでしょう。
システムを比較検討する
自社の課題を整理できたら、複数のシステムから機能やコストなどを比較検討します。機能性に富んだシステムほど料金が高額になりやすいため、機能のバリエーションではなく、自社が必要とする機能が備わったシステムを選定しましょう。
システムを選ぶときに着目すると良いポイントは、後ほど解説します。
導入後の運用フローを確認する
導入するシステムを選定し、契約手続きを終えたら、導入後の具体的な運用フローを提供会社の担当者へ確認します。
確認の際に注意すべきポイントは、運用フローの詳細を自社で事前に話し合っておく点です。方向性が曖昧な状態で担当者と打ち合わせをすると、設定に時間を要して、システムの導入が難航しうるため注意が必要です。
システムの基本設定をする
システムの基本設定として、企業や社員の情報、使用する勘定科目などを設定します。
申請した経費精算を、誰がどのような順で承認するかについても、部署や部門ごとに設定が必要です。申請者と経理担当者の間に上長を加えると、経理担当者の負担軽減につながるでしょう。
基本的な項目を設定することにより、申請時は事前に登録した項目を選択するのみで情報を自動入力できます。申請内容の不備による、差戻しの対応も想定した上で設定しましょう。
テスト運用を行う
多くの経費精算システムでは、無料トライアルを利用できます。まずは一部の社員を対象にテスト運用を行い、運用フローやシステム設定に問題がないかを確認しましょう。
対象社員は、経費精算システムの使用が想定される営業部や管理部など、複数の部署から選定するのがおすすめです。
テスト運用では、機能の使い勝手や設定内容に関する所感のほか、操作方法に関する疑問も聴取するのがポイントです。システム導入の担当者は、テスト運用に参加した社員の声を取りまとめ、問題解決が可能かを提供会社の担当者と相談しましょう。
マニュアルを整備し本格的に運用を開始する
社員の意見をもとに操作方法のマニュアルを更新して、全社員が閲覧できるように準備します。テスト運用の際に出た疑問点は、よくある質問としてまとめておくのがおすすめです。
システムの操作マニュアルは、基本的に提供会社が所持しています。すべて自社で作成するのではなく、原本に必要な加筆をすることで、マニュアル整備の負担を軽減できるでしょう。
これまでの経費精算に慣れている社員は、新たなシステムの導入に抵抗を感じるかもしれません。操作方法だけでなく、システム導入の目的も周知した上で本格的な運用を開始しましょう。
必要に応じて、システムの使用方法やパソコンの基本操作に関する研修も実施するのがおすすめです。
自社に合う経費精算システムの選び方
経費精算システムに求める要素は、企業ごとに異なります。自社が必要とする機能が備わっているか、コストのバランスが良いかなどを考慮しながら、最適な経費精算システムを選定しましょう。
本章では、自社に合う経費精算システムの選び方について詳しく解説します。
運用のしやすさ
経費精算システムは、実際に使用する社員のことを考慮して選ぶことが重要です。運用方法が複雑な経費精算システムの場合、実務で活用できない可能性があります。
導入後に社員が抵抗なくシステムを利用するためにも、無料トライアルなどによるテスト運用を極力実施しましょう。
導入の目的と機能の適合性
経費精算システムを導入する際は、自社の課題を整理し、解決につながるシステムを選定することもポイントです。経費精算に関して企業が抱えやすい課題と、解決に適したシステムの例は以下をご覧ください。
| 企業の課題 | 適したシステム |
| 外回りや出張が多い |
|
| 経費精算を効率化したい |
|
| 外国籍の社員や海外を拠点とする企業との取引が多い |
|
他システムとの連携性
経費精算システムを活用するには、社内で運用中の既存システムとスムーズなデータ連携が可能かを確認することも重要です。
たとえば、仕訳業務の効率化には、会計システムと連携可能なシステムがおすすめです。書類のペーパーレス化に取り組みたい企業には、既存のワークフローシステムと連携できるものが適しているでしょう。
連携方法も、システムごとに異なるため注意が必要です。すべて自動で反映されるシステムもあれば、手作業やプログラムの構築が別途必要なものもあります。連携方法も、事前に確認しておくと安心です。
サポート体制
システムの導入に関して疑問や不具合が発生した際は、提供会社に相談しなければなりません。導入前・導入後でそれぞれどのようなサポートを受けられるか、事前に確認しましょう。
サポートの方法には電話やメール、ビデオ通話、直接訪問などがあるものの、対応方法は会社ごとに異なります。たとえば、マニュアルの提供と会社のホームページを通じた問い合わせのみが可能な場合、回答を得るまでに時間を要する可能性があります。
システム導入に関する問題の多くは導入後に発覚しやすいため、導入後のサポートも充実した会社を選ぶのがおすすめです。導入後に会計システムなどとの連携を検討している場合は、連携作業のサポートが可能かどうかも併せて確認しましょう。
法令への対応
経費精算はさまざまな法令と深い関わりがあるため、法令への対応についても確認が必要です。
たとえば電子帳簿保存法では、電子データで帳票を保存する場合に要件を満たさなければなりません。電子帳簿保存法に対応したシステムであれば、経理担当者の負担を最小限に抑えてスムーズに運用できます。
今後の法改正に、柔軟に対応できそうか否かも併せて確認してください。提供会社の担当者に直接確認するほか、会社が法改正に関して積極的に情報発信しているか否かでも判断可能です。
電子帳簿保存法について理解を深めたい方は、以下の記事をご参照ください。
経費精算システムの導入後に改善したいポイント
経費精算システムは導入して終わりではなく、社内での定期的なアップデートが必要です。スムーズな運用のために、導入後に改善すると良い2つのポイントを紹介します。
社員の意見を運用フローに反映させる
経費精算システムを実際に利用する社員が、操作性に疑問を感じている状態では適切に運用できません。導入後も社内アンケートや面談を通じて、システムの使用感や問題点などを定期的に確認しましょう。
特に人事異動や社内ルールの変更があった際は、積極的な聴取が必要です。社員の意見をもとに、運用フローへ反映させましょう。
マニュアルをより充実させる
経費精算システムをスムーズに活用するには、マニュアルの充実化を図ることも重要です。導入時に見落としていた細かな点を随時追記し、定期的にマニュアルを更新しましょう。
社内で多い問い合わせをもとに追記すると、回答する側の手間が省けるメリットもあります。更新したマニュアルを全社員がいつでも閲覧できるように、配布方法や設置場所にも工夫が必要です。
「バクラク経費精算」の導入で業務効率化!申請・承認フローが一本化
経費精算システムとは、経費の申請や承認、会計システムへのデータ入力など、経費精算に関わる業務を効率化するシステムのことです。
経費精算システムの導入には、経理担当者だけでなく、申請者や承認者、経営者にもメリットがあります。まずはシステムの目的や解決したい課題を社内で整理し、自社が求める機能が搭載されたシステムを選定しましょう。
バクラク経費精算は、あらゆるミスを防ぐ機能のほか、自動仕訳やERP・会計ソフトとの連携など、さまざまな機能を搭載しています。
電子帳簿保存法やインボイス制度といった各種法令にも対応しており、経理担当者の負担軽減と効率化を図れる点もポイントです。
経費精算システムの導入を検討中の方は、バクラク経費精算をご検討ください。詳しいサービス内容や無料トライアルについては、以下のページからご確認いただけます。