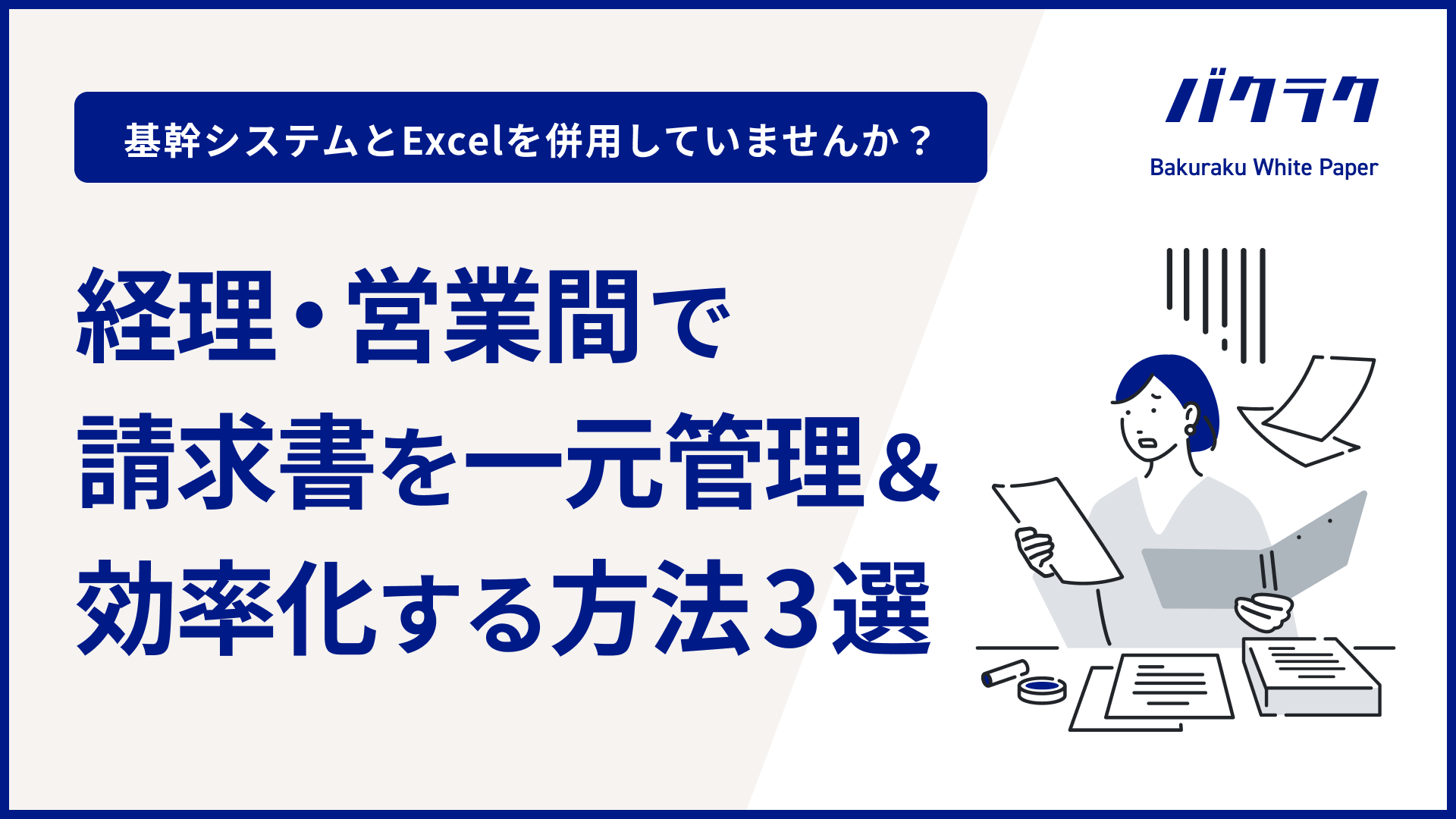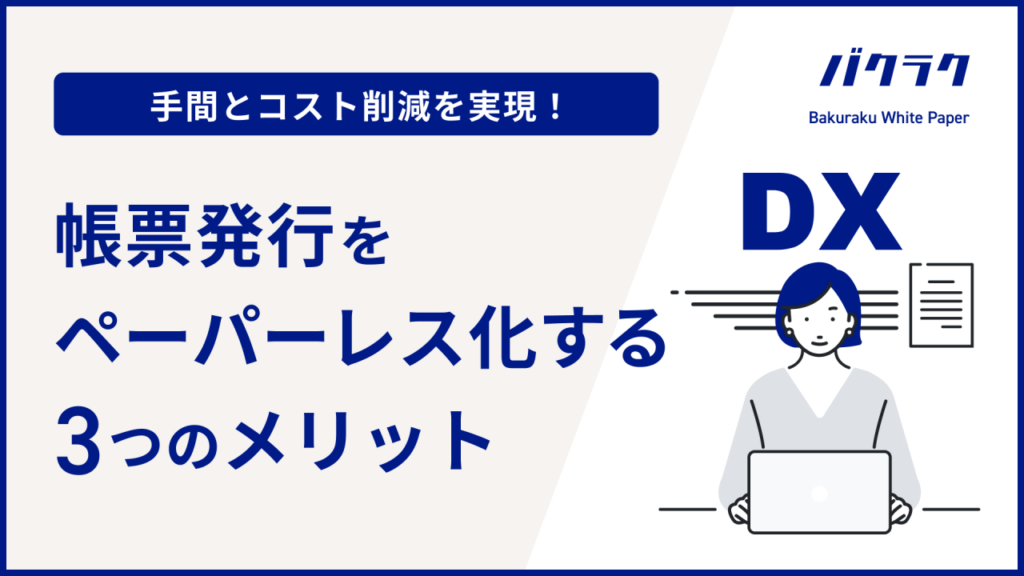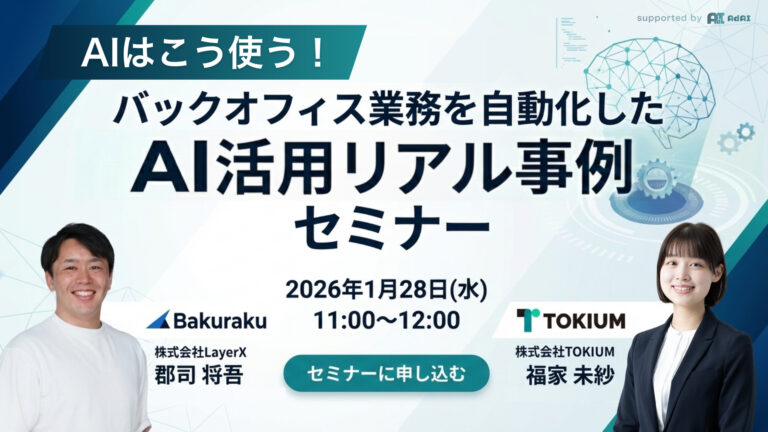
電子帳簿保存法における紙で発行された請求書の保存方法とは?期間についても解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-26
- この記事の3つのポイント
- 紙でもらった請求書は、紙のまま保存する方法とスキャナ保存があるが、任意で選択できる
- スキャナ保存の場合、電子帳簿保存法に則った要件を満たして保存する必要がある
- スキャナ保存では社内ルールや保存フローを構築するなど、ポイントを守って保存することが大切
電子帳簿保存法の改正により、紙で受け取った請求書の保存方法に悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、紙で受け取った請求書を紙のまま保存する場合のポイントを解説します。そのほかスキャナ保存の手順や要件まで、効率的に法令遵守をしつつ請求書を管理する方法も説明するので、参考にしてください。
電子帳簿保存法における紙で発行された請求書の保存方法とは?期間についても解説
紙でもらった請求書は紙のまま保存して問題ない
紙で受け取った請求書は電子帳簿保存法に基づいて、そのまま紙の形で保存しても問題ありません。紙のまま保存する場合はファイリングを行い、日付や取引ごとに整理して保管場所に収めるだけで済むため、ITに不慣れな企業や社員でも管理が容易です。
また紙のまま保存することで電子化に伴う業務フローの変更がないため、現場への影響が最小限に抑えられる点も、紙のまま保存するメリットといえるでしょう。
2022年1月に改正された電子帳簿保存法の詳細について詳しくは、以下の記事で解説しているのでぜひご覧ください。
紙でもらった請求書はスキャナ保存も可能
紙で受け取った請求書は、電子帳簿保存法に基づいてスキャナ保存が可能です。スキャナ保存とは、専用のシステムやスキャナー機器を使って請求書をデータ化し、その電子データを保存する方法です。
スキャナ保存は任意で選択でき、業務のIT化や省スペース化を図りたい企業にとって、便利な選択肢といえます。スキャナ保存には要件があり、原本の改ざん防止を目的としたタイムスタンプの付与が求められるほか、訂正・削除の履歴管理機能が整ったシステムでの保存が必要です。
スキャナ保存には必ずしもスキャナー機器が必要ではなく、要件を満たしていればスマートフォンやカメラでの撮影を通じて画像データ化する方法も認められています。
電子帳簿保存法に則ったスキャナ保存の要件
紙で受け取った請求書をスキャナ保存する場合、電子帳簿保存法の要件を満たすことが必要です。スキャナ保存の要件については、以下のとおりです。
| スキャナ保存の要件 | |
| 解像度 | 200dpi以上 |
| カラー | RGBそれぞれ256階調以上(一般書類は白黒も可) |
| タイムスタンプ | 付与(入力期間中にスキャナ保存したことを確認できれば省略可) |
| システム | 訂正・削除の履歴を保持できるシステムでの保存 |
| 入力期間 | 請求書を受領してから概ね7営業日以内にデータ化をする もしくは、事務の処理サイクルを最長2カ月とした場合、その期間経過後7営業日以内にスキャンが必要 |
上記のほかにも帳簿との関連性を確保するため、スキャナデータと帳簿に同じ番号を振るなどしてリンクさせることも求められます。スキャンデータの検索機能の充実も必要で、取引日や金額、取引先などからの検索が可能であることが条件です。
さらに14インチ以上のカラーディスプレイや、カラープリンターの設置も必要で、適切な閲覧環境を整える必要があります。
紙の請求書をスキャナ保存する手順
紙の請求書を電子帳簿保存法に則ってスキャナ保存する手順は、以下のとおりです。
- 受け取った請求書の原本をスキャナで読み込むか、スマートフォンなどで撮影し、データとして取り込む
- データを電子帳簿保存法の要件を満たしたシステムにアップロードし、タイムスタンプを付与する
- 法人であれば原則7年間、個人事業主は5年間の保存期間を確保し、適切に管理する
タイムスタンプは訂正削除の履歴が保存されるシステムを利用している場合、省略可能です。電子化をすすめれば、ペーパーレス化や効率的なデータ管理が実現しやすくなりますが、手順に沿って正確に運用していく必要があります。
紙の請求書の保管期間
紙で受け取った請求書の保管期間は電子データと同様で、法人の場合、原則7年間の保存が必要です。ただし青色申告で繰越欠損金や災害損失金が発生した年度は、10年間の保存が義務付けられています。
個人事業主の場合、保管期間は原則5年間です。副業収入が300万円を超える会社員も、該当する場合には同様に、5年間の請求書保存が求められます。法人個人関係なく、保存期間の起算日は、確定申告書の提出期限翌日からです。
また適格請求書(インボイス)に該当する場合、法人個人を問わず、一般課税の方法で仕入税額控除を受けるためには、7年間の保存が必要です。この場合、保存期間の起算日は課税期間末日の翌日から2カ月後となります。
適格請求書と一般の請求書が混在している場合、すべての請求書を少なくとも7年間保管しておけば、管理ミスを防ぎやすくなります。
請求書の保管期間について詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
スキャナ保存した場合、紙の原本は破棄できる
スキャナ保存の要件を満たして請求書をデータ化した場合、紙の原本は破棄しても問題ありません。ただしスキャナ保存の要件を満たさずにデータ化し、原本を破棄してしまえば、法令違反となることもあるため注意しましょう。
たとえば適切な解像度やカラー階調で保存したとしても、閲覧用の機器が設置されていなかったり、システムに関する書類が備え付けられていなかったりした場合、法令遵守の観点で問題となる可能性も否定できません。
スキャナ保存の要件は詳細かつ厳格なため、データ化直後にすぐ原本を破棄することにはリスクがあるといえます。要件を完全に満たしているかを確認し、万が一に備えて一定期間は紙の原本も保管しておくことで、安全性を高められるでしょう。
請求書の破棄については、以下の記事で詳しく解説しています。
電子帳簿保存法に則り紙の請求書を保存する際のポイント
電子帳簿保存法に沿って、紙の請求書を適切に管理するためには、いくつかのポイントを知っておかなければなりません。管理方法にばらつきが生じないようにするため、今から紹介する3つのポイントを参考に、全社的なルールの策定と周知を徹底しましょう。
社内ルールやフローを構築する
電子帳簿保存法に則って紙の請求書を保存する際、社内ルールやフローを構築することがポイントです。請求書を受け取った後の社内フローを明確にしておけば、電子帳簿保存法を確実に遵守できます。
スキャナ保存を選択する場合、必要な解像度やカラー階調、タイムスタンプの付与など、法的要件を担当者全員が正確に把握することが重要です。また複数の部署や担当者が関与する場合は、保存方法や手順を統一し法令違反のリスクを未然に防ぎましょう。
取引先に社内の請求書保存方法を伝える
自社が電子帳簿保存法に基づき、請求書を電子データで保存する場合、取引先に社内の方針を事前に伝えておくこともポイントです。取引先も紙の請求書を発行し、郵送する手間が省けるため、業務負担軽減につながります。
また電子データ保存を選択すれば不要な紙書類が減るため、社内の管理効率も向上します。事前に運用方法を共有すれば、自社と取引先双方にとってメリットがあるため、ぜひ伝えるようにしてください。
電子帳簿保存法やインボイス制度などに対応したシステムを導入する
電子帳簿保存法の要件を満たしつつ、紙の請求書をスキャナ保存するには、手作業では複雑になりがちです。スキャナ保存は解像度やタイムスタンプなどの厳密な条件があるため、すべて手動で管理しようとすれば、大きな負担となるでしょう。
そのため法令に対応したシステムを導入することも、紙の請求書を保存する際のポイントです。専用システムを導入すれば、スキャナ保存の要件を自動で満たす仕組みが活用できるため、請求書の電子保存や管理が一層効率化します。
またインボイス制度への対応も視野に入れ、最新の法令に対応したシステムを選べば、今度の運用もスムーズです。
バクラク請求書受取なら電子帳簿保存法に対応して業務効率化が可能
電子帳簿保存法における紙の請求書の保存方法は、紙のままでもスキャナ保存でも構いません。どちらの保存方法を選択した場合でも、法令に基づいた保存要件を守ることが重要です。
スキャナ保存を選択した場合、管理の効率化が図れますが、解像度やタイムスタンプ、システムの要件などを確実に満たさなければならないため、専用のシステムの導入が有効といえます。
受け取った請求書の処理を効率化するサービスの「バクラク請求書受取」を利用すれば、請求書を電子帳簿保存法に準拠した形式での保存が可能です。自社開発した高精度AI-OCRにより手入力がゼロなので、工数が削減できるだけでなく入力ミスも防止できます。
「バクラク請求書受取」に関して詳しくは、以下のページをご覧ください。