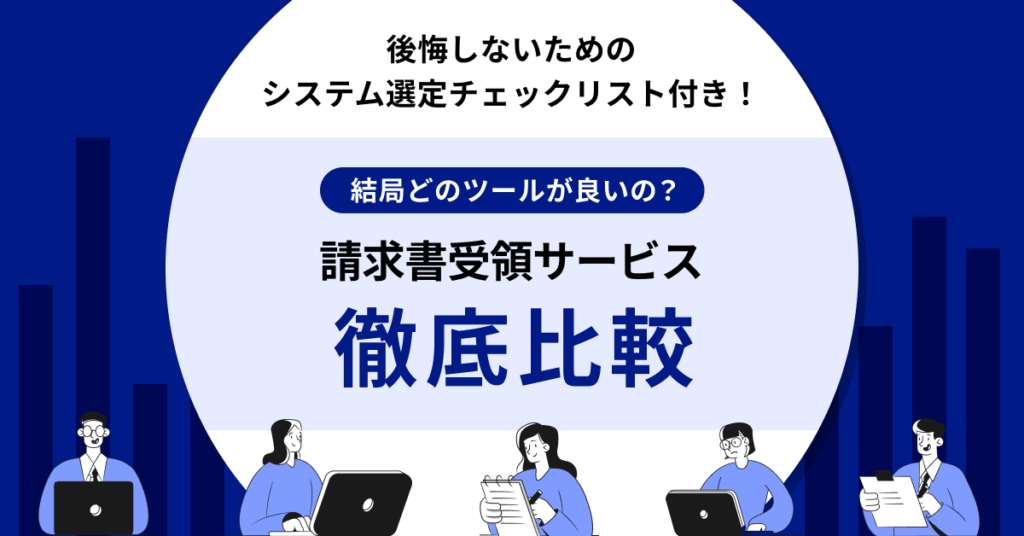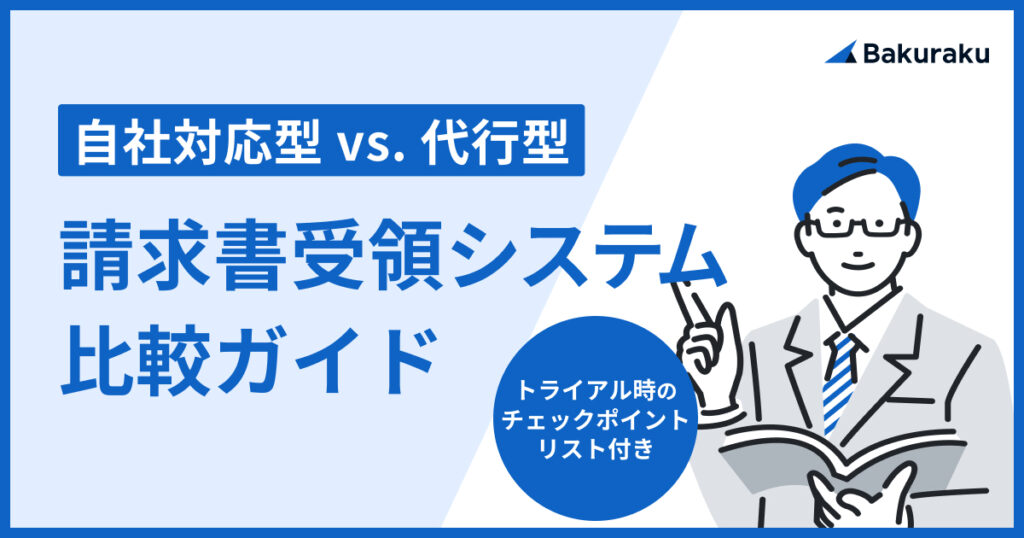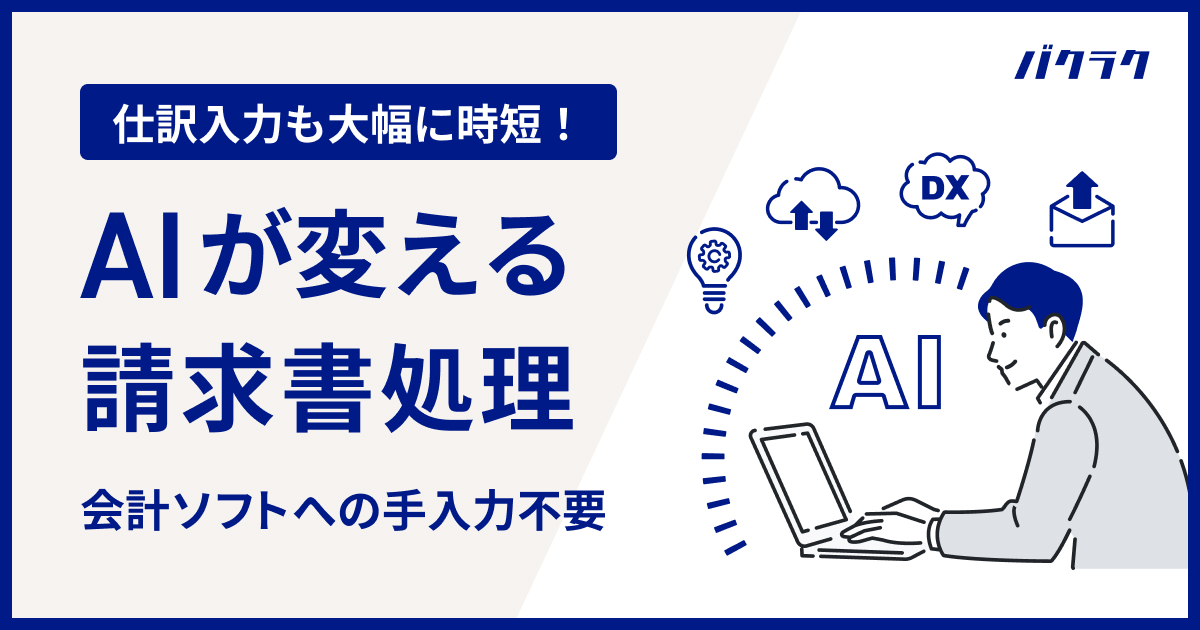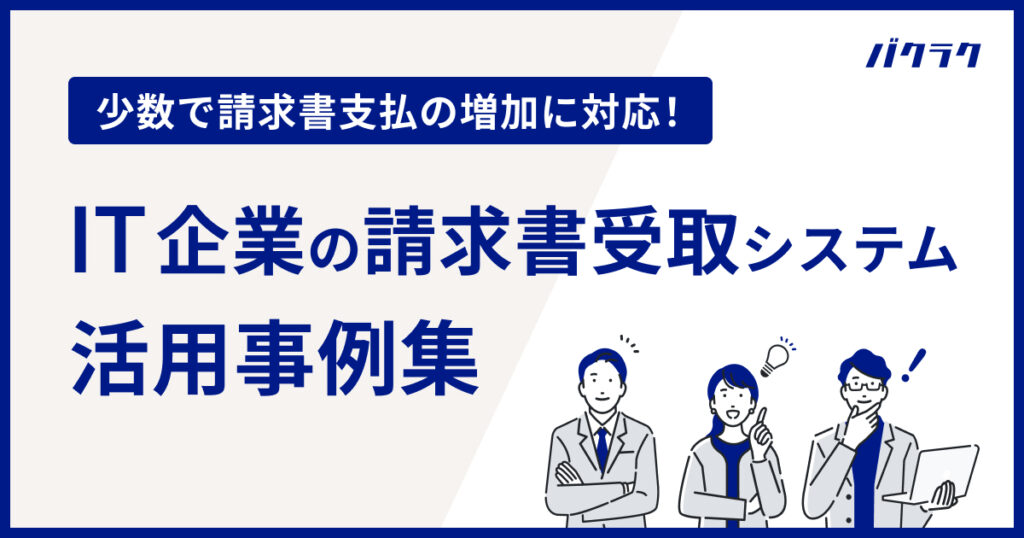請求書の処理業務を自動化するには?おすすめシステムや選び方を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-09-17
- この記事の3つのポイント
- 紙での請求書処理は、時間や費用がかかるほか、取引先ごとの雛型の管理や人的ミスの防止が必要
- 請求書処理を自動化するには、電子化・システムの導入・承認プロセスの効率化・外部委託が有効
- 請求書システムを導入する際は、必要な機能・導入形態・費用・サポート体制の事前確認が重要
紙での請求書処理は、時間やスペースの確保にコストがかかるだけでなく、人的ミスも発生しやすいことから、業務を自動化する企業も増えてきました。
本記事では、請求書処理を自動化する方法やメリット、システムを導入する際の選び方を詳しく解説します。業務を効率化して負担を減らし、正確な請求書処理ができる環境を整えましょう。
請求書受領サービス比較資料のご紹介
受領した請求書の受取〜仕訳、支払といった諸業務を効率化するために重要な役割を担う請求書受領サービスの比較表や選定のポイントを紹介した資料が以下のリンクからダウンロードできます。
全6社のサービスの機能や値段の違いを記載した比較表に加え、サービスのトライアル時などに確認しておきたいチェックリスト付きです。システム選定時の参考にぜひお役立てください。
請求書の処理業務を自動化するには?おすすめシステムや選び方を解説
請求書の処理業務にまつわる課題
請求書にまつわる業務は、企業の規模に関わらず多くの課題があります。
ここでは、特に多くの企業が抱えている課題について解説します。
発行や送付にコストと時間がかかる
請求書を紙で発行する場合、用紙や郵送、スペースの確保にコストがかかります。また、複数の工程があり、送付するまでには時間を要します。
業務量に比例して請求書の発行数も多くなることから、繁忙期ほどコストと時間の両面で負担が増えるといえるでしょう。
取引先ごとにフォーマットが異なる
取引先のシステムから出力された請求書は、企業ごとにフォーマットが異なります。
そのため、会計システムに手入力する際は、項目に気を配りながら行わなくてはなりません。しかしフォーマットが多岐にわたると、確認にも時間がかかり、入力内容を誤ってしまうリスクも高くなります。
また、取引先によって項目の名称などが異なることも、ミスが発生する要因です。新人へ入力業務を指導する際にも、詳しく解説しなければいけません。
扱うフォーマットが増えると、たとえ入力業務に慣れていても、決してミスしないということは非常に困難といえるでしょう。
受領後の入力作業が面倒
請求書受領の業務で特に大きな課題とされているのが、受領後の入力作業です。
入力作業は時間や手間が多くかかります。取引先ごとにフォーマットが異なれば、それだけ集中力が必要となりますし、数多くの請求書を、誤りのないように手入力でシステムへ入れて振り込みまで繋げなくてはなりません。
請求書は月末などの決まった時期に集中する傾向にあります。さらに、請求書受領の作業をしつつ通常業務も並行して進めなければいけないため、入力作業は大きな負担となります。
手入力だと人的ミスが発生しやすい
電卓で請求金額を計算したり、手作業で会計システムへの入力を行ったりする場合、人的ミスのリスクが高まります。
二重チェックなどを行っている企業もありますが、チェック作業が負担となり担当者に余計なストレスを与えモチベーションの低下を招いているケースもあるでしょう。
また、コア業務が圧迫される可能性も高いため、影響を最小限に抑えた仕組みやチェック体制の構築などが必要です。
スキャンやファイリングが面倒
受領・発行した請求書は、スキャンを行いデータで保存し、原本もファイリングして保管しなければいけません。請求書関連業務では、特にこのスキャンやファイリングが大きな手間となります。
適切に管理できるよう、細かくラベル付けをして整理するのに時間がかかるのはもちろん、保管スペースの確保も必要となるため、準備が大きな負担になります。
請求書関連業務における課題は、以下の記事で解説していますのでご確認ください。
請求書の処理業務を効率化・自動化する方法
請求書の受領・発行を自動化・効率化することで、業務にまつわる課題を解決できます。
ここでは、請求書処理業務をスムーズに行える自動化・効率化の方法を確認しておきましょう。
ペーパーレス化の推進
ペーパーレス化することで、原本をファイリングする手間を排除でき、保管場所が不要になります。
しかし、ペーパーレス化を進める際には「電子帳簿保存法」「インボイス制度」など最新の法令を正しく理解し、法令に沿って電子化を行う必要があります。
ペーパーレス化は適切な方法で行えば、特別な費用をかけずできるため、自動化・効率化しやすいといえるでしょう。
システムの導入
請求業務を効率化する手段として、システムを導入するのも有効です。
請求書管理システムには、請求書を発行するシステムと、受領した請求書を保管するシステムの2つがあります。
発行システムは、請求額の算出から請求書の送付までを一括管理できるのが特徴です。
受領システムは、オンライン上での電子保管や検索に対応しています。
双方のシステムを導入すれば、請求書の作成・送付から受領・管理までが効率化され、リモートワークでもスムーズに経理処理ができるでしょう。
請求書発行システムの詳細は、以下の記事でご確認ください。
関連記事:請求書発行システムとは?機能・種類から導入するメリットと注意点まで解説
請求書受領システムについては、以下の記事で解説しています。
関連記事:請求書受領サービスとは?種類やメリット・デメリット、選び方
承認プロセスの簡略化
請求書受領・発行に「ワークフローシステム」があれば、承認プロセスをスムーズに行えます。ワークフローとは、請求書受領・発行を行うための一連の作業や手続きのことです。
複雑な承認プロセスを導入している企業も少なくありません。承認可能となるステップ数、適用条件について改めて確認し、工数を見直すことが効率化につながります。
アウトソーシングの活用
アウトソーシングを利用して業務を効率化する方法もあります。
請求書発行のアウトソーシングでは、取引データを提出すると、作成から送付までを代行会社が行います。入金確認や未回収金の催促、消込業務を代行している企業もあるでしょう。受領業務では、書類の開封やデータ化が委託できます。
アウトソーシングの活用によって本来のコア業務に集中できるため、全体的な生産性向上につながるでしょう。
請求書の処理業務をシステムで自動化する効果やメリット
ここでは、請求書処理業務を自動化することで得られる効果やメリットについて詳しく解説します。
リモートで完結する
コロナ禍を機に、業務体制を見直してリモートワークを導入する企業が増えました。請求書業務も環境を整えることでオンラインで完結できます。
請求書の受領を自動化すると、ネット環境があれば請求書のチェック・承認ができます。請求書の発行であれば、作成から送付・保管・検索の一連の工程ができるでしょう。
育児や介護を抱える社員でも、自宅から業務できるようになります。また、居住地に関わらず優秀な人材を発掘しやすくなるのもメリットです。
経理部門だけでなく部門間のやり取りもスムーズになり、企業全体の業務効率化が見込めます。
業務負担を軽減できる
請求書業務は月末や月初に集中しやすく、残業や休日出勤を余儀なくされるケースも少なくありません。
請求書の受領を自動化すれば、入力や確認作業の手間を減らせます。発行業務では、印刷や封入、発送工程を削減できます。
システム化により、重要業務に時間を割けるため、リソースを有効活用できるでしょう。また、人的ミスが防げるのもメリットです。
請求書の処理業務を自動化するシステムの選び方
請求書処理業務をシステムの導入によって自動化する場合は、以下の視点でツールを選ぶと自社に最適なものを選定できます。
必要とする機能があるか
自動化する目的を明確にすることで、自社に必要な機能を見極めやすくなります。請求書には発行者名や支払期限、請求金額、税額などの情報記載が必要です。業種によっては源泉徴収税や軽減税率への対応が必要な場合もあります。
データの詳細な記録やマスター情報との連携機能があるシステムを選定することで、仕訳作業の効率化や入力ミスの防止が期待できます。
たとえば、請求書発行システムは作成・送付・保管・入金管理などを一元化できるツールですが、作成から送付のみを効率化したいのであれば、多くの機能を搭載していなくてもよいでしょう。
そのため、現在の業務課題や状況、将来的なニーズまでを分析して、どこまでを自動化するのかを明確にし、無駄なく運用できるシステムを選ぶことが重要です。
また、業務負担を減らすのがメインなのか、人的ミスを減らすことに注力したいのか、導入目的もはっきりさせておくようにしましょう。
導入形態
ツール導入を行う際は、導入形態にも気を配りましょう。一般的なツールは、オンプレミス型・クラウド型・インストール型の3つです。
オンプレミス型は、自社サーバーでの管理が必要で、運用には知識のある人材が欠かせません。一方で既存システムとの親和性を高めるカスタマイズが可能なため、大企業や長期的に使用する企業に向いています。
クラウド型は、オンラインでサービスを利用するため、社外での運用が可能です。少人数〜中規模の企業に適しているでしょう。
インストール型は、専用のソフトウェアを購入し、パソコンに導入する形態で、外部と接続せずに管理したい場合や、コストを抑えたい企業に向いています。ただし、法改正やバージョンアップについては、最新バージョンを再度購入する必要があります。
導入形態により、業務環境・効果は大きく変わるため、比較しながら慎重に検討しましょう。
導入費用
クラウド型システムの場合、月額課金制が主流で、利用者が増えるほどコストが高くなる可能性があります。そのため、自社の取引件数や業務規模に適したプラン選びが重要です。
取引量が少ないのに大規模なシステムを導入するとコストが無駄になり、反対に取引先が多いのに小規模なツールを使うと業務効率が低下します。初期費用は抑えられるものの、長期的なランニングコストを考慮しなければ、結果的に割高になることもあります。
必要最小限のプランから始め、業務の拡大に応じてアップグレードするなど、無駄のない運用ができるようコスト面も考慮しましょう。
サポート体制
ツールの提供元のサポート体制も選定のポイントとして重要です。ツールを導入した初期は、問題やトラブルが発生しやすくなります。問い合わせた時に、素早い対応をしてくれるサポート体制が整っていると、業務の効率がさらに高まります。
スピーディで安心感のあるサポートが受けられるかどうかをしっかりと確認するようにしましょう。
請求書作成ツールの比較は以下で詳しく解説しています。ぜひご確認ください。
関連記事:請求書作成ツールの徹底比較【バクラクvs.他3タイプ】とおすすめポイントの紹介
関連記事:請求書管理システムの徹底比較【バクラクvs.他3タイプ】とおすすめポイントの紹介
請求書の処理業務を自動化するなら「バクラク請求書発行」「バクラク請求書受取」
請求書処理を自動化することは、経理担当者の業務負担を軽減できるだけでなく、リモートワークの推進や、企業全体の業務効率化につながります。
ただし、自動化するにあたってシステムを導入する場合には、自社の状況や将来性を見越して最適なシステムを見極めることが重要です。
バクラク請求書発行・受取なら、従来の業務を大きく変えずに、帳票作成や稟議・送付・保存をペーパーレスに移行し、一元化できます。また、請求書発行前後のワークフローもワンストップで行えるため、業務にかかる時間も大幅に短縮することが可能です。
受領業務であれば、書類の受取から仕訳入力、振込データの出力までをオンラインで完結でき、一連の業務効率化を図れます。
請求書処理システムの導入を検討中であれば、ぜひバクラク請求書発行・受取をご利用ください。