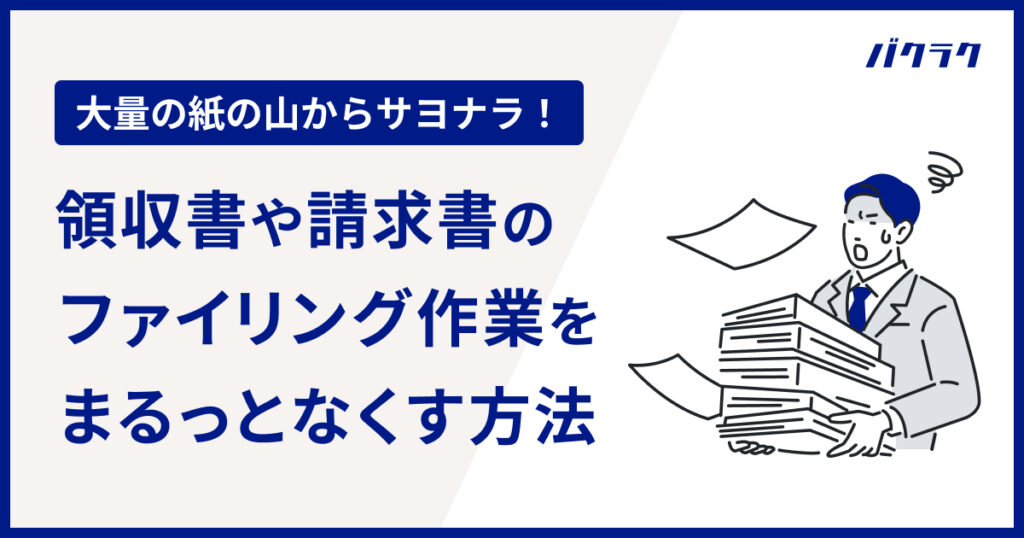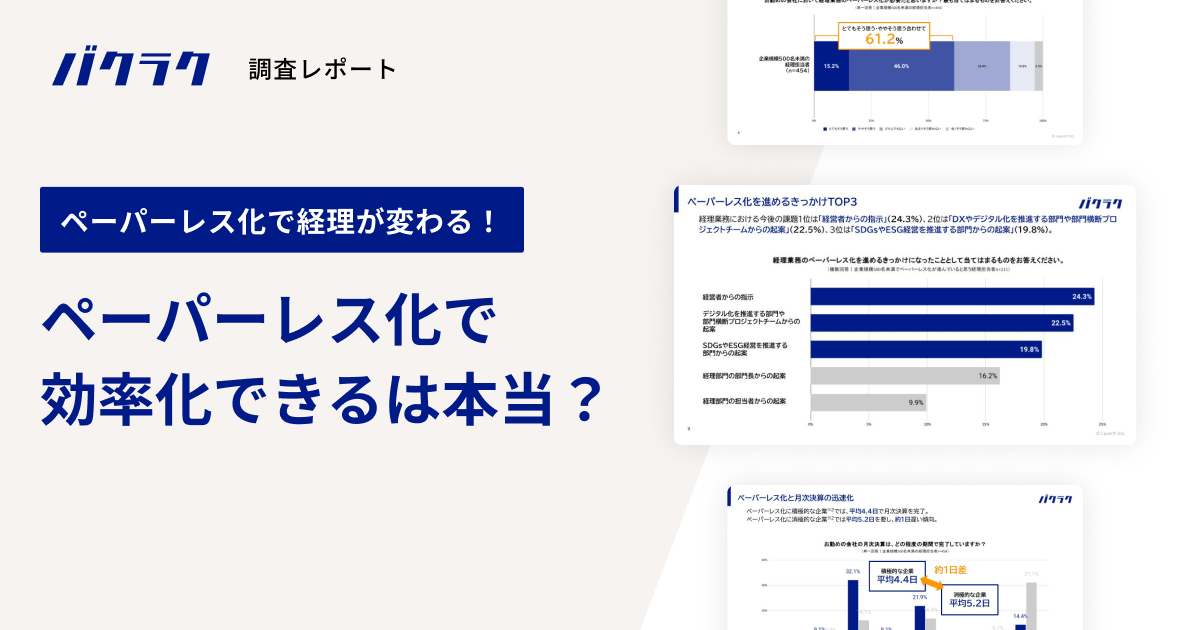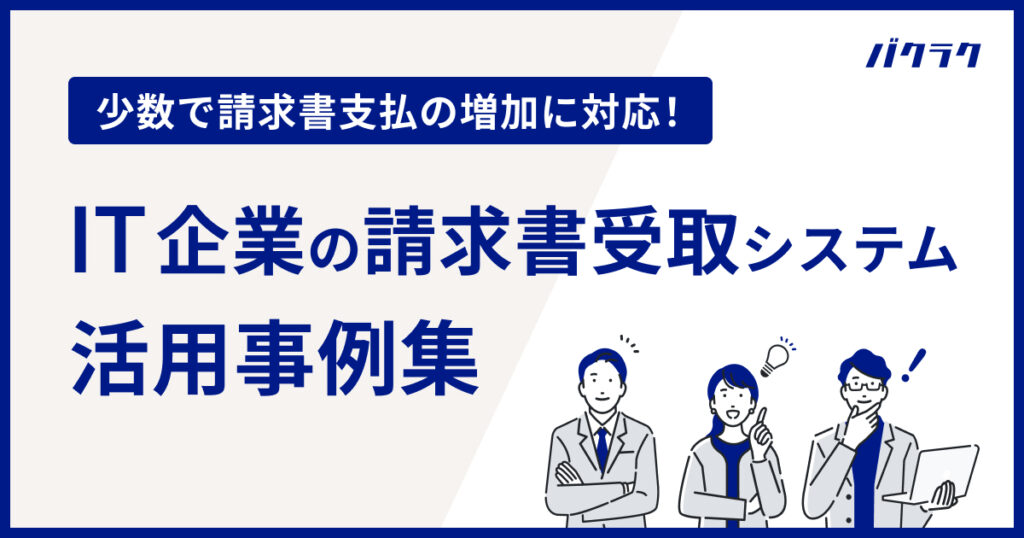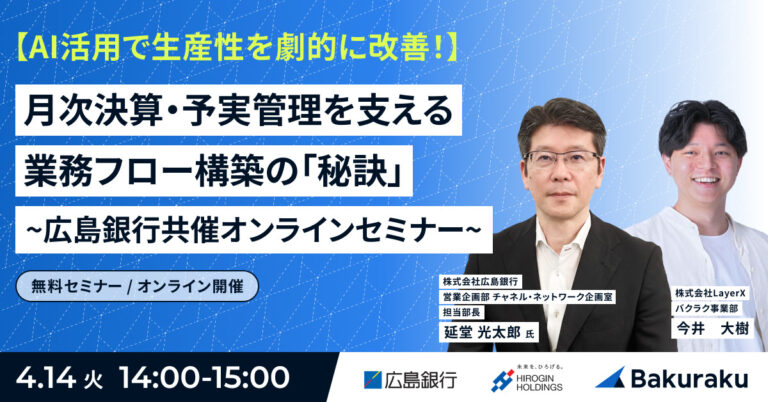
請求書の保管期間は?法人・個人事業主ごとの年数やインボイスの影響を解説
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 請求書は、個人事業主で5年間、法人で7年間保管しなくてはならない
- 適格請求書発行事業者の場合、適格請求書の発行側は控えを、受領側は原本を保管する
- 請求書の保管方法は、紙での保管・マイクロフィルムでの保管・電子データでの保管の3つがある
請求書の保管期間は、個人事業主と法人で異なります。請求書の保管期間は法律で義務付けられているため、自社での保管する期間や保管方法を把握・理解しておくことが大切です。
本記事では、個人事業主と法人それぞれの請求書保管期間、およびインボイス制度が与える影響について詳しく解説します。これらの知識は、効率的な経理業務と税務対策に役立つでしょう。
領収書や請求書のファイリング作業をまるっとなくす方法とは?
書類のファイリングや保管など、紙の書類管理に時間がかかっていませんか?アナログな管理方法だと、従業員からの申請や承認状況が分からないことによるコミュニケーションストレスも発生します。
こうした紙の書類の管理の手間をなくすときに押さえておきたいポイントをまとめた資料がダウンロードできます。自社のペーパーレス化状況がわかるチェックリスト付きです。ぜひご活用ください。
請求書の保管期間は?法人・個人事業主ごとの年数やインボイスの影響を解説
請求書は法律で保管が義務付けられている
請求書は証憑書類に該当するため、法律によって保存期間が決められています。基本的に個人事業主は5年間、法人では7年間請求書を保管しなければならず、保管期間中に破棄することはできません。
主に関係する法律は、以下の3つです。
法人税法
法人税法とは、納税義務者や課税所得等の範囲、税額の計算方法および申告、納付および還付の手続きについて定めた法律です。
法人の納税義務を適正に果たすために、必要な事項が定められています。
所得税法
所得税法とは、所得税の納税義務者や課税所得等の範囲、税額の計算方法および申告、納付や還付の手続きについて定めた法律です。
そのほか、源泉徴収に関する事項なども所得税法で定められており、納税義務を適正に果たすために必要な事項を定めています。
消費税法
消費税法とは、消費税の納税義務を適正に果たすために必要な事項を定めた法律です。
消費税の納税義務者や課税所得等の範囲、税額の計算方法・申告、納付・還付の手続きなどを規定しています。
【法人】請求書の保管期間
法人の請求書保管期間の数え方は、事業年度の確定申告の提出期限翌日から7年間です。たとえば6月末決算の企業(8月31日が確定申告期限日)の場合、令和5年7月1日から令和6年6月30日までに発生した請求書は、令和13年9月1日まで保管が必要です。
ただし欠損金が生じた場合の繰越年度は、平成27年・28年度の税制改正により保存期間が10年に変更されました。たとえば3月末決算の企業(5月31日が確定申告期限日)であれば、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに発生した欠損金に関する書類の保管期間は、令和17年6月1日までとなります。
【個人事業主】請求書の保管期間
個人事業主の請求書保管期間の数え方は、確定申告の提出期限翌日から5年間です。
たとえば、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに発生した請求書の保存期間は、令和12年4月1日までです。
ただし、年間の課税売上が1,000万円を超過する等の一定の条件を満たしている場合、個人事業主であっても消費税課税事業者にあたります。消費税課税事業者の請求書保管期間は、7年間となるため注意しましょう。
インボイス制度による請求書保管への影響
令和5年10月1日から適用されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、請求書の保管期間が変更されました。適格請求書発行事業者の場合、発行側・受領側それぞれ、事業年度終了日の翌日から2カ月経過した日から7年間保管しなければなりません。
適格請求書を発行する側は控えを、受領する側は原本を保管します。
控えの保管を怠ると、消費税の仕入税額控除を受けられないので注意しましょう。
適格請求書発行事業者でない場合でも、請求書の控えを発行していたら保管する必要があります。なお、控えを作成していなければ保管義務は生じません。
参考:国税庁「5 適格請求書等の写しの保存」
請求書の保管方法
受領した請求書や取引先に発行・送付した請求書の保管方法は、以下の3つがあります。
- 紙での保管
- マイクロフィルムでの保管
- 電子データでの保管
本項目では、上記3つの保管方法に関して、解説します。
紙での保管
紙媒体で受領した請求書や発行した請求書の控えは、自社の規定に基づき(月別や取引先別等)ファイリングして保管します。
マイクロフィルムでの保管
一定の要件を満たすことで、請求書をマイクロフィルムで保管することが認められています。マイクロフィルムは、一般の写真フィルムとは異なり画像の粒子が細かく、新聞紙等の極めて小さい文字であっても鮮明に記録することが可能です。
ただし、必ず規定通りのマイクロフィルムリーダー、マイクロフィルムリーダープリンタの設置が義務付けられています。
なお、マイクロフィルムとして保管ができる期間は、法定保存期間における最後の2年間のみです。
電子データでの保管
電子帳簿保存法に定められているスキャナ保存要件を満たせば、紙の請求書を電子データにして保管ができます。
ただし、元々受領した請求書が電子データである場合や、自社から取引先に発行する請求書が電子データである場合には、電子帳簿保存法の要件を満たした上で電子データのまま保管しなくてはなりません。
令和4年1月の電子帳簿保存法改正により、元々電子データである請求書を紙に印刷して保管することは認められなくなったので注意しましょう。
電子帳簿保存法の概要や請求書の保管方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
請求書を保管するときのポイント
請求書を効率的に保管するためには、いくつかポイントがあります。
まず請求書の整理や検索が容易になるよう、請求書番号を適切なルールに従って付与することが大切です。たとえば、年月日と連番を組み合わせた番号付けを行うことで、時系列の管理が可能になるでしょう。
次に、入金状況に基づいた分類も有効です。入金が確認できた請求書と未入金の請求書を分けて保管しましょう。受領した請求書についても支払期日順に整理すると、支払いの優先順位が明確になり、期日管理がスムーズに行えます。
最後に、デジタル化での管理もおすすめです。請求書をスキャンし、クラウドストレージに保存することで、物理的なスペースの節約や検索性の向上につながります。ただし、原本の保管も法的に必要な場合があるため、両方を併用するのが賢明です。
請求書管理と保管に最適な方法について詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
「バクラク請求書受取」で法令への対応もスムーズに
請求書は、個人事業主で5年間、法人で7年間保管しなくてはなりません。また、適格請求書発行事業者の場合、発行側は控えを、受領側は原本の保管が必要です。
近年はペーパーレス化が進み、請求書を電子データ化して保管することも増えていますが、適切な管理や保管を確立するには、システムの導入がおすすめです。バクラク請求書受取なら、請求書に関する最新の法令に自動で対応します。また、紙もPDFも正確に読み取れる機能など、請求書の保管に関わる業務負担を軽減できます。
自社のフローを今一度見直し、スムーズに請求書の発行および保管を行うために、ぜひバクラク請求書受取の導入をご検討ください。