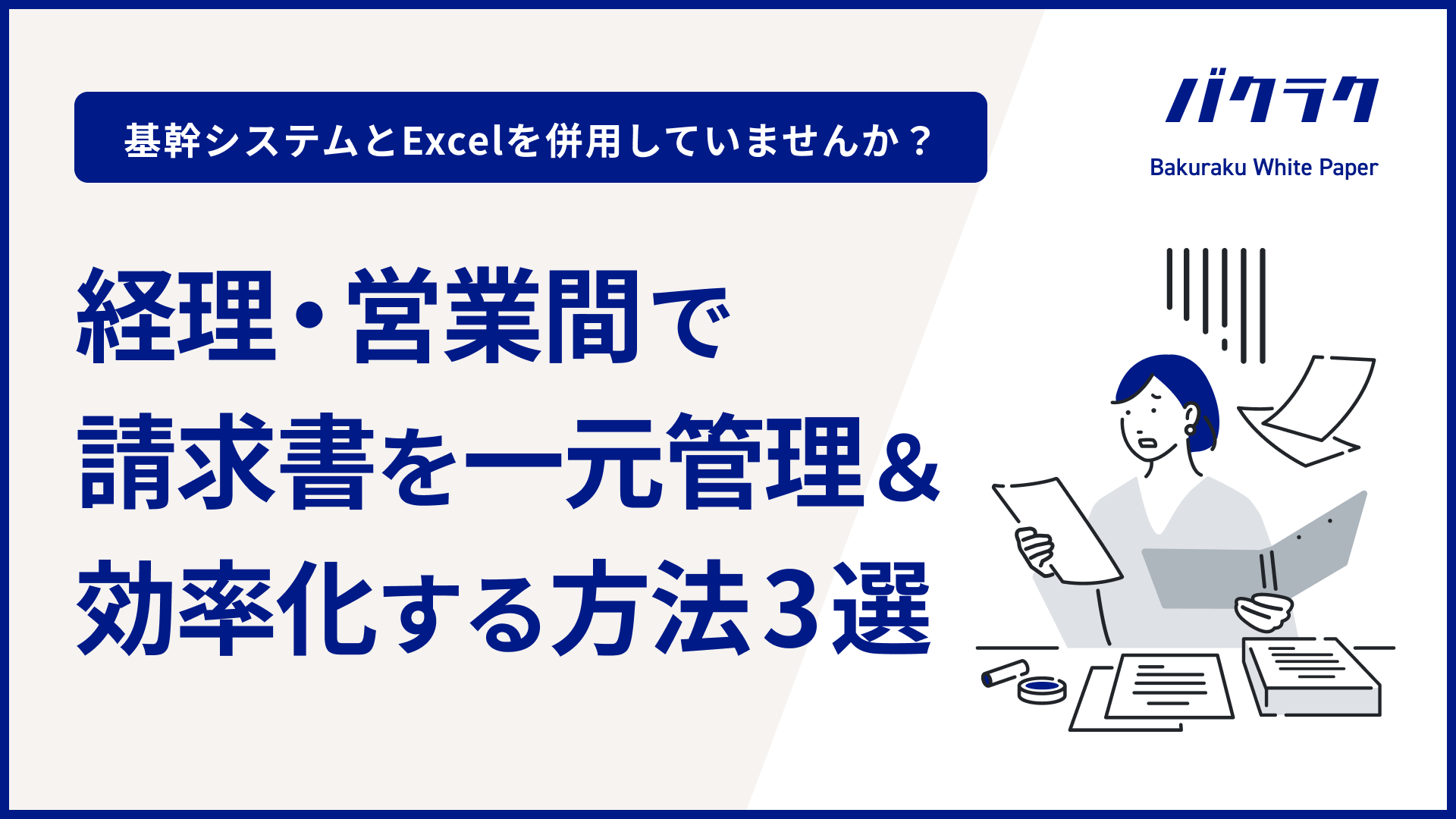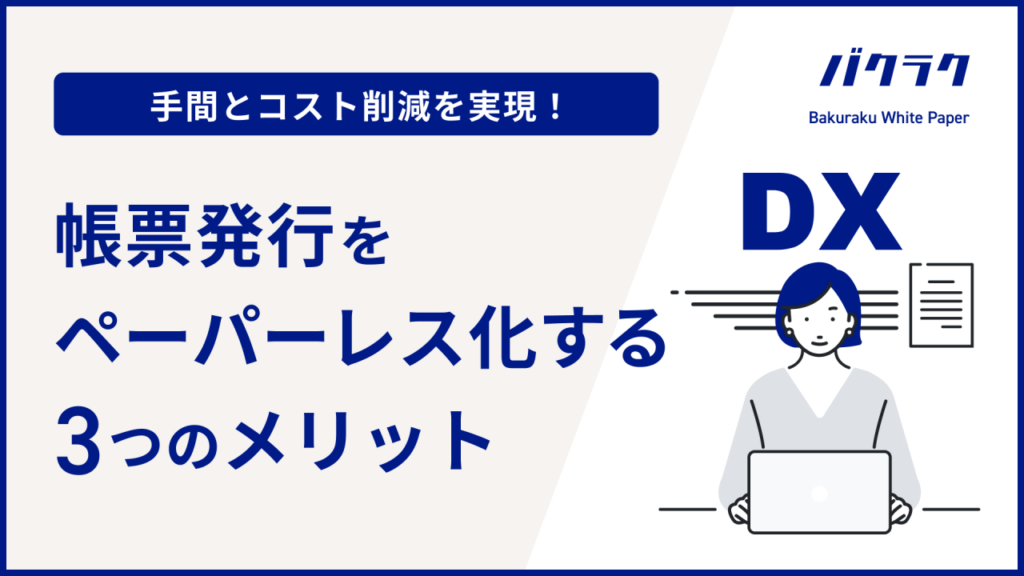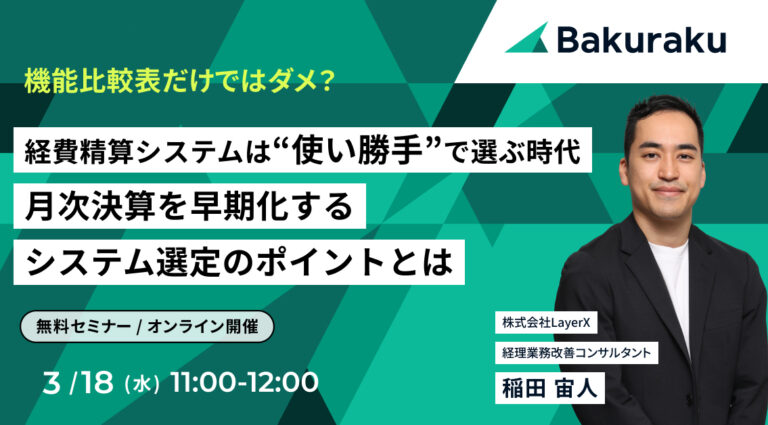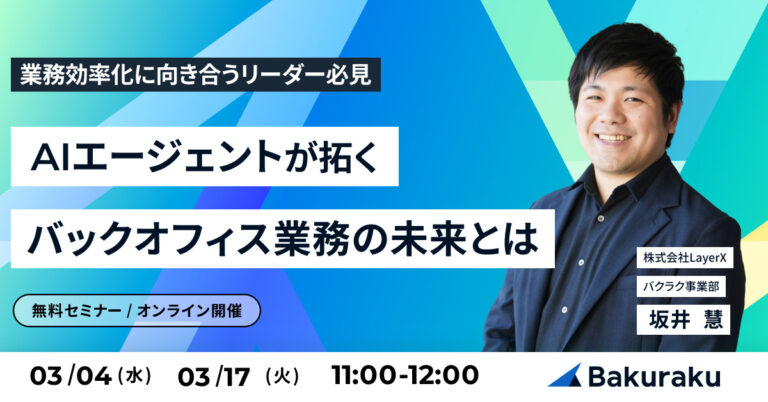
メールで受け取った請求情報・請求書の保存方法は?電子帳簿保存法に沿って解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-26
- この記事の3つのポイント
- 請求書の受領時、本文に取引情報が記載されていればメールも保存対象となる
- 電子帳簿保存法における電子取引の保存要件では「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められる
- 請求書をメールで受領した場合、電子帳簿保存法に基づいた適切な方法で保存する必要がある
メールで請求書を受領したとき、本文に取引情報が記載されていればメール自体も保存対象となります。保存の際には、電子帳簿保存法の定める要件を満たさなければなりません。
本記事では電子取引の保存要件や、適切な保存方法について解説します。請求書を送付する際の注意点についても紹介するので、メールでのやり取りの際にはぜひ参考にしてください。
メールで受け取った請求情報・請求書の保存方法は?電子帳簿保存法に沿って解説
メール本文に取引情報が記載されていても保存対象となる
電子帳簿保存法の改正により、メールの本文に取引情報が記載されている場合、そのメール自体も保存対象となります。
具体的には取引日付や取引先、金額などの情報がメール本文に含まれていれば、メールを電子データとして保存することが必要です。
メールをPDFに変換して保存することも認められており、クラウドサービスを利用してデータの改ざん防止やタイムスタンプ機能を活用することが推奨されています。さらに、必要なときに保存データをすぐに検索・確認できるよう、検索性の向上やマニュアルの整備も重要です。
売上高1,000万円を超える事業者には検索機能の要件も課されるため、自社に合った方法で管理体制を整えることが求められます。
参考:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」
電子帳簿保存法における電子取引の2つの保存要件
電子帳簿保存法では、電子取引で授受した請求書や領収書の保存時に「真実性の確保」と「可視性の確保」の保存要件が求められます。
真実性の確保とはデータの信頼性を守るための要件で、対応するためにはタイムスタンプの利用や、訂正・削除ができないシステムの使用、事務処理規程の運用が必要です。
可視性の確保では、保存されたデータを明瞭かつ整然と閲覧できる状態で保持することが求められ、取引日や金額などでの検索機能も必要になります。
これらの要件を守らなければ法に準拠していない保存となってしまうため、注意が必要です。電子帳簿保存法の詳しい概要や請求書の管理方法については、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。
メール本文に取引情報が記載されている場合の保存方法
メール本文に取引情報が記載されている場合、電子帳簿保存法に基づき、以下の2つの方法で保存することが推奨されます。
- メールシステムにメール自体を保存する
- メール本文をPDFやスクリーンショットとして保存する
1つ目は、メールシステムにメール自体を保存する方法です。自社サーバーやクラウドメールサービスの使用が一般的ですが、真実性や可視性の要件を満たすシステムであることに注意しなければなりません。
多くのメールシステムでは、訂正や削除履歴を残す機能が少ないため、タイムスタンプの付与や、事務処理規程の設定などで対応する必要があります。
2つ目は、メール本文をPDFやスクリーンショットとして保存する方法です。この方法では、取引年月日や取引先、取引金額が確認できるファイル名をつけると可視性が確保され、保存対象としての要件を満たします。
保存時には容量や管理方法も考慮し、保存データの効率的な管理と検索性を確保する仕組みを整えるとよいでしょう。
請求書がメールに添付されている場合の保存方法
メールに請求書が添付されている場合、電子帳簿保存法に基づき適切な保存方法を選択することが求められます。保存方法として代表的なものは、以下の4つです。
- メールシステムで添付ファイルごと保存
- 検索要件を満たしたファイル名で保存
- 事務処理規程を作成して保存
- 連番をつけ索引簿で管理
それぞれの方法について、概要と注意点を順番に見ていきましょう。
添付の請求書ファイルとともにメールを保存する
添付された請求書ファイルとともにメールをそのまま保存する方法は、シンプルに情報を保持できる点がメリットです。
自社サーバーやクラウドメールシステムに保存すれば、メール本文と添付ファイルを一元管理できます。
しかし、メールシステム上でメールを削除しないでおくだけでは適切な保存とはいえません。前述のとおり、電子帳簿保存法に基づき、保存システムは真実性と可視性の要件を満たしていることが前提です。
保存場所にシステムマニュアルや概要書を備えつけ、検索要件を満たすための機能も整えることも求められます。
検索要件を満たしたファイル名で請求書データを保存する
請求書データは、検索要件を満たしたファイル名で保存しても問題ありません。
ファイル名に「取引年月日」と「取引先」「取引金額」の3つの項目を含めれば、電子帳簿保存法の検索要件を満たします。たとえば「241001_取引先_10000」といったファイル名にすれば、一目で内容を把握でき、必要な検索を迅速に行えるでしょう。
ファイルをフォルダで整理する際には、取引先や月別にフォルダを分けるとさらに管理しやすくなります。
事務処理規程を定め、規程に沿った保存をする
「真実性の確保」の手段として、事務処理規程を定めることも有効です。具体的には、データの信頼性を保つための運用ルールをあらかじめ作成し、その規程に基づいて保存することを指します。
たとえば「保存対象のメールは取引日や金額を確認し、対応するフォルダへ必ず保存する」などの具体的な操作手順や、保存作業の担当者を明確に規定します。タイムスタンプや削除履歴をつけられない場合でも、規程に従った運用を証明して法的要件を満たすことが可能です。
国税庁Webサイトでは事務処理規程のサンプルも提供されているため、自社に合わせて活用するのもおすすめです。
参考:国税庁「参考資料(各種規程等のサンプル)」
索引簿で管理する
最後に挙げる保存方法は、索引簿での管理です。具体的な方法は、各ファイルに「0001」「0002」のような連番をつけて保存し、取引年月日や取引先、金額などの詳細情報を索引簿に記載していきます。
ファイルを検索しなくとも索引簿から必要な情報を確認できるため、整理しやすいことがメリットです。ただし取引量が増えると索引簿の更新作業が増えるので、記入漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすい点に注意しなければなりません。
国税庁からは索引簿のサンプルも公開されているので、参考にして運用ルールを定めるとよいでしょう。
参考:国税庁「参考資料(各種規程等のサンプル)」
請求書をメール送付する際の注意点
ここまでは請求書をメールで受け取った場合について述べましたが、本章では請求書をメールで送付する際の注意点について解説します。
改ざんできないPDF形式で作成する
送信後に内容を改ざんされないよう、請求書はPDF形式で作成しましょう。WordやExcelで作成した請求書は数値や項目の編集が容易であるため、データの信頼性が低くなってしまいます。
PDF形式で作成すれば改ざんリスクを大幅に減らし、取引先にも安心して送付できます。WordやExcelからPDFに変換する方法は簡単で、多くの文書作成ソフトにPDF変換機能が標準で備わっているため、手間もかかりません。
あらかじめファイル名は分かりやすくする
請求書ファイルを送付する際、受取先が内容をすぐに把握できるようわかりやすいファイル名をつけることも重要です。ファイル名が曖昧だと、ダウンロード後に先方がファイル名を変更する必要が生じるため、明確な名前をつけましょう。
メール件名にも「10月分請求書_添付」などと明記しておけば、受け取った担当者が重要な書類とすぐに認識でき、請求書の見落としを防ぎます。
送信履歴を確認する際にも件名がわかりやすければ、迅速に該当のメールを見つけることが可能です。
押印の代わりに電子印鑑を使用する
日本では以前から請求書に押印する商習慣がありましたが、法的に押印は必須ではありません。2020年6月に政府が押印の廃止を発表したこともあり、現在では多くの企業が押印を省略する動きにシフトしています。
ただし取引先によっては、トラブル防止や手続き上、押印された請求書を求めるケースもあるため、必要に応じて電子印鑑を利用する方法も検討してみるとよいでしょう。
電子印鑑は、物理的な押印とほぼ同様に扱われ、手軽に導入できます。取引先の信頼を得られるため、押印が必要な場合には電子印鑑を活用しつつ、効率的な業務運用を目指しましょう。
送付時の確認項目やパスワードを設定する
請求書をメールで送付する際は、誤送信による情報漏洩のリスクがあるため、慎重な確認が必要です。送信する際はメールアドレスや担当者が正しいか、アドレス帳の設定に誤りがないかを確認しましょう。
特に月末において、複数の取引先へ請求書を送信する場合、送信先を間違えると重大なトラブルにつながります。また予測変換機能に頼りすぎず、毎回宛先を確認することも重要です。
さらに万が一の誤送信に備えて、請求書ファイルにはパスワードの設定をするとよいでしょう。パスワード付きZIPファイル(PPAP)送信はウイルス感染の懸念があるため避け、PDFのパスワード設定や、セキュリティ強化されたファイル共有サービスの利用がおすすめです。
請求書をメールで送る場合の方法やルールについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
スキャナ保存した場合、紙の原本は破棄できる
スキャナ保存の要件を満たして請求書をデータ化した場合、紙の原本は破棄しても問題ありません。ただしスキャナ保存の要件を満たさずにデータ化し、原本を破棄してしまえば、法令違反となることもあるため注意しましょう。
たとえば適切な解像度やカラー階調で保存したとしても、閲覧用の機器が設置されていなかったり、システムに関する書類が備え付けられていなかったりした場合、法令遵守の観点で問題となる可能性も否定できません。
スキャナ保存の要件は詳細かつ厳格なため、データ化直後にすぐ原本を破棄することにはリスクがあるといえます。要件を完全に満たしているかを確認し、万が一に備えて一定期間は紙の原本も保管しておくことで、安全性を高められるでしょう。
請求書の破棄については、以下の記事で詳しく解説しています。
請求書の管理はバクラク請求書受取がおすすめ
メールで受け取った請求情報や請求書を保存する際は、電子帳簿保存法に基づいた管理が重要です。メールの本文や添付ファイルに取引情報が記載されている場合、保存対象として適切な形式で管理することが求められます。
受け取った請求書の処理を効率化できる「バクラク請求書受取」なら、メールからPDFを自動回収できる機能がついているため、業務効率化につながります。受取や仕訳、振込データの出力まですべてバクラク上で完結できるのも特徴です。
バクラク請求書受取の詳細は以下のページで解説しているため、毎月の請求書管理の手間を省きたい方はぜひご覧ください。