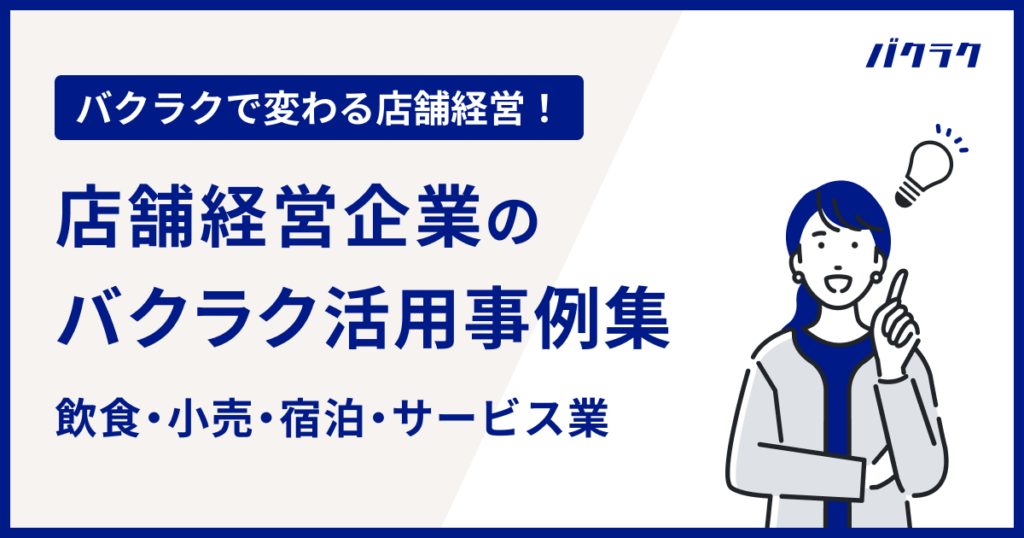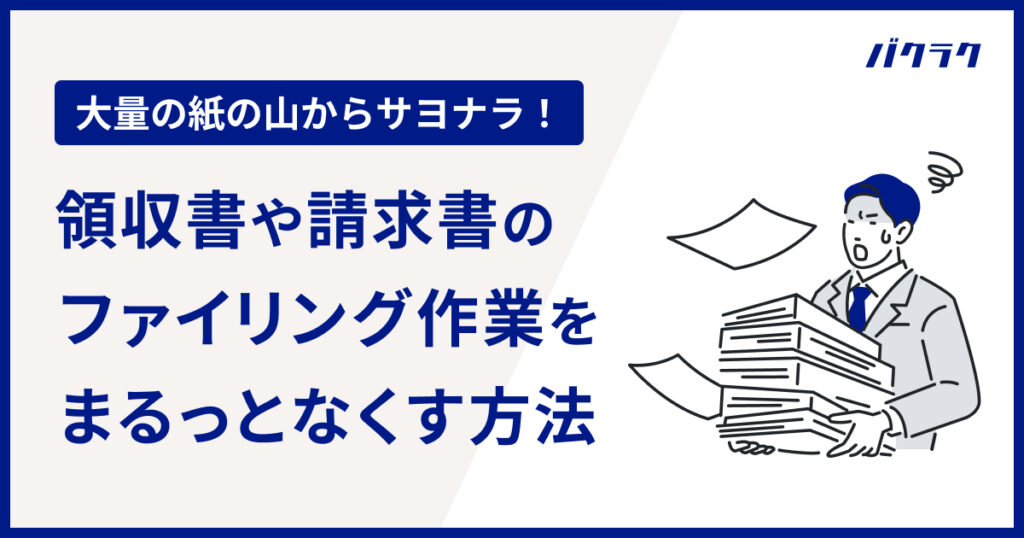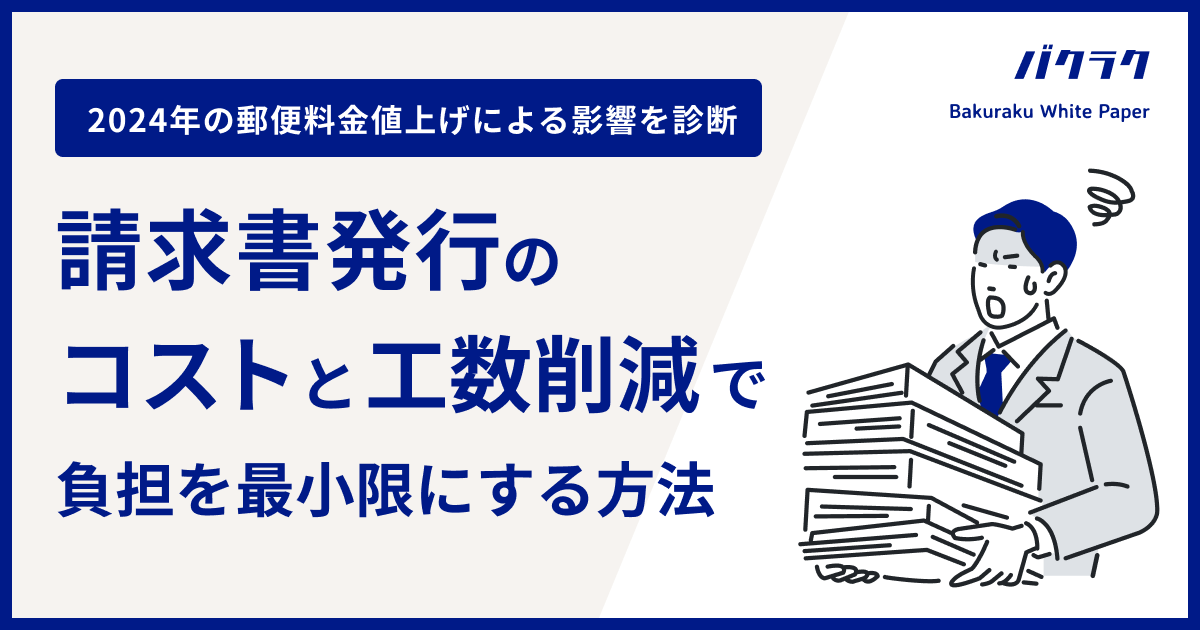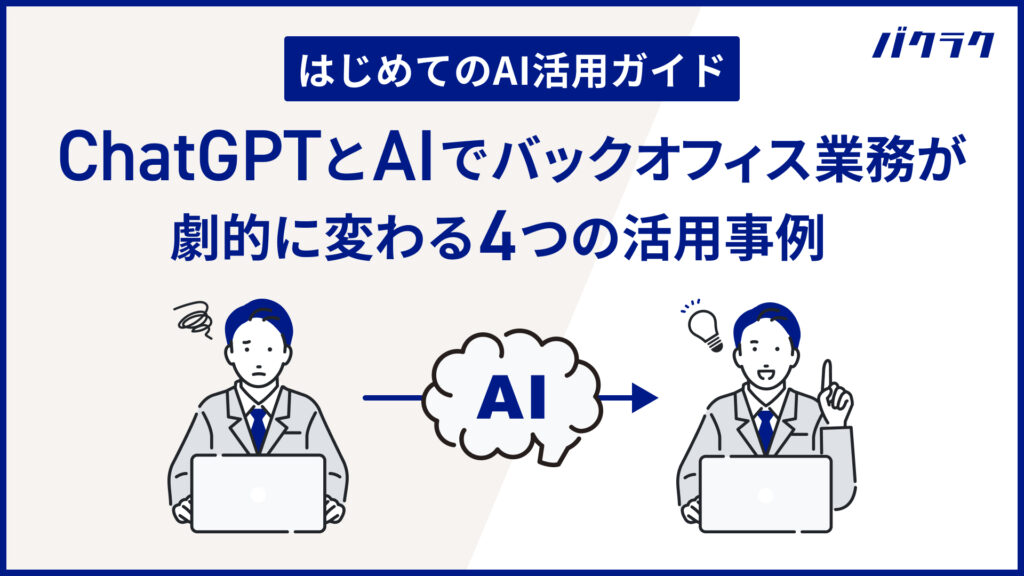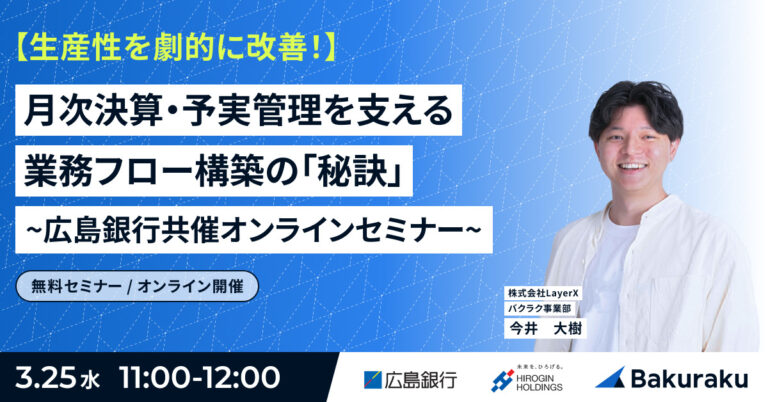インボイス制度による保険会社・保険代理店・保険外交員への影響を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 保険料は非課税だが、代理店手数料には消費税が課税される
- インボイス発行には適格請求書発行事業者への登録が必要であり、登録すると納付義務が発生する
- 免税事業者の保険外交員は、代理店が仕入税額控除を受けられないため契約終了となるリスクがある
2023年10月から開始されたインボイス制度は、各業界にさまざまな変化をもたらしています。保険業界は、保険料が非課税なので関係ないと考える方もいますが、保険会社・代理店・外交員の方の事業運営に影響を与える可能性があるため注意が必要です。
そこで本記事では、インボイス制度が保険業界に及ぼす具体的な影響について、詳しく解説します。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
インボイス制度による保険会社・保険代理店・保険外交員への影響を解説
インボイス制度による「保険会社」への影響
保険会社の主要な収益である保険料は非課税取引であるため、適格請求書(インボイス)の発行は基本的に不要です。インボイス制度が導入されても、多くの保険会社はインボイスの発行に対応していません。
しかし、保険会社のすべての取引が非課税とは限らず、一部の取引には消費税が発生する場合があります。そのため取引内容を、正確に把握しておくことが大切です。
また、保険会社が代理店に支払う「代理店手数料」には消費税が課されます。代理店が適格請求書発行事業者でない場合、保険会社は仕入税額控除を受けられず、コストが増加する可能性があります。
そのため今後、保険会社は代理店の適格請求書発行事業者登録状況を重視するようになるでしょう。状況によっては、適格請求書発行事業者に登録していない代理店との取引を見直すケースも考えられます。
インボイス制度の概要や仕入税額控除の仕組みについて詳しくは、以下の記事で解説しています。
関連記事:消費税の「仕入税額控除」とは? 計算方法・仕組み・要件をわかりやすく解説
インボイス制度による「保険代理店」への影響
保険代理店がインボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として登録が必要です。保険会社との取引を継続するためにも、登録を検討しましょう。
また、保険代理店は、多くの保険外交員と提携しています。保険外交員が免税事業者の場合、代理店は取引における仕入税額控除を適用できず、納税額が増加する可能性があります。
消費税免責事業者と課税事業者の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
インボイス制度による「保険外交員」への影響
前述したとおり、免税事業者と提携している取引先の保険代理店は、税負担が増す可能性があります。保険代理店によっては、免税事業者との契約を終了する可能性もあるでしょう。契約が終了することで、免税事業者である保険外交員の収入が減少するリスクも高まります。
リスクを避けるために、保険外交員も適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があるといえるでしょう。ただし、登録すると消費税の納付義務が発生するため、自身の経済状況や、取引先の方針を踏まえた慎重な判断を要します。
なお、会社員として保険外交員をしている場合は、給与として受け取る固定給は非課税ですが、歩合制で得た報酬部分は課税対象となります。そのため、給与体系に応じて、インボイス制度の影響を把握することも重要です。
インボイス制度のメリット・デメリットを以下の記事で解説しています。適格請求書発行事業者になるか検討されている場合は、以下の記事を参考にしてください。
適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要
インボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。登録手順は、以下のとおりです。
- 申請書の提出:適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する
- 審査と登録:税務署の審査を経て、問題がなければ登録される
- 登録番号の通知:適格請求書発行事業者としての登録番号が通知される
- 請求書の発行:登録番号を記載した適格請求書を発行できるようになる
インボイス制度導入後の一定期間、免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合に適用される経過措置があります。経過措置について、下表のとおりです。
| 経過措置 | 期間 | 内容 |
| 80%控除 | 2023年10月~2026年9月 | 仕入税額控除の80%を適用 |
| 50%控除 | 2026年10月~2029年9月 | 仕入税額控除の50%を適用 |
| 2割特例 | 2023年10月~2026年9月 | 課税売上税額の2割を納税すればよい特例 |
経過措置を活用することで、税負担を軽減しながらインボイス制度に対応することが可能です。
参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要― インボイス制度の理解のために ー」
適格請求書発行事業者への登録手続きや経過措置については、以下の記事で詳しく解説しました。
適格請求書発行事業者になる場合の注意点
インボイス制度に対応するために、適格請求書発行事業者として登録する保険代理店は多いでしょう。しかし、適格請求書発行事業者に登録する前に、デメリットも考慮する必要があります。本章では、注意点について解説します。
消費税の納付義務が発生する
適格請求書発行事業者として登録すると、消費税の納付義務が発生します。
これまで免税事業者として活動していた場合、税負担が大きくなるかもしれません。仕入税額控除を活用できる点はメリットですが、業種や取引形態によっては、納税額の増加が避けられないケースもあるでしょう。
事前に十分なシミュレーションをしておくことが重要です。
経理の負担が増える
インボイス制度の導入により、適格請求書の発行・受領・管理が必要となり、経理業務の負担が増加します。特に小規模事業者にとっては、経理体制の見直しや会計ソフトの導入などの対策が求められるでしょう。
さらに、適格請求書を発行するためには、書式の理解や記載ミスを防ぐ管理体制の強化が必要です。また、仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先から適格請求書を確実に受領し、適切に保管することが求められます。
結果として、経理業務の負担は増え、従来の業務フローの見直しが必要になる可能性があります。
「バクラク請求書受取」なら請求書の受取から仕訳までをスムーズに
インボイス制度の導入は、保険業界にも影響を与えています。保険料は非課税ですが、代理店手数料には消費税が課税されるため、適格請求書発行事業者への登録が必要です。
しかし、適格請求書発行事業者に登録すると消費税の納付義務が発生し、経理負担増加のリスクもあります。今後の取引に影響を与える可能性があるため、インボイス制度を理解し、適切に対応しましょう。
インボイス制度を導入した際、煩雑化を避けるためには、システムの導入がおすすめです。「バクラク請求書受取」は、請求書の受取から仕訳までを自動化し、経理業務を大幅に効率化できるサービスです。適格請求書の要件を満たす形式でデータ管理が可能なため、インボイス制度に対応しながら、スムーズな経理処理を実現できます。ぜひ導入をご検討ください。