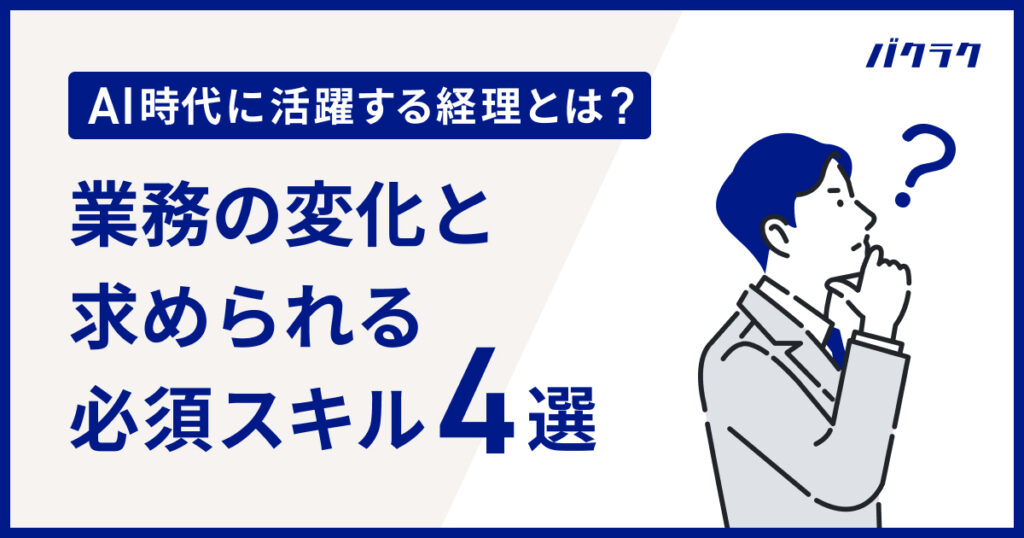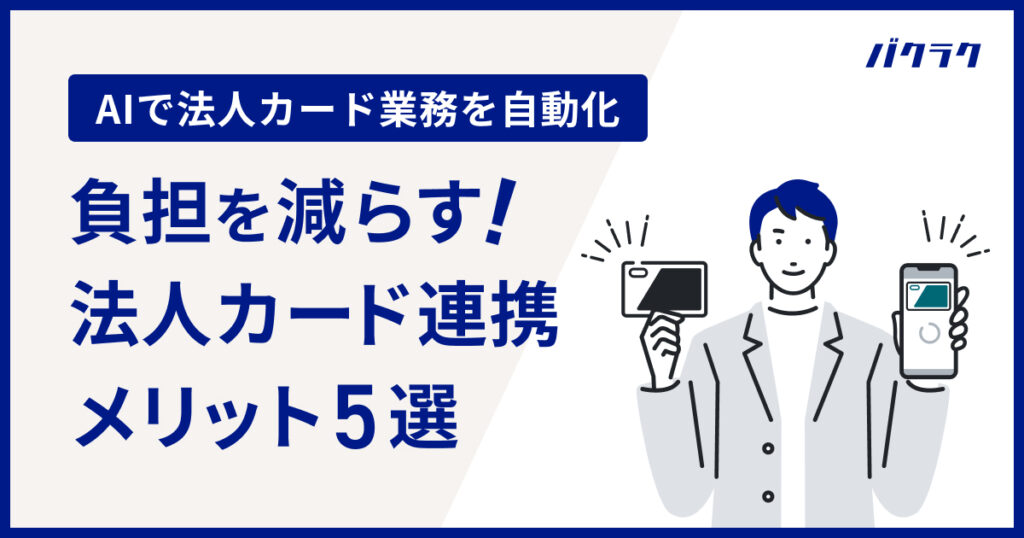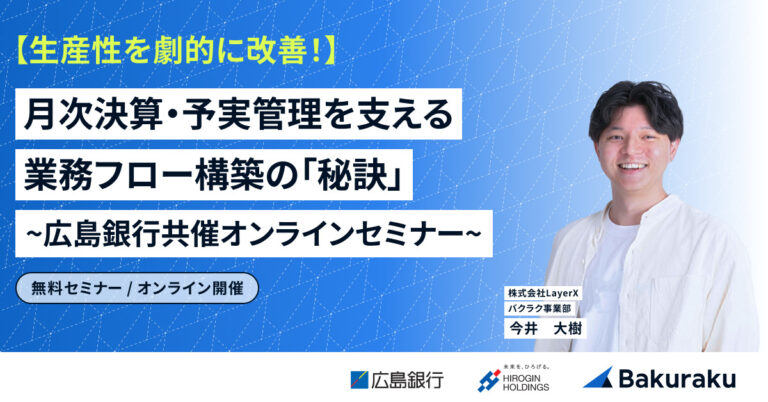軽減税率・インボイス制度に対応した請求書の書き方・項目は?適格請求書の注意点も解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 軽減税率制度及びインボイス制度の開始によって、適格請求書の作成や保存が必要になった
- 適格請求書は登録番号や税率ごとの取引合計・消費税額を区分して記載するなど必須項目が7つある
- 適格請求書を発行するには、事前の登録申請が必要である
2019年に導入された軽減税率制度、そして2023年から始まったインボイス制度によって、請求書の作成方法は大きく変わりました。
本記事では、軽減税率に対応したインボイス(適格請求書)の書き方や必要項目をわかりやすく解説します。
作成時の注意点についても解説していますので、ポイントを押さえて適切な請求書を作成しましょう。
軽減税率・インボイス制度に対応した請求書の書き方・項目は?適格請求書の注意点も解説
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
軽減税率制度とインボイス制度の導入による請求書の変更点
軽減税率制度は、一部の対象品目について8%で取引するように定めたもので、2019年10月に消費税が10%に引き上げられたことに伴って導入されました。以降、商品やサービスの売買取引において標準税率10%の品目と軽減税率8%の品目が混在するようになっている状態です。
請求書についても、軽減税率制度に合わせて「区分記載請求書保存方式」の採用に変わりました。区分記載請求書では、軽減税率対象の品目がわかるように明記したり、税率別の合計額(税込)を記載したりすることが求められます。
しかしその後、2023年10月にインボイス制度が開始して区分記載請求書は廃止となり、新たに「適格請求書」の形式へと変わりました。適格請求書では、区分記載請求書の項目に加え、発行者の登録番号や税率ごとの合計額(税抜もしくは税込)、税率ごとの消費税額などを記載しなくてはなりません。
従来の区分記載請求書との違いを理解したうえで、適格請求書の要件を満たした請求書を作成することが、現在は求められています。
区分記載請求書と適格請求書の相違点は、以下の記事で詳しく解説しています。
適格請求書で記載が必要な項目
適格請求書は、これまでの区分記載請求書よりも記載する項目が増えたため、記載漏れがないよう注意が必要です。
適格請求書に記載する項目は以下をご覧ください。
- 請求書発行事業者の氏名や名称
- 登録番号
- 取引のあった年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目がわかるように記載)
- 税率ごとの合計取引金額(税込もしくは税抜)と適用税率
- 税率ごとの消費税額
- 請求書受領者の氏名や名称
軽減税率の対象品目については、品目の横に「※」を記載して「※は軽減税率対象」などと別途明記しておけば問題ありません。
適格請求書では、区分記載請求書形式から新たに増えた「登録番号」「税率ごとの合計額と適用税率」「税率ごとの消費税額」の記載に注意しましょう。
なお、取引内容が標準税率の品目のみだった場合の記載方法については、以下の記事をご確認ください。
適格請求書に関する注意点
適格請求書を発行する際には気をつけるべきポイントもありますので、よく確認しておきましょう。
あらかじめ適格請求書発行事業者の登録が必要になる
適格請求書は従来の請求書とは異なり、すべての事業者が発行できるものではありません。
所轄税務署長への登録が認められた「適格請求書発行事業者」のみが発行できます。
ただし、この登録が可能なのは課税事業者に限られており、免税事業者では登録ができない点に注意が必要です。つまり免税事業者だと適格請求書を発行できず、従来の形式などその他の形式でしか請求書を作成できません。
もし免税事業者が適格請求書だと誤認されるような書類を作成した場合は、罰則を受ける可能性もあります。また適格請求書でないと、請求書の受領側が仕入税額控除を受けられなくなるため、場合によっては取引を継続するのが困難になるかもしれません。
したがって適格請求書を用いた取引を希望するのであれば、適格請求書発行事業者の登録は必須です。
消費税の端数処理方法が定められている
これまでの請求書方式では、消費税の端数処理について明確に定められていませんでした。
しかし適格請求書の導入からは、各税率の合計額につき1回のみ端数処理を実施するルールが制定されています。もし1品目ごとに端数処理を行っていた場合には誤りとなるため、気をつけましょう。
端数処理の方法については、従来どおり「切り上げ・切り捨て・四捨五入」などから都合の良い方法を選択してかまいません。
端数の詳しい処理方法については、以下の記事もお読みください。
関連記事:消費税に小数点以下の端数が発生した場合の処理方法は?税率の種類なども解説
発行後は一定期間の保存が必要になる
適格請求書は、受領した場合だけでなく、発行した際も控えを保存しておかなくてはなりません。
保存期間は、確定申告期限日の翌日から7年間です。交付した請求書のコピーを取るのが難しい場合は、記載項目内容がきちんと確認できる明細書などで代用してもかまいません。また電子帳簿保存法の導入により、電子データで請求書を交付した際には、原則電子データのままで保存することが義務付けられています。
このように、保存期間や取引方法に応じた保管方法が定められている点に注意しましょう。
適格請求書の発行なら「バクラク請求書発行」
軽減税率制度やインボイス制度の導入に伴って、請求書の作成方法もより細かく、そして複雑になりました。特に適格請求書を作成する際には、必要な事項をきちんと記載しないと正式な請求書と認められず、取引先に迷惑をかける可能性もあります。
ミスなく適格請求書取引をしたいのであれば、専用ツールを導入するのも一つの方法です。
バクラク請求書発行は、最新の法令に沿った請求書を自動で一括作成できるサービスです。電子送付・郵送代行・保管までワンストップで進められるため、ミスの抑制だけでなく業務効率化も期待できます。適格請求書の発行に課題を抱えているのであれば、ぜひバクラク請求書発行をご利用ください。