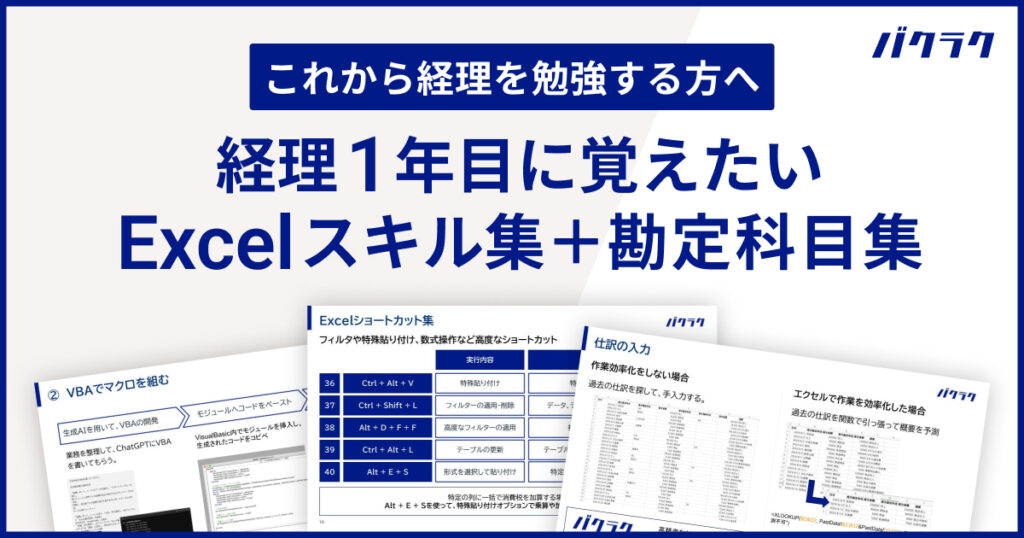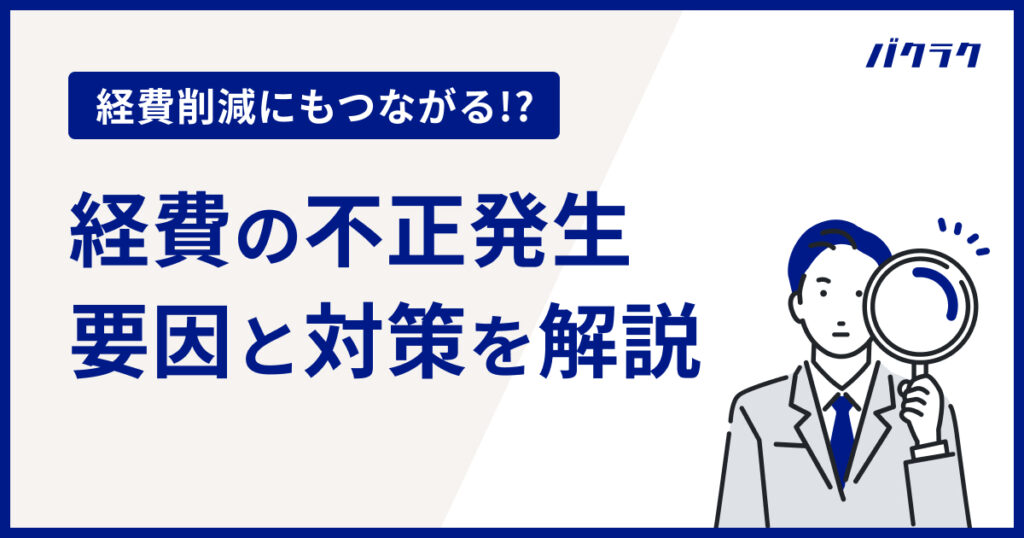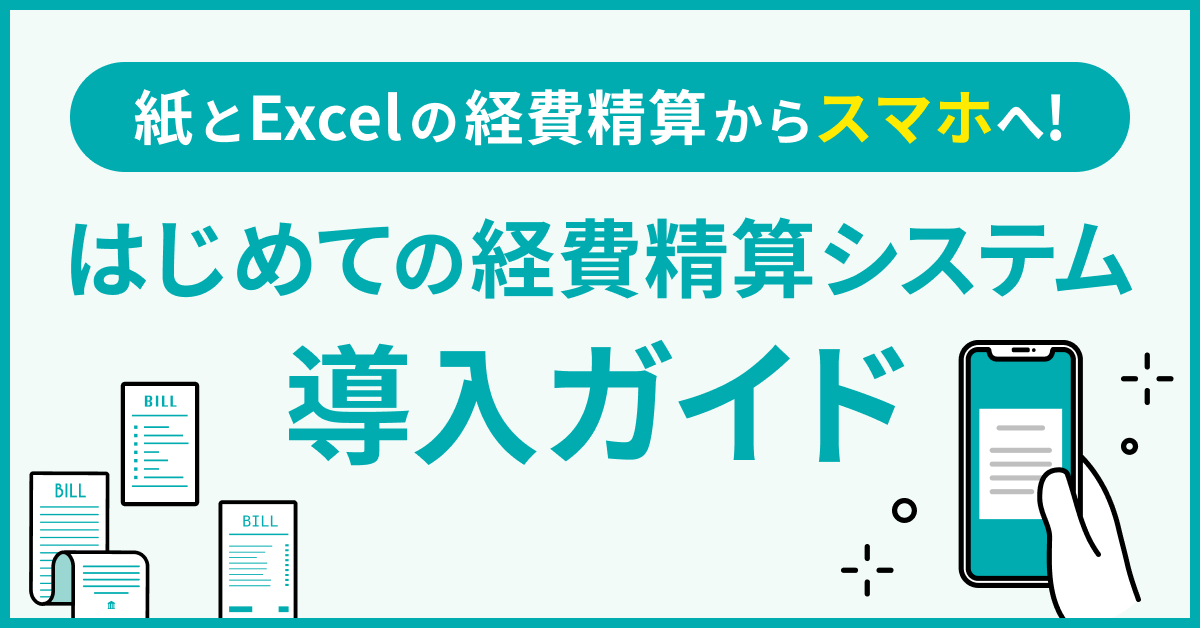所得証明書とは?種類や取得方法、発行・提出時の注意点を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-10-01
- この記事の3つのポイント
- 所得証明書とは、1年間の収入総額や控除額、税額などが記載された書類の総称を指す
- 所得証明書には、源泉徴収票や課税証明書、確定申告書、納税通知書など、さまざまな種類がある
- 所得証明書の発行には手数料や身分証明書が必要なため、自治体ごとの詳細を確認しておくべき
所得証明書は、1年間の所得額を証明する書類です。住宅ローンや奨学金の申請、入園・入学時の申し込みなど、さまざまな場面で提出を求められます。
所得証明書は総称であり、源泉徴収票や課税証明書など複数の種類があります。混同しやすい言葉もあるため、提出を求められた際に「どの書類が所得証明書に該当するのか」と迷う方も多いでしょう。
本記事では、所得証明書の種類や取得方法を解説します。発行・提出時の注意点にも触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
所得証明書とは?種類や取得方法、発行・提出時の注意点を解説
所得証明書とは
所得証明書とは、前年(1月1日〜12月31日)の所得額を証明する書類のことを指します。所得額は、収入総額から控除額などの必要経費を差し引いたもので、各市町村が住民税を算出する際の基準となる金額です。
所得証明書は各市町村が発行しており、収入を証明する公的な書類の一つです。なお、提出を求める業者によっては「収入証明書」と呼ばれることもありますが、所得証明書と同書類として認識して問題ありません。
所得証明書と課税証明書の違い
所得証明書と混同しやすい言葉に「課税証明書」があります。
所得証明書は所得額を証明する書類の総称であり、課税証明書は所得証明書のひとつです。課税証明書に記載されているのは、所得額、住民税額、扶養・所得控除額などです。
市町村によっては、所得証明書を発行せず、課税証明書のみに対応している場合もあります。多くの場合、所得証明書を求められても課税証明書で代用が可能です。課税証明書で代用したい場合は、事前に書類の提出先に確認してみてください。
所得証明書が必要なケース
所得証明書が必要なケースは以下のとおりです。
- 賃貸物件の契約
- ローンやキャッシングの申し込み
- 配偶者の扶養に入る手続き
- 保育園や学童保育の入園手続き
- 児童手当や奨学金の申請
賃貸物件を契約したり、住宅ローンを申し込んだりする場合には所得証明書が必要です。また、カードローンやキャッシングなど、融資を受ける際にも、審査の一環として所得証明書の提出を求められる場合があります。
そのほか、入園・入学の際にも所得証明書を提出しなければいけません。保育料は前年の収入によって変動し、奨学金には所得制限が定められているためです。
所得証明書がない場合は申請や手続きができないため、必要に応じて期限までに準備をしておくことが大切です。
不動産賃貸業において住宅の賃貸時にインボイスの影響があるかは、以下の記事で解説しています。
所得証明書の種類
所得証明書には複数の種類があります。ここでは、所得証明書に含まれる書類を紹介します。
源泉徴収票
源泉徴収票とは、前年に個人が得た収入と所得税額が記載された書類です。
会社員の場合は、企業が毎月給与から「所得税の概算」を徴収しています。12月の年末調整にて、支払った金額と本来支払うべき所得税額を照らし合わせて調整し、源泉徴収票を発行します。
源泉徴収票に記載されている内容は以下のとおりです。
- 給与額
- 所得税額
- 控除額(扶養・各種保険・配偶者控除)など
賃貸物件の契約や住宅ローンの申請を行う際には、源泉徴収票の提出を求められる場合が多いです。そのため、交付されたあとは自宅でしっかりと保管しておく必要があります。
源泉徴収票については、こちらの記事で詳しく解説しています。所得税額の計算方法や書類の見方などを紹介しているので、気になる方はぜひ読んでみてください。
関連記事:源泉徴収制度について|対象となる事業者や計算方法、税金の納付方法などを解説
給与の支払明細書
給与の支払明細書とは、一般的に「給与明細書」と呼ばれる書類です。企業は従業員に給与や賞与を支払う際に支払明細書の発行・交付が義務付けられており、以下のような内容が記載されています。
- 給与の支給額
- 社会保険料
- 税金などの控除額
- 勤怠情報(有給残日数など)
住宅ローンや奨学金などの申請において、給与の支払明細書の提出を求められるケースはあまり多くありません。ただし、源泉徴収票だけで直近の収入状況の把握が難しい場合、主に賃貸住宅の契約時に提出を求められる場合があります。
支払調書
支払調書とは、主に自営業で働く人に対して、発注元が発行する公的書類のひとつです。事業者が、前年(1月1日〜12月31日)のうちに誰にどのくらいの報酬を支払ったのかをまとめ、税務署に報告するために発行します。
支払調書は「法人が税務署に提出するための書類」であり、請負先への交付義務はありません。そのため、すべてのフリーランスや個人事業主が発注元から支払調書を受け取れるわけではないため、理解しておきましょう。
確定申告書
確定申告書とは、確定申告をする際に提出する書類です。自営業やフリーランス、一部の会社員は年末調整の対象外のため、毎年2月中旬〜3月中旬までに確定申告を行う必要があります。
確定申告書には、前年に得た収入額や控除額などが記載されており、控えを残しておくことで、収入証明書として利用できます。
e-Tax(電子申告)で確定申告をした場合は、書類が手元に残りません。電子申告後にe-Taxの「受信通知」から、受付日時と受付番号の記載された確定申告書の控えを取得し、保存しておきましょう。
なお、住宅ローンを申し込む際には「青色申告決算書」と「収支内訳書」を求められる場合があります。以下でそれぞれ解説します。
青色申告決算書
青色申告決算書とは、確定申告を「青色申告」で行う場合に作成・提出する書類です。日々の帳簿付けの結果を決算書の形式で記入する書類であり、以下で構成されています。
- 損益計算書
- 損益の内訳の記入書
- 貸借対照表
住宅ローンを申し込む際は、過去3年間の青色申告決算書が必要になるのが一般的です。確定申告を終えても、一定期間は破棄せず保管しておきましょう。
収支内訳書
収支内訳書とは、確定申告を「白色申告」で行う場合に作成・提出する書類です。1年間の所得を計算するために、以下の内訳をまとめたものを指します。
- 前年(1月1日~12月31日)の収入
- 売上原価
- 経費の内訳 など
収支内訳書には「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」の3つの種類があります。青色申告の対象でない自営業の方や、副業をしている方などは、破棄せず大切に保管しておきましょう。
納税通知書
納税通知書とは、住民税の明細が記載された書類です。各市町村が発行し、個人事業主の場合は毎年5月〜6月頃に郵送で自宅に届きます。
一方、会社員で毎月の給与から住民税が天引きされている場合は、会社を通して「住民税(市民税・県民税等)の特別徴収額の通知書」が渡されるのが一般的です。
賃貸物件への引っ越しや住宅ローンの申し込みを行う際、不動産会社によっては、この納税通知書の提出を求められる場合もあります。
なお該当者には、4月〜6月頃に固定資産税や都市計画税の納税通知書が送付されますが、この通知書は所得とは関係がないため、混同しないよう注意してください。
課税証明書
課税証明書とは、所得や課税額などを証明する書類です。以下のような内容が記載されています。
- 所得額
- 所得金額と住民税の課税額
- 扶養家族の人数
- 課税標準額
- 控除の内訳 など
課税証明書は、賃貸物件の契約や住宅ローンの申し込みのほか、入学・入園の手続きなど、提出を求められる場面が比較的多い書類です。
課税(所得)証明書を取得するには、申請する年の1月1日時点で居住している地域の役所で交付申請手続きを行う必要があります。地域によっては、役所窓口以外にオンライン申請やコンビニエンスストアでの発行などが可能です。
年金通知書
年金(振込)通知書とは、日本年金機構から年金受給者に送られる書類です。年金通知書には支給された年金の振込額が記載されており、毎年6月に郵送で自宅に届きます。
所得証明書の取得方法
ここでは、所得証明書(課税証明書)の取得方法を紹介します。
なお、課税証明書以外の所得証明書は、各市町村や事業者、年金事務所などに問合せてください。
市役所や区役所で取得する
所得証明書(課税証明書)は、住民票を置く自治体の市役所や区役所で取得できます。原則、本人が窓口に出向き、必要書類の記入と数百円の手数料を支払うことで、所得証明書の受け取りが可能です。
市役所や区役所へ直接出向かなくても、郵送での申請・受け取りができます。自治体のホームページから申請書を印刷し、手数料・返信用封筒・本人確認書類の写しを同封して、役所宛てに郵送します。
日数は市役所によって異なるものの、申請から発送までに1週間程度かかるのが一般的なため、必要な際は余裕をもって手配しましょう。
コンビニで取得する
多くの市町村では、所得証明書(課税証明書)をコンビニで取得できるサービスを導入しています。マイナンバーカードを持参し、コンビニのマルチコピー機から取得します。
自治体や使用するコピー機によって若干違いがあるものの、主な手順は以下のとおりです。
- マルチコピー機の「行政メニュー」を選択
- 「証明書交付サービス」を選択
- マイナンバーカードを所定の場所(ガラス部分)に設置
- 所得証明書を選択し、マイナンバーカードの暗証番号を入力
- 交付種別、記載事項項目、発行部数を選択
- 料金を支払う
- 印刷されたら完了
コンビニで所得証明書を取得する場合は、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない場合は、市役所の窓口申請や郵送申請を利用しましょう。
所得証明書を発行するときの注意点
所得証明書を発行する際には、いくつか押さえておくべき注意点があります。スムーズに発行手続きができるよう、以下を参考にしてみてください。
発行時には手数料と身分証明書が必要
所得証明書の申請および発行には、手数料と身分証明書が必要です。身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真がついているものを持参するのが好ましいです。
顔写真がついている身分証明書がない場合は、健康保険証など住所が記載された2種類の公的証明書が必要になる可能性が高いため、併せて持参しましょう。
手数料は自治体によって異なるものの、1通あたり300円前後かかるのが一般的です。特にオンライン・郵送で申請する場合は、料金が不足していると改めて手続きをし直す必要があります。
スムーズに申請・発行を受けられるよう、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
代理人が発行する際に、委任状が必要な場合がある
本人が窓口に足を運べない場合は、代理人による所得証明書の申請が可能です。ただし、所得証明書を代理人が発行する場合には、委任状が必要な可能性があるため、事前確認が欠かせません。
代理人が所得証明書を発行する際に必要なものは以下のとおりです。
- 委任状
- 本人の身分証明書のコピー
委任状は、各市町村のホームページからダウンロードし、必ず本人が記入しなければいけません。
ただし自治体によっては、同居している親族に限り委任状が不要な場合もあります。委任状の要否は自治体により異なるため、事前に確認しておきましょう。
書類には有効期限がある
所得証明書に該当する書類(課税証明書・源泉徴収票など)には、それぞれ有効期限があるため注意が必要です。たとえば、住宅ローンやキャッシング枠の設定を申請する際は「直近1年の所得証明書が必要」などと定められている場合があります。
有効期限の範囲外の書類を提出しても、所得を証明する書類として認められません。使用する場合は有効期限内のものかを確認し、提出しましょう。
発行までに時間がかかる場合がある
所得証明書をオンラインや郵送で申請する場合は、発行までに時間がかかる可能性があります。
自治体によって異なるものの、申請書類が役所に届いてから発送までに1週間程度かかるのが一般的です。所得証明書を郵送で申請する場合は、スケジュールに余裕をもって手配することが大切です。
窓口で申請する場合は、基本的に即日で発行されます。ただし、窓口発行も自治体によっては時間がかかる場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
所得証明書を提出する際の注意点
住宅ローンや奨学金などの申請で、所得証明書を提出する際の注意点は以下のとおりです。
- 必要な所得証明書を漏れなく用意する
- 原本ではなくコピーを提出する
- 書類を一定期間保管しておく
所得証明書の提出を求められる場合は、必要な書類を漏れなく用意することが重要です。指定された書類が必要枚数分あるか、有効期限は切れていないかなどを確認してください。
「原本を提出」といった指定がない場合は、コピーを提出するのをおすすめします。原本を手元に残しておけば、別の機会で所得証明書が必要になった際に、新たに申請・発行する手間を省けます。
また、提出後に原本や書類の控えなどを使用する機会がなくても、一定期間は保存しておくのが望ましいです。不備があって再提出を求められた場合でも、早急に対応できるためです。
まとめ
所得証明書は所得額を証明する書類の総称であり、源泉徴収票や課税証明書、確定申告書などが含まれます。住宅ローン・奨学金の申請やキャッシング枠の設定、保育園・学童保育の申し込みなどで必要となる重要な書類です。
所得証明書(課税証明書)は、本人もしくは代理人が窓口へ出向くか、郵送やオンラインで申請することで発行できます。所得証明書について正しく理解し、提出を求められても焦らず対応できるよう備えておきましょう。