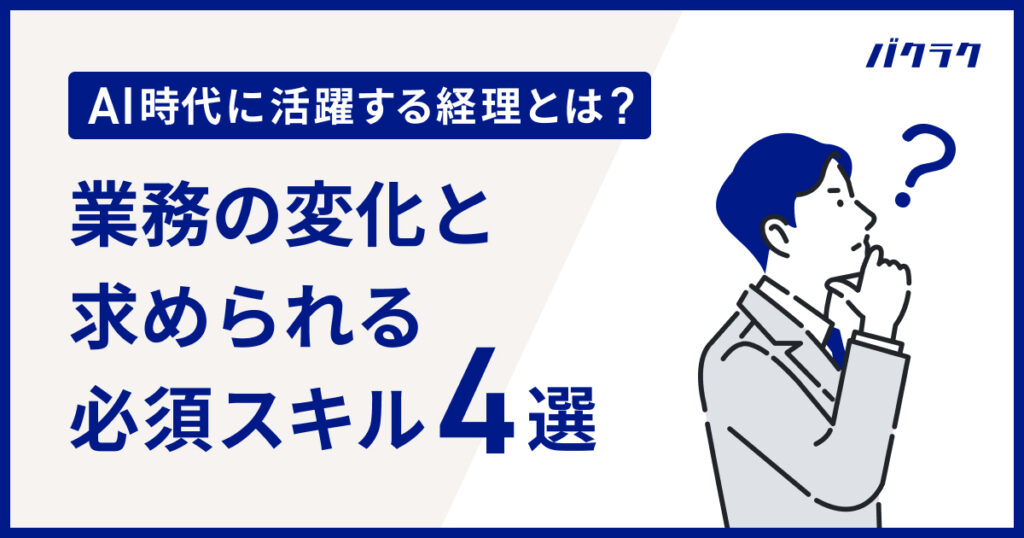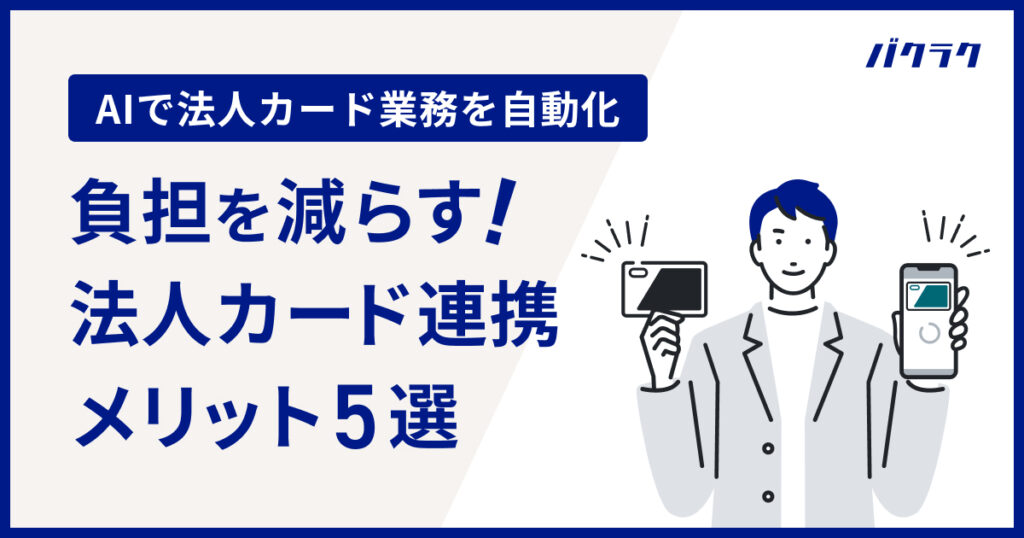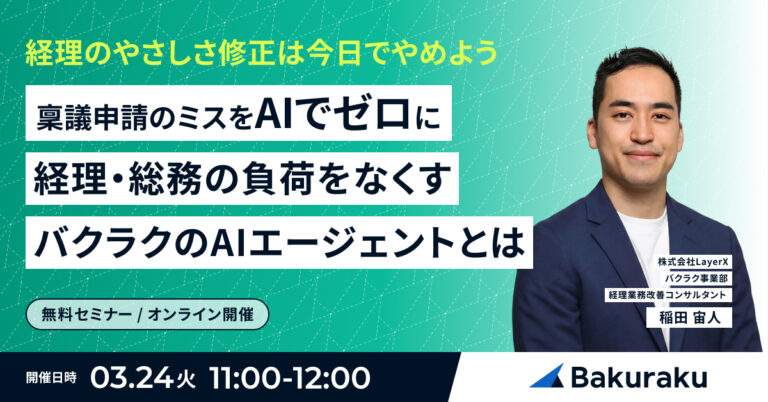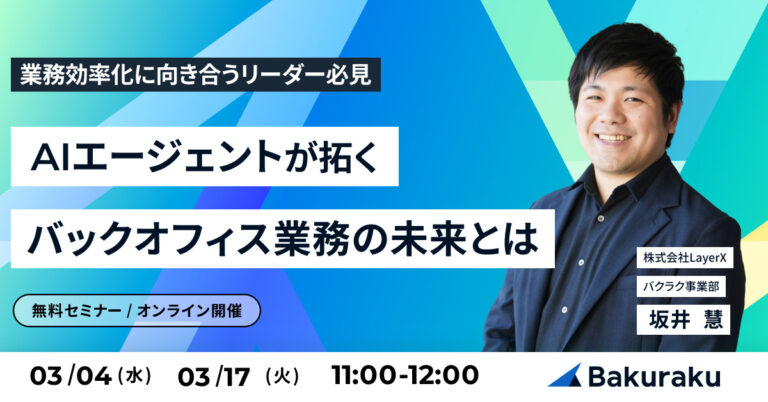
長形3号封筒に貼る切手代はいくら?速達や書留の金額も解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-09-12
- この記事の3つのポイント
- 長形3号封筒に貼る切手代は重さによって決まるため、同封する用紙の枚数により金額が異なる
- 郵便料金値上げにより、郵送のやり取りが多い企業ではコスト負担が増える場合がある
- 値上げには郵便区内特別郵便物を利用したり、メールで送ったりといった対策がある
長形3号封筒に貼る切手代は重さで決まります。
本記事では、封筒に入れるA4用紙の枚数に合わせた切手代の目安を解説します。長形3号封筒の郵送で使えるオプションの料金や利用方法についても紹介しているので、ぜひご覧ください。
長形3号封筒に貼る切手代はいくら?速達や書留の金額も解説
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
長形3号封筒に貼る切手代(郵便料金)は重さで決まる
切手代(郵便料金)は、封筒の重さによって決まります。入れる用紙の枚数や添付物によっては金額が変わるため、注意しましょう。
用紙やクリアファイルの重さの目安は、以下のとおりです。
種類 | 重さの目安 |
長形3号封筒 | 約5~6g |
A4用紙 | 約4g |
A3用紙 | 約8g |
B5用紙 | 約3g |
クリアファイル | 約20~25g |
請求書に使用する封筒の選び方や切手を経費にできるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:切手は経費にできる?勘定科目と仕訳の例・消費税の扱い方を解説
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
長形3号封筒の使用例
長形3号封筒のサイズは120×235mmで、三つ折りにしたA4用紙がちょうど収まる大きさです。使用例は以下のとおりです。
- 見積書
- 請求書
- 契約書など
長形3号封筒は文書をスマートに収納できるため、社内外を問わず多くの場面で活用されているのが特徴です。
【2024年10月~】郵便料金の改定により値上げ
2024年10月から郵便料金が改定され、長形3号封筒に貼る切手代も値上げされました。値上げの料金は、以下のとおりです。
種類 | 重量 | 旧料金(~9/30) | 新料金(10/1~) |
定形郵便物 | 25g以内 | 84円 | 110円 |
50g以内 | 94円 | 110円 | |
定形外郵便(規格内) | 50g以内 | 120円 | 140円 |
100g以内 | 140円 | 180円 | |
150g以内 | 210円 | 270円 | |
250g以内 | 250円 | 320円 | |
500g以内 | 390円 | 510円 | |
1kg以内 | 580円 | 750円 |
従来であれば84円で送れた25g以内の定形郵便は、110円へと大幅に引き上げられています。A4書類を数枚送るようなケースにおいても、従来より高い料金を想定しておくことが重要です。
参考:郵便局「2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。」
長形3号封筒で使用する切手の種類
長形3号封筒で使用する切手は、封入する用紙の枚数によって使い分けなければいけません。長形3号封筒の重さを6g、A4用紙を4gとしたときの重さ目安と必要な切手は、以下のとおりです。
A4用紙枚数 | 重さ目安 | 必要な切手 |
1枚 | 約10g | 110円切手 |
2枚 | 約14g | |
3枚 | 約18g | |
4枚 | 約22g | |
5枚 | 約26g | |
6~10枚 | 約30~46g | |
11~12枚 | 約50g超 | 140円切手 |
計算では10枚程度であれば110円で送れるため、何通にも分けて送るより、まとめて送るほうが送料を節約できます。送る際は重量を確認し、適切な切手を貼りましょう。
長形3号の郵送に使えるオプションの料金と利用方法
長形3号の郵送に使えるオプションには、以下のものがあります。
- 速達
- 書留
- 特定記録
- 配達日指定
それぞれのオプションの料金や利用方法を見ていきましょう。
速達
速達は、通常より早く郵便物を届けたいときに便利なサービスです。提出期限がある書類の送付など、急を要するシーンで重宝され、以下のように重さに応じた追加料金の切手を貼って利用します。
重量 | 追加料金 |
250gまで | 300円 |
1kgまで | 400円 |
4kgまで | 690円 |
縦長封筒であれば表面右上、横長なら右端に赤い線を引き、郵便ポストまたは窓口から差し出します。配達の日数は地域によって異なるため、日本郵便のサイトで事前に確認しておくと安心です。
参考:郵便局「速達」
書留
書留は送達の過程を記録して、万が一の紛失や事故の際に補償を受けられるオプションです。重要書類を送る際に適しています。
書留の料金は、以下のとおりです。
書留の種類 | 補償上限 | 料金 |
簡易書留 | 5万円 | 350円 |
一般書留 | 10万円 | 480円 超過は5万円ごとに23円 |
現金書留 | 1万円 | 480円 超過は5千円ごとに11円 |
書留は長形3号封筒でも問題なく利用できますが、ポスト投函ができません。利用時は「書留・特定記録郵便物等差出票」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。
参考:郵便局「書留」
簡易書留の出し方については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:「簡易書留の出し方を解説!一般書留・現金書留との違いや発送時の注意点も紹介」
特定記録
特定記録は、引受け時の記録を残すことができるサービスです。主にオークションの発送や納品書・請求書の郵送など、相手に届いたことを確認したい場合に向いています。
特定記録の料金は、一律210円です。
特定記録も書留と同様にポスト投函はできないため、郵便局の窓口からの差出が必要です。差出時には「書留・特定記録郵便物等差出票」の提出が求められます。配達の際は受取人のポストに投函され、対面受取は不要です。
参考:郵便局「特定記録」
配達日指定
配達日指定は、差出人が希望する日に郵便物を届けることができるサービスです。記念日や在宅日など、確実に受け取ってもらいたい日に合わせて送付できます。
配達日指定の料金は、以下のとおりです。
曜日 | 料金 |
平日指定 | 42円 |
土日・休日指定 | 270円 |
配達日指定は郵便局にある「配達日指定シール」に配達希望日を記入し、郵便物に貼り付けて、窓口に出します。配達日は、差出日の3日後から10日以内の日を指定可能です。
参考:郵便局「配達日指定」
追加で切手を貼る際の注意点
郵便物は機械で仕分けされるため、追加で切手を貼る際は、貼る位置や順番に注意しましょう。縦長の封筒では左上、横長の場合でも縦長に見立てたときの左上が基本の貼付位置です。
複数の切手を貼る場合は、金額の高い切手を上側(または右側)に配置するのがルールです。切手を貼る範囲は、縦長封筒であれば「縦7cm×横3.5cm」、横長封筒なら「縦3.5cm×横7cm」内に収める必要があります。
あまりにも多くの切手を貼ると寄せ集め感が出て印象が悪くなるため、2〜3枚程度にとどめるのがマナーです。
正確な切手を貼るなら郵便局へ持ち込む
封筒に正確な切手を貼りたい場合は、郵便局に持ち込むのが確実な方法です。郵便局ではその場で封筒の重さを計測して、正しい料金を提示してもらえます。
郵便局へ持ち込んで一度重さを計測しておけば、次回から同じ内容、同じ封筒での郵送時には、正しい切手をあらかじめ用意できることもメリットです。
定型・定形外以外に発送する方法
長形3号封筒で送れない厚さや重さのある郵便物は、定形・定形外以外の発送方法を検討しましょう。日本郵便では用途に応じたさまざまなサービスを提供しています。
クリックポスト
クリックポストは、自宅でラベルを印刷してポスト投函できる手軽な発送サービスです。対応サイズは、以下のとおりです。
- 長さ14~34cm
- 幅9~25cm
- 厚さ3cm以内
- 重さ1kg以内
クリックポストの料金は全国一律185円で、追跡サービスも付いています。主に書類や薄手の冊子、小物の発送に向いており、フリマアプリでの利用にも人気です。
クリックポストの利用時は、ラベルの印刷とクレジットカードによる事前決済が必要となるため注意しましょう。
参考:郵便局「クリックポスト」
ゆうメール
ゆうメールは書籍・CD・DVD・資料など、印刷物や学術資料の発送に適した配送サービスです。サイズを見ていきましょう。
- 長辺34cm以内
- 短辺25cm以内
- 厚さ3cm以内
- 重量1kg以内
また料金は重量ごとに異なります。
重量 | 料金 |
150gまで | 180円 |
250gまで | 215円 |
500gまで | 310円 |
1kgまで | 360円 |
追跡や補償はありませんが、コストを抑えて印刷物を送る際に有効なサービスです。
参考:郵便局「ゆうメール」
ゆうパケット
ゆうパケットは小型の荷物を安価に送れるサービスで、フリマサイトや通販業務などで広く使われています。サイズは以下のとおりです。
- 長辺34cm以内かつ3辺の合計が60cm以内
- 厚さ3cm以内
- 重量1kg以内。
送料は、厚さに応じて変わります。
厚さ | 料金 |
~1cm | 250円 |
~2cm | 310円 |
~3cm | 360円 |
ゆうパケットはポスト投函可能で追跡もでき、軽量小型の郵送に適しています。
参考:郵便局「ゆうパケット」
レターパック
レターパックは、信書も送れる追跡付きの封筒型サービスです。A4サイズ、重量4kg以内の郵便物に対応し、書籍や書類、カタログ、商品サンプルなどの発送に適しています。
料金は以下の2種類です。
種類 | 料金 |
レターパックライト(厚さ3cm以内) | 430円 |
レターパックプラス(対面受取・厚さ制限なし) | 600円 |
レターパックは全国一律料金で追跡サービスが付いている上、切手不要でそのまま投函できます。
参考:郵便局「レターパック」
レターパックの値上げ後の料金については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:レターパックの値上げ後の料金は?旧料金との差額の対応方法も解説
スマートレター
スマートレターは、専用封筒を使ってポストから手軽に発送できる全国一律料金のサービスで、対応サイズは以下のとおりです。
- A5(25cm×17cm)
- 厚さ2cm以内
- 重さ1kg以内
スマートレターはビジネス文書やCD、アクセサリーなどの発送に向いており、料金は210円です。切手の貼付は不要で、専用封筒に料金が含まれています。
スマートレターの厚紙製の封筒は中身を保護しやすく、書類や小物の簡易送付に最適ですが、現金や貴重品の発送はできないため注意しましょう。郵便局やオンラインで専用封筒を購入して利用します。
参考:郵便局「スマートレター」
スマートレターの料金や用途、利用方法などは以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
郵送料金の値上げに伴う対策方法
2024年10月の郵便料金値上げにより、日常的に郵便を使う個人や法人は、コスト増への対応が求められます。ここからは、郵送料金の値上げに伴う対策方法を2つ見ていきましょう。
郵便区内特別郵便物を利用する
一つ目の対策は、郵便区内特別郵便物を利用することです。郵便区内特別郵便物とは、同一配達区域内に送付する郵便物に適用できる特別割引制度です。
たとえば地元顧客や近隣企業にDMや請求書を送る場合、通常よりも安い料金で発送できます。配達エリアが限定されていることが条件ですが、コスト削減に有効です。
参考:郵便局「郵便区内特別郵便物」
メールで送る
郵便の代わりに電子メールで書類や連絡事項を送る方法も、コスト対策です。特に請求書や見積書、社内文書などはPDFで送れば郵送料も紙代も不要で、ペーパーレス化も進められます。
またメールでのやり取りは即時性があるため、業務効率の向上にもつながります。環境配慮を意識した企業姿勢のアピールにもつながり、取引先にも好印象を与えやすい点もメリットです。
切手代のコストを削減するなら「バクラク請求書発行」
見積書や請求書など、ビジネスで使う書類を送るのに便利な長形3号に貼る切手代は、重さで決まります。
郵便料金の値上げにより、切手代の負担が無視できないコストになってきた企業もあるのではないでしょうか。特に取引先ごとに請求書や領収書を郵送している企業では、印刷や封入、切手貼付、投函といった作業も工数や経費の面で大きな負担です。
このような郵送業務を効率化してコストを削減するなら、電子化による送付手段への切り替えが有効です。「バクラク請求書発行」であれば業務の流れを大きく変えず、請求書や領収書をPDFまたはダウンロードURLで送付できます。
帳票は取引先に合わせて形式を柔軟に作成でき、請求書や見積書、納品書、領収書などに対応しています。
送付後のステータス管理ができるため、未着や確認漏れのリスクも最小限に留めることが可能です。郵送コストを削減しながら、請求業務全体のスピードと正確性を向上させたい方は、ぜひ以下のページから詳細をご確認ください。