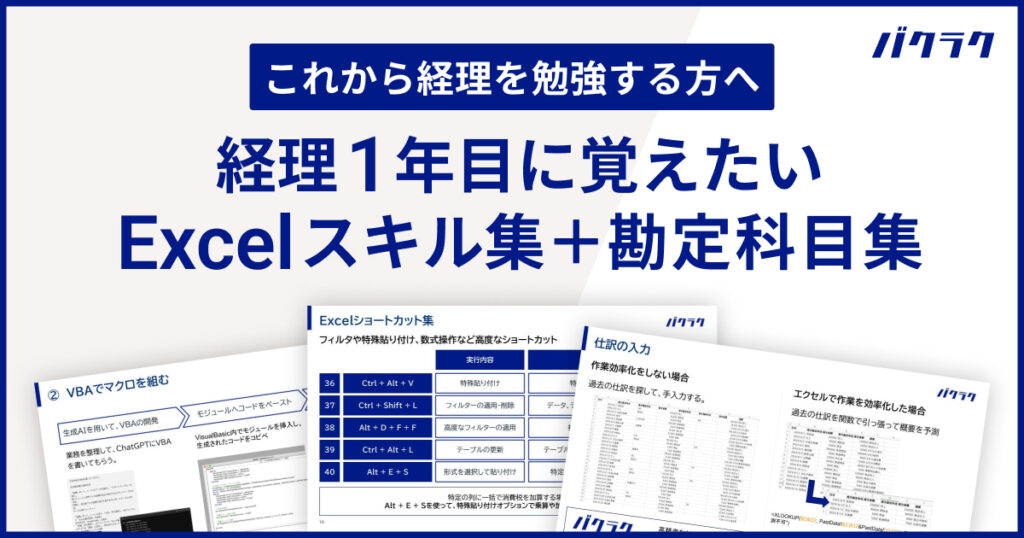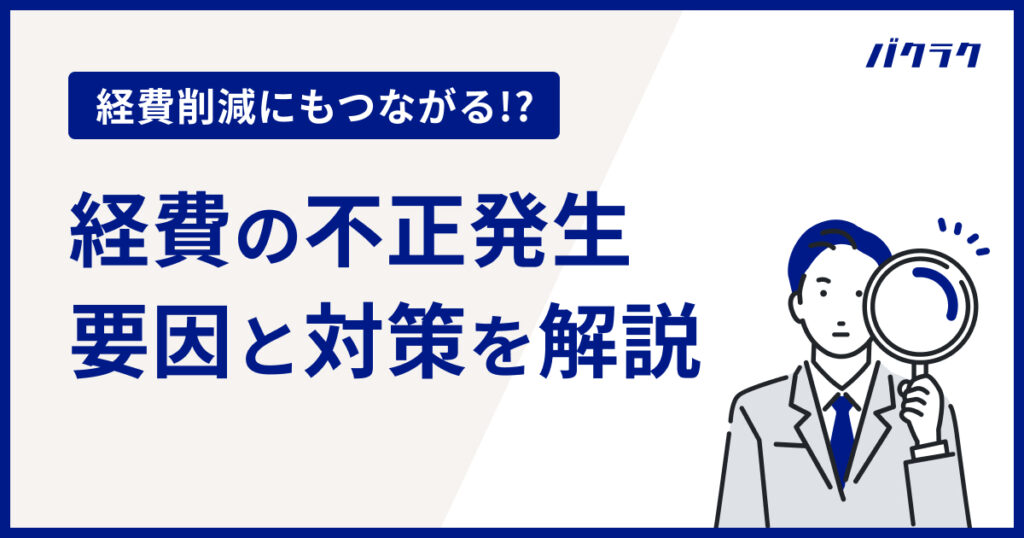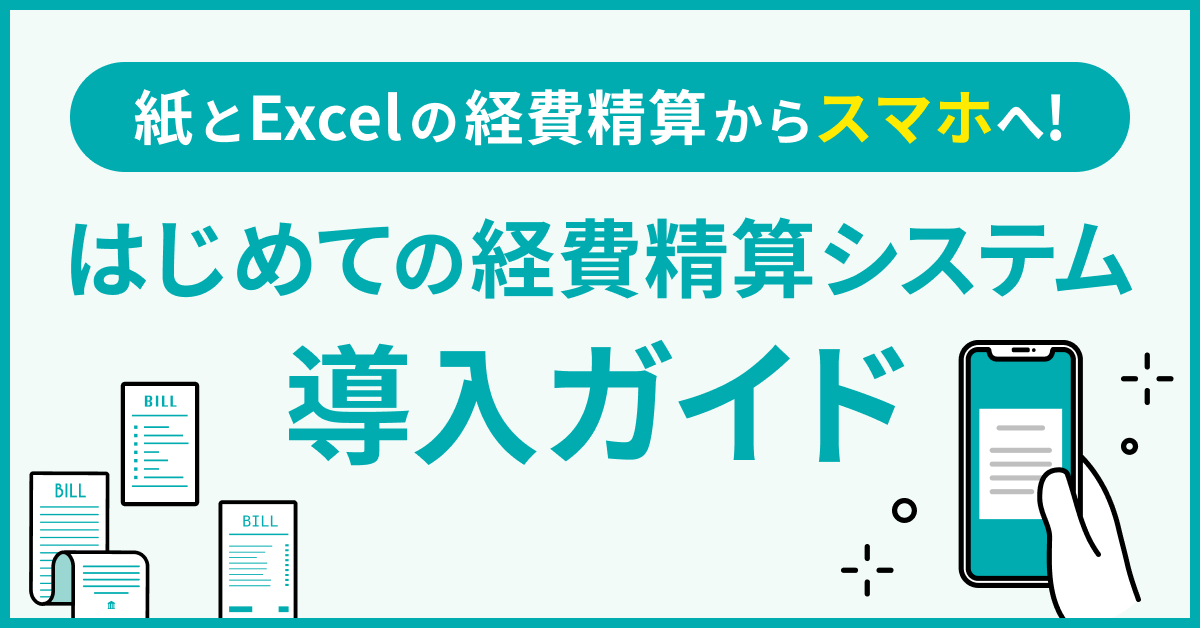勘定科目「出資金」とは?信金や生協の仕訳例や払い戻しなどのデメリットを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-01-17
- この記事の3つのポイント
- 固定資産は取得金額が10万円以上、使用期間が1年以上の資産で、減価償却が必要
- 固定資産には有形固定資産や無形固定資産、投資などがあり、正確な会計処理が求められる
- 固定資産税は、土地、家屋、償却資産が対象で、評価額に基づき税率をかけて算出される
固定資産は、企業の財務状況や税務処理に大きな影響を与える重要な項目です。しかし固定資産の対象や基準、特例について正確に理解していない方も多いのではないでしょうか。
固定資産とは長期にわたって使用する資産であり、取得金額や使用期間によっては特例が適用される場合もあります。そこで本記事では、固定資産の基準や特例、固定資産税について詳しく解説します。
固定資産の対象となるものは?基準や特例、固定資産税についても解説
固定資産になるかどうかの基準と特例
固定資産になるかどうかは、主に取得金額と使用期間によって判断されます。取得金額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上の資産は固定資産となり減価償却が必要です。
特例1)一括償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産で、一括で償却すること、または償却した資産を「一括償却資産」と呼びます。
一括償却資産は、取得価額を3年間で均等に費用計上することが可能です。
たとえば、一括償却資産を1年間で240万円分購入した場合、3年で割ることで1年間で80万円を損金として計上できます。
このように初年度に大きな費用負担を避けつつ、計画的に減価償却を行うことができます。一括償却資産は減価償却資産として扱われますが、残存価額はゼロとなる点に注意が必要です。
関連記事:一括償却資産とは?少額減価償却資産との違い、仕訳方法を解説
特例2)少額減価償却資産
中小企業者等が取得価額30万円未満の什器や備品を購入した場合、少額減価償却資産の特例を利用できます。
この特例を適用すると、取得年度に全額を損金として計上でき、減価償却を待たずに費用化が可能です。ただし特例を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 中小企業者等であること
- 対象期間内に取得し、事業の用に供すること
- 取得価額が30万円未満であること
- 1年間の合計取得額が300万円までであること
※中小企業の中でも「常時使用する従業員の数が500人を超える法人」「連結法人」「前3事業年度の平均所得が年15億円を超える法人」は対象外。
たとえば、中小企業者が取得価額20万円のパソコンを5台(合計100万円)購入した場合、特例を適用すると、その100万円全額を取得年度に損金算入できます。
しかし、同じパソコンを16台(合計320万円)購入した場合、300万円までは特例適用可能ですが、超過した20万円分は通常の減価償却が必要です。
固定資産の対象となるもの
固定資産は大きく分けて、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産の3種類があります。ここからは固定資産の種類について、詳しく解説します。
有形固定資産
有形固定資産とは形のある資産で、企業が長期的に使用するものを指します。具体的には、土地、建物、機械装置、車両運搬具、工具、器具、備品などです。 有形固定資産はさらに「減価償却資産」と「非減価償却資産」に分けられます。
減価償却資産は時間の経過や使用によって価値が減少していく資産であり、建物、機械設備、車両運搬具、工具、器具、備品などが該当します。決算時に減価償却を行って費用を計上します。
非減価償却資産は時間が経過しても価値が減少しない、または価値が上昇する資産です。代表的なものは土地や骨董品などで、これらは減価償却の対象とならず貸借対照表には取得原価で記載します。
有形固定資産を適切に管理するためには、購入時の費用だけでなく、その後の維持費や修繕費も含めて計画的に管理することが重要です。
また、減価償却を正確に行うことで、適切な財務報告と税務申告が可能となります。
無形固定資産
無形固定資産とは形のない資産で、企業が長期的に使用または保有するものを指します。具体的には、ソフトウェア、特許権、商標権、営業権などが該当します。
無形固定資産も、有形固定資産と同様に「減価償却資産」と「非減価償却資産」に分けられます。減価償却資産は、技術の進歩や時間の経過によって価値が減少する資産です。ソフトウェア、特許権、商標権などが該当し、耐用年数に基づいて減価償却を行います。
たとえば、国税庁が定める市場販売目的のソフトウェアの耐用年数は、複写して販売するための原本や研究開発用であれば3年、その他の利用目的の場合は5年で減価償却を行います。
非減価償却資産は、時間が経過しても価値が減少しない資産です。代表的なものは借地権などで、これらは減価償却の対象とはならず貸借対照表に取得原価で記載されます。
無形固定資産はその評価や償却方法が有形固定資産と異なるため、専門的な知識が必要です。適切な会計処理を行うことで、財務状況を正確に反映できます。
投資その他の資産
投資その他の資産は、有形固定資産や無形固定資産のいずれにも該当しない固定資産で、主に投資目的で長期的に保有する資産を指します。
具体的には、投資有価証券、長期貸付金、長期前払費用などが該当し、これらの資産は短期的な売買益を目的とするのではなく、長期的なリターンや事業関係の維持・強化を期待して保有されるのが一般的です。
たとえば、関係会社の株式を保有することで、経営の安定化や事業シナジーを図ることができます。また長期前払費用は、1年以上にわたって効果が期待できる支出(長期の保険料やリース料など)を計上します。
評価損益の計上や減損処理が必要になる場合もあり、適切な財務管理と会計処理が必要です。これらの資産を適切に管理することで、企業の財務健全性や投資戦略の効果を正確に反映させることができます。
固定資産税の対象となるもの
固定資産税の対象となる資産は、土地、家屋、償却資産の3種類です。固定資産税は、市町村が課税する地方税であり、毎年1月1日時点の固定資産所有者に対して課税されます。
| 固定資産税の対象 | 内容 |
| 土地 | 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)を指し、評価額に基づいて固定資産税が計算される |
| 家屋 | 住居、店舗、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫、その他の建物を指し、評価額に基づいて税額が算出される |
| 償却資産 | 事業の用に供することができる有形固定産のうち、土地および家屋以外のものを指す |
ただし、以下の資産は償却資産から除外され、固定資産税の対象とはなりません。
| 項目 | 内容 |
| 無形減価償却資産 | 営業権(のれん)などの形のない資産は対象外 |
| 少額資産 |
|
| 特定の車両 |
|
| 特定の生物 |
※観賞用や興行用など事業に使用される生物は償却資産として課税 |
固定資産税は、固定資産評価額に税率(標準税率1.4%)を掛けて算出します。ただし特例措置や減免制度が適用される場合もあるため、詳細は自治体の税務担当窓口に確認するようにしましょう。
固定資産税の勘定科目や仕訳方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
固定資産に関わる経費の管理なら「バクラク経費精算」
固定資産の取得や維持管理に関連する費用は、適切に経費として計上することが重要です。
取得価額が10万円以下の資産は固定資産の対象とならず、全額を当期の費用として計上できます。
また、固定資産の購入に伴う運送費や設置費、修理費や保守費用なども経費として計上可能です。しかし、経費を手作業で管理するのは、煩雑でミスが発生しやすい作業になります。
そこでおすすめしたいのが、バクラク経費精算です。バクラク経費精算を利用すれば、経費の申請から承認、仕訳までを自動化でき、経理業務の効率化が図れます。固定資産に関連する経費も一元管理できるため、財務状況の把握や税務申告にも役立ちます。
経費の分類や仕訳処理が自動で行われるため、専門知識がなくても正確な経費管理が可能なだけでなく、固定資産に関する特有の経費処理もサポートしており税務調査への対応も安心です。
経費管理でお困りの方は、ぜひ一度バクラク経費精算を活用してみてください。