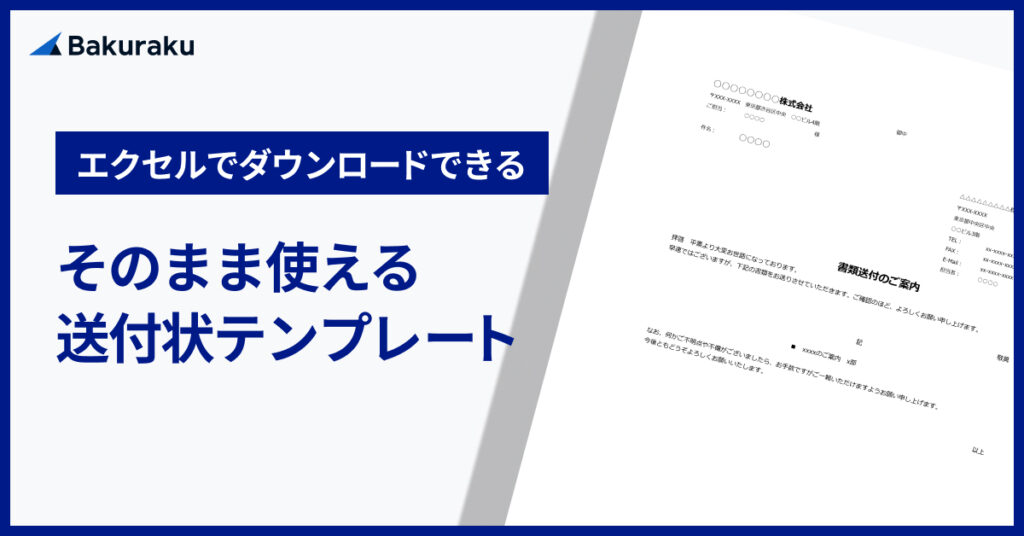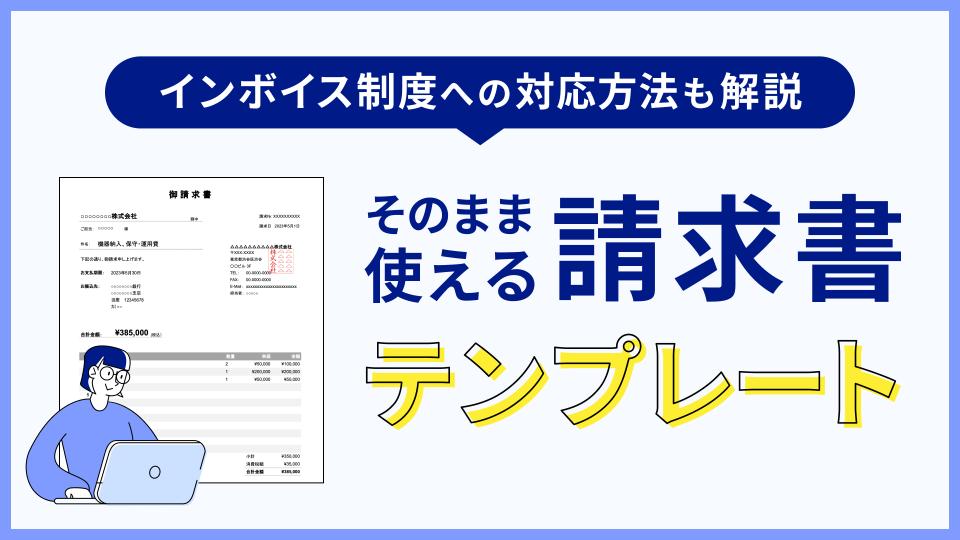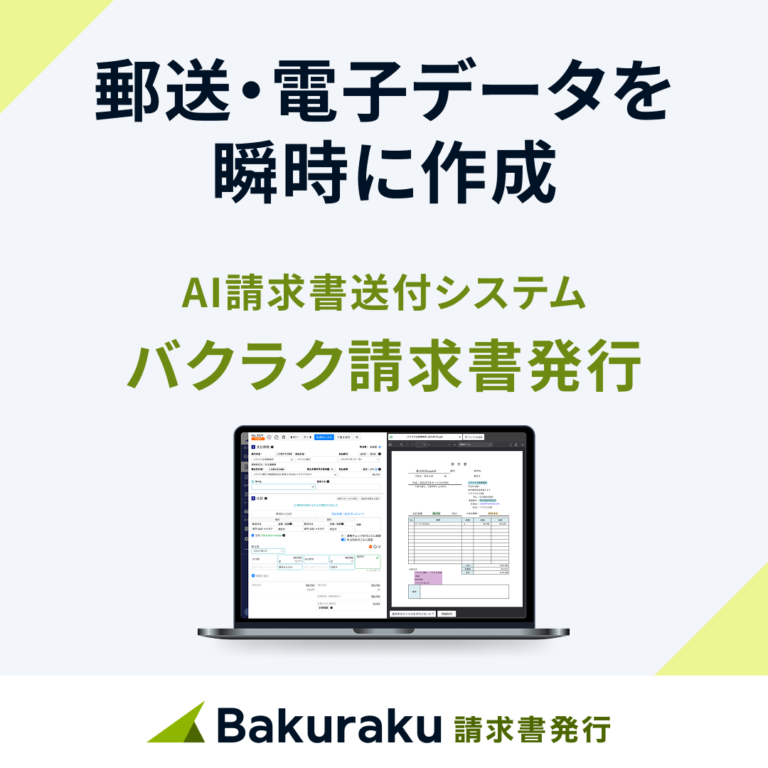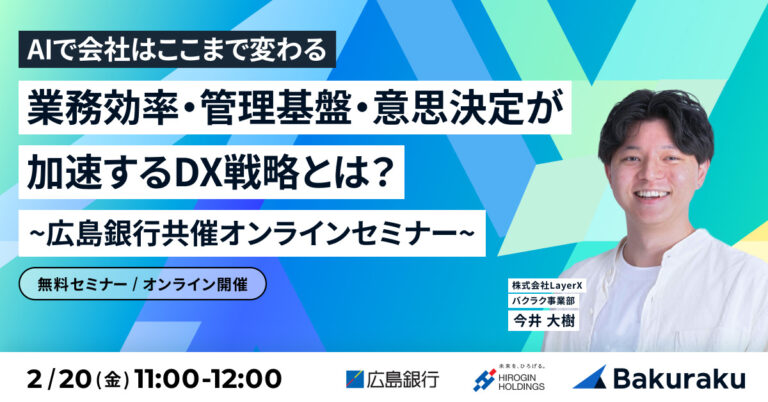請求書の不備や送付漏れはどう対処する?再発行時のお詫びメール例文や改善策も紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-10-21
- この記事の3つのポイント
- 請求書作成で起こるミスは日付や金額、内容などであるため、作成の際にはよく確認することが大切
- 不備のある請求書を送ってしまった場合は早急な謝罪と請求書の再発行をし、再発防止策を立てる
- 改善策として、ナンバリングやこまめな帳簿記入のほか、請求書発行システムの導入が挙げられる
請求書の不備は、取引先の信頼低下や支払い遅延につながる重大な問題です。
本記事では、請求書の不備で起こりえるミスや対処法、お詫びメールで送る内容や例文を解説します。改善策についても提示しているので、ぜひ参考にしてください。
請求書の不備や送付漏れはどう対処する?再発行時のお詫びメール例文や改善策も紹介
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
請求書の不備でよくあるミスと対処方法
請求書は取引先との金銭のやり取りに直結する重要な書類ですが、意外にもミスが発生しやすいものです。記載ミスや送付ミスが発生すると、支払い遅延や取引先の信頼低下につながる可能性があるため、正確な作成・送付が求められます。
この章では、請求書作成において間違いやすい項目を整理し、それぞれの対処方法を解説します。
請求書作成において間違いやすい項目
請求書の作成時に間違いやすい項目として、以下のものが挙げられます。
- 請求書・支払日などの日付
- 請求金額の誤り
- 取引内容や支払い条件の記載漏れ
- 振込手数料の所在
- 押印漏れ
請求書は数字や記載すべき項目が多いため、ミスが取引先とのトラブルにつながる可能性があります。請求書の作成に慣れてきたとしても都度確認し、ミスのないように努めましょう。
不備のある請求書を送ってしまった際の対処方法
請求書のミスは、継続的な取引の信用に影響を与えます。万が一請求書に不備があった場合は、以下のように迅速な対応を行いましょう。
- 電話やメールで迅速に謝罪し内容を伝える
- 請求書を再発行する
- 再発防止策を立てる
特に重要なのは、再発防止策の実施です。チェック体制を強化したりテンプレートを見直したりして、取引先との信頼関係を維持することが大切です。
請求書でミスした場合の対処法や再発予防策などは、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
請求漏れが発生したときの対処方法
請求漏れは、資金繰りや先方との関係性に影響を与える重大な問題です。請求漏れへの適切な対応について解説します。
自社の上長や経理部門へ対応の相談をする
請求漏れが発覚したら、直ちに上長に報告し経理部門と相談してください。お詫びの方法には電話、メール、直接訪問があり、状況や先方との関係性に応じて適切な方法を選択する必要があります。
また、お詫びを伝える担当者についても、案件の重要度に応じて適切な判断が求められます。
請求書送付の遅延がわかっている場合は早急に取引先へ連絡する
請求書の発行遅延が予想される場合、先方への早期連絡が不可欠です。遅延の可能性が判明した時点で速やかに報告し、先方に迷惑をかけないようにしましょう。
先方の締め日を過ぎてからの連絡は避け、誠実な対応を心がけることが重要です。
請求漏れが発生した理由をあらかじめ電話で伝える
請求漏れの際は、まず電話口で謝罪と状況説明を行い、その後お詫びのメールを送付する流れが一般的です。直接言葉で謝罪の意を伝えると、真摯な印象を与えられます。
電話では、請求漏れの事実と理由を明確かつ簡潔に説明してください。言い訳めいた表現は避け、責任を持って対応しましょう。
できるだけ早く請求書を送付する
先方への連絡後は、速やかに請求書を作成し送付してください。ただし、急ぐあまり記載ミスを起こさないよう、細心の注意を払いましょう。
なお、郵送の場合は、基本的に速達を利用し、できるだけ早く先方に請求書が届くようにしましょう。
請求漏れが発生した原因を究明・改善策を考える
取引先とのやり取りが落ち着いた後、社内で請求漏れの根本原因を分析します。特定した原因に基づき具体的な改善策を立案し、再発リスクの最小化に努めましょう。
個々の担当者レベルの対策に留まらず、必要に応じて請求書作成・送付の仕組み全体の見直しも検討すべきです。
請求漏れ発覚後に請求書を送付すべきタイミング
先方の締め日がまだ先であれば、速やかに送付すれば間に合うかもしれません。請求書を送付する適切なタイミングについて解説します。
請求書を送付する基本的なタイミングとは
請求書を送付する適切なタイミングは、請求方法によって異なります。都度請求の場合は、取引ごとに請求書を発行し送付します。
一方、継続的な取引がある場合は、売掛金の一括請求が一般的です。月単位で発生した取引分の売掛金を、先方の締め日までにまとめて請求しましょう。
先方の締め日を目安にする場合もある
売掛金を一括請求する場合は、一般的に先方の締め日に合わせて請求書を発行・送付します。一般的な締め日は月末締め翌月末払いですが、企業によって異なる場合があります。
請求書の送付方法と合わせて、必ず事前に締め日を確認しておきましょう。
請求書の締め日について、詳しくは以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。
請求漏れ発生後にお詫びメールで送る内容
請求漏れをお詫びするメールの文面を解説します。適切なお詫びの言葉とともに、経緯や状況を明確に説明しましょう。
件名
お詫びメールの件名は、請求漏れの内容が一目で分かるような工夫が必要です。日々多くのメールが届くなかで、相手に重要性と内容を即座に伝えられる件名を記載しましょう。
たとえば「【重要】請求書の遅延につきまして」のように、メールを開かなくても要件が理解できる件名にしてください。明確な件名は行き違いを防ぎ、情報伝達を確実にします。
冒頭の言葉
基本的なビジネスメールのマナーに従い、まずはあいさつの言葉を記載してください。
その後「お電話で申し上げました請求書遅延について、あらためてご連絡いたします」などと続け、請求書を締め日までに送付できなかった事実、または送付が遅延する可能性を簡潔に説明します。
回りくどい表現は不快感を与える可能性があるため避け、丁寧かつ簡潔な言葉遣いを心がけましょう。
経緯の説明文章
請求漏れが発生した原因や経緯について、再発防止のための情報共有の一環として説明します。
繰り返しになりますが、言い訳のような文章にならないように徹底してください。
発行日、送付日
請求書の発行・送付が可能な日付をメールに記載します。具体的な日程については、必ず先方と事前に相談し、双方にとって適切な日を決定しましょう。
事前に確認がとれている場合は、合意を得られた発行日と送付日、および送付方法についてメールに明記してください。
改善策、再発防止策
社内で検討した再発防止策も、メールに記載します。今後の取引に影響を与える可能性があるため、内容は慎重に検討してください。
適切な対応策を明確に説明できると、先方との良好な関係継続につながります。具体的な改善策や再発防止策の詳細については、後ほど詳しく解説します。
お詫びの言葉
メールの結びには、適切なお詫びの言葉を添えてください。たとえば「請求書の送付が遅延し、誠に申し訳ございません」や「ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」といった簡潔な表現を用いてメールを締めくくりましょう。
お詫びのメールは、通常のビジネスメールよりも丁寧な語調で作成することが重要です。ただし、簡潔さも意識する必要があります。
特に、すでに電話で謝罪の意を伝えている場合は、相手の貴重な時間を考慮し、簡潔な表現を心がけましょう。また、相手によっては、発生した問題よりも今後の対応策が気になる場合もあります。
その場合、お詫びの言葉は簡単な記載に留め、改善策や再発防止策を具体的に示した方が納得を得られやすいでしょう。
請求漏れ・請求内容の入力ミスがあった際のお詫びメールで使える例文3選
請求漏れに関するお詫びメールを作成しようとしても、良い言葉が浮かんでこない人も多いのではないでしょうか。ここからは、請求内容の入力ミスや請求漏れがあった際のお詫びメールの例文を3つ紹介します。
参考にして、取引先に誠意が伝わる丁寧な文面を作成しましょう。
請求書の送付が遅れてしまった場合
以下、例文を紹介します。
件名:【重要】請求書送付の遅延につきまして
○○株式会社
○○部 ○○様
いつもお世話になっております。○○社営業部の○○でございます。
先ほどお電話にてご連絡いたしました請求書送付の遅延につきまして、あらためてご報告申し上げます。
遅延の原因は、弊社内の事務処理の遅れによるものです。現在、最優先で対応しており、○○月○○日には確実に発送する予定でございます。
今後このようなことが起きぬよう、請求書発行の社内チェックリストを導入し、複数の担当者による確認を徹底します。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今月の請求書につきまして、本来の締め日である○○月○○日までに送付できず、ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
請求書を発行し忘れた場合
以下、例文を紹介します。
件名:【重要】当月分請求書の発行遅延と今後の対応について
○○株式会社
○○部 ○○様
平素よりお世話になっております。○○株式会社営業部の○○でございます。
先ほどお電話にてご連絡いたしました請求書発行の遅延につきまして、あらためて書面にてご報告申し上げます。
誠に申し訳ございませんが、○○月分の請求書の発行を失念しておりました。
現在、最優先で対応しており、本日中に請求書を発行し、明日○○月○○日には確実にお手元に届くよう速達で発送いたします。
また、再発防止のため、部門内におけるダブルチェック体制の確立を進める所存です。
今後このような事態が二度と起こらぬよう、細心の注意を払ってまいります。
何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
請求内容に入力ミスがあった場合
以下、例文を紹介します。
件名:【お詫び】請求書の誤記に関するご連絡
○○株式会社
○○部 ○○様
いつもお世話になっております。○○株式会社の○○でございます。
先日送付いたしました請求書に、誤記がございましたことを深くお詫び申し上げます。
【誤記の内容】
(誤)請求金額:〇〇円
(正)請求金額:△△円
本日中に正しい請求書を再発行し、速達にて発送いたします。
またデータ版も添付しておりますので、添付ファイルをご確認いただけますと幸いです。
大変お手数をおかけいたしますが、既にお手元にある請求書につきましては破棄いただきますようお願い申し上げます。
今後は同様のミスが発生しないよう、請求書発行時のチェック体制を見直し、ダブルチェックを徹底いたします。
この度は、ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。引き続きよろしくお願い申し上げます。
電話口で謝罪を伝えるのも重要な解決策の1つ
電話での謝罪は、信頼回復に向けた効果的な方法です。請求漏れや請求内容のミスなど、トラブルが発生した際には、先方に電話で謝罪の気持ちを伝えましょう。
謝罪の際は、まず深くお詫びの言葉を述べます。相手から苦情や厳しい言葉を受ける場合もありますが、真摯に受け止め共感する態度で対応してください。相手の感情を理解し、誠実に耳を傾けることは、信頼関係の修復に不可欠なステップといえます。
謝罪の電話は、問題発覚後、早急にかけるべきです。ただし、電話をかけるタイミングは、先方の都合を最優先に考えましょう。早朝や昼休憩、繁忙時間帯は避け、先方が落ち着いて話を聞ける時間帯を選ぶことが大切です。
請求漏れ・請求内容の不備が発生した場合の改善策
請求漏れや請求内容不備の主な原因は、管理不足や管理体制が原因です。再発防止のため、以下の具体的な改善策を実施して、不備を防ぎましょう。
ナンバリングする
請求書に固有の番号を割り当てて管理すると、請求書の不備や漏れを大幅に低減できます。請求書の番号を見積書や納品書などの関連書類と紐付けておくと、一連の取引を効率的に追跡できます。
ナンバリングのルールを導入する際は、番号の記載位置を統一し、一目で識別できるようにしましょう。
こまめに帳簿記入する
取引先別の売掛金元帳を作成し、こまめに記入・管理することは、請求漏れ防止に効果的です。業務量は増加しますが、商品やサービスの納品時点で売上を計上すると、請求漏れを防げます。
また、こまめな記帳により、定期的な確認作業が効率化されるだけではなく、リアルタイムでのキャッシュフローの把握が可能です。
ダブルチェックの体制を整え業務フローを見直す
請求書のミスを防ぐためには、ダブルチェック体制の確立と業務フローの見直しが不可欠です。請求書の入力ミスや送付漏れは企業の信頼を損なうだけでなく、取引先に迷惑をかける要因になりかねません。
作成者自身の確認だけでなく、第三者の目を通す仕組みを取り入れることで、ミスの発生を防ぎましょう。
請求書発行システムを導入する
請求書の発行・管理をシステム化すれば、入力ミスや請求漏れを防ぎ、業務の効率化を図れます。請求書の作成や送付、進捗を一元管理できるため、人的ミスの発生を大幅に低減でき、担当者の負担軽減も可能です。
また近年は、販売管理システムや在庫管理システムと連携可能な請求書発行システムも多く、販売データを基に自動で請求書を作成する機能を備えたものもあります。取引先からの信用維持のため、一度検討してみることもおすすめです。
請求書の不備をなくし、作成から送付まで効率化するなら「バクラク請求書発行」
請求書の作成から送付、保存までのプロセスで発生しやすいミスや業務負担の増加は、多くの企業にとって課題です。
「バクラク請求書発行」を導入すれば、帳票作成から稟議、送付、保存までをデジタル化し、一気通貫で対応できるため、手作業によるミスを削減しつつ業務を効率化できます。
また取引先に応じた送付方法を選択でき、一括送付にも対応しているため、送付の手間や誤送信のリスクも軽減できます。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しており、法令改正の影響を受けることなくスムーズな運用が可能です。
請求書業務の負担を減らし、精度を向上させたい方は、ぜひ以下のページから「バクラク請求書発行」の導入をご検討ください。