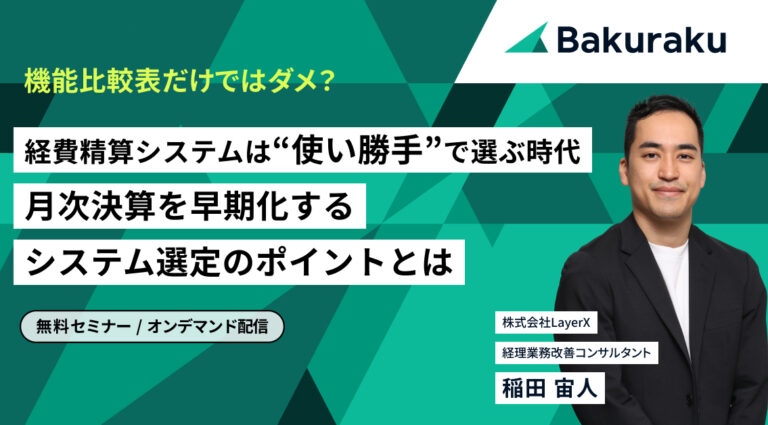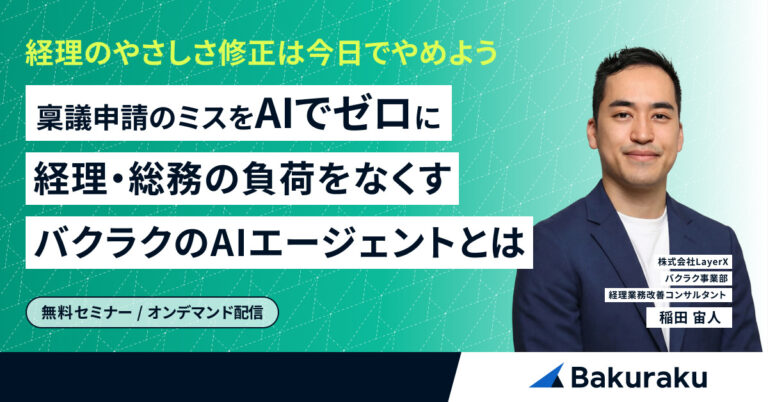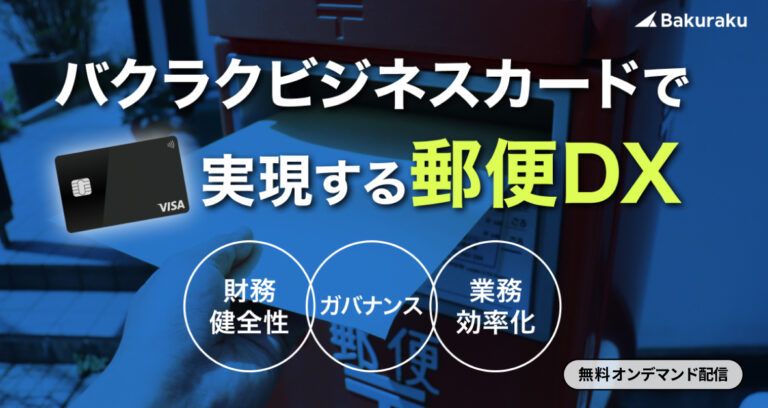
委託とは?委任・準委任・受託・請負との違いや簡単に意味を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-10-01
- この記事の3つのポイント
- 委託とは特定の業務や役割を第三者に任せる契約形態で、個人間や企業間の取引で利用されている
- 委任や準委任、請負、受託などは委託と混同しやすいが、定義や契約の性質が異なる
- 業務委託契約書を作成する際には、契約形態や業務内容、報酬条件などを明確に記載する
委託は、業務を外部に任せて効率化や品質向上を図る契約形態です。
本記事では、委任・準委任・請負との違いや特徴、業務委託契約書の必須項目や作成時の注意点などを詳しく解説します。契約形態の選び方に迷う方もぜひ参考にしてください。
委託とは?委任・準委任・受託・請負との違いや簡単に意味を解説
委託とは
委託とは、特定の業務や役割を第三者に任せる契約形態です。委託は個人間や企業間の取引で広く利用され、効率性や品質向上を目的としています。
海外ビジネスにおいても委託は重要で、英語の表記には、以下のものがあります。
- Contract of Delegation(委託契約)
- Entrustment Agreement(委託契約書)
- Outsourcing Agreement(業務委託契約書)
企業が自社業務の一部を外部企業や専門家に任せれば、社内リソースをコア業務に集中できるため、委託は重要なものといえるでしょう。
委託の意味
委託は、業務などを人に任せたり代行を依頼したりするような意味をもちます。企業では業務効率や品質向上のために、自社業務の一部を外部の企業や専門家に依頼するケースが多いです。
委託する際は、依頼者(委託者)と受託者(委託を受ける者)の間で、以下の項目を契約書で定めることが重要です。
- 業務内容
- 範囲
- 期限
- 報酬 など
委託は日常生活での使用頻度は少ないですが、ビジネスシーンでは欠かせない用語です。
委託以外の呼び方
委託はシーンによって呼び方が変わります。たとえば人件費削減や専門技術活用を目的とした「外注」や、企業戦略としての「アウトソーシング」も委託です。
契約形態に応じて「委任」「準委任」「請負」といった用語が使われる場合もありますが、いずれも第三者に業務や行為を依頼するという点では共通しており、目的や契約内容に合わせて使い分けられます。
委託と委任・準委任・請負・受託の違い
委託と似た言葉に委任や準委任、請負、受託などがありますが、それぞれ定義や契約の性質が異なるものです。ここからは、それぞれの意味や委託との違いについて解説します。
委託と委任の違い
委託が特定の業務や役割を第三者に任せる幅広い契約形態であるのに対し、委任はその中でも法律行為を第三者に任せる契約形態です。
委託の一形態であり、民法643条では「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾することで成立する」と定義されています。
具体例としては以下のとおりです。
- 企業が弁護士に法的手続きを依頼する場合
- 税理士に決算処理を任せる場合
- 司法書士に登記書類作成を依頼する場合 など
受任者(弁護士等)は法律行為の権限をもちますが、その結果に対する最終的な責任は委任者にあります。
委任契約には、業務の一部が履行された時点で報酬が発生する「履行割合型」と、業務の成果が完成したときに報酬が発生する「成果完成型」の2種類があります。
委任契約では契約書の作成義務はありませんが、業務範囲や期間、報酬、禁止事項に加え、民法644条で定められた「善管注意義務」などを明記し、書面化することが望ましいです。
委託と準委任の違い
準委任は、法律行為以外の事務を第三者に依頼する契約であり、委託の一種です。民法656条で「法律行為でない事務の委託」と定義されています。
具体例としては、以下のとおりです。
- コンサルタントによる経営改善
- プロジェクト管理
- システム設計や運営、広告代理店への企画依頼
- コールセンター業務 など
準委任では、受任者に業務遂行の権限が与えられますが、業務結果に対する最終責任は委任者にあります。報酬は労務提供やその成果に対して発生し、業務完了の有無に関わらず支払う義務があるのが特徴です。
契約書の作成義務はないものの、業務範囲・期間・報酬・禁止事項・善管注意義務などを記載した契約書を作成することで、業務の透明性が高まり、トラブル防止にもつながります。
委託と受託の違い
委託と受託は、立場の違いによる用語です。
- 委託:業務や役割を任せること
- 受託:業務や役割を引き受けること
契約書では委託する側を「委託者」、受ける側を「受託者」と呼びます。取引形態によっては委託者のことを発注者や注文者、委任者と呼び、受託者を受注者や請負人、受任者と呼ぶ場合もあります。
つまり発注する立場なら「委託」、依頼を受ける立場なら「受託」となり、文脈に応じて使い分けることが重要です。
委託と請負の違い
請負は、委託の中でも「仕事の完成」を目的とする契約形態です。民法632条により、当事者の一方が仕事を完成することを約束し、相手方がその成果に対して報酬を支払うことを約束することで成立します。
請負の例としては、以下のとおりです。
- 工事
- ウェブサイト制作
- ソフトウェア開発
- デザイン制作 など
請負の特徴は、成果物が完成しなければ報酬が発生しない点です。請負人は工程や作業方法を自由に決定できますが、成果物の品質や納期について全責任を負います。
また請負契約には「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」が適用され、成果物が契約内容に適合しない場合は、依頼者は修補や履行の追完を請求できます(民法562条等)。この責任は契約書に明記がなくても発生するため、請負側は十分注意しなければなりません。
受託請負は、受託の中でも仕事の成果物納品を目的とし、その完成をもって報酬が発生する契約を指します。受託と混同しやすい言葉ですが、受託は作業自体への従事が目的で、請負は完成品の引き渡しが目的という違いを認識しておきましょう。
委託の具体例
委託は業務の種類や目的により、以下のような形態があり、それぞれ契約内容や責任範囲が異なります。
- 業務委託
- 製造委託
- 販売委託
ここからは、それぞれの具体例について解説します。
業務委託
業務委託とは、当事者の一方が相手方に特定の業務を依頼し、相手方がこれを受託する契約です。委託者と受託者の間に指揮命令関係はなく、業務の進め方は受託者の裁量に委ねられます。
依頼される業務は多岐にわたるのが特徴です。社内の人材や設備では対応が難しい場合や、コスト削減・効率化をしたい場合に利用されます。
具体例としては、以下のとおりです。
- システム保守業務委託契約
- コンサルティング業務委託契約
- 弁護士・税理士の顧問契約
- 営業代行業務委託契約
- 店舗運営に関する業務委託契約
- ウェブサイト制作の業務委託契約
- コンテンツ制作業務委託契約
- 建築設計監理業務委託契約
近年はITの発達により、オンラインで外部と連携して進める形態も増加しています。
業務委託と雇用の違い
業務委託が、委託者と受託者の間に指揮命令関係がない契約形態であるのに対し、雇用は労働者が使用者の指揮命令下で働き、その労働に対して報酬を得る契約です。
ただし、業務委託であっても実態として受託者が委託者の指揮命令下にある場合は「偽装請負」と見なされ、労働法が適用される可能性があります。トラブルを防ぐには、契約書で指揮命令関係がない旨を明記し、現場運用でもそれを徹底することが重要です。
業務委託と派遣の違い
派遣は、派遣元の労働者が派遣先企業の指揮命令下で働く形態です。雇用契約は派遣元と結びますが、実際の業務指示は派遣先が行います。
業務委託では委託者と受託者の間に直接的な指揮命令関係はありませんが、もし受託者が委託者以外の者の指揮命令下で働く形態になると、それは派遣とみなされ、労働者派遣法の規制対象となります。
派遣を行うには厚生労働大臣の許可が必要で、無許可派遣は法令違反となるため注意が必要です。
製造委託
製造委託とは、一方が相手方に製品の製造や納品を依頼し、相手方がこれを引き受ける契約です。「製造物供給契約」と呼ばれる場合もあり、自社製品の製造を他社に委託するケースでは「OEM契約」ともいいます。
たとえば、メーカーが自社ブランドの商品を他社工場で製造してもらう場合や、原材料・部品を委託先に支給して組み立ててもらう場合が該当します。
製造設備や人員をもたない企業でも商品供給が可能になるため、新規事業立ち上げやコスト削減の手段として利用されることが多いです。
販売委託
販売委託とは、自社商品の販売を他社に任せる契約形態です。「販売代理店契約」と呼ばれることもあり、方式によって「販売店契約」や「代理店契約」に区分されます。
販売委託では、販売業者に手数料を支払い、売上から差し引いた額を受け取るのが一般的です。自社店舗を構える必要がない利点がある一方、販売数が伸びない場合は損失リスクもあるため、実績や管理体制を確認した上で業者を選ぶことが重要です。
業務委託契約と他の契約の違い
業務委託契約は法律上の明確な定義がなく、契約内容を自由に定められます。法的には民法上の「請負契約」(第632条)や「委任契約」(第643条)を根拠に作成されることが多く、準委任契約も含め、契約形態ごとに目的や責任範囲が異なります。
契約形態ごとに法的根拠や目的、義務などをまとめた表は、以下のとおりです。
契約形態 | 法的根拠 | 目的 | 成果物納品義務 |
業務委託契約 | 定義なし | 自由に設定可能 | 契約による |
委任契約 | 民法643条 | 法律行為の遂行 | 不要 |
準委任契約 | 民法656条 | 法律行為以外の遂行 | 不要 |
請負契約 | 民法632条 | 必須 | 必須 |
たとえば請負契約では、請け負う側が成果物の完成に責任を負いますが、委任契約や準委任契約では成果物納品が必須ではなく、業務遂行そのものが目的です。
業務委託契約はこれらの特徴を柔軟に組み合わせられる反面、契約自由度が高い分だけトラブル回避のための条項設定が不可欠になります。
参考:e-Gov法令検索「民法」
業務委託契約については、以下の記事で詳しくまとめているのでぜひ参考にしてください。
業務委託契約書の項目
業務委託契約では契約書の作成がトラブル防止の要です。契約形態や業務内容、報酬条件などを明確に記載すれば、双方の認識のズレや誤解を防げます。
特に業務委託契約は法律上の明確な定義がないため、請負契約や委任契約の規定を参考にしながら必要な条項を整えることが重要です。以下に業務委託契約書に盛り込む項目をまとめたので、参考にしてください。
項目 | 内容のポイント |
契約形態 | 請負型か委任型かを明記 |
委託業務の内容 | 業務範囲・変更可能性を具体的に記載 |
成果物・納品期限 | 所有権や著作権の帰属を含め明示 |
報酬額・支払方法 | 金額や計算方法、支払期日、振込手数料 |
経費負担 | 委託者・受託者のどちらが負担するか |
再委託の可否 | 必要に応じて条件も設定 |
禁止事項 | 機密保持や不正行為の防止 |
損害賠償 | 責任範囲と負担方法 |
契約期間・解除条件 | 自動更新の有無や中途解約の条件 |
上記の項目を盛り込めば、抜け漏れが防げ、双方納得のいく契約書が作成できるでしょう。
まとめ
委託とは、特定の業務や役割を第三者に任せる契約形態で、委任・準委任・請負・受託などに分類されます。委任は法律行為を、準委任は法律行為以外を目的とし、請負は成果物の完成に責任を負う点が特徴です。
業務委託契約は法的定義がなく、契約内容を自由に設定できますが、トラブル回避のためには業務範囲や報酬、権利関係、解除条件などを契約書に明記し、双方の認識を一致させることが重要といえるでしょう。