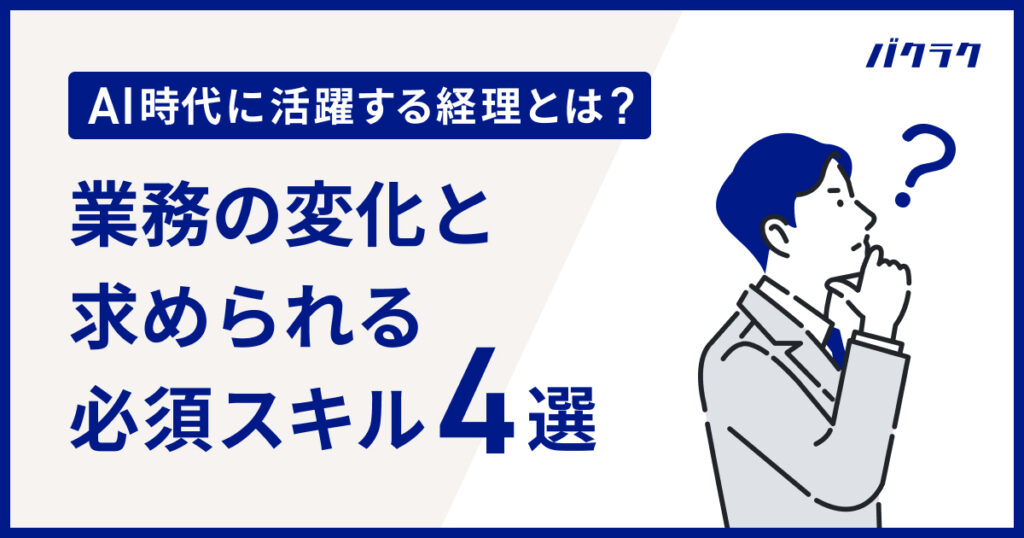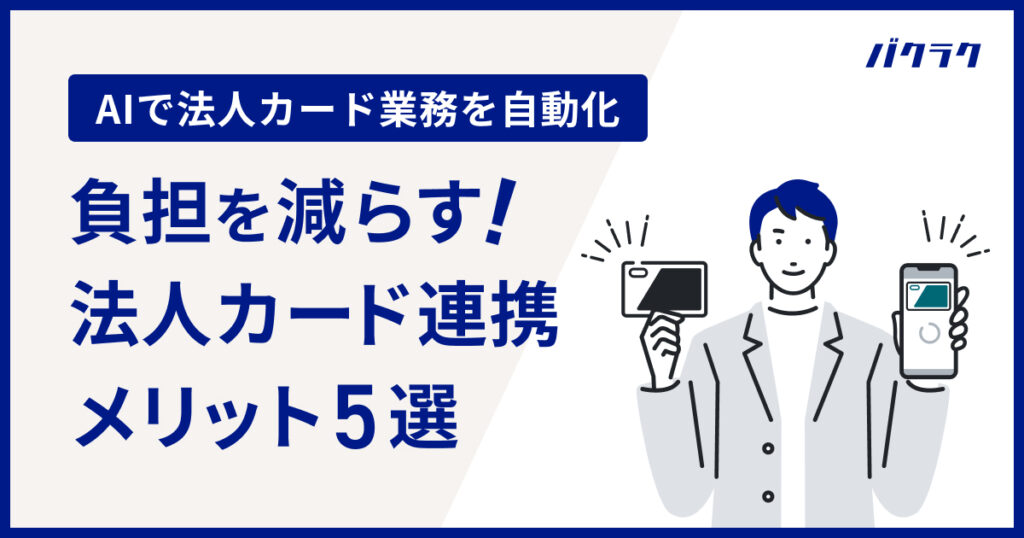簡易書留の出し方を解説!一般書留・現金書留との違いや発送時の注意点も紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- 簡易書留の出し方は一般的な郵便物の出し方とは異なり、窓口で料金を支払う必要がある
- 簡易書留は一般書留や現金書留よりも安価で、最大5万円の補償がついている
- 簡易書留は値上げ対象外だが、メールにすることで大幅な費用削減を実現できる
簡易書留は、配達状況を確認できたり補償がついていたりする便利な郵便サービスです。履歴書や契約書のほか、請求書などビジネスシーンにおいても重要な郵便物を送る際に適しています。
一方で、日常生活で多く利用することはないため、簡易書留の出し方がわからないという方もいるでしょう。
そこで本記事では、簡易書留の出し方を4つのステップで解説します。一般書留・現金書留との違いや発送時の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
簡易書留の出し方を解説!一般書留・現金書留との違いや発送時の注意点も紹介
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
簡易書留の出し方
簡易書留は、窓口での手続きが必要です。一般的な郵便物とは出し方が異なるため、注意しなければいけません。以下では、簡易書留の出し方を詳しく解説します。
送る書類を準備する
簡易書留を出す際は、送る書類を準備します。封筒やはがきには宛先を正確に記載しましょう。切手は窓口で貼ってもらえるため、事前に用意する必要はありません。
封筒は市販のものを使用します。一般書留や現金書留の場合は専用の封筒を使用する必要がありますが、簡易書留は規定がないため一般的な封筒で郵送できます。
郵便局で差出票を記入する
簡易書留を出す際は「書留・特定記録郵便物等差出票」が必要です。差出票は郵便物の追跡や紛失時の補償に不可欠な書類です。差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名、郵送する内容などを正確に記載しましょう。
書留・特定記録郵便物等差出票は郵便局に備え付けられており、窓口で受け取ることもできます。わからない場合は職員に確認しましょう。
窓口で料金を支払う
書類が準備できたら、職員に簡易書留で送りたい旨を伝えたうえで窓口で料金を支払います。料金は「郵便料金+350円」です。
たとえば、定形郵便(50g以内)を簡易書留で送る場合の料金は「110円+350円=460円」です。すでに切手を貼っている場合は、窓口で簡易書留の料金350円のみを支払います。
なお、掲載している金額は2025年4月時点のものです。定形郵便の料金は2024年10月に変更されており、今後も料金改定がある可能性があるため、窓口で支払う際に確認しましょう。
受領証を受け取る
簡易書留の手続きが終わったら、受領証を受け取ります。受領書には郵便物の追跡番号が記載されており、配達状況を確認したり、万が一紛失した際の補償時に必要になったりするので、忘れずに受け取り保管しておきましょう。
郵便局の「郵便追跡サービス」を使えば、追跡番号を基にパソコンやスマホから簡単に配達状況を確認できます。ただし、簡易書留の追跡機能はあくまでも簡易的なものであり、引受けと配達のみ確認が可能です。
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
簡易書留を使うメリット
簡易書留を使うメリットは、以下が挙げられます。
- 破損や紛失時に最大5万円まで補償される
- 配達状況を確認できる
- 休日(土曜、日曜、祝日)配達がある
- 当日中の日時指定、再配達に対応してもらえる
- 一般書留・現金書留よりも料金が安い
簡易書留には、配達過程において破損や紛失が発生した際に最大5万円まで補償されるというメリットがあります。
なお、到着した郵便局や時刻などの配達状況を把握することも可能です。配達状況は郵便局の「郵便追跡サービス」で簡単に確認できます。
また、普通郵便ではできない休日配達も対応してもらえます。当日中の再配達や日時指定なども可能なため、大切な書類を指定した日に届けたいときに最適です。
簡易書留と一般書留・現金書留の違い
郵便サービスの「書留」には、簡易書留・一般書留・現金書留があります。それぞれの違いは、以下のとおりです。
種類 | 簡易書留 | 一般書留 | 現金書留 |
料金 | +350円 | 郵便物:+480円 ゆうメール:+420円 (補償額5万円ごとに+23円) | +480円 (補償額5,000円ごとに+11円) |
補償額 | 最大5万円 | 10万円~500万円 | 1万円~50万円 |
専用封筒 | 不要 | 必要 | |
配達記録 | 郵便物を出した時刻・郵便局、および郵便物が到着した時刻・郵便局 | 郵便物がどこを経由していつ・どこの郵便局に到着したのか | |
簡易書留と一般書留、現金書留には、料金や補償額などに違いがあります。簡易書留はその他の書留よりも安価で利用できる反面、補償額は低く配達記録が簡易的です。
簡易書留は、業務上必要な書類や履歴書、チケットなど「補償額の大きさにこだわりはないが紛失すると不安」というものの郵送に利用するのが適しています。
関連記事:適格請求書とは?概要や書き方(見本付き)をわかりやすく解説
簡易書留を出す際の注意点
簡易書留を出す際の注意点は以下が挙げられます。
- コンビニエンスストアやポストではなく窓口で手続きをする必要がある
- 現金や貴金属を送ることはできない
簡易書留の手続きができるのは、郵便局の窓口もしくはゆうゆう窓口のみです。コンビニエンスストアやポストでは発送できません。各窓口の営業時間を確認したうえで手続きを行いましょう。
また、金や銀、ダイヤモンドなどの郵便局が約款で定める貴重品は、一般書留で送らなければいけません。現金を郵送する場合も簡易書留ではなく、必ず現金書留を利用する必要があります。
参考:郵便局「書留」
簡易書留につけられるオプション
簡易書留では、速達や配達日指定などのオプションがつけられます。大切な書類を正確かつ安全に送れるので、ぜひ参考にしてみてください。
速達
簡易書留には速達のオプションをつけられます。速達とは、郵便物を通常配達よりも短い日数で届けるサービスです。簡易書留の配達日数は通常の郵便物と同じですが、速達で出せば最短翌日に到着します。
速達の料金は以下のとおりです。
郵便物の場合 | ゆうメールの場合 | ||
250g以内 | +300円 | +330円 (1kg以内) | |
1kg以内 | +400円 | ||
4kg以内 | +690円 | ||
※2024年10月1日改定後
たとえば、定形郵便(50g以内)の簡易書留を速達で送る場合の料金は「110円+350円+300円=760円」です。
※掲載している情報は、2025年4月時点のものです。金額は変更になる可能性があるのでご注意ください。
通常と比べて料金は高くなりますが「とにかく急いでいる」「締切日ギリギリに発送する」という方でも安心して郵送できます。簡易書留は窓口で手続きをするため、速達にしたい場合は、その旨を伝えて料金を支払いましょう。
配達日指定
簡易書留は、オプションで配達日指定もできます。配達日指定は郵便物の到着日を指定できるサービスで、記念日や休日に送りたいという場合に適しています。配達日の指定は、原則として差出日の3日後から起算して10日以内です。
配達日指定にかかる料金は以下のとおりです。
種類 | 郵便物 | ゆうメール | |
料金 | 平日指定:+42円 土日休日を指定:+270円 | +52円 | |
※2024年10月1日改定後
郵便局に備え付けられている「配達日指定シール」に希望の配達日を記入し、簡易書留の封筒に貼り付けて窓口に出すことで送れます。
内容証明・配達証明を付けたい場合は一般書留を利用する
簡易書留を一般書留にすれば、オプションとして内容証明・配達証明もつけられます。
- 内容証明:いつ・どのような内容の文書を誰から誰あてに出されたかを証明する
- 配達証明:郵便物について、配達したという事実を証明する
内容証明・配達証明のサービスを利用すれば「郵便物を出した」「誰がどのような文書を郵送した」「重要な通知がいつ誰に届いた」などを確実に記録として残せます。
法律や契約に基づく通知・請求書等を発送する際や、相手に対して強いメッセージ・意思を伝えたい場合などに利用するケースが多いです。速達と同様、追加の料金が発生します。
種類 | 内容証明 | 配達証明 |
料金 | 480円 (2枚目以降は290円増) | 350円 ※差出後に配達証明を請求する場合は480円 |
※2024年10月1日改定後
たとえば、定形郵便(50g以内)で内容証明を出したい場合の料金は「110円+480円(一般書留)+480円=1,070円」です。
内容証明はすべての窓口で取り扱っているわけではないため、郵便局の公式HPから最寄りの取扱い窓口を確認しておきましょう。
※掲載している情報は、2025年4月時点のものです。金額は変更になる可能性があるのでご注意ください。
簡易書留の料金は値上げ対象外
2024年10月に郵便料金が値上げになり、一部の料金が改訂されましたが、簡易書留を含む書留は値上げ対象外であり、料金に変更はありません。
ただし、定形・定形外郵便の料金は2024年10月1日に値上げされているので、簡易書留にかかる総額は高くなっていることを理解しておきましょう。
たとえば、定形郵便(50g以内)は94円から110円、速達は260円から300円(250g以内)に変更されています。定形郵便の簡易書留を速達で送る場合は、2024年9月よりも計56円高くなります。
料金を節約したい場合は、割引制度を利用するのがよいでしょう。簡易書留には、300通以上もしくは1,000通以上を郵送したり、オプションを利用したりしない場合に1通あたり11円以上の割引を受けられる制度があります。
また、郵便からメール送付への移行を検討するのも、郵便料金の節約に有効です。特に、毎月大量の請求書や納品書などの郵送が発生するビジネスシーンでは、郵便からメールに変えることで大幅な費用削減を実現できます。
参考:郵便局「書留の割引制度」
紙の請求書を用いる場合は、郵送時のサイズ感を把握しておく必要があります。請求書のサイズや用紙の選び方について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
「バクラク請求書発行」ならメール送付への移行がスムーズ
簡易書留は、重要な書類を確実に届けられる便利なサービスです。窓口にて簡易書留で出したい旨を伝え、料金を支払うことで簡単に手続きできます。
しかし、簡易書留の料金に変更はないものの、一般郵便物の値上げにより郵送にかかる総額は高くなっています。特に、毎月大量の郵送物が生じるビジネスシーンでは、コスト面で大きな懸念となっているのが現状です。
郵送料金を節約したい場合は「バクラク請求書発行」の導入がおすすめです。請求書や納品書などをメールで送信できるため、郵送代を大きく節約できます。システム利用料を踏まえても、郵送費や人件費等の大幅なコスト削減が見込めます。
また、帳票の作成・稟議・送付・保存までをデジタルに一本化できる点も魅力です。従来の業務を大きく変えることはなく、請求書、納品書、見積書など、あらゆる帳票を発行できます。
「簡易書留にかかる郵送料金を節約したい」「毎月の請求書や納品書の作成、管理、郵送の手間を省きたい」と悩む方は、ぜひバクラク請求書発行をご検討ください。