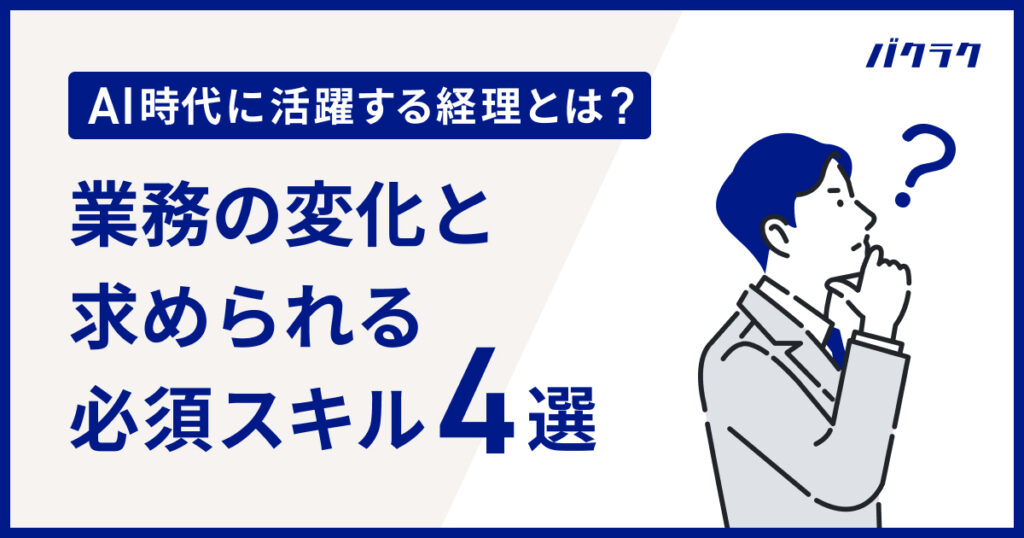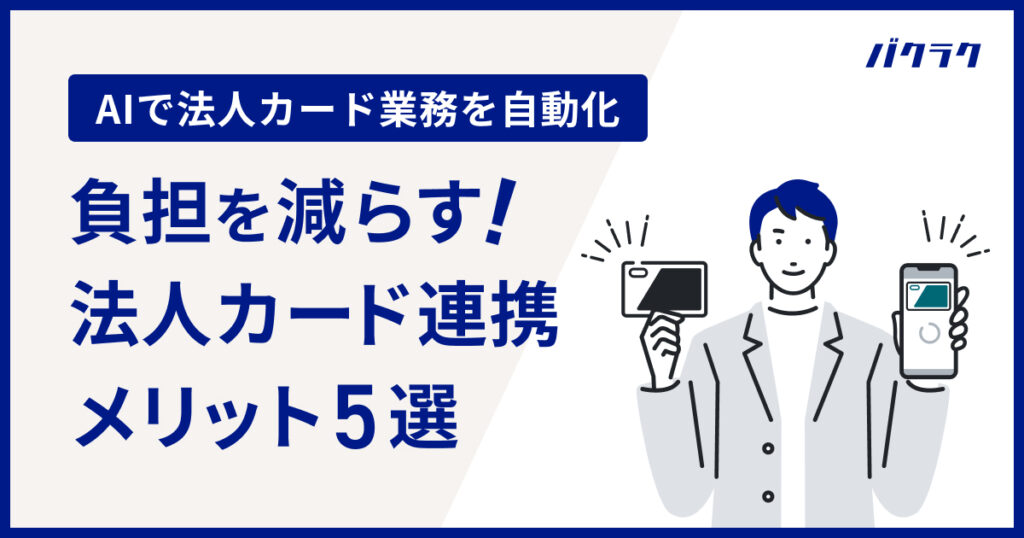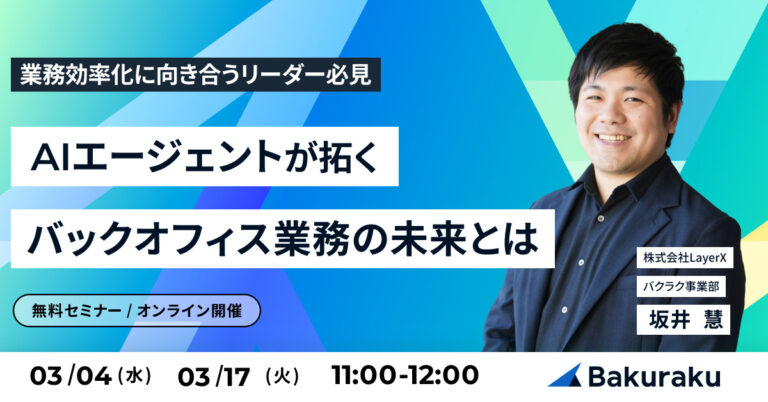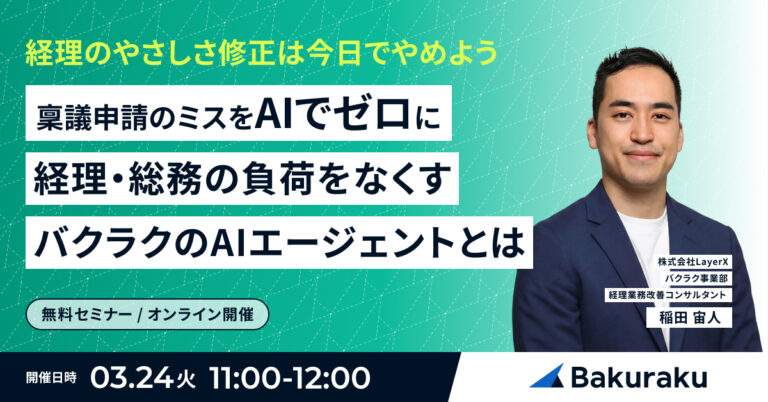
料金後納郵便とは?利用条件や料金別納郵便との違いを詳しく解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-09-09
- この記事の3つのポイント
- 料金後納郵便は1カ月分の郵便料金を翌月にまとめて支払う仕組みで、経理業務の効率化が可能
- 継続的に大量発送するなら「後納」単発なら都度払いの「別納」と、発送頻度で使い分ける
- 料金後納郵便の利用開始には事前申請と郵便局の承認が必要で、利用できる郵便局も限定される
毎月大量の請求書やダイレクトメールなどを発送する企業にとって、料金後納郵便は業務効率化に役立つサービスです。
本記事では、料金後納郵便の仕組みや利用条件、料金別納郵便との違い、メリット・デメリットを詳しく解説します。自社に合った発送方法を見つけるために、ぜひ最後までお読みください。
料金後納郵便とは?利用条件や料金別納郵便との違いを詳しく解説
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
料金後納郵便とは
料金後納郵便とは、1カ月分の郵便料金を翌月にまとめて支払える日本郵便のサービスです。料金後納を活用すると、郵便物や荷物を発送するたびに切手を貼ったり、現金で支払ったりする手間が省けます。
以下のようなシーンでは、特に料金後納郵便の利用が適しています。
- 毎月、数100通の請求書を送付する
- 定期的に販促用のダイレクトメールを発送する
- ECサイトで販売した商品を発送する
発送業務ごとの支払いが月1回に集約されるため、担当者の負担を軽減できる仕組みです。また、経理上も切手の在庫管理や小口現金の準備が不要になり、業務全体の効率化につながるでしょう。
継続して郵便物を多く扱うビジネスで、業務を円滑に進めるための有効な手段が料金後納郵便です。
参考:郵便局「料金後納」
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
料金後納郵便を利用する条件
料金後納郵便を利用するには、いくつかの条件を満たして事前の承認を得なければなりません。利用にあたって、主に以下の条件が定められています。
- 毎月50通(個)以上の郵便物・荷物を差し出す
- 継続して毎月郵便物や荷物を差し出す
- 利用を希望する郵便局長の承認を得る
基本的には、毎月一定量の郵便物を継続して発送する法人や個人事業主が対象です。その上で、支払い能力を保証するために、1カ月の料金概算額の2倍以上に相当する額の担保(現金、国債証券など)の提供を求められる場合があります。
まずは、自社が利用条件に合致するか、事前に確認しておきましょう。
参考:郵便局「料金後納」
料金後納郵便と料金別納郵便の違い
料金後納郵便と料金別納郵便の最も大きな違いは、料金の支払いタイミングです。料金後納郵便が1カ月分の料金を翌月にまとめて支払う「後払い」であるのに対し、料金別納郵便は発送の都度、一括で支払う仕組みです。
料金別納郵便は、同じ料金の郵便物を10通以上差し出す際に利用でき、事前の手続きは不要です。継続的に大量発送がある場合は後納郵便、単発での発送が多い場合は別納郵便と使い分けるのがよいでしょう。
料金後納郵便を利用するメリット
料金後納郵便を利用するメリットは、発送担当者と経理担当者、双方の業務負担を軽減し、コスト削減にもつながる点です。料金後納郵便のメリットを詳しく解説します。
発送業務の効率化
料金後納郵便は、発送業務の効率化に貢献するサービスです。通常、郵便物を差し出す際には、一点ずつ重さを量って料金を計算し、切手を貼るか窓口で支払う必要があります。
しかし料金後納郵便の場合、発送する郵便物をそのまま郵便局の窓口へ持ち込むだけで手続きは完了です。郵便物の料金計算は郵便局側でまとめて対応してくれるため、発送担当者は料金計算や切手貼りといった煩雑な作業から解放されます。
毎日大量の郵便物を扱う部署にとって、作業時間の短縮は大きなメリットになるでしょう。
経理業務の効率化
発送業務だけでなく、経理業務の効率化にもつながるのが、料金後納郵便のメリットです。これまでは発送のたびに現金で支払ったり、切手を購入したりして、その都度経費精算の処理が発生していました。
料金後納郵便を導入すると、支払いは月に1回で済みます。日本郵便から一括で届く請求書に基づいて処理すれば良いため、日々の細かな精算業務は不要です。
また、切手代の仮払いや在庫管理といった手間からも解放され、経理部門全体の業務負担が軽減されます。会計処理がシンプルになる点は、大きなメリットといえるでしょう。
経費の削減
料金後納郵便は、通信費の削減にも寄与します。ゆうパックなどを料金後納郵便で利用すると「月間割引制度」を適用できます。発送量が多いほど割引率も高くなるため、コスト削減につながるでしょう。
料金後納郵便のデメリット
料金後納郵便は便利ですが、導入前に知っておくべきデメリットもあります。自社の状況と照らし合わせて導入を検討しましょう。
発送部数が少ないと利用できない
料金後納のサービスは、原則として「毎月50通(個)以上の郵便物・荷物を差し出す」が利用条件の一つです。
継続して条件を満たせないと利用は難しいでしょう。自社の月間平均発送数を確認しておく必要があります。
事前の承認が必要
料金後納郵便を利用するには、事前に所定の手続きを経て、郵便局長の承認を受けなくてはなりません。申請書類の準備や、場合によっては担保の提出も求められます。
申込みから承認までには一定の日数がかかるため、利用したいと思ったその日からすぐに使えるわけではありません。料金後納郵便の導入を検討する際は、スケジュールに余裕を持たせましょう。
利用できる郵便局は決まっている
料金後納郵便は、どの郵便局からでも差し出せるわけではないため注意が必要です。郵便物の差し出しは、原則として承認を受けた郵便局、またはその郵便局が指定した場所限定です。利便性を考慮し、自社の発送業務に最も適した郵便局へ申請を出しましょう。
料金後納郵便を利用する流れ
料金後納郵便を利用するまでの流れは、大きく4つのステップに分けられます。
- 必要書類の準備・申請
- 承認とカード・書類の受領
- 郵便物の差し出し
- 料金の支払い
それぞれのステップを詳しく解説します。
必要書類の準備と申請
始めに、利用したい郵便局の窓口へ料金後納の申請をするために、書類を準備してください。必要となるのは「料金後納承認請求書」です。また、手続きの際に印鑑が必要になるため、準備しておきましょう。
法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は事業の届出書などが別途求められる場合があります。提出する書類は郵便局の窓口で受け取るか、日本郵便の公式サイトからダウンロードが可能です。
必要事項を記入し、捺印のうえ、発送業務で利用する郵便局へ提出します。
参考:郵便局「料金後納にはどのような手続が必要ですか?」
事前に郵便局からの承認を受け、カード・書類を受領
申請書類を提出すると、郵便局側で継続的な利用が見込めるかなどを審査します。審査を通過して承認されると、料金後納郵便の利用に不可欠な「ゆうびんビズカード」と、発送時に提出する「後納郵便物差出票」が発行されます。
ゆうびんビズカードは利用者本人の証明になり、後納郵便物差出票は発送内容を記録するための書類です。カードと差出票が手元に届いて初めて、料金後納郵便の利用を開始できます。
申請から承認までには一定の期間を要するため、余裕をもって手続きを進めましょう。
郵便物を差し出す
承認後は、発送したい郵便物と、事前に記入した「後納郵便物差出票」を準備し、承認を受けた郵便局の窓口へ持ち込んでください。
提示を求められた場合に備えて「ゆうびんビズカード」も忘れずに携帯しましょう。窓口での料金支払いは不要です。郵便物を預けるだけで発送手続きは完了します。
料金を支払う
料金は、1カ月分をまとめて翌月に支払います。1カ月分の利用料金は、月末締めで翌月の20日頃に請求書として届きます。
支払期限は翌月末日で、指定された金融機関口座へ振り込みましょう。また、毎月の振込手続きを自動化できる口座振替も申し込めます。
なお、利用明細は日本郵便の法人向けポータルサイト「JP Business ToolBox」にログイン後、「料金後納利用状況確認インターネットサービス」から確認が可能です。過去の利用履歴をデータでダウンロードもできるため、経費の管理が容易になるでしょう。
料金後納郵便の表示方法
料金後納郵便として差し出すには、郵便物の表面に規定の表示を記載する必要があります。表示は、郵便局が荷物を一目で後納郵便と識別し、スムーズに処理するための印です。
表示を記載する位置は、縦長の封筒やはがきの場合は表面の左上部、横長の場合は右上部と定められています。形状は直径2〜3cmの円形、または縦横2〜3cmの四角形で、上部に承認を受けた「差出郵便局名」を、下部に「料金後納郵便」の文字を明記する決まりです。
差出人の事業所名や広告を合わせて記載することも認められています。ルールに沿った表示をあらかじめ封筒などに印刷しておくと、発送準備がより円滑に進むでしょう。
「バクラク請求書発行」で請求書送付を電子化
料金後納郵便は、請求書やダイレクトメールを大量に送付する企業にとって、発送や経理の手間を削減できる有効な手段です。
一方、より抜本的な業務改善を目指すなら、請求書発行そのものの電子化もご検討ください。バクラク請求書発行は、請求書の作成から社内承認、送付、控えの保存まで、一連の業務をデジタル上で完結させます。
バクラク請求書発行は、PDFのメール送付やリンクでの共有にも対応しており、取引先のニーズに合わせた柔軟な送付が可能です。印刷・封入・投函といった物理的な作業と郵送コストそのものを削減できるでしょう。
また、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法制度にも対応しており、法令遵守の負担も軽減します。紙の請求書発行と郵送業務に課題を感じているなら、バクラク請求書発行をご検討ください。詳しい機能は、資料でご確認いただけます。