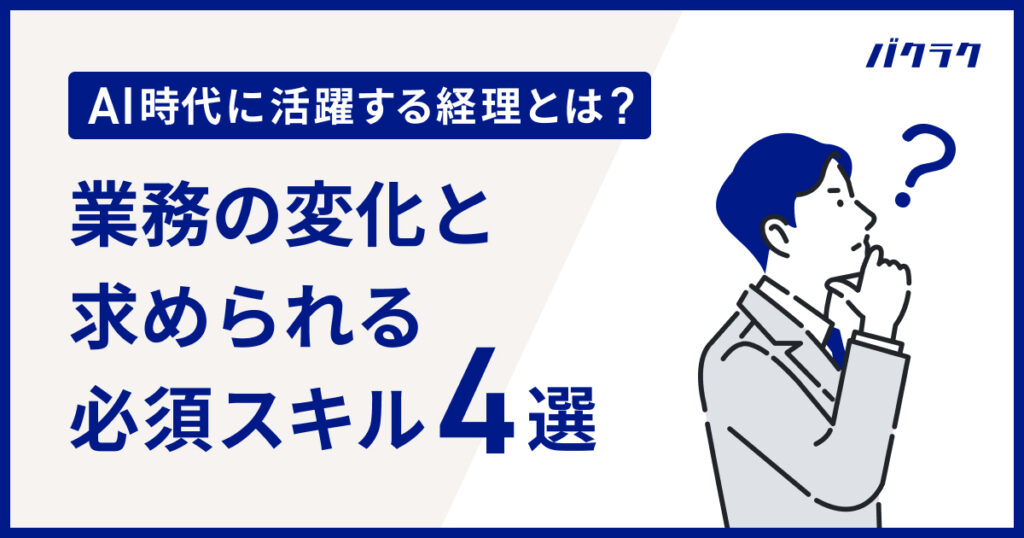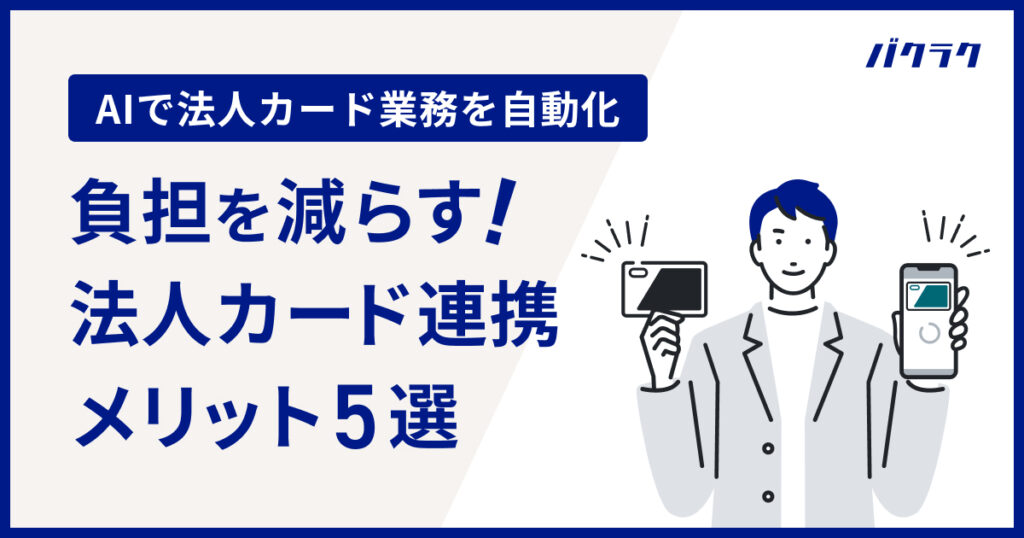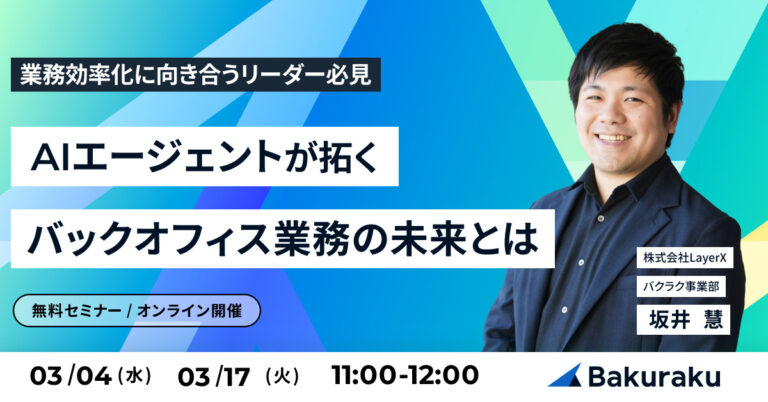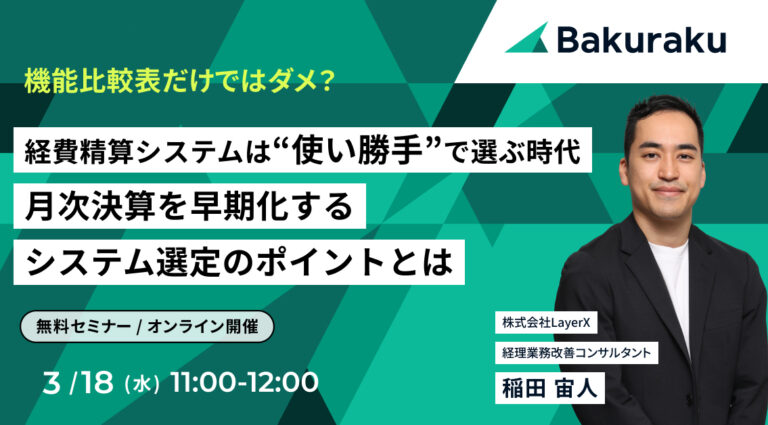
定形外郵便の厚さとサイズは?定形郵便との違いや料金比較も紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-09-09
- この記事の3つのポイント
- 定形外郵便の厚さとサイズは規格内・規格外で異なり、最大は「縦60cm+横+厚さ=90cm」
- 定形外郵便物で送れる重さは4kg以内であり、重量区分ごとで料金が異なる
- サイズによって、定形外郵便で送れない・他の発送方法のほうが送料が安い場合がある
定形外郵便は、日本郵便が提供する普通郵便のうちのひとつです。普通郵便はサイズ・厚さ・重さによって「定形郵便」「定形外郵便」に分類され、それぞれ料金も異なります。
定形外郵便にも最大で送れるサイズの規定があります。正しく理解しておかないと料金や発送方法のミスで送れない、といった事態を招く可能性があるため注意が必要です。
この記事では、定形外郵便のサイズと厚さを解説します。定形郵便との違いやそれぞれの料金、他の発送方法との比較も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
定形外郵便の厚さとサイズは?定形郵便との違いや料金比較も紹介
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
定形郵便と定形外郵便のサイズ・厚さ
定形郵便と定形外郵便の規定(サイズ・厚さ)は以下のとおりです。
定形郵便 | 定形外郵便 | ||
規格内 | 規格外 | ||
重さ | 50g以内 | 1kg以内 | 4kg以内 |
最大 | 縦23.5cm×横12cm×厚さ1cm | 縦34cm×横25cm×厚さ3cm | 縦60cm+縦+厚さ=90cm |
最小 | 縦14cm×横9cm |
| |
参照:日本郵便株式会社「第一種郵便物 手紙」
定形郵便の規定サイズ・厚さを超えるものは、定形外郵便に該当します。サイズや厚さはいずれの規定も満たす必要があり、たとえば、23cm×12cm以内でも、厚さが1cmを超える場合は定形ではなく定形外郵便で送らなければいけません。
また、最小サイズより小さなものでも、以下を満たす場合は差し出しが可能です。
- 郵便物のサイズが6cm×12cm以上
- 耐久力のある厚紙や布製のあて名札を付けている
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
定形郵便と定形外郵便の料金
定形郵便(50g以内)の料金は一律110円です。2024年10月1日の料金改定にて、25g以内・50g以内の重量区分がなくなっているため注意しましょう。
一方、定形外郵便の料金は、以下のように規格内か規格外かで異なります。
重さ | 規格内 | 規格外 |
50g以内 | 140円 | 260円 |
100g以内 | 180円 | 290円 |
150g以内 | 270円 | 390円 |
250g以内 | 320円 | 450円 |
500g以内 | 510円 | 680円 |
1kg以内 | 750円 | 920円 |
2kg以内 | - | 1,350円 |
4kg以内 | 1,750円 |
出典:日本郵便株式会社「料金制度について」
1kgを超えるものは規格外として扱われ、1,350円以上の料金がかかります。2024年10月1日以降、普通郵便の料金はすべて値上げされているため、理解しておきましょう。
※掲載している情報は、2025年7月時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。
定形外郵便の送り方
定形外郵便の送り方は、以下の2つがあります。
- 切手を貼って郵便ポストへ投函する
- 郵便局の窓口に持っていく
郵便ポストへ投函する場合は、サイズに注意が必要です。投函できるサイズはポストの種類によって異なりますが、従来のものは「幅23.5cm×厚さ3cm」が目安です。
コンビニ設置のポストは「幅25cm×厚さ3.4cm程度」、新しいポストは「幅29cm×厚さ4cm程度」まで投函できます。郵便ポストの投函口が複数ある場合は「大型郵便」と記載されている箇所に入れましょう。
郵送料金がわからなかったり、ポストに投函できなかったりする場合は、郵便窓口に持参する必要があります。梱包資材に指定はないので、サイズに合った封筒、段ボールなどを準備して、発送手続きを行いましょう。
定形外郵便を送るときの注意点
ここでは、定形外郵便を送るときの注意点について解説します。発送時に混乱しないよう、しっかり押さえておきましょう。
追跡サービスや補償はない
定形外郵便には追跡サービスや補償がないため、確実に届いたことを知りたかったり、高価なものを送ったりするのには向きません。
「定形外郵便で送りたいが追跡や補償もつけたい」という場合は「書留」のオプションを付けるのがおすすめです。郵便追跡システムで配達情報を確認できたり、万が一の際に補償を受けられたりします。
コンビニからの発送はできない
定形外郵便は、コンビニ内にポストがある場合に投函はできるものの、レジでの発送はできません。以下のような対応は受けてもらえないため注意が必要です。
- 発送前の計量
- 郵便物の預かり
- 発送手続き
郵便物がポストに入らない場合でも、荷物を預かってもらえません。コンビニから送りたい場合は、事前にサイズや重さを量り、料金分の切手を貼ったうえでポストに投函しましょう。
コンビニのポストに入らない場合は、郵便局で発送手続きをしてください。
他の発送方法のほうが安い場合もある
郵便物の厚みや大きさによっては、定形外郵便よりも他の発送方法のほうが送料を安く抑えられる可能性があります。
たとえば、サイズは小さいものの、重量が2kgを超える場合の定形外郵便の送料は1,750円です。一方、レターパックを利用すれば、最大でも600円で送れます。
郵便物のサイズや重さなどの状況に合わせて、どのサービスが適しているかを比較、検討するとよいでしょう。
定形外郵便と他の発送方法の比較
郵便物の内容によっては、定形外郵便以外の発送方法を用いるのが適している場合があります。ここでは、定形外郵便と他の発送方法を比較していきましょう。
レターパック
レターパックは、A4サイズ・4kgまでの荷物を全国一律料金で送れるサービスです。小さな商品や書類、信書など、さまざまな郵便物を簡単に発送できるほか、土日、休日も対応しています。
レターパックは「レターパックプラス」「レターパックライト」の2つに分かれており、以下のように送れるサイズ、料金が異なります。
種類 | サイズ・重さ | 重さ | 厚さ | 料金 |
レターパックプラス | 340mm×248mm (A4ファイルサイズ) | 4kg以内 | – | 600円 |
レターパックライト | 3cm以内 | 430円 |
※掲載している情報は、2025年7月時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。
レターパックプラスのみ、封筒に入るA4ファイルサイズ、かつ4kgまでの郵便物であれば、3cmの厚みを超えても発送できます。いずれも配達追跡システムで配達状況の確認が可能です。
2025年10月1日以降、レターパックの料金も改訂されています。以下の記事で解説しているので、料金についてより詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
関連記事:レターパックの値上げ後の料金は?旧料金との差額の対応方法も解説
ゆうパケット・ゆうパケットプラス
ゆうパケットは、小さな荷物の発送に便利なサービスです。重さ1kg以内の荷物に最適な「ゆうパケット」と、2kgまで発送できる「ゆうパケットプラス」の2種類があります。
それぞれのサイズ規定は以下のとおりです。
- ゆうパケット:縦+横+厚さ=60cm以内(縦=34cm以内、厚さ=3cm以内)
- ゆうパケットプラス:縦24cm×横17cm×厚さ7cm
送料は以下のとおり、荷物の厚さによって異なります。
厚さ | 料金 |
1cm以内 | 250円 |
2cm以内 | 310円 |
3cm以内 | 360円 |
ゆうパケットプラスの場合は、上記の送料に加えて、専用箱代(定価65円)が必要です。
※掲載している情報は、2025年7月時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。
ゆうパック
ゆうパックは、サイズ3辺の合計170cm以下、重さ25kgまでの荷物を発送できるサービスです。最大30万円の賠償補償がついているため、大切な荷物の発送に適しています。
料金はサイズ・重さ・宛先などで変わりますが、日本郵便の公式HPから簡単に調べられます。たとえば、東京都から愛知県まで荷物を送る場合、サイズ3辺の合計が60cm以下なら880円、最大の170cm以下であれば3,070円です。
参考:日本郵便株式会社「ゆうパック 概要・運賃」
「バクラク請求書発行」で面倒な郵送を電子化
定形郵便や定形外郵便は幅広いサイズ・厚さの郵便物を発送できるサービスですが、補償や追跡サービスが付いていない・サイズによってはポスト投函ができない、などの難点があります。そのため、業務や取引における重要な書類のやり取りには向きません。
また、請求書や発注書などを紙媒体で送ると、郵送代がかさみます。コストを削減したい、毎月の書類発行・郵送にかかる手間を削減したい、とお考えの方は「バクラク請求書発行」の導入がおすすめです。
あらゆる帳票の作成から送付までを一気通貫でシステム化できるため、大幅な業務効率化が期待できます。帳票の個別作成、一括作成などは自由自在です。
送付時においては、取引先ごとに送付方法や宛先、添付書類の有無を設定できるため、都度対応の手間やコストを削減できます。電子帳簿保存法やインボイス制度などにも対応しており、法律に遵守した取引、管理が可能です。
書類の発送にかかるコストや手間を削減したい企業さまは、ぜひ「バクラク請求書発行」の導入をご検討ください。