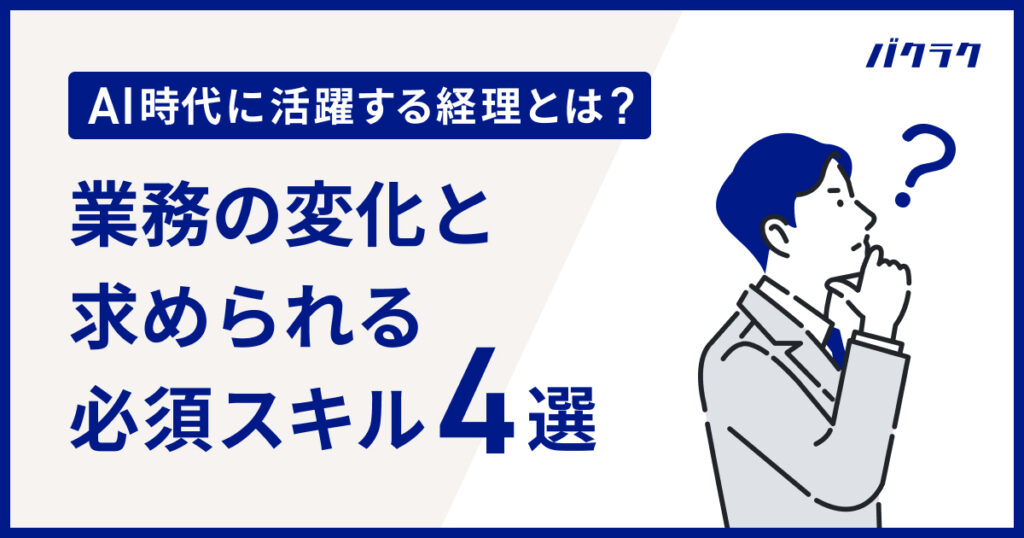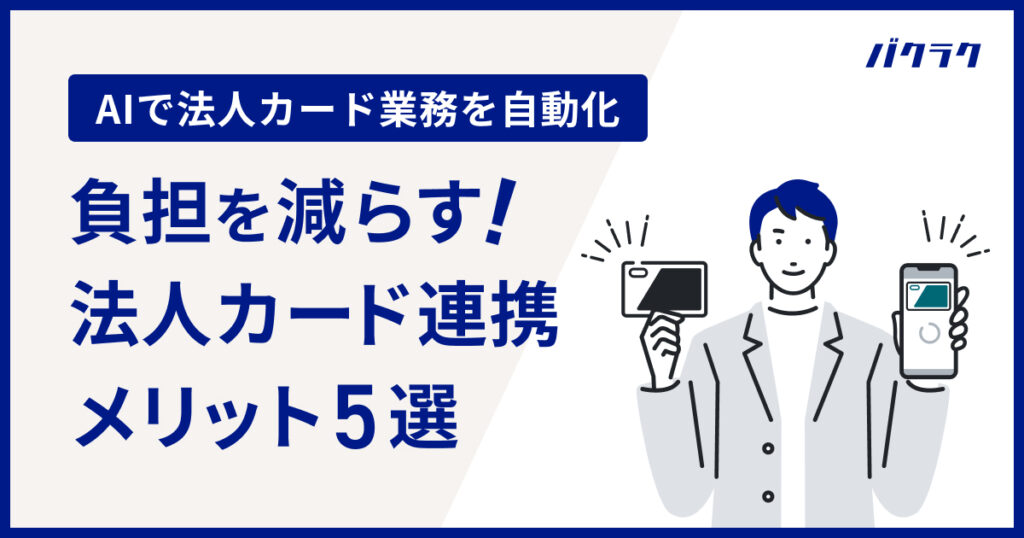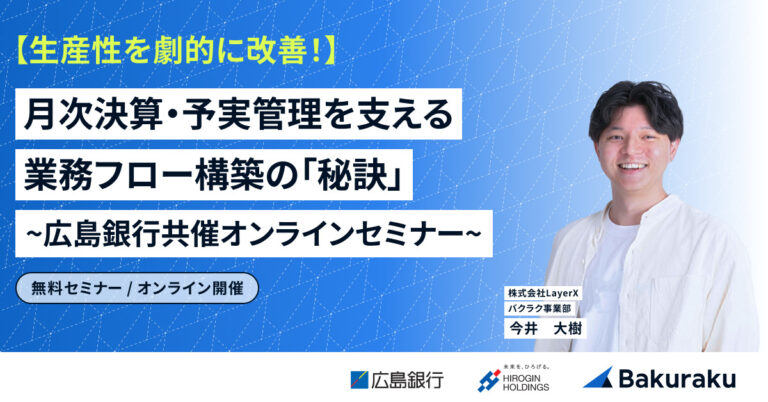封筒の郵便料金はいくら?料金表とよく使うサイズの封筒を紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-10-01
- この記事の3つのポイント
- 封筒は定形郵便物または定形外郵便物で送るのが一般的で、重量や規格によって料金が異なる
- 書類を折らずに封入する場合は角形、折っても問題ない場合は長形や洋形の封筒を使用すると良い
- 送達を急ぐ場合は速達、破損や紛失に備えたい場合は書留などのオプションをつけるのがおすすめ
取引先や顧客に封筒を送る際は、定形郵便または定形外郵便を利用するのが一般的です。しかし、封筒の大きさや内容物によっては、ほかの方法で郵送した方がコストを削減できるケースもあります。
本記事では、封筒の郵送方法と郵便料金、使用頻度が高い封筒の種類について詳しく解説します。
封筒の郵便料金はいくら?料金表とよく使うサイズの封筒を紹介
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
定形郵便・定形外郵便の料金
封筒は、定形郵便物または定形外郵便物で送るのが一般的です。いずれも料金は重量制で、2024年10月に値上げされています。
定形郵便物・定形外郵便物の新料金は、以下のとおりです。
〈定形郵便物〉
重量 | 料金 |
50g以内 | 110円 |
〈定形外郵便物〉
重量 | 規格内料金 | 規格外料金 |
50g以内 | 140円 | 260円 |
100g以内 | 180円 | 290円 |
150g以内 | 270円 | 390円 |
250g以内 | 320円 | 450円 |
500g以内 | 510円 | 660円 |
1kg以内 | 750円 | 920円 |
2kg以内 | – | 1,350円 |
4kg以内 | – | 1,750円 |
料金改定前の定形郵便物は25g以内と50g以内で異なる料金設定でしたが、新料金は重量区分が統合されています。
定形外郵便物には、規格内と規格外の2種類があります。長辺34cm以内・短辺25cm以内・厚さ3cm以内・重量1kgまでの郵便物は規格内、いずれかの規格を超えたものは規格外とみなされるため注意しましょう。
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
よく使う封筒の郵便料金は?
一般的に使用頻度が高いとされる封筒は「長形」「角形」「洋形」の3種類です。それぞれの封筒の大きさや、郵便料金について詳しく解説します。
長形
長形封筒は、A4サイズやB5サイズの書類を折り畳んで入れるのに適した縦長の封筒です。ビジネスでは、長形3号または長形4号が多く使用されます。
長形3号は、横3つ折りのA4用紙が入る大きさです。封入後、封筒の左右・天地に適度なスペースがあるため、開封時にハサミで書類を切る心配がなく、書類を出し入れしやすいのが特徴です。
長形4号には、横4つ折りのB5用紙が入ります。手書き伝票や領収書など小さい書類の送付に利用するほか、返信用封筒として同封されることも多い規格です。
長形3号と長形4号はいずれも定形郵便物で送付できますが、重量50gまたは厚み1cmを超えると、定形外郵便物の扱いになるため注意しましょう。
角形
角形封筒は、角形2号・角形A4号・角形3号などがあり、A4サイズやB5サイズの書類を折らずに封入できます。
角形2号は、クリアファイルに入れたA4用紙を封入できる大きさです。契約書や請求書、履歴書などの送付に適しています。
角A4封筒もA4用紙を折らずに封入できますが、角形2号に比べると封筒の規格が小さめです。角形3号は、B5用紙を折らずに封入できます。
折り曲げたくない重要書類を送る場合や、受取人に好印象を与えたい場合は角形封筒を使用するのがおすすめです。ただし、角形封筒のほとんどが定形外郵便に該当する大きさのため、長形封筒よりも郵便料金が高くなる点に注意しましょう。
洋形
洋形封筒は、長辺に封入口がある横長の封筒です。ビジネスシーンで利用が多いのは、洋形0号・洋形2号・洋形4号の3種類で、いずれも定形郵便物として送付できます。
洋形0号と洋形4号は横3つ折りのA4用紙、洋形2号はハガキを封入できる大きさです。
洋形封筒は長形封筒に比べて洋風な印象を与えやすいことから、招待状や挨拶状の送付に適しています。また、ダイレクトメールの発送に利用されることもあります。
請求書を送る封筒の選び方と書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。請求書の折り方や封入方法も、わかりやすく解説しています。
封筒の郵送時にオプションをつける場合の料金
定形郵便物や定形外郵便物は、郵送時にオプションを付帯できます。速達・書留・特定記録をつける場合の料金を、利用シーンとともに詳しく見ていきましょう。
速達
速達は、郵便物を早く届けられるサービスです。速達をつける場合、郵便物の重量に応じた以下の料金が基本料金に加算されます。
重量 | 加算料金 |
250gまで | +300円 |
1kgまで | +400円 |
4kgまで | +690円 |
速達は、書類の急な送付が必要となったときや、送付期限が迫っているときに役立つサービスです。
利用の際は、縦長封筒の場合は表面の右上部分、横長封筒の場合は封筒の右側部分に赤い線を引いて、郵便窓口へ差し出します。加算料金分の切手を貼付して封筒に赤い線を引き、ポストに投函しても問題ありません。
書留
書留は、郵便物の引受けから配達までの過程を記録するサービスです。送達中に破損や紛失があった場合は、損害要償額の範囲内で実損額が賠償されます。
書留の種類と加算料金、損害要償額は以下のとおりです。
種類 | 加算料金 | 損害要償額 |
一般書留 | +480円 | 10万円まで (5万円増額ごとに23円加算/上限500万円) |
現金書留 | +480円 | 1万円まで (5,000円増額ごとに11円加算/上限50万円) |
簡易書留 | +350円 | 5万円まで |
書留は、重要書類を送る場合や、破損・紛失に備えたい場合に適しています。
利用の際は、郵便窓口に置かれている「書留・特定記録郵便物等差出票」に必要事項を記入して、封筒とともに差し出しましょう。
特定記録
特定記録は、郵便物の引受けを記録するサービスです。定形郵便物や定形外郵便物に特定記録をつける場合、基本料金に210円が加算されます。
請求書や納品書などの書類を送った証明が必要な場合や、懸賞品を送る場合に利用するとよいでしょう。料金受取人払を利用できるため、顧客や取引先から書類を回収するときも役立ちます。
特定記録を利用する際も「書留・特定記録郵便物等差出票」に必要事項を記入し、封筒とともに郵便窓口へ差し出しましょう。
封筒を郵送する他の方法
封筒は、定形郵便物や定形外郵便物以外の方法でも送付できます。本章では4種類の郵送方法について、特徴や料金、利用シーンなどを詳しく解説します。
レターパック
レターパックは、A4サイズ・4kgまでの荷物を専用封筒に入れて送れるサービスです。追跡サービスがついており、郵送後に配達状況を確認できます。
レターパックには、レターパックプラスとレターパックライトの2種類があり、前者は対面による手渡し、後者はポストに投函される点が主な違いです。それぞれの料金は以下のとおりです。
種類 | 新料金 (2024年10月以降) | 旧料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
レターパックプラス | 600円 | 520円 | 80円 |
レターパックライト | 430円 | 370円 | 60円 |
旧料金のレターパックは、新料金との差額分の切手を貼付することで使用できます。郵便窓口で手数料を支払い、新しい封筒に交換してもらうことも可能です。
レターパックは、領収書や請求書などの信書、業務用サンプル、カタログなどの送付に利用できます。ただし、レターパックライトには、厚さ3cmまでの制限があるため注意しましょう。
クリックポスト
クリックポストは、小型荷物を全国一律185円で送れるサービスです。追跡サービスがついており、土日・休日も含めて毎日配達されます。
クリックポストを利用する際は「Amazonアカウント」または「Yahoo! JAPAN ID」による事前登録およびクレジットカード決済が求められます。封筒の大きさに規定があり、重量1kg以内、厚さ3cm以内の決まりがある点にも注意が必要です。
クリックポストの主な利用シーンは、カタログやパンフレット、CD・DVDなどの送付です。信書は送れないため注意しましょう。
ゆうメール
ゆうメールは、厚さ3cm・重量1kgまでの印刷物やCD・DVDなどを、比較的安価に送れるサービスです。ゆうメールの料金は以下のとおりです。
重量 | 料金 |
~150g | 180円 |
~250g | 215円 |
~500g | 310円 |
~1kg | 360円 |
ビジネスでは、書籍やカタログの送付に適しています。印刷を利用していないものや、信書は送付できないため注意が必要です。
ゆうパケット
ゆうパケットは、1kgまでの小さな荷物を追跡付きで送れるサービスです。発送時はポストに投函でき、土日・休日も含めて毎日配達されます。
ゆうパケットの料金は、以下のとおりです。
厚さ | 料金 |
1cm以内 | 250円 |
2cm以内 | 310円 |
3cm以内 | 360円 |
ゆうパケットは、カタログやパンフレットなどの小冊子、CD・DVDの送付に適しています。ただし、長辺+短辺+厚さ=60cm以内(長辺34cm以内・厚さ3cm以内)の規格があるため注意しましょう。
「バクラク請求書発行」で郵送コストを削減できる
封筒は、定形郵便物または定形外郵便物で送るのが一般的です。急ぐ場合は速達、破損や紛失に備えたい場合は書留など、必要に応じてオプションの付加を検討しましょう。
封筒を郵送する際、レターパックやクリックポスト、ゆうメール、ゆうパケットを利用する選択肢もあります。封筒の大きさや重量、内容物などを確認の上で、コストを極力抑えられる郵送方法を選ぶことが重要です。
郵便料金の値上げによる郵送コストの問題にお悩みの方は、請求書発行システムの導入がおすすめです。バクラク請求書発行は、帳票の作成・稟議・送付・保存を一気通貫で管理でき、作成した書類は取引先に応じた方法で送付できます。
PDFやリンク送付だけでなく、郵送代行も利用できるため、取引先が電子化に未対応でもスムーズな取引が可能です。バクラク請求書発行に興味をおもちの方は、以下のページをご覧ください。