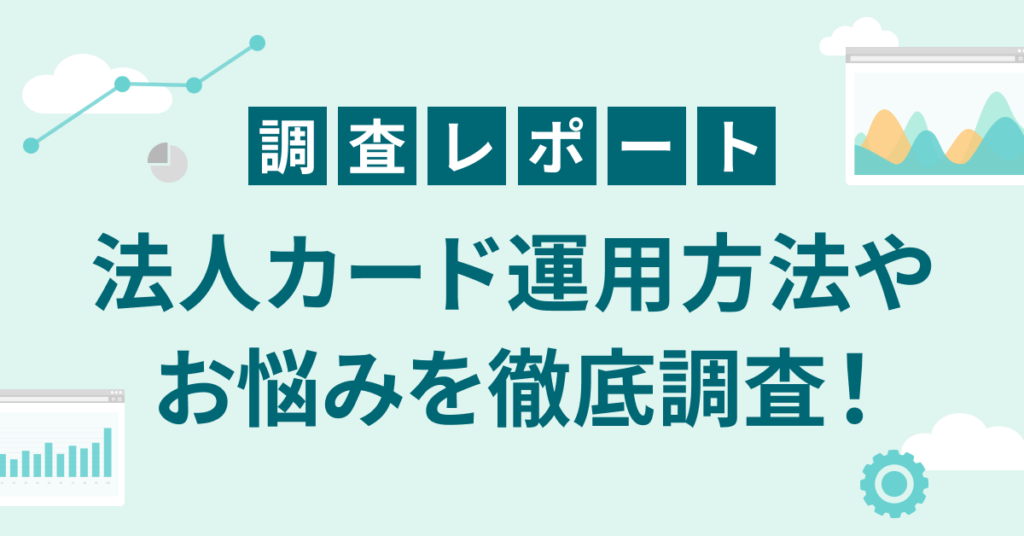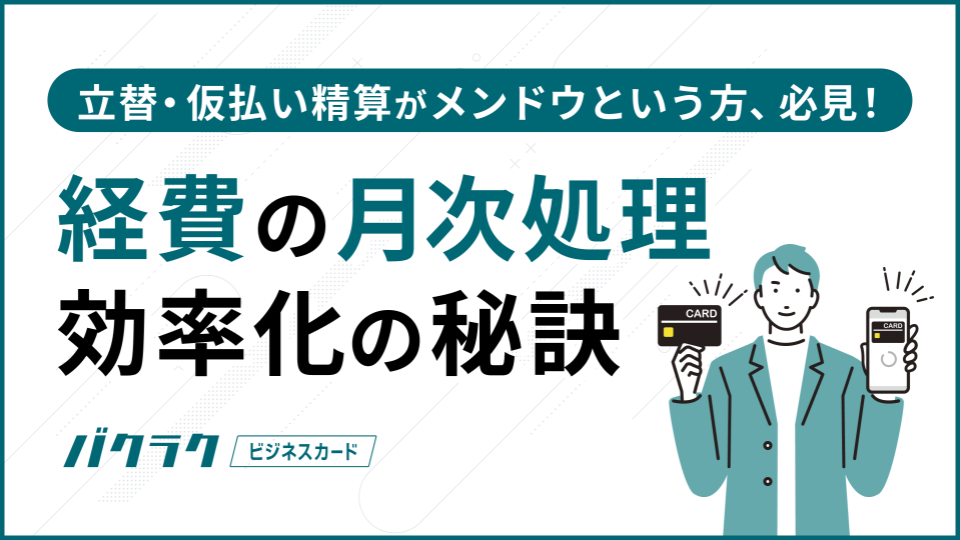2025年4月から改正旅費法が施行!国家公務員の旅費精算のDXはどう進めるべき?
- この記事の3つのポイント
- 2025年4月から国家公務員の旅費は定額支給から「実費精算」へ変更され、自己負担が軽減される仕組みに変わった
- 出張命令や精算はすべて電子申請され、領収書は電子化が求められるなどDXと業務効率化の加速が必要になる見込み
- 「バクラクビジネスカード」であれば改正旅費法に対応しつつ、業務効率とガバナンス強化を両立できる
2025年4月1日、国家公務員の定額支給制度が見直され、「実費精算(上限付き)」制度に移行しました。これにより、国家公務員であっても宿泊費や交通費などを実際にかかった金額で精算できるようになりました。
本記事では、この新しい旅費法ついて「改正内容の概要」と「公務員の業務にどう影響するか」について解説します。合わせて、本改正に際して活用を最大化できる法人向けクレジットカードについても案内します。

バクラクビジネスカードなら社員専用カードを下記3ポイントで安全・効率的に運用できます。
①クレジットカードごとに上限金額・利用期間・決済先の条件を個別設定できる
②万が一カードを紛失した際も管理者側で即時利用停止が可能
③カード発行枚数無制限だから社員ごとや部署・チームごとで専用カードを所持できる
\簡単30秒ダウンロード!製品資料をご覧ください/
2025年4月から改正旅費法が施行!国家公務員の旅費精算のDXはどう進めるべき?
旅費法の内容の新旧対照表
25年3月までの旧旅費法と、4月以降の新しい旅費法の内容の違いは以下の通りです。
| 項目 | 旧旅費法(改正前) | 改正旅費法(2025年4月施行) |
| 支給方式 | 定額支給(宿泊料・日当などを地域や職位に応じて一律支給) | 実費精算方式(領収書等に基づき実際の費用を精算) |
| 宿泊費の対応 | 支地域ごとの定額上限あり。高騰しても定額を超える補填なし。 | 実際の宿泊費を精算可能(上限は設けられる可能性あり) |
| 海外出張 | 地域別の定額制。宿泊費が高額でも定額範囲内で自己負担が生じる | 実費精算により高額な海外宿泊費にも対応可能 |
| 調整・改定フロー | 各省庁+財務省間の協議が必要。改定に時間がかかる | 実費ベースのため柔軟な運用が可能。頻繁な見直し不要に |
| 職員の負担 | 支給額と実費の差額を職員が自己負担するケースあり | 実費精算により自己負担リスクが軽減 |
| 事務手続き | 一定の単純さはあるが、精緻な実態反映は難しい | 領収書確認など事務負担は増加。ただしクラウド精算等で軽減可能 |
| 公平性・透明性 | 同じ地域でも実際の費用と支給額が乖離しやすい | 実費ベースにより、出張内容に即した公平な精算が可能に |
改正旅費法の最大のポイントは、支給方式が「定額」から「(上限付き)実費精算」に変わった点です。これにより、宿泊費や出張費が実際の利用額に基づいて支給され、自己負担の発生が抑えられる仕組みに変更されました。
また、従来のように金額改定のたびに各省庁と財務省の協議が必要だった煩雑な調整プロセスが不要となり、制度運用の柔軟性が大幅に向上した点も特筆すべきポイントです。一方で、領収書などに基づく精算処理が必須となるため、事務負担の増加には業務効率化の工夫が求められる状況になったとも見ることができます。
改正旅費法の背景 – なぜ実費精算に変わった?
旅費法が改正に至った経緯について、その主な3つの理由を解説します。
①定額支給の限界と事務負担の増加
元々公務員の経費精算に用いられてきた「定額支給制度」には限界があり、現在の出張実態に合わないケースが増えています。なぜなら、物価や宿泊費の上昇により、定額内での出張が困難になってきており、結果として職員が実費との差額を自己負担するケースも生じているからです。
たとえば、都市部ではダイナミックプライシングなどでビジネスホテルの価格が上昇しており、定額での宿泊が難しい場面が増加しています。また、海外出張では1泊数万円以上の費用がかかることも珍しくありませんが、定額支給額との差が大きいため、制度との乖離が問題視されています。
このような背景から、旅費制度を現状に合わせて柔軟に対応できるよう見直す必要があったのです。
②働き方改革と制度のミスマッチ
旧旅費法の制度は、現代の多様化した働き方に十分対応できていません。なぜなら、旧来の制度設計が出張の出発地を「所属庁舎(職場)」と想定しており、テレワークや自宅からの直行など、新しい勤務形態に即していないからです。
たとえば、自宅から直接出張先に向かった場合でも、制度上の起点は職場と見なされるため、実際の移動距離や費用とは乖離した支給額となり、職員の負担が生じます。
このように、柔軟な働き方が一般化する中で、出張旅費制度も実態に即して見直すことが必要とされたことも、法改正の背景の1つです。
③公務員が出張をする際の経費申請の複雑性
申請手続きの煩雑さも、旅費法改正の大きな要因の一つとなりました。その理由は、定額を超えた費用の立て替え精算が制度上は可能であっても、申請書類の作成や添付資料の提出、複数段階の承認などが必要で、現場の負担が非常に大きかったためです。
実際には、こうした手続きを回避し、やむを得ず自己負担を選ぶ職員も少なくありませんでした。結果として、制度は存在していても、実態としては活用されにくい状況に陥っていたのです。
そのため、制度の信頼性と公平性を担保するには、申請のしやすさを含めた運用面の改善が不可欠であり、今回の改正ではその課題にも対応が図られました。
【要点まとめ】改正旅費法の5つのポイント
改正旅費法の要点を5ポイントで解説します。
1. 宿泊費・引越し費用は「実費精算(上限付き)」に
これまでの定額支給制度から転換し、宿泊費や引越し費用は原則「実費精算」となりました。ただし、都道府県ごとに上限額が設定されており、たとえば東京では19,000円、大阪13,000円、福岡18,000円など地域の実勢価格を反映した範囲で支給されます。
また、引越し費用も新旧の居住地間の距離等に応じた実費支給となり、職員の自己負担が抑えられる設計です。
2. 日当制度の見直し
出張手当(旧:日当)については、昼食代を除いた実費相当の「宿泊手当」として再構成され、宿泊時の朝食・夕食などに対応する金額が支給されます。具体的な金額は政令・省令で定められており、支給額を超える食費等が発生した場合でも、追加の支給はされず、超過分は自己負担となります。
3. 交通費はすべて実費ベースに
交通費の精算はすべて実費ベースとなり、特急料金の支給に関する「100km以上」の制限は撤廃されました。
また、これまで使用されていたタクシー代の定額支給(1kmあたり37円)も廃止され、実際に支払った運賃を領収書に基づいて精算する形式に統一されます。航空券やJRなどの交通機関の利用もすべてこのルールに従います。
4. 完全デジタル化へ|申請は電子システム化
出張命令書や精算書の紙運用は廃止され、手続きはすべて電子申請システムに一本化されます。これにより、申請から承認までのプロセスが迅速化されるだけでなく、不正チェック機能の導入によりガバナンスの強化にもつながります。職員・管理者双方の業務効率向上が期待される改正です。
5. 職員の立替負担を軽減
職員が出張費や引越し費用を一時的に立て替える負担を軽減するため、旅行代理店や引越し業者、カード会社への「直接支払い」が可能になりました。これにより、個人での精算申請や立替金の管理が不要となり、現場の事務負担と心理的負担の双方が大きく軽減されます。
改正旅費法を受け公務員に求められる業務改革とは?
今回の旅費法改正を機に、公務員の業務の現場で推進すべき業務改善を紹介します。
総務・財務部門でのマニュアル整備と職員教育
改正旅費法のスムーズな運用には、総務・財務部門によるマニュアル整備と職員への教育が重要です。なぜなら、実費精算方式や電子申請システムの導入により、従来とは異なる手順や判断基準が必要となるため、現場職員が正しく対応するための指針と知識が求められるからです。
たとえば、精算可能な費目や領収書の取り扱い、上限額の確認方法などを明記した新マニュアルを整備し、それをもとに全職員へ研修を実施することで、制度の誤解や申請ミスを防ぎ、業務効率と透明性の両立が図れます。
このように、制度対応の要となる部門が率先して準備を進めることが、現場全体のスムーズな適応につながります。
電子申請システムの導入とテスト運用
電子申請システムの導入と事前のテスト運用は、改正旅費制度の実効性を確保する上で不可欠です。紙ベースからデジタルへの移行により、申請・承認・精算のすべてが電子化されるため、業務フローや操作方法に慣れていない職員が混乱する可能性があるからです。
たとえば、システム導入直後に本運用を開始すると、不具合や入力ミスが相次ぐリスクがありますが、あらかじめテスト運用期間を設け、実際の出張を想定した模擬申請を行うことで、課題を洗い出し、マニュアル整備や職員教育に反映させることができます。
このように、導入だけでなく運用前の検証フェーズを重視することが、制度改正を現場に定着させる鍵となります。
旅費支給規程の改訂と社内周知
旅費支給規程の改訂とその社内周知は、制度改正の実効性を担保するために欠かせません。改正内容が実費精算や上限設定、申請フローの変更など多岐にわたるため、現場での誤認や運用ミスを防ぐには、ルールを明確化し全職員に理解させる必要があるからです。
たとえば、支給上限や必要書類、電子申請での入力項目などを新たに反映させた規程を作成し、イントラネット上で公開するとともに、説明会やQ&A資料を通じて各部署へ確実に伝えるといった取り組みが効果的です。
このように、制度の土台となる規程を正確に整備し、その内容を漏れなく周知することが、安定した制度運用の前提となります。
領収書の電子化と保管体制構築
領収書の電子化とそれに伴う保管体制の構築は、改正旅費制度の実務運用において極めて重要です。なぜなら、すべての費用が実費精算となる中で、支給根拠となる領収書の信頼性と管理体制が制度の公正性と監査対応力に直結するからです。
たとえば、紙の領収書をスキャンして電子データとして保存し、電子申請システムと連携させて管理する運用に切り替えることで、検索性や保管コストの改善が期待できるほか、ガバナンス強化にもつながります。また、保管期間や形式などのルールも明確に定めておく必要があります。
このように、電子化対応は単なる業務効率化にとどまらず、制度の信頼性を支えるインフラとして整備すべき項目です。
改正旅費法に即し公務員のDXを一気に促進「バクラクビジネスカード」
改正旅費法に対応するうえで、実費精算や電子申請への移行に加え、現場の業務負荷をいかに軽減するかが各組織にとって大きな課題となっています。こうした実務上の課題に対して、バクラクビジネスカードは単なる法人カードにとどまらない、非常に実用性の高いソリューションです。
まず、職員の立替精算業務を根本からなくすことができます。カードでの直接決済により、立替・仮払処理が不要になり、バクラク経費精算との連携によって申請・承認・証憑提出まで一気通貫で管理可能になります。また、カード利用明細と領収書はAIで自動突合され、スマホアプリでの証憑提出にも対応しているため、領収書回収の手間や突合作業の負担も大幅に削減できます。
また、カード利用明細と領収書はAIで自動突合され、スマホアプリでの証憑提出にも対応しているため、領収書回収の手間や突合作業の負担も大幅に削減できます。
さらに、バクラクビジネスカードは「利用金額・期間・決済先・通貨」ごとの細やかな決済制限機能を備えており、出張費の不正利用や上限超過をシステム側で統制可能です。この機能は特に「都道府県別上限金額」が導入された改正旅費法のもとでは、現場管理の実効性を高めるうえで非常に有用です。
このように、バクラクビジネスカードは改正旅費法で求められる「実費精算・電子申請・領収書管理・法令対応」のすべてに直接的な解決策を提供しており、制度改正の趣旨を現場レベルで確実に定着させるための基盤となるサービスです。運用効率とガバナンスを同時に実現できるこのカードは、旅費業務の最適化を図るうえで、導入を検討すべき最有力な選択肢と言えるでしょう。

2025年4月から施行された改正旅費法によって、全国の自治体で、法人向けクレジットカードの導入の動きが加速しています。導入はしたいと思いつつも、運用設計のハードルが高く、導入検討で止まっている自治体が多いのが現状です。
法人カード導入時の不安を払拭するための法人向けクレジットカードの選び方や、実際に法人向けクレジットカードを導入された自治体のみなさまの活用事例などを紹介しています。
- セキュリティ面で安心できる法人向けクレジットカードをお探しの方
- 全国の自治体で導入実績のある法人向けクレジットカードをお探しの方
- 法人向けクレジットカードの導入を検討しているが、運用設計のハードルが高くお悩みの方
\簡単30秒ダウンロード!資料をご覧ください/