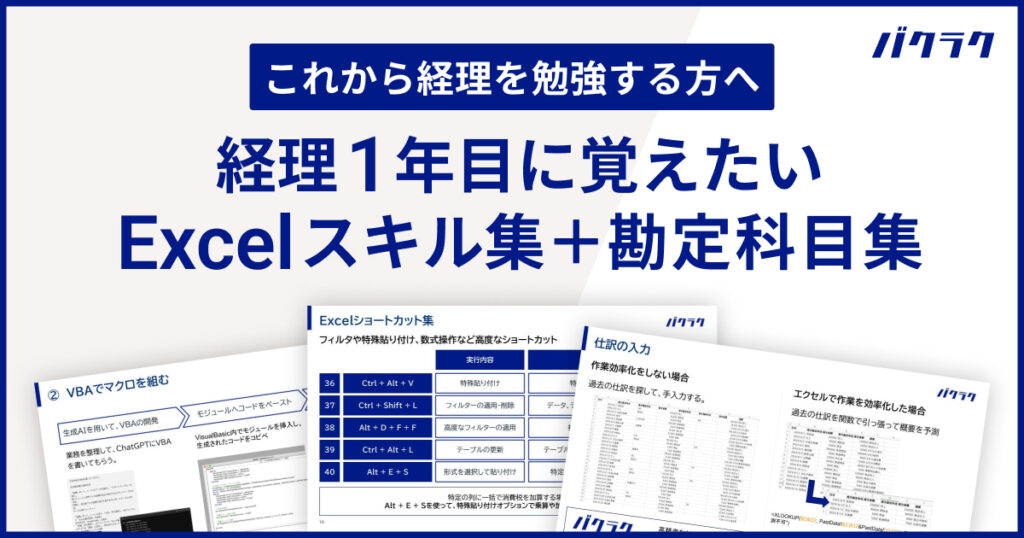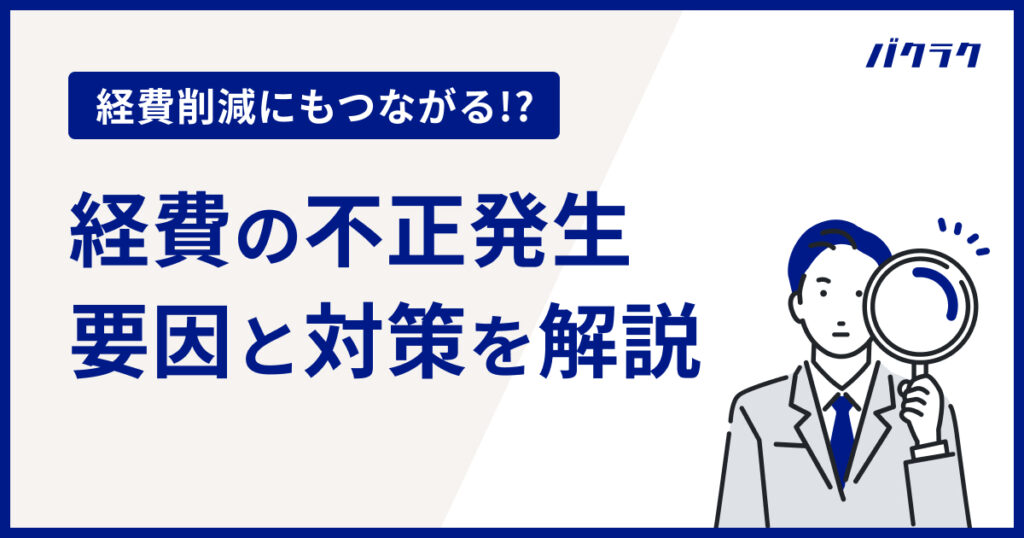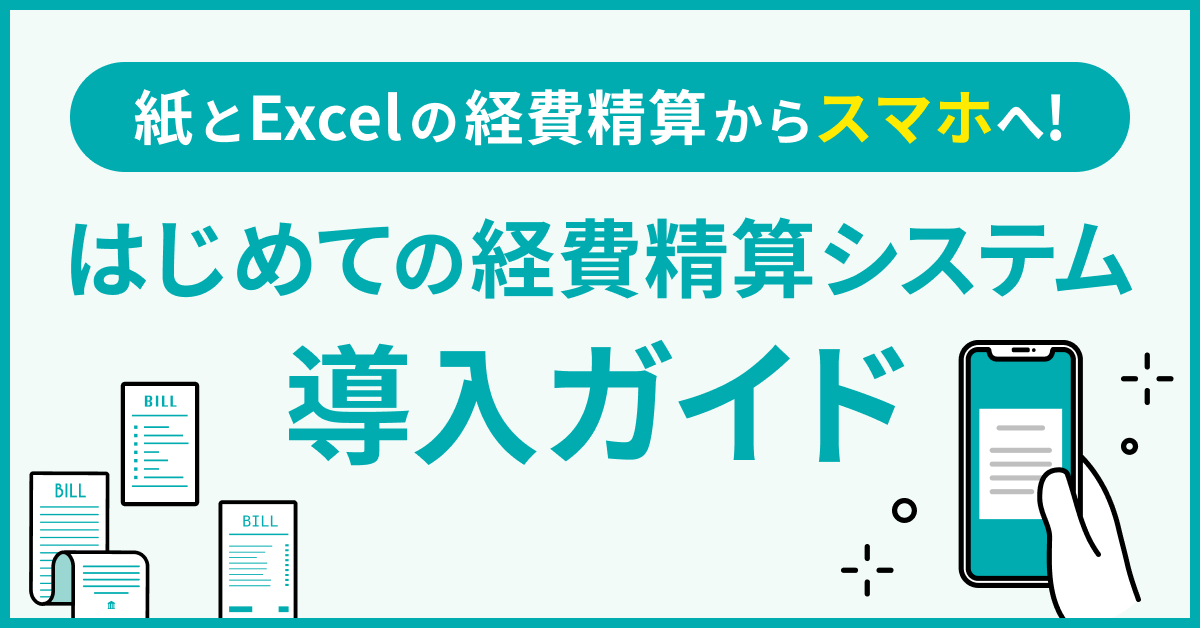リバースチャージ方式とは?対象となる取引や仕訳例をわかりやすく解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-09-09
- この記事の3つのポイント
- リバースチャージ方式は、国外事業者のサービスに、国内事業者が消費税を申告・納税する仕組み
- リバースチャージ方式の取引は、事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供がある
- 仕訳では、仮払・仮受消費税を同時に記録し、決算時に控除対象外の差額を雑損失などで処理する
リバースチャージ方式とは、従来の「サービス提供者が納税」という原則を逆転させ、サービス受領者に納税義務を課す制度です。国外取引のある会社にとっては重要な制度といえるでしょう。
本記事では、リバースチャージ方式の概要から対象取引の具体例、実務で必須の仕訳法まで、事業者が知るべき全容を体系的に解説します。
リバースチャージ方式とは?対象となる取引や仕訳例をわかりやすく解説
リバースチャージ方式とは?
リバースチャージ方式とは、役務の提供側ではなく、役務の提供を受けた事業者が消費税の申告・納税義務を負う制度です。
通常、消費税はサービス提供者が顧客から預かり納税しますが、リバースチャージ方式では「対価を支払った側」が直接税務署に申告・納付します。
具体的には、国外事業者から特定の役務提供を受けた国内事業者が、当該取引について自ら消費税額を計算し納税します。
リバースチャージ方式は、国外事業者への課税執行が困難なデジタル取引(電子書籍配信等)の急増に対応するために導入されました。制度の核心は「課税権の所在」をサービス提供側から受領側へ転換した点にあり、国際的な課税の公平性を確保することが目的です。
参考:国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
リバースチャージ方式が適用される取引
リバースチャージ方式の適用対象は、主に2種類の取引に限定されます。
これらの取引は、役務の性質や提供形態によって明確に区分されているため、注意が必要です。本章では、各取引について詳述します。
事業者向け電気通信利用役務の提供
「電気通信利用役務の提供」とは、インターネット等の通信回線を介して提供されるデジタルサービスのことです。
具体的には、電子書籍・音楽・映像・ゲームなどのデジタルコンテンツの配信、クラウドサービスによるデータ保存やソフトウェア提供があります。ほかにも、オンライン広告の配信、ECサイトや予約サイトの利用サービス、オンライン英会話などが該当します。
ただし、通信回線の提供そのものや、商品の販売に付随する通信の利用、領収書の送付などは対象外です。
サービスの性質や契約条件から、利用者が法人や事業者に限定される取引は「事業者向け電気通信利用役務の提供」と見なされ、消費税のリバースチャージ方式が適用されます。
たとえば、企業が業務用に契約する専門的なクラウドサービスなどが該当します。一方、一般消費者も利用できるサービス(例:AWS、Google Apps、Adobe CCなど)は含まれません。
また、ソフトウェアの開発や市場調査のように、インターネットの利用が主たる役務ではない取引も「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当しません。対象かどうかの判断には、契約内容や利用実態を丁寧に確認することが重要です。
特定役務の提供
「特定役務の提供」とは、国外の事業者が日本国内で提供する特定のサービスのうち、芸能人やスポーツ選手などの活動を主な内容とし、事業者間で提供されるものを指します。
ただし、不特定多数を対象としたサービス提供はこれに含まれません。たとえば、海外の俳優が日本国内で映画や舞台に出演したり、国外のプロアスリートが日本で開催される試合やイベントに出場したりする場合は除外されます。
なお、これらの特定役務には電気通信を利用した配信などの電気通信サービスも含まれません。サービスの内容や契約相手が明確に限定される点に注意しましょう。
リバースチャージ方式導入に至るまでの背景
以前は、海外企業が提供する電子書籍やオンライン広告などのサービスには日本の消費税が課されていませんでした。課税されるのは、同様のサービスを国内事業者が提供した場合のみです。
このような制度上の差異が、価格競争において国内事業者に不利に働いていたため、是正が求められた経緯があります。
上記のような背景を受け、2015年10月に消費税法が改正され、インターネットを介した役務提供(電気通信利用役務)の課税基準が変更されました。
従来の「提供者の所在地」ではなく、「サービスを受ける側の所在地」に基づいて課税の有無が判断されるようになったのです。そして、国外事業者による国内向けサービスにも消費税が課されることになりました。
課税基準の変更により、国内の消費者向けサービスには国外事業者が直接申告・納税する義務が生じました。国内の事業者向け取引については「リバースチャージ方式」が導入され、サービスを受けた側が代わりに消費税を納める形が取られています。
しかし、海外大手企業の影響を受ける広告業界などでは、公平性の確保という意義はあるものの、実務負担やコスト増といった課題も指摘されています。
リバースチャージ方式における経過措置
リバースチャージ方式は、すべての事業者に適用されるわけではありません。課税売上割合が95%未満で、一般課税を選択している事業者のみが対象です。簡易課税を選択している事業者や、課税売上割合が95%以上の事業者は対象外です。
また、外国人旅行者向けの免税販売では、商業施設内に免税手続きカウンターを設置し、承認を受けた業者に手続きを委託する制度があります。しかし、不正な国内転売が問題となっており、今後の対策が検討されています。
参考:国税庁「リバースチャージ方式による申告を要する者」
リバースチャージ方式での仕訳例
国内企業が海外のクラウドサービスを月額22,000円で利用し、請求書に「リバースチャージの対象」と明記されていた場合を見ていきましょう。
上記の支払いは課税仕入れとして扱われます。支払い時には、クラウドサービスの月額料金22,000円に加え、仮払消費税2,200円と仮受消費税2,200円をそれぞれ仕訳する必要があります。
決算時には、課税売上割合が90%であれば、2,200円のうち1,980円が仕入税額控除として認められ、差額の220円が納税対象です。差額は「雑損失」などの科目で処理します。
【取引の概要】
- 支払先:国外事業者(インターネットサービス)
- 利用料:22,000円(税抜)
- 消費税:10%(2,200円)
- 課税売上割合:90%(仕入税額控除は2,200円×90%=1,980円)
≪取引発生時の仕訳例≫
借方 | 貸方 | ||
支払手数料 | 22,000円 | 現金 | 22,000円 |
仮払消費税 | 2,200円 | 仮受消費税 | 2,200円 |
≪決算整理時の仕訳例(仕入税額控除を反映)≫
借方 | 貸方 | ||
仮受消費税 | 2,200円 | 現金 | 2,200円 |
雑損失 | 220円 | 未払消費税 | 220円 |
※雑損失(220円)は、控除できなかった消費税(2,200円-1,980円)の処理です。
インボイス制度によるリバースチャージ方式への影響は?
令和5年10月からのインボイス制度導入で、登録国外事業者制度は廃止されました。
新制度下では、国外事業者が「適格請求書発行事業者」として登録されている場合、国内事業者は請求書に記載された消費税額を仕入税額控除できます。
具体的には、登録国外事業者は「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない限り、自動的に適格請求書発行事業者とみなされます。
リバースチャージ方式が適用される取引では、適格請求書があれば仮払消費税の全額を控除可能です。ただし、請求書に「リバースチャージ対象」の明記がない場合、税務調査で否認リスクがあるため、契約書での事前確認が推奨されます。
リバースチャージ方式の対象取引か正しく判断しよう
リバースチャージ方式とは、国外事業者からのサービス提供に対し、受け手である国内事業者が消費税の申告・納税を行う制度です。
2015年の制度改正で導入され、電子書籍やクラウドサービス、オンライン広告などが対象です。特に、法人向けのサービスや、国外芸能人・スポーツ選手による特定の役務提供が該当します。
課税売上割合が95%未満の一般課税事業者にのみ適用され、仕訳では、仮払・仮受消費税を同時に記録し、決算時に控除対象外の差額を「雑損失」などで処理します。
課税対象の判断には契約内容の確認が重要です。取引がリバースチャージ方式の対象かどうか、正確に判断しましょう。