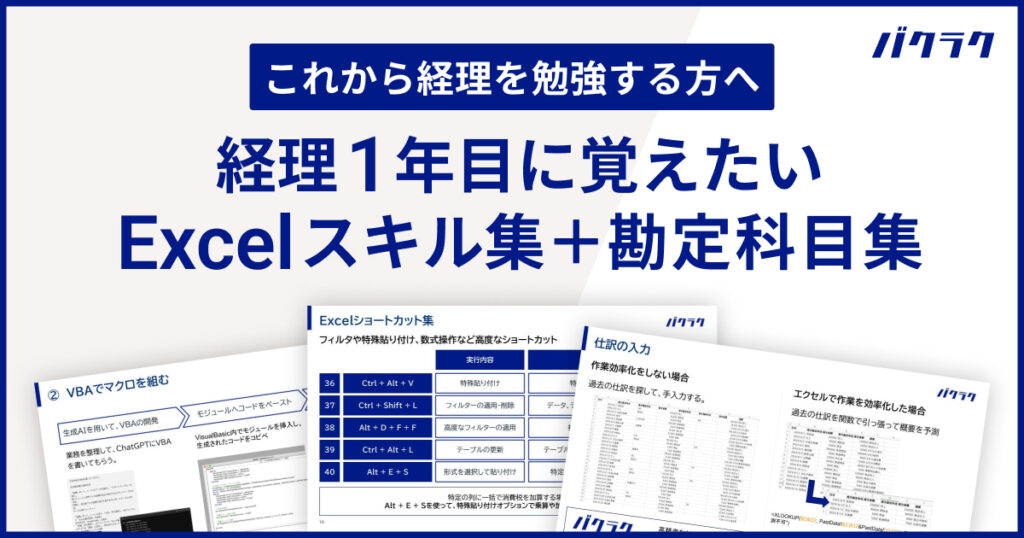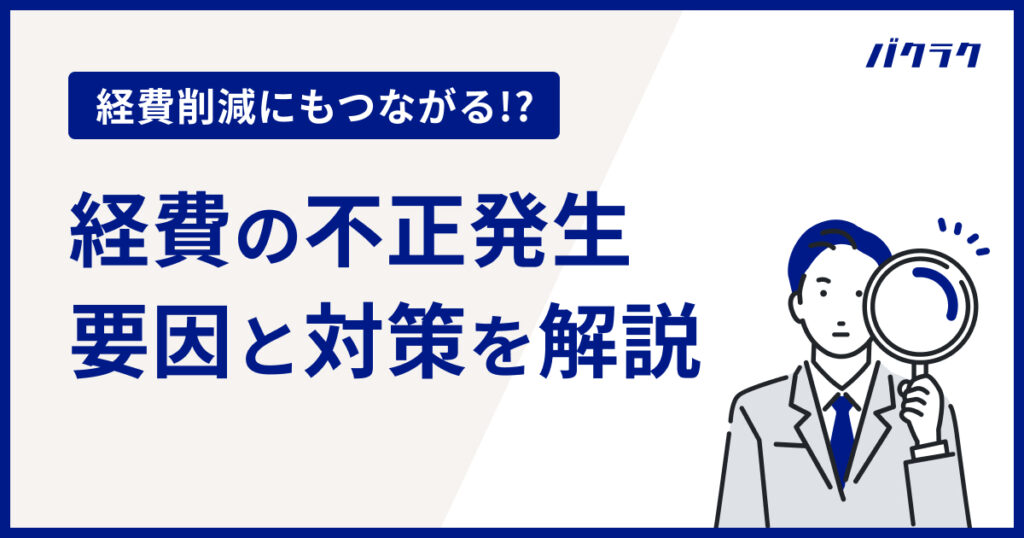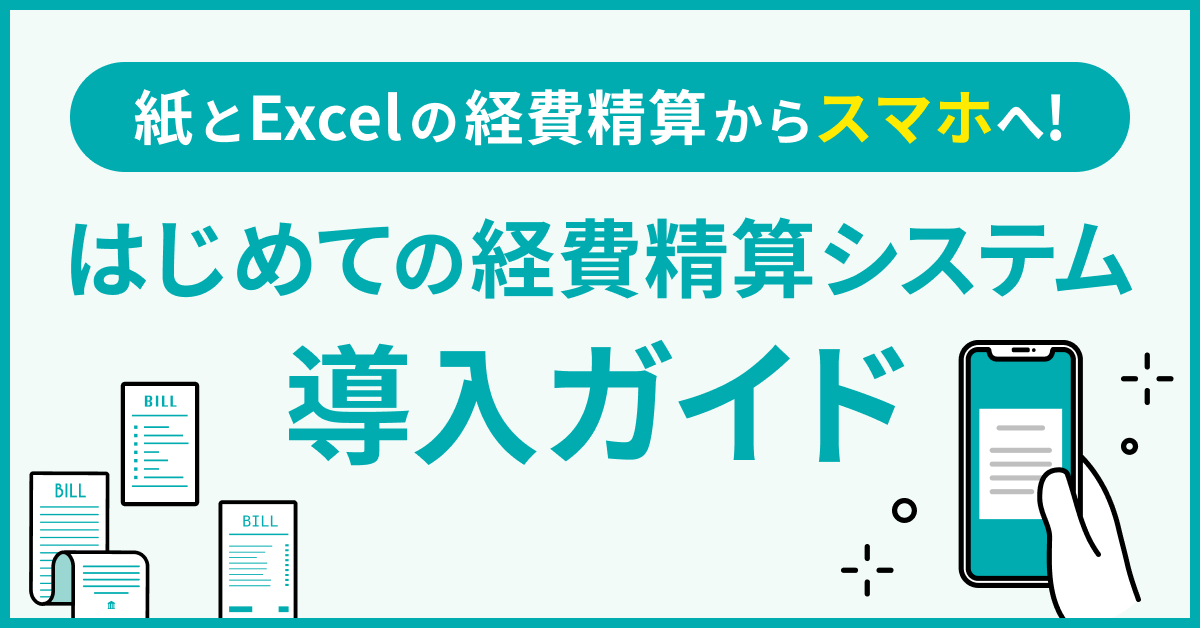固定資産税は経費にできる!勘定科目や仕訳例・注意点をわかりやすく解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-02-21
- この記事の3つのポイント
- 「固定資産税」とは、土地や家屋などの「固定資産」を所有している人が納める地方税
- 固定資産税は経費にできる
- 固定資産税の税額は「課税標準額×税率(多くは1.4%)」で計算する
固定資産税は経費計上できるため、正しい勘定科目で帳簿に記載する必要があります。正確な仕訳で処理を行い、企業の税負担を減らしましょう。
この記事では固定資産税の概要と、勘定科目や仕訳例を解説しています。固定資産税を経費計上する際に役立ててください。
固定資産税は経費にできる!勘定科目や仕訳例・注意点をわかりやすく解説
固定資産税とは?固定資産の種類
「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で土地や家屋などの「固定資産」を所有しいる人が納める地方税です。主な用途は、地域の公共サービスや施設整備などです。
固定資産税の対象となる固定資産の種類には、土地・家屋・償却資産が含まれます。それぞれの詳しい内容は以下の表のとおりです。
| 土地 | 住宅地、田畑、池沼、山林など |
| 家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫など |
| 償却資産 | 備品、運搬具、構築物など |
参考:総務省「固定資産税」
企業がこれらのものを所有していると、それぞれに税額が課せられていることになるため、間違いのないよう帳簿に計上をしましょう。
固定資産税の勘定科目
固定資産税は、法人税法上で経費計上が認められます。経費として計上しておくことで、法人税の負担を減らせるでしょう。
ただし、同じ税金でも法人税・所得税・延滞税・過怠税などは経費計上できないので注意が必要です。
法人が固定資産税を記帳・仕訳する際の勘定科目は、一般的に「租税公課」を使用します。
租税とは国税・地方税など税金のこと、公課とは税金以外で国・地方公共団体が徴収する金銭のことです。つまり租税公課とは、税金や各公共団体に納める公的な目的で支払った経費を指します。
租税公課について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
固定資産税の計算
固定資産税は何をもとに計算されるのか、疑問に思うケースもあるかもしれません。ここでは固定資産税の計算方法を確認してみましょう。
固定資産税の計算式
固定資産税の計算式は、以下のとおりです。
| 課税標準額×税率(多くは1.4%) |
固定資産税の税率は、一般的に1.4%とされています。ただし自治体によって異なる場合があるため、疑問があれば各自治体のウェブサイト・窓口で確認してみましょう。
参考:総務省「固定資産税」
固定資産の評価額
前項の計算式で固定資産税を計算するには、課税標準額(住民税の計算の基礎となる金額)が必要です。
課税標準額は、固定資産評価額(土地・建物の評価額)をもとに決定されます。固定資産評価額は、総務大臣による基準に基づいて各自治体により評価されます。
土地、家屋、償却資産それぞれの評価方法は、以下の表のとおりです。
| 土地 | 売買実例価格を基本に評価、宅地については地価公示価格などの7割を目途に評価 |
| 家屋 | 再建築価格方式により評価 |
| 償却資産 | 取得価格を基に、経過年数から評価 |
固定資産の評価額の確認方法
固定資産評価額を確認するには、納税通知書の課税明細書を見るとよいでしょう。
納税通知書が手元にない場合、固定資産課税台帳を閲覧することでも評価額を算出できます。もしくは、自治体の窓口や郵送で固定資産評価証明書を入手すると、固定資産税の計算の元となる固定資産評価額が明確にわかり便利です。
固定資産税の納付
固定資産税を経費計上するときは、固定資産税の納付についても理解しておきましょう。本章では、固定資産税の納付先や時期、方法を解説します。
固定資産税の納付先
固定資産税は、固定資産のある市町村の自治体に納付します。ただし、東京23区内は東京都に納付すると定められています。納付先は固定資産税の納付書にも記載されているため、確認しておくとよいでしょう。
また固定資産税の分類は、市町村では市町村税、東京都では都税に該当します。
固定資産税の納付時期
固定資産税の納付時期は、5月・7月・12月・翌年2月の年4回が一般的です。納税義務者に送付される納税通知書に、納付期限が記載されています。市町村によって納付時期が異なる場合があるため、納税通知書を必ず確認しましょう。
また固定資産税は企業の方針によって、一括納付も可能です。一括納付の期限も同様に納付書で確認してください。
固定資産税の納付方法
固定資産税の主な納付方法は、下記のとおりです。
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)
- スマートフォン決済
- クレジットカード
- コンビニエンスストア
- 口座振替
- 金融機関・税事務所の窓口
eLTAXは、事前に利用者IDを取得することで利用が可能です。クレジットカード決済をしたい場合は、自治体の納付サイト「地方税お支払サイト」などを利用しましょう。
固定資産税の仕訳例
固定資産税の仕訳方法は2種類あります。以下では、それぞれの方法を具体的に解説します。
固定資産税の金額が決まった日に経費処理
1つめは、固定資産税の金額が決まった日(賦課決定日)に経費処理する方法です。
固定資産税の金額を納税通知書で確認をしたら、借方の勘定科目を「租税公課」、相手勘定を負債の科目である「未払金」として帳簿へ記載しましょう。この処理自体は賦課決定日に処理しますが、実際にはまだ支払いが行われていないため、科目としては未払金を用います。
固定資産税17万円を、賦課決定日に経費処理する場合の仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 租税公課 | 170,000円 | 未払金 | 170,000円 |
固定資産税の納付日には未払金を取り崩し、納付した金額の分だけ記載を行いましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払金 | 170,000円 | 現金 | 170,000円 |
固定資産税を支払った日に経費処理
固定資産税を実際に支払った日に、経費処理する方法もあります。
この場合、借方の勘定科目は「租税公課」、相手勘定を「現金」として、支払った分の金額だけを帳簿に記載します。賦課決定日には仕訳の必要がなく、実際に支出となった分だけを都度記載する方法です。
固定資産税17万円を、実際に支払った日に経費処理する場合の仕訳例を見てみましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
| 租税公課 | 170,000円 | 現金 | 170,000円 |
固定資産税の節税手段
固定資産税を節税する方法には、以下のようなものがあります。
特例措置を活用する
一定の要件を満たすと、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置の対象の例として、資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)などが挙げられます。
160万円以上の機械装置や、30万円以上の工具・器具・備品を導入し、その他の要件を満たせば、固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減可能です。このほか、従業員の賃上げで1/3となる措置もあります。
これらの措置は、設備投資の促進や賃上げを目的としているものです。詳細は経済産業省の資料で確認してください。
参考:経済産業省 中小企業庁「【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について」
固定資産税の免税点を知る
固定資産税の免税点を知っておくと、資産を取得する際に免税点を上回らないよう計算できる可能性があります。
免税点とは、固定資産税がかからない課税標準額のことです。固定資産税の免税点は以下のように定められています。
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
土地の分筆で評価額を下げる
分筆とは、土地を登記簿上で複数に分けることです。土地の分筆で評価額を下げることで、固定資産税を減らせる場合があるでしょう。
たとえば1つの土地のなかで、利便性の高い部分と低い部分があるケースでは、登記簿上で土地を分けると評価額が下がりやすいといえます。
固定資産税に関する注意点
固定資産税に関しては、いくつか注意すべき点もあります。正しい勘定科目で帳簿に記載するだけではなく、以下の点にも注意しておきましょう。
滞納すると延滞金が課される
固定資産税は、期限を1日でも過ぎれば延滞金が発生します。1日単位での延滞金が加算され続けるため、遅れることのないよう早めに納付を行いましょう。
延滞期間によって変わる延滞金の年率は、以下のとおりです。
| 期限の翌日から1カ月経過までに納付 | 年2.4% |
| 期限の翌日から1カ月以上を過ぎて納付 | 年8.7% |
ただし税額2,000円未満であれば、延滞金は発生しません。
減額・減免措置は申告が必要
固定資産税は、減額・減免措置によって税負担を減らせますが、制度を利用するには申告が必要です。
まずは減額・減免の申告方法や条件を、自治体のウェブサイト・窓口で確認しましょう。その上で、該当する条件がある場合は漏れなく申告を行うようにしてください。
個人事業主は固定資産税の家事按分が必要
個人事業主が自宅の一部を事業に使用している場合、固定資産税の家事按分が必要です。家事按分とは、事業の経費と家計の出費を合理的な基準を用いて分けることを指します。
なお、固定資産税の家事按分は、事業に使用している床面積の割合や事業に費やす時間の割合に基づいて行うのが一般的です。
たとえば、総床面積100平米の自宅のうち30平米を事業に使用している場合、固定資産税の30%を事業経費として計上できます。また、1日の在宅時間20時間のうち8時間を業務に使用している場合は、固定資産税の40%を経費として計上可能です。
家事按分は、青色申告と白色申告のどちらを選択しても適用されます。
青色申告の場合、事業利用の根拠があれば使用割合に関わらず家事按分が可能です。たとえば、20%しか事業利用していなかったとしても、業務上の必要性が明確であれば経費計上できます。
一方、白色申告では原則として、事業利用の割合が50%を超えていないと経費計上が難しいため注意しましょう。
固定資産税の他に経費にできる税金の例
個人事業主が、固定資産税の他に経費にできる税金は以下の表のとおりです。
| 個人事業税 |
|
| 消費税(免税事業者ではない場合) |
|
| 自動車税(事業利用部分) |
|
| 償却資産税 |
|
| 不動産取得税 |
|
| 都市計画税 |
|
| 印紙税 |
|
| 登録免許税 |
|
| 利子税 |
|
「バクラク経費精算」で経費処理の手間を削減
「固定資産税」とは、土地や家屋などの「固定資産」を所有している人が納める地方税のことです。税額の計算は、固定資産の評価額に基づいて課税標準額を決定し、そこに税率(原則1.4%)を乗じます。
個人事業主の場合、固定資産税の家事按分が必要なので注意しましょう。
固定資産税の仕訳が面倒、ミスが心配といったケースでは、バクラク経費精算の利用がおすすめです。バクラク経費精算は、経費精算業務を効率化するクラウドベースのシステムです。自動仕訳機能があるため、早く正確に仕訳が行えます。
詳しいサービス内容は以下の資料からご覧いただけます。また導入のご相談、お問い合わせなどは、お気軽にご連絡ください。