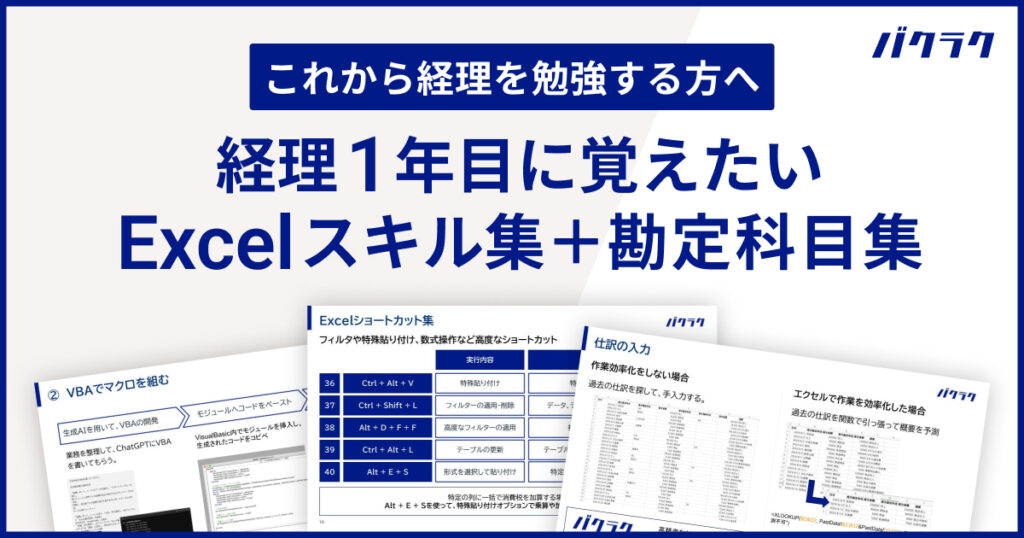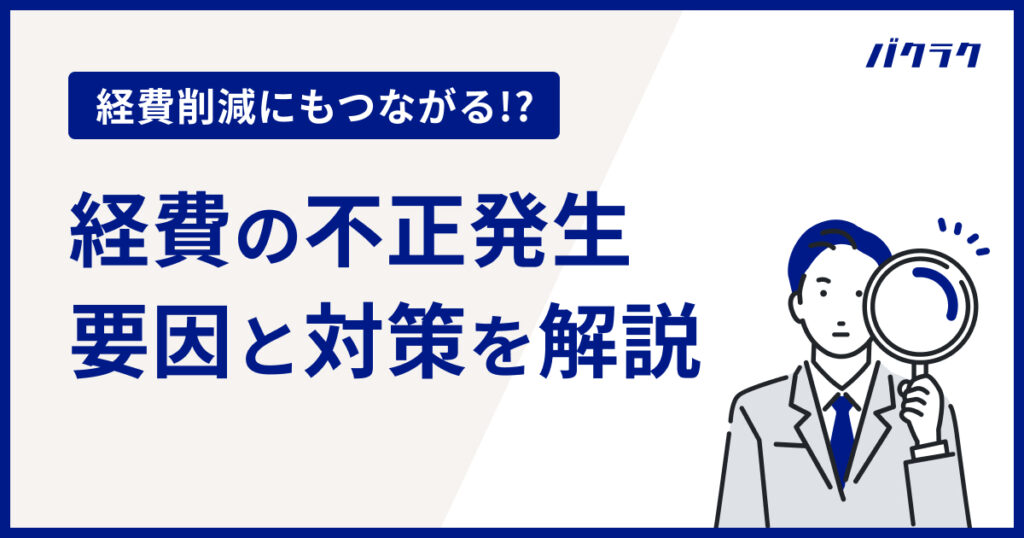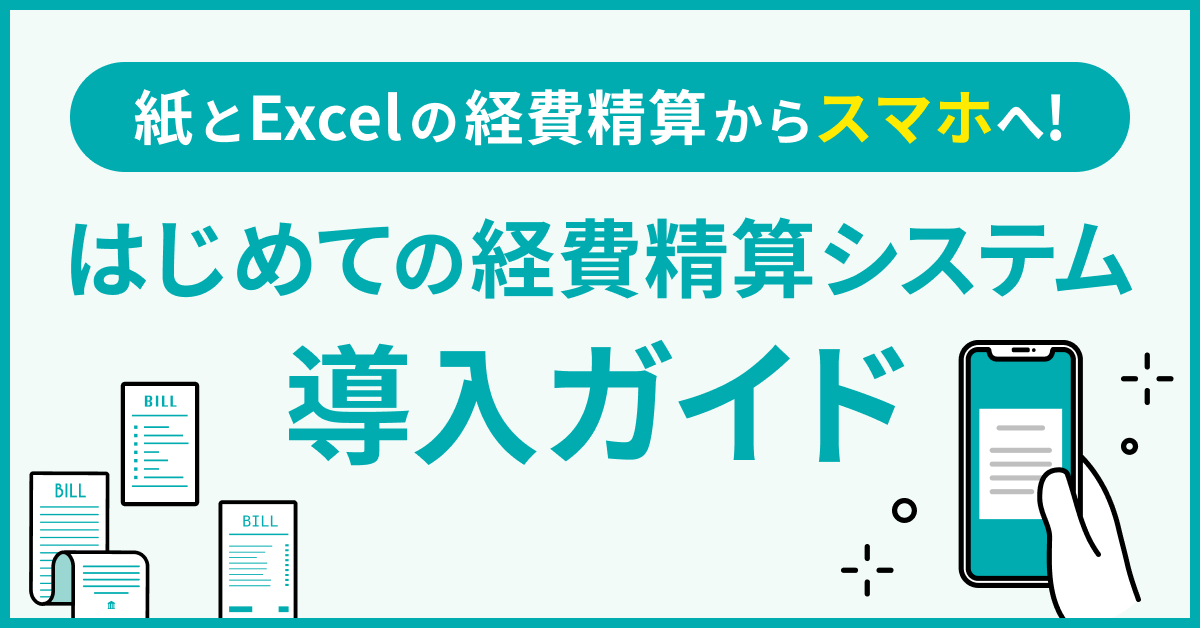ECRS(イクルス)とは?改善の4原則や導入メリット・注意点を紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-08-07
- この記事の3つのポイント
- ECRSとは業務改善のためのフレームワークで、改善の視点と実行の順序を明確にする手法である
- ECRSを導入すれば、効率的な業務改善や属人化の解消、生産性向上といったメリットが見込める
- 長期的な視点で計画を立て、社員の理解を得ながら進めるなど、注意点を理解することも重要である
ECRSとは、業務の無駄や非効率を見直すために用いられるフレームワークです。
本記事ではECRSとは何か、ECRSに沿った業務改善の進め方について解説します。また導入のメリットや注意点についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ECRS(イクルス)とは?改善の4原則や導入メリット・注意点を紹介
ECRS(イクルス)とは?
ECRS(イクルス)とは、業務改善を進める際に用いられるフレームワークです。改善の視点と実行の順序を明確にする手法で、以下の英単語の頭文字をとって名付けられました。
- Eliminate(排除)
- Combine(結合)
- Rearrange(入替え)
- Simplify(簡素化)
もともとは製造業の現場で課題を的確に抽出し、効率的な改善を図るために考案されたものですが、現在では営業やサービス業をはじめとした、さまざまな業種で広く活用されています。
ECRSを用いれば無駄な作業を省き、業務の流れを見直し、よりシンプルで効果的な形に再構築することが可能です。改善効果が高く、トラブルの発生も抑えられることから、業務効率化を目指す現場で重要な指針となっています。
ECRSに沿った業務改善の考え方
ECRSは、業務改善を進める際に「排除・結合・入替え・簡素化」の順で検討することが推奨される手法です。それぞれの視点に基づいて改善案を出せば、効率よく業務の見直しができ、不要な作業やコストの削減につながります。
各ステップについて、詳しく見ていきましょう。
Eliminate(排除)
Eliminate(排除)は、業務改善の最初のステップであり「そもそもこの業務は必要か?」という視点から見直す手法です。作業の目的や成果物を再確認し、不要な業務を削除し、大きな改善効果を得ます。
たとえば誰も確認していない報告書の作成や、実施目的が不明瞭な定例会議などは、排除の対象です。製造現場であれば、必要性の低い検査項目を見直して、時間やコストの削減につながることもあります。
排除は最も効果が大きく実行も容易であるため、業務改善の出発点として重視されます。
Combine(結合)
Combine(結合)は、Eliminateの次に検討される改善視点で、類似した業務や工程を一つにまとめて効率化を図るものです。
たとえば複数部署で同様の業務を行っている場合、業務を一つの部署に集約すれば、設備やスキルの重複を防ぎ、全体の業務負担を軽減できます。逆に、複雑な業務を複数の担当者に分離して実施することで効率が向上するケースもあります。
チェックリストの統一や業務の担当切り分けなど、結合と分離の工夫によって、作業のスムーズさや分かりやすさが向上するため、従業員にとっても負担の少ない改善です。
Rearrange(交換)
Rearrange(交換)は、業務の順序や作業場所、担当者を見直し、より効率的な形に入れ替える改善手法です。E(排除)、C(結合)の検討が済んだ後に実施するステップで、小さな変更でも業務の流れを大きく改善できることがあります。
たとえば作業手順「A→B→C」を「B→C→A」に変更したり、使用頻度に併せて道具の配置を見直したりすることで、移動や準備の手間を削減できます。また担当者を入れ替えることで、各人の得意分野を活かした業務分担の実現が可能です。
Rearrangeは比較的実行のハードルが低く、現場で取り組みやすい改善策といえます。
Simplify(簡素化)
Simplify(簡素化)は、ECRSの最後に検討すべき改善手法で、業務そのものをより単純で標準化されたものに再構成する考え方です。
たとえば作業報告書をテンプレート化したり、マニュアルを整備したりすることで、業務の属人化を防ぎ、誰でも同じ品質で作業ができます。
製造現場では、自動検知機器を導入して欠陥品の発見や異物の排除といった工程を自動化し、生産ライン全体の品質を安定させることも可能です。ただし設備投資などコストがかかる場合もあるため、Simplifyは最後のステップとして慎重に検討されるべき改善策です。
ECRSを導入するメリット
ECRSを業務改善に活用すれば、多くのメリットが見込めます。ここからは、ECRSを導入するメリットを4つ見ていきましょう。
業務改善を効率的に進められる
業務改善に取り組む際「何から手をつければ良いか分からない」と感じることは少なくありません。
ECRSは、Eliminate(排除)→Combine(結合)→Rearrange(入替え)→Simplify(簡素化)の順番で検討するという明確な道筋を示してくれるフレームワークです。
そのため順に課題を整理すれば自然と優先順位がつき、改善の手順や方向性に迷いが生じにくくなるため、無駄なくスピーディーに業務改善を進められます。
属人化を防ぎ生産性向上が見込める
属人化とは、特定の業務が一部の社員に依存し、その人がいなければ業務が回らない状態を指します。ECRSの考え方に沿って業務の目的や手順を見直せば、属人化の解消が期待できるでしょう。
たとえばE(排除)やS(簡素化)を通じて不要な工程を削減し、マニュアルや自動化によって誰でも対応できる体制を整えれば、特定の人に依存せず安定した業務運用が可能です。
引き継ぎや人員の入れ替えにも柔軟に対応でき、作業の効率化やスピードアップにつながるほか、業務の標準化が進めば、組織全体の生産性向上も実現できます。
ミスを減らせるため、業務品質向上につながる
ECRSを活用すれば、不要な業務や複雑な手順を見直せるため、業務のシンプル化や標準化が可能です。その結果作業負担が軽減され、ヒューマンエラーの発生率も低下します。
たとえば不要な報告書を廃止したり、作業手順をテンプレート化したりすれば、担当者の判断に左右されない一貫した対応が可能です。業務品質が安定し、顧客満足度や信頼性の向上にもつながるでしょう。
さらに作業ミスが減れば従業員の心理的負荷も軽くなり、ストレスや疲労の軽減にも寄与します。ECRSは、品質改善と従業員満足の両立にも有効なアプローチといえるでしょう。
コスト削減が期待できる
ECRSの導入により、不要な業務や重複作業を排除できるため、人的リソースの最適化が可能です。業務に必要な人員を抑えられ、人件費や採用コスト、福利厚生費の削減が期待できます。
また複数の業務を統合することで使用機器やITシステムを減らせば、備品やインフラの保守・運用コストの削減にもつながります。業務の簡素化が進めば作業時間も短縮され、空いた時間やリソースをより付加価値の高い業務へと振り向けることが可能です。
結果として、組織全体の経営資源を効率的に活用でき、持続的なコスト最適化と経営力の強化を実現します。
ECRSで業務改善を進めるときの注意点
ECRSは効果的な業務改善を可能にするフレームワークですが、導入時にはいくつかの注意点があります。ここからは、ECRS活用時に意識すべきポイントを見ていきましょう。
目的・目標・達成方法を明確にする
業務改善の効果を最大化するには、目的と目標、達成手段を明確にすることが欠かせません。目的や目標が曖昧なままだと改善の方向性が定まらず、行動の効果測定も難しくなるためです。
たとえば「オウンドメディアの改善」が目的であれば「不要なページの削除」や「視線誘導を意識したレイアウト変更」といったKPIを設定し、達成手段を具体的な行動計画に落とし込みます。
目的から施策までを言語化しておけば、ECRSを活かした改善活動がブレることなく進められます。
長期的な視点で計画を立てる
ECRSによる改善は、短期的な成果よりも中長期での成果を見据えて取り組むべきです。改善施策の中には設備やシステムの導入、社員の意識改革が伴うものもあり、即時に効果が出るとは限らないためです。
たとえば自動化設備の導入にはコストや納期がかかり、段階的な展開が求められます。加えて、従業員が新しい体制に慣れるには時間が必要です。
ECRSはリスクや人的負担も考慮しつつ、継続的な取り組みとして改善を進めることが重要です。
社内の協力体制を構築する
ECRSを機能させるには、部署を越えた社内の協力体制づくりが欠かせません。特定の部署だけで改善を進めてしまえば、他部門との情報共有ができず、業務全体の最適化を妨げる「局所最適」に陥るリスクがあるためです。
たとえば製品の品質改善を目指すなら、購買や生産、物流、販売など、サプライチェーン全体の連携が必要です。全社的な視点で改善に取り組めば、共通の目的意識をもてるため、組織全体で成果を上げる体制が整うでしょう。
社員の理解を得ながら進める
業務改善を成功させるには、社員の理解と納得を得ることが不可欠です。業務の大幅な見直しは、これまでのやり方に慣れている社員から反発を受ける可能性があるためです。
たとえば属人化した作業を排除する際には、当事者が自分の業務を否定されたと感じてしまうこともあります。そのような場合でも、改善の目的や実現したい姿を丁寧に説明し、協力を得られるよう働きかけましょう。
業務改善を「自分ごと」として受け止めてもらうことが、円滑な導入と定着につながります。
ECRSを理解して業務改善に活用しよう
ECRSは「排除(Eliminate)」「結合(Combine)」「入替え(Rearrange)」「簡素化(Simplify)」の4つの視点を用いて業務を見直す、非常に実践的な改善フレームワークです。
業務改善に取り組む際の優先順位や考えるべきポイントが明確になるため、効率的に課題を整理、解決できます。導入にあたっては目的や目標を明確にし、長期的な視点で計画を立てると共に、社内の連携や従業員の理解を得ることも欠かせません。
特に属人化の防止やミス削減といった副次的な効果も期待できるため、組織全体の生産性や業務品質の向上につながります。ECRSを正しく理解し、継続的な改善に役立てていきましょう。