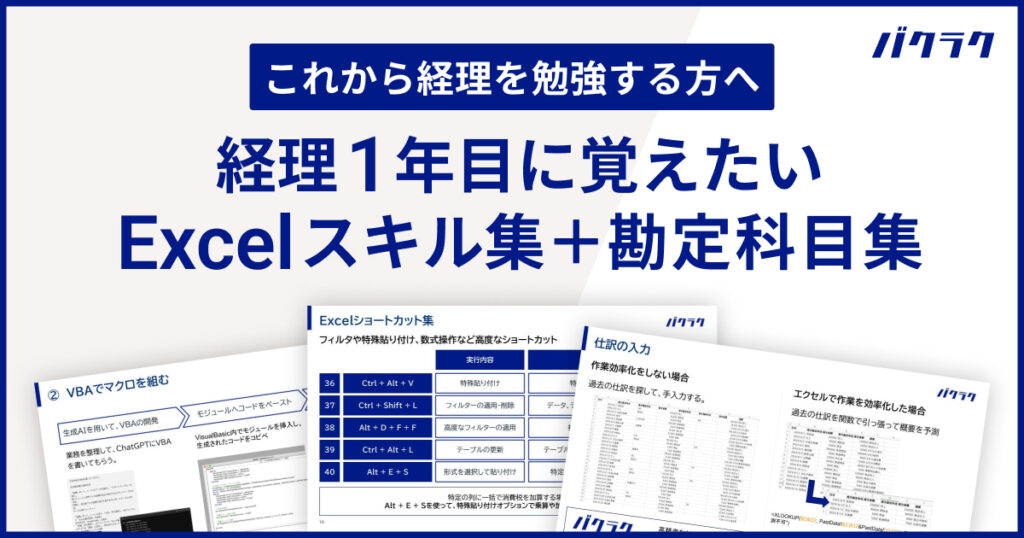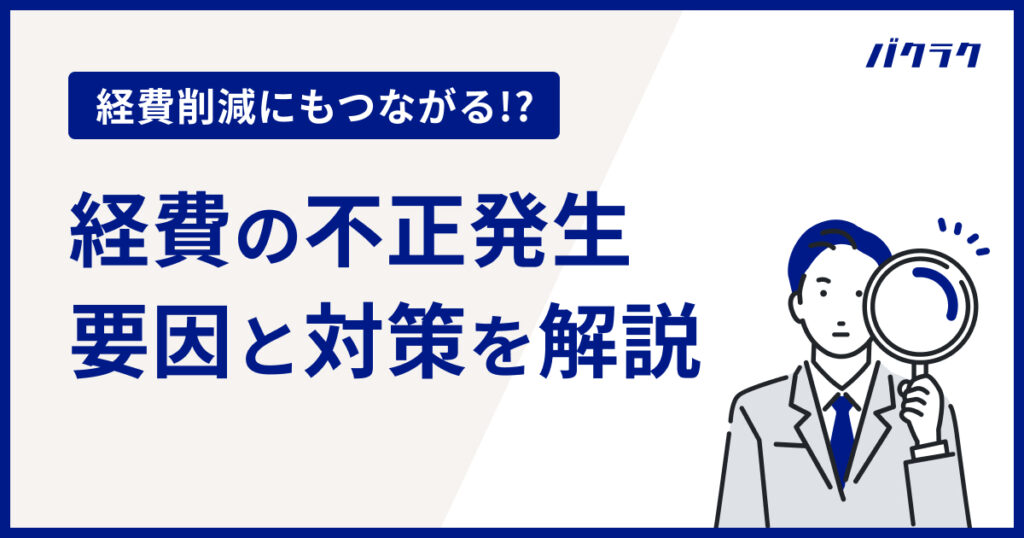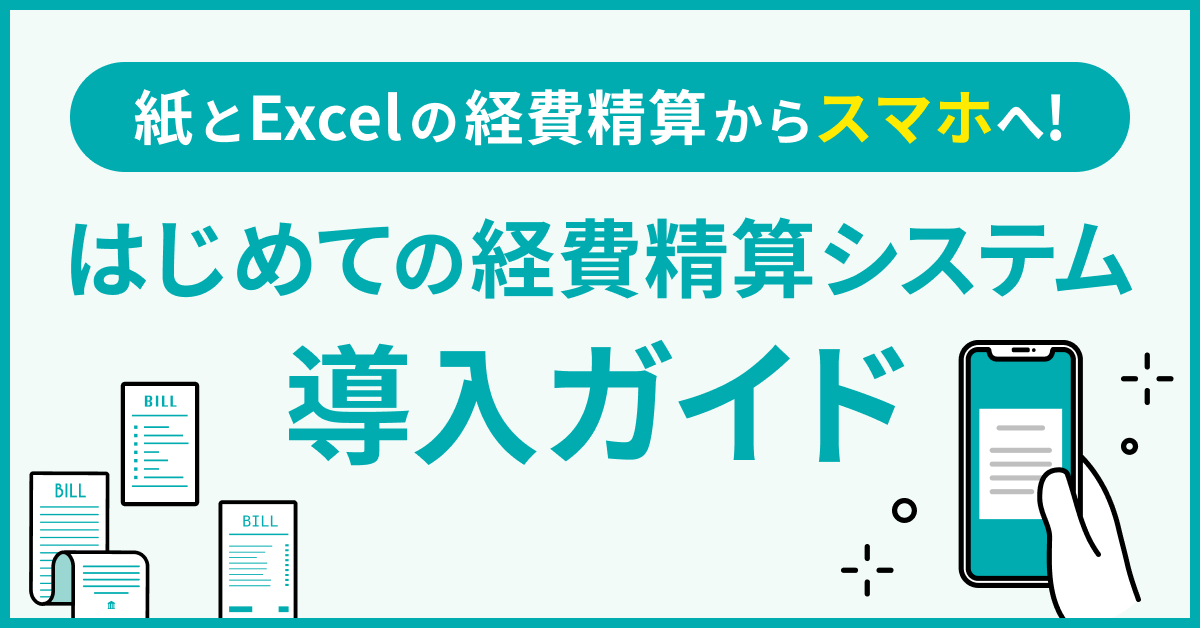企業会計原則とは?7つの一般原則や企業会計基準との違いを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-01-17
- この記事の3つのポイント
- 企業会計原則とは、会計処理を行う際に企業が守るべき基準となるものである
- 企業会計の3つの原則のうち一般原則は、7つの原則によって構成されている
- 重要性の原則は一般原則に含まれていないものの、会計処理を円滑化させるための役割を担っている
企業会計原則とは、会計処理を行う際に企業が守るべき基準となるものです。
本記事では企業会計原則とはなにか、一般原則を構成する7つの原則について詳しく解説しています。重要性の原則や、企業会計基準との違いについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
企業会計原則とは?7つの一般原則や企業会計基準との違いを解説
企業会計原則とは?
企業会計原則とは、会計処理を行う際に企業が守る基準となるルールです。1949年に旧大蔵省の企業会計審議会によって定められ、規模に関わらず、企業は日々の会計業務や財務諸表を、この原則に則って行わなければいけません。
企業会計原則は、以下の3つの原則によって成り立っています。
- 一般原則
- 損益計算書原則
- 貸借対照表原則
一般原則とは「包括的原則」とも呼ばれ、企業会計全般の理念や指針となるものです。詳しくは後述しますが、一般原則は損益計算書原則と貸借対照表原則の上位に位置しています。
損益計算書原則は収益と費用の会計処理方法や、損益計算書の表示方法の基準が定められています。損益計算書は企業の一会計期間の収益と費用の損益計算書をまとめた書類で、決算書の一つです。
貸借対照表原則は、資産と負債、資本の会計処理方法や、貸借対照表の表示方法の基準が定められています。貸借対照表は財務諸表の一つで、決算日時点での資産と付帯、総資産の状態を表す書類です。
企業会計原則はすべての企業が遵守すべき基準とされているものの、法令ではないため、違反したとしてもペナルティは課せられません。
しかしすべての企業が守るべき基準として位置づけられており、会計監査の際にも企業会計原則に則って、財務諸表が適正かどうかの判断がされます。
一般原則を構成する7つの原則
一般原則は、以下の7つの原則で構成されています。
- 真実性の原則
- 正規の簿記の原則
- 資本取引・損益取引区分の原則
- 明瞭性の原則
- 継続性の原則
- 保守主義の原則
- 単一性の原則
企業会計原則は会計処理において基礎となる重要な原則のため、確実に覚える必要があります。簿記1級や会計士・税理士学習者の暗記方法としてよく使われるのは、「しん・せい・し・めい・けい・ほ・たん」と頭文字を取って覚える方法です。
あまり意味のある文章にはならないため、「しん・せい」を「申請」、「し・めい」を「氏名」など当てはまる漢字などになおし、ストーリー性を持たせると覚えやすくなります。
それでは7つの原則について、順番に解説します。
1)真実性の原則
真実性の原則とは、作成する財務諸表が客観的な取引事実に基づき、不正や利益操作のないものであることを求める原則です。企業の財政状態と経営成績をありのまま伝えることを目的とし、虚偽の記載は厳しく禁止しています。
会計において「真実」には「絶対的真実」と「相対的真実」の2通りの捉え方がありますが、真実性の原則で求められているのは「相対的真実」です。
絶対的真実とは時代や状況に関わらず、唯一絶対ということを意味し、相対的真実とは、時代によって異なることもあり、企業のおかれている環境によっても変化するという意味で使われます。
会計処理は、固定資産の減価償却法など、複数の会計処理を選択することが認められ、企業の実情に合わせた方法で行えます。処理方法が結果と異なったとしても、算出方法が妥当であればどちらも真実として容認可能です。
2)正規の簿記の原則
正規の簿記の原則は、以下の3つの要件を兼ね備えている必要があります。
- すべての取引を網羅して記録する「網羅性」
- 検証可能な客観的な証拠で記録する「検証可能性」
- 秩序を持ってすべての取引を記録する「秩序性」
簿記の記録方法には単式簿記と複式簿記があります。単式簿記とは収入と支出のみを記録していく簡易的な方法であるのに対し、複式簿記は収入と支出だけでなく、資産や負債の増減も含めて記録する方法です。
正規の簿記の原則では明記されてはいないものの、これら3つの要件を備えた簿記は「複式簿記」であるのが一般的な解釈です。
3)資本取引・損益取引区分の原則
資本取引とは株主との取引によって資本が増減する取引のことで、損害取引とは売買など収益や費用に関する取引のことです。加えて資本取引・損益取引区分の原則は、資本剰余金と利益剰余金についても、混同してはなりません。
同じ資本であっても、資本金に組み込まれなかった出資者からの払い込み分である「資本剰余金」は維持しなければいけないもので、「利益剰余金」は、分配可能なものです。
資本取引・損益取引区分の原則は、維持すべき資本が取り崩されてしまわないようにするため、また利害関係者や投資家に適切な情報を与えるために定められています。
4)明瞭性の原則
明瞭性の原則は理解しやすい明瞭な表示を心がけることや、貸借対照表や損益計算書だけではわからない情報を集計し、適正な開示をすることを要請する原則のことです。たとえば一年基準を適用した貸借対照表の科目の分類などを要請する内容です。
企業の詳細な状況の情報が入手できない外部の利害関係者が、判断を誤らないようにするために規定されているのが、明瞭性の原則です。
5)継続性の原則
継続性の原則は、一度採用した会計処理や手続き方法は理由無く変更せず、毎期継続して使用することを要請するといった内容の原則です。
継続性の原則が必要とされる主な理由は、経営者による利益操作を排除するためと、決算書の期間比較性を保つための2つです。
たとえば選択適用が可能な会計処理を毎期変更して適用してしまえば、経営者による利益操作が可能です。さらに会計処理の継続性がなければ、会計処理が変わる可能性もあり、決算書の期間を比較することも難しくなるでしょう。
ただし会計処理にはどうしても変更が必要な場合もあります。正当な理由があれば変更は可能であるため、一度決めたら変えられないというわけではないということを認識しておくとよいでしょう。
6)保守主義の原則
保守主義の原則とは企業の安全性を確保するために、企業にとってのリスクが予測できる場合、それを考慮した会計処理を要請することです。
たとえば以下のようなものが、保守主義に該当します。
- 固定資産の減価償却費を定率法にして費用を上げる
- 貸倒引当金を多めに計上して負債額を大きくする など
ただし利益操作につながるため、どのような状況でも保守主義の原則が認められるわけではありません。真実性の原則に触れる場合も考えられるため、企業の財政に不利な影響がある場合のみに限られます。
過度な保守主義は、適正な会計処理といえなくなるため注意が必要です。
7)単一性の原則
単一性の原則は「さまざまな目的で作成される決算書の形式が異なっていたとしても、一つの会計帳簿を基としており、事実を変えてはならない」ことを要請した原則です。
外部報告や金融機関向けの財務諸表と法人税申告のための財務諸表は都合良いものに作成せず、会計記録の内容まで変えてはいけないと明示しています。
企業会計原則注解で規定されている「重要性の原則」について
重要性の原則とは、一般原則を補足する役割をもった企業会計の一部です。一般原則には含まれておらず、一般原則に準ずる位置づけの「企業会計原則注解」で言及されています。
重要性の原則には、おおむね以下の内容が記されています。
- 会計上の重要性に乏しいものは、本来の処理ではなく簡便に処理することが可能である
- 重要性の低い取引に関して簡便な処理を行ったとしても、正規の簿記の原則に違反したものとはならない
重要性の原則は、重要性が低く全体に与える影響が少ないものは簡便な処理で構わないということが記されたものです。この重要性の原則は、会計事務の円滑化において大きな役割を担っているといえるでしょう。
企業会計基準との違い
企業会計原則と混同しやすいものに、企業会計基準があります。企業会計基準とは財務諸表を作成する際のルールで、日本で認められている会計基準は、以下の4つです。
| 日本会計基準 | 1949年公表の企業会計原則をベースにした日本独自の基準 |
| 米国会計基準 | 米国財務会計基準審議会(FASB)が発行した、アメリカで採用されている会計基準 |
| 国際会計基準(IFRS) | 国際会計基準審議会が世界共通の会計基準を目指して作成した基準 |
| J-IFRS | 国際会計基準の日本版と位置づけられるもので、国際会計基準の内容を日本国内の経済状況に合わせて調整した基準 |
具体的な会計処理について知りたい場合は、実務のメインとなる企業会計基準を確認するとよいでしょう。
「バクラク経費精算」なら正確かつ一貫した経費の記録・計上が可能
企業会計原則は経費精算のプロセスにおいても重要な役割を果たし、経費の記録や計上が、正確で一貫性のあるものとなるよう求められています。特に「重要性の原則」に基づく判断は日々の経費処理にも適用され、企業の財務管理を健全に保つための基盤となるでしょう。
バクラク経費精算は、企業会計原則に準拠したシステムを提供し、適切な経費処理を自動化・効率化します。企業の経理業務負担を軽減し、信頼性を高められるツールであるバクラク経費精算について気になった方は、ぜひ以下のページをご覧ください。