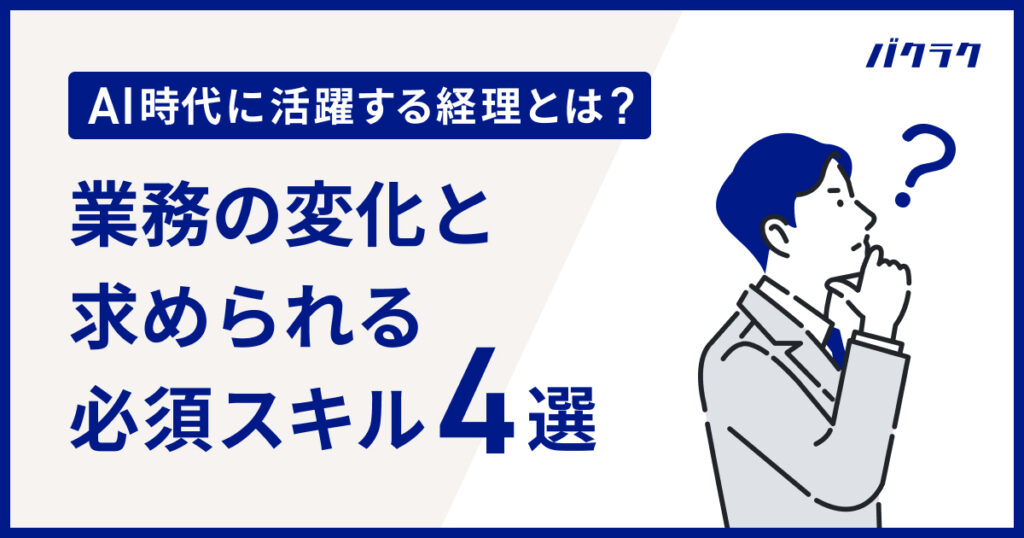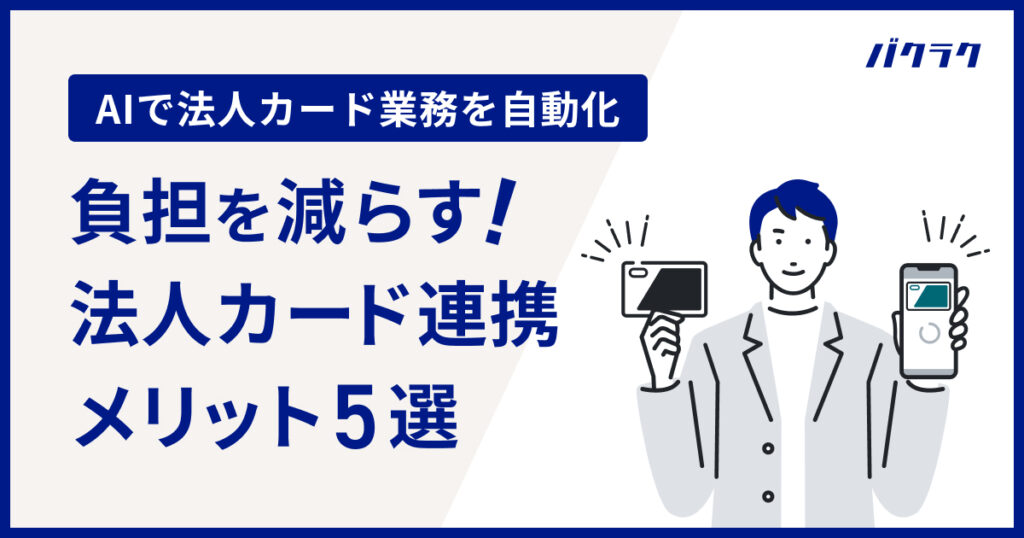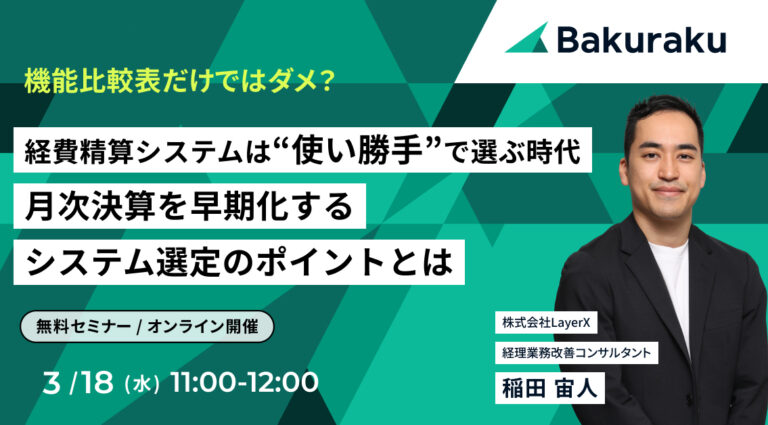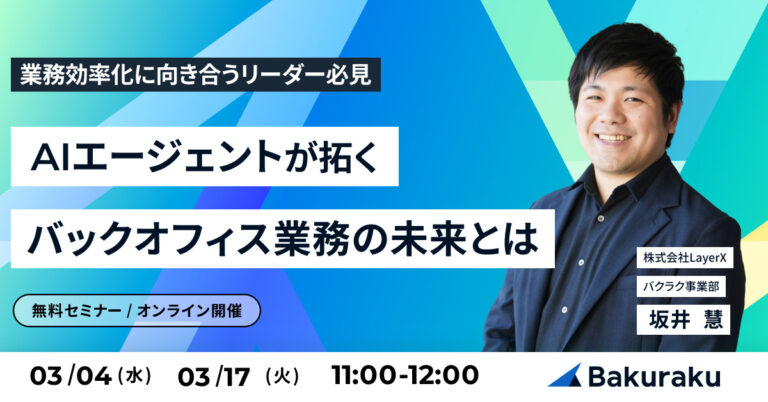
はがきのサイズ・重さは種類で異なる?自作するときの注意点も紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-10-01
- この記事の3つのポイント
- はがきには、通常・往復・大判・A4の4種類があり、サイズによって郵便物の種別も変わる
- 自作することも可能だが、内国郵便約款の規定から外れたものは、はがきとして認められない
- はがきを自作する際にはサイズや重さの他、宛名面のデザインにも注意して作成する
はがきは、年賀状や暑中見舞いの他、企業が顧客に送るDMなどでもよく利用される身近な存在です。しかし、はがきにはさまざまな種類があり、サイズによって「はがき」ではなく「定形外郵便」となる可能性があります。
本記事では、はがきの一般的なサイズや種類、郵便物としての取り扱いの差について解説します。はがきを私製する際の注意点も紹介していますので、規定を満たすはがきを自作したい方は、ぜひお役立てください。
はがきのサイズ・重さは種類で異なる?自作するときの注意点も紹介
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
はがきは種類別にサイズと重さが決まっている
はがきは、一般的に通常・往復・大判・A4と4つの種類に分類されます。各種類の主なサイズや重さを紹介しますので、違いを確認しましょう。
通常はがき
通常はがきは、最小9cm×14cm、最大10.7cm×15.4cmの長方形のもので、重さは2〜6gです。一般的なサイズは10cm×14.8cmで、年賀状や暑中見舞いといった挨拶状や招待状、販促DMなどで利用されています。
また、通常はがきは第二種郵便物の扱いとなり、料金は1通85円(全国一律)です。
※掲載している情報は、2025年8月時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。
往復はがき
往復はがきは、一枚の紙に「送信用」と「返信用」のはがきが連結された形式の郵便物を指します。折りたたんで送付し、返信部分を切り離して投函する仕組みです。
サイズは最小18cm(9cm+9cm)×14cm、最大21.4cm(10.7cm+10.7cm)×15.4cmで、一般的なサイズは、20cm×14.8cmです。重さは4〜12gが往復はがきとして認められます。
結婚式や同窓会の出欠確認など、往復のやりとりが必要な場面で多く活用され、返信側に必要事項をあらかじめ記入しておくと、相手の負担を軽減できます。
往復はがきは、通常はがきと同様に第二種郵便物となり、料金は1通170円(全国一律)です。
※掲載している情報は、2025年8月時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。
はがきの値段や値上がり時の対応については以下の記事で解説していますので、併せてお読みください。
関連記事:はがきの値段はいくら?差額分の切手の貼り方、値上がりへの対応策
大判はがき
大判はがきは、一般的に長形3号封筒と同じ12cm×23.5cmのものを示します。B5サイズやA5サイズの大判はがきも存在しますが、長形3号サイズが一般的です。
大判はがきは通常はがきより多くの情報を掲載でき、他の郵便物と差別化できるサイズのため、販促DMなどでよく利用されています。
長形3号タイプで重さが50gであれば定形郵便物、B5サイズやA5サイズだと定形外郵便物として扱われます。
A4はがき
A4はがきの大きさは、21cm×29.7cmです。長形3号タイプの大判はがきと比べると郵便料金も割高です。
ただし、大判はがきよりもさらに多くの情報を掲載できるため、商品やサービスの魅力を顧客にしっかり伝えたい場合に役立ちます。また、サイズが大きく目立つため、他の郵便物より手にとってもらいやすい点もメリットです。
クーポンなどを一緒につける際には、顧客が持ち運びやすいように切り離せるデザインにするとよいでしょう。
なお、A4はがきは定形外郵便として扱われます。
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
はがきを自作するときに注意したいポイント
はがきは自作して郵送することも可能です。
ただし、はがきと認められるには、内国郵便約款という所定のルールに従って規定内に収まるように作成しなくてはいけません。規定を満たさない場合は、第二種ではなく第一種郵便物として扱われ、郵便料金も割高になってしまいます。
本章では、はがきを自作する際の注意点を解説します。
サイズ・重さを規定内に収める
一般的に、はがきとして認められるサイズの上限は、10.7cm×15.4cmの長方形です。重さは2〜6g以内にする必要があります。
大きさにこだわりがない場合は、一般的な官製はがきサイズである10cm×14.8cmにしておくと安心です。
はがき用として販売されている用紙を選択すると、重さの規定を超える心配はほとんどありません。自分で用紙を選ぶ際は、薄すぎたり厚すぎたりするものを選ばないようにしましょう。
宛名の面に郵便はがきと明記する
宛名面に「郵便はがき」または「POST CARD」の記載がないと、はがきとして認められません。宛名面の上部か左側中央のどちらかに、文言を忘れず記載しましょう。
宛名の面は白か淡い色にする
宛名面の背景色は、白か淡い色と規定されています。他の色にすると宛先情報が読み取りづらくなる可能性があります。
濃い背景色にしたい場合は、宛先部分にのみ白い背景を施すようにしましょう。
切手を貼る位置に注意する
切手は、長辺より3.5cm、短辺より7cmの範囲内に収まるように貼付しましょう。機械ではがきを読み取って仕分けする際に、切手の位置が統一されていると読み取りやすくなるため、貼り付け位置にも規定があります。
縦書きであれば左上、横書きであれば右上に貼付すると覚えておくとよいでしょう。
郵便番号枠がある場合は赤色にする
郵便番号枠の色は、赤(朱色・金赤色)にしてください。仕分け時に機械で郵便番号の読み取りを行うとき、黒や青のインクで枠がデザインされていると読み込みがしにくくなるため規定されています。
ただし、郵便番号枠の設置は必須ではないため、デザイン上不要であれば設けなくても問題ありません。
宛名以外の情報は用紙の半分までにする
宛名面に、広告や相手へのメッセージ文など宛名以外の情報を載せる場合は、宛名をわかりやすくするために、他の文面は用紙の半分以内に収めなくてはいけません。
たとえば、縦型であれば宛名の下半分、横型であれば左半分に広告を掲載します。宛名との境界線を明確にするために区切り線をつけたり、宛名と広告部分の間に十分なスペースを設けたりしてもよいでしょう。
「バクラク請求書発行」でペーパーレス化を推進
はがきには複数のサイズがあり、サイズによって郵便物としての取り扱いも異なります。また私製はがきは、規定を守って作成しないとはがきとして認められず、郵便料金が高くなる可能性があるため注意が必要です。
はがきを使ってDMや販促を送付する際には、規定を守ったデザインになっているか確認しましょう。
顧客に対しては、はがきを使ったアナログなアプローチも必要ですが、社内の管理業務はペーパーレスにして負担を軽減するのがおすすめです。
バクラク請求書発行なら、社内のあらゆる帳票の作成や送付を一括管理してシステム化できます。帳票の送付もメール送付(一括・個別)や郵送などから自由に選択でき、複雑なレイアウトの帳票も簡単に作成可能です。
ペーパーレス化を推進するなら、ぜひバクラク請求書発行の導入をご検討ください。