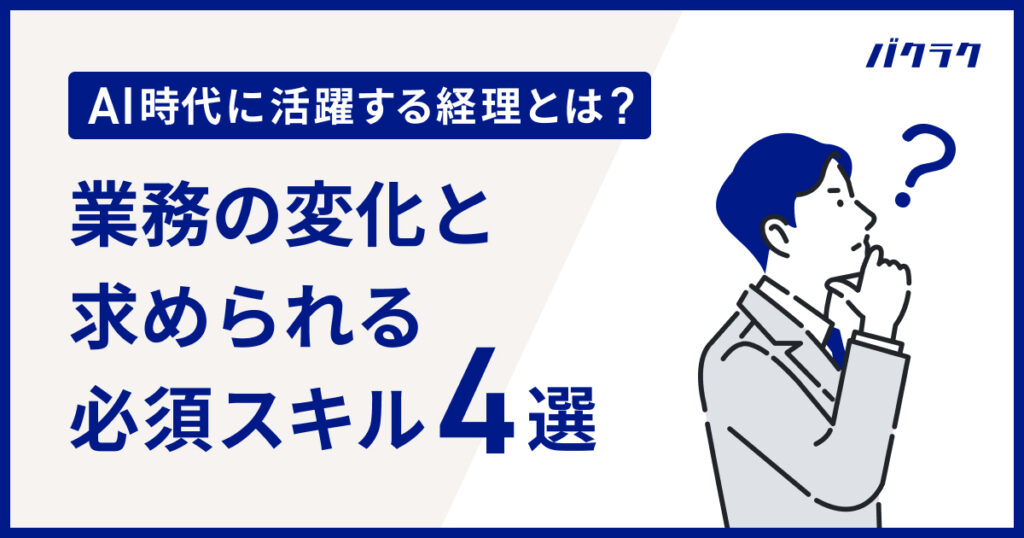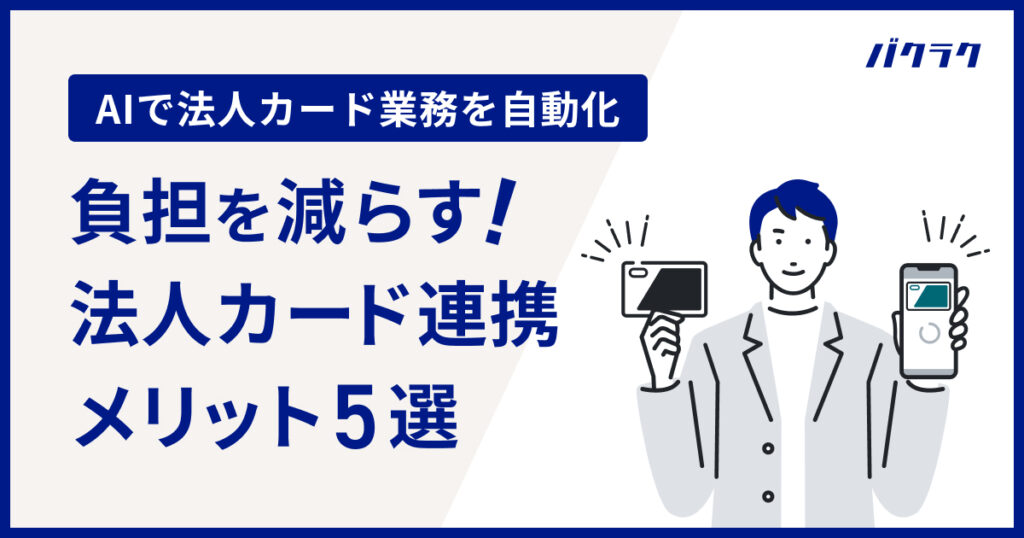スマートレターの料金は?用途や購入・利用方法とあわせて解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- スマートレターとは日本郵便が提供しているサービスで、全国一律料金で送れるメリットがある
- コンビニや郵便局で購入し、ポストから投函できるため手軽だが、2024年10月に値上げされた
- 値上げへの企業の対応は、他の郵便サービスの検討や、書類を電子化して送る2つの方法がある
スマートレターは、日本郵便が提供するサービスで、全国一律料金で利用できます。主に書類や小物を送るのに便利です。
本記事ではスマートレターの用途や料金とともに、値上げによって今まで郵送業務を行っている企業が求められる対応について解説します。
スマートレターの料金は?用途や購入・利用方法とあわせて解説
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
スマートレターとは?用途と料金
スマートレターとは、日本郵便が提供する全国一律料金の郵送サービスで、以下の書類や小物を送るのに適しています。
- A5サイズ(25cm×17cm)
- 厚さ2cm以内
- 重さ1kg以内
スマートレターは中身が折れにくい厚紙製の専用封筒を使ってポストから手軽に発送できるため、ビジネス文書やCD、アクセサリー、文具などの送付に便利です。ただし、現金や貴重品、生ものなどは送れないため、注意しましょう。
なお、スマートレターの料金は2024年10月1日の郵便料金改定により、180円から210円へ値上げされました。専用封筒の購入費用に送料が含まれているため、切手を貼る必要はありません。
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
旧料金と新料金の差額分の対応方法
2024年10月の郵便料金改定により、スマートレターの料金は180円から210円に変更されました。旧料金で購入したスマートレターも、差額分の対応をすれば引き続き利用可能です。
ここからは、旧料金のスマートレターを持っている人が、新料金で送る場合の対応方法を3つ紹介します。
旧料金のスマートレターに差額分の切手を貼る
旧料金のスマートレターを持っている場合、差額の30円分の切手を貼れば引き続き利用可能です。貼る位置は宛名面の左上など目立つ場所が推奨されますが、文字や印刷のある部分は避けるようにしましょう。
この方法であれば、手元の旧スマートレターを無駄にせず使い切ることができ、ポスト投函も可能です。なお切手の種類は1枚でも複数枚でも問題なく、差額合計が30円であれば有効です。
差額を郵便局に支払う
郵便局の窓口で差額30円を支払う方法もあります。旧スマートレターを窓口に持ち込み、「旧料金の封筒であること」と「差額を支払いたい旨」を伝えれば、職員が対応してくれます。
郵便局に行く手間はかかりますが、切手の貼付に不安がある方や、確実に対応したい方にとって安心な方法です。
差額と手数料を支払って新しいスマートレターに交換してもらう
大量に旧スマートレターがある場合は、郵便局で新スマートレターに交換してもらう方法もあります。ただし、差額30円に加え、1枚あたり55円の手数料が必要です。たとえば旧スマートレターを1枚交換する際は、差額30円と手数料55円で合計85円を支払います。
コストはやや高めですが、封筒の管理を新旧で分けたくない方に便利な方法です。
普通郵便やレターパックとの違い
スマートレターは手軽に送れる点が魅力ですが、他の郵送サービスと比べて制限やサービス内容に違いがあります。
たとえば普通郵便(定形外)では100g以内は140円、100gを超えると205円以上かかるため、210円で1kgまで送れるスマートレターはコストパフォーマンスが高いといえるでしょう。
ただしスマートレターは専用封筒のサイズ(A5・厚さ2cm)内に収める必要があり、形状の自由度は定形外郵便よりも劣ります。
またレターパックの場合、A4サイズまで対応しているうえ追跡サービスや土日祝の配達も可能ですが、料金は430〜600円と高めです。その一方で、スマートレターは210円と安価な分、A5サイズ・厚さ2cm・1kgまでと制限があり、追跡や補償がありません。
はがきの値段やレターパックの値上げ後の料金については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:はがきの値段はいくら?差額分の切手の貼り方、値上がりへの対応策
関連記事:レターパックの値上げ後の料金は?旧料金との差額の対応方法も
関連記事:適格請求書とは?概要や書き方(見本付き)をわかりやすく解説
スマートレターは郵便局やコンビニで購入できる
スマートレターの専用封筒は、以下の場所で購入できます。
- 郵便局
- コンビニ
- 郵便局のネットショップなど
郵便局では1枚から購入可能で、急ぎのときにも便利です。コンビニではローソンやセブン-イレブン、ファミリーマートなどが取り扱っていますが、一部の店舗では販売していない場合もあるため、事前に確認しましょう。
また郵便局のネットショップでは、20部単位でのまとめ買いのみ対応しているため、頻繁に使う人や法人利用に適しています。
個人で時々使う程度であれば、都度、郵便局やコンビニで購入するのがおすすめです。
スマートレターの利用方法
スマートレターの使い方は簡単で、宛名と差出人情報を専用封筒に記入し、中身を封入してポストに投函するだけです。
切手は不要で、郵便局の窓口や、ポストのあるコンビニからも発送できます。コンビニによってはポストが設置されていない店舗もあるため、事前に確認しましょう。
またスマートレターの利用時には、いくつかの注意点があります。
- 速達や追跡サービスが利用できない
- 損害賠償が付帯していない
- 日本国内に限られており、海外発送はできない
- 土日祝日の配達がない
スマートレターは荷物が破損・紛失しても補償されないため、重要な書類や貴重品には不向きです。上記の制限を理解したうえで、用途に合った使い方をしましょう。
スマートレターの値上げに対する企業の対応策
スマートレターは手軽さと安さが魅力のサービスですが、2024年10月の料金改定での値上げにより、郵送コストの見直しが求められる企業もあるでしょう。ここからは、企業がとれる具体的な対応策を2つ紹介します。
他の郵便サービスを検討する
1つ目の方法は、郵送物の内容や目的に応じて、より適した配送方法を選ぶことです。たとえば書類を数枚送るだけであれば、スマートレターではなく定形郵便(新料金110円)や定形外郵便(100g以内180円)を使った方が安く済みます。
全国一律料金のレターパックでも、プラス(600円)ではなくライト(430円)に切り替えるだけで負担は減ります。DMなどの場合は、封書からハガキに変更することでコストダウンが可能です。
さらに発送ロットをまとめて一括発送の割引を利用したり、発送業務を外部委託したりするのもよいでしょう。
書類は電子データで送付する
2つ目は、紙の書類を電子データに置き換える方法です。請求書や見積書、契約書などはPDFデータとしてメール送信するか、専用システムを通じて電子送付すれば、郵送が不要です。
書類をデータ化すれば郵便料金だけでなく、紙代や印刷代、封入作業コストの削減にもつながります。加えて会計システムや請求書発行システムを導入すれば、帳票の作成から送付までを自動化でき、業務効率化も実現可能です。
ただし専用システムを導入する場合、導入コストや運用コスト、社員への教育といった負担も考えられます。費用対効果を見極めつつ、段階的に導入を検討するのが望ましいでしょう。
請求書発行システムについては、以下のページで詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
あらゆる帳票を電子データで作成・送付できる「バクラク請求書発行」
2024年10月に郵便料金が値上げされてから、企業は郵便コスト削減の対応が求められています。対応は別の発送方法を検討するか電子化するかの2択ですが、専用システムを導入すれば発送代だけでなく印刷代や作業コスト削減も可能です。
「バクラク請求書発行」であれば、請求書・納品書・見積書など、あらゆる帳票を電子データで作成・送付でき、従来の業務フローを大きく変えずに導入可能です。現在の帳簿レイアウトをそのまま使える柔軟カスタマイズ機能も備えています。
また帳票の作成や稟議、送付、保存までを一括でデジタル化でき、メール添付やURL送付での一括・個別送信にも対応しています。コスト削減と業務効率化を両立できる「バクラク請求書発行」について、詳しくは以下のページをご覧ください。