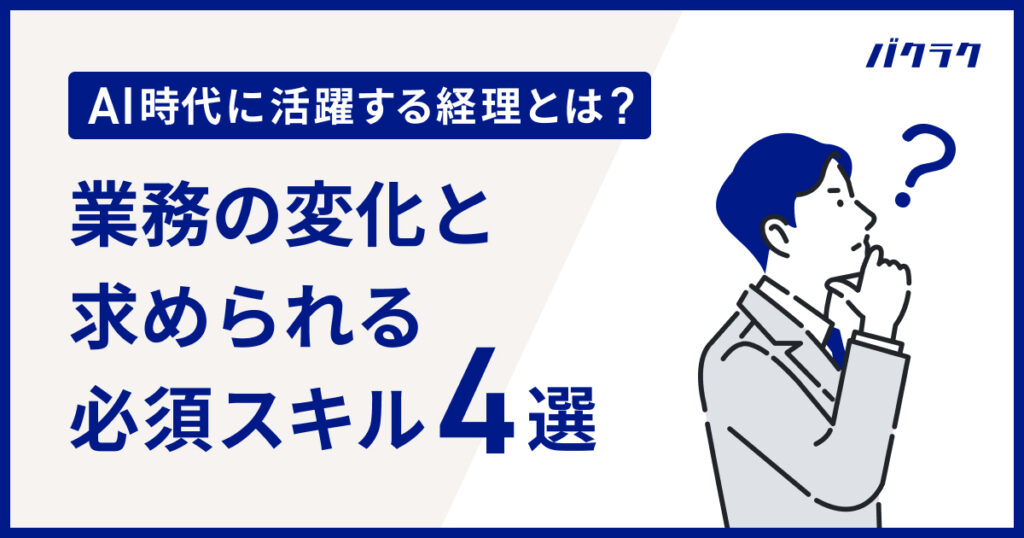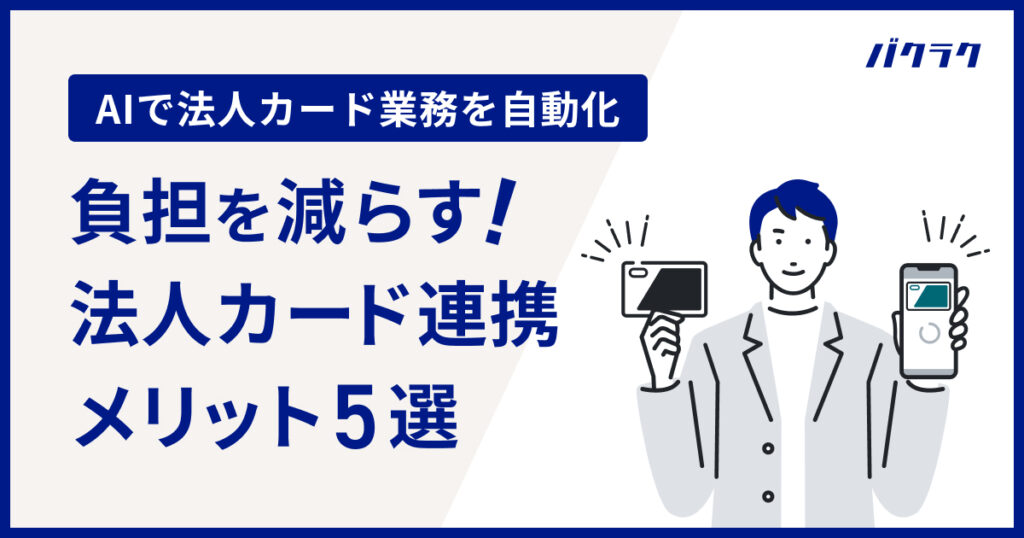はがきの値段はいくら?差額分の切手の貼り方、値上がりへの対応策
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-25
- この記事の3つのポイント
- はがきの値段は、2025年10月1日より1通85円に値上がりしている
- はがきには通常はがきと往復はがきがあり、それぞれサイズ・重さに規定がある
- はがきの郵送料金を削減するには電子データでの送付がおすすめ
はがきの値段は、近年値上げを繰り返しています。そのため「今のはがきの値段はいくらだろう」と疑問を抱く方もいるでしょう。
そこで本記事では、はがきの値段について解説します。差額分の切手の貼り方や値上がりへの対応策も解説していますので、ぜひ参考にしてください。
はがきの値段はいくら?差額分の切手の貼り方、値上がりへの対応策
請求書作成・発行システムを検討している方は以下のリンクもご覧ください。
【2025年最新版】請求書作成・発行システムの徹底比較とおすすめポイントの紹介
はがきの値段(切手代)はいくら?
はがきには、相手方にメッセージを送る「通常はがき」と、受取人が返事を出すための返信用はがきがセットになった「往復はがき」があります。
通常はがきと往復はがきの値段(切手代)について、以下でそれぞれ解説します。
通常はがき
2024年10月1日以降の通常はがきの値段は、1通85円です。2024年9月30日までの値段とは、以下のとおり異なります。
値段 | 2024年9月30日まで | 2024年10月1日から | ||
1通あたり | 63円 | 85円 | ||
郵送料金の改定によって、1通あたり22円値上がりしています。以前の値段では、はがきを送れないため注意しましょう。
はがきの値段は、距離による変動はありません。通常はがきとして送れるか否かは重さやサイズで異なります。
- 重さ:2~6g
- サイズ(最大):長辺15.4cm×短辺10.7cm
- サイズ(最小):長辺14cm×短辺9cm
参考:日本郵便「はがきのサイズ・重さについて」
上記の規格を超える場合は、はがきとしては送れないため、定形郵便物もしくは定形外郵便物での手続きが必要です。
日本郵便が発行している「通常はがき」には、もともと切手がプリントされているため、改めて切手を貼る必要はありません。ただし、一般企業が販売している「私製はがき」には切手がついていないため、別途購入する必要があります。
往復はがき
2024年10月1日以降、往復はがきの切手代は1通170円です。通常はがき同様、2024年9月30日までの値段とは異なるため注意しましょう。
値段 | 2024年9月30日まで | 2024年10月1日から | ||
1通あたり | 126円 | 170円 | ||
改定前より、1通あたり44円値上がりしています。
往復はがきの値段も、郵送距離ではなく重さやサイズによって異なります。
- 重さ:4~12g
- サイズ(最大):長辺15.4cm×短辺10.7cm
- サイズ(最小):長辺14cm×短辺9cm
参考:日本郵便「はがきのサイズ・重さについて」
往復はがきは、長方形の紙の短辺部分をそろえて、折り目が右側になるよう折り合わせた際のサイズを測って郵送します。不明な場合は職員に確認しましょう。
以下の記事では、インボイス制度の概要や影響を図解で解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
通常はがきのサイズや重さを超える場合の値段
通常はがきの規格を超える場合は、サイズに応じて定形郵便物もしくは定形外郵便物で送る必要があります。送れるサイズや値段について、以下でそれぞれ解説します。
定形郵便物
定形郵便物とは、日本郵便が提供する普通郵便サービスの一つで、値段は一律110円です。
定形郵便物のサイズと重さは以下のとおりです。
- 重さ:50g以下
- サイズ(最大):長辺23.5cm×短辺12cm×厚さ1cm
- サイズ(最小):長辺14cm×短辺9cm
定形郵便は宅配便に比べて値段を安く抑えられるため、書類の郵送に適しています。
定形外郵便物
定形郵便物のサイズ・重さを超える場合は、定形外郵便物に分類されます。定形外郵便物として送ることができるのは、重さ1kg以内で長辺34cm・短辺25cm以内、かつ厚さ3cm以内の郵便物です。
定形外郵便物は重さによって値段が異なります。2024年10月1日以降の重さ別の値段は以下のとおりです。
重さ | 値段 | |
50g以内 | 140円 | |
100g以内 | 180円 | |
150g以内 | 270円 | |
250g以内 | 320円 | |
500g以内 | 510円 | |
1kg以内 | 750円 | |
参考:日本郵便「手紙(定形郵便物・定形外郵便物)の基本料金」
1kgを超える場合は定形外郵便物の規格外に分類され、さらに値段も高くなります。
旧料金の通常はがきを利用する場合は差額分の切手が必要
旧料金の通常はがきを利用する場合は、現在の郵便料金との差額分の切手が必要です。以下で切手の種類、追加分の貼り方を解説します。
切手の種類
旧料金のはがきを利用する場合は、切手に印刷されている数字を確認しましょう。数字は切手料金を示しており、「63」の場合は63円と判断できます。
旧料金のはがきは、そのまま投函しても相手方に届きません。2024年10月1日以降の料金を確認し、差額分の切手を追加購入する必要があります。
販売されている30円以下の切手の種類は以下のとおりです。
- 1円
- 2円
- 5円
- 10円
- 20円
- 22円
- 26円
- 30円
たとえば、63円の切手が貼られている通常はがきを85円で送る場合は、郵便局やコンビニエンスストアなどで差額22円分の切手を購入しましょう。
差額分の切手の貼り方
差額分の切手は、印刷されている箇所より下へ縦に並べるのが正しい貼り方です。貼る範囲は「縦7.0cm×横3.5cmの範囲内」という規定があります。機械で押す消印が切手にかぶさる範囲である必要があるためです。
規定の範囲をはみ出てしまう場合は、郵便局の職員が手動で消印を押さなければいけません。職員の負担を減らすためにも、差額分の切手は決められた範囲内で貼るのが好ましいです。
なお、範囲をはみ出てしまうからといって、切手を重ねて貼るのは避けましょう。重ねて貼ることで料金が見えなくなると、無効となり返送される可能性があります。差額が発生する場合は、できるだけ少ない枚数で追加切手を用意しましょう。
関連記事:適格請求書とは?概要や書き方(見本付き)をわかりやすく解説
はがきを送る時の注意点
はがきを送る際は、料金や喪中時などの注意点があります。それぞれ詳しく解説します。
料金が不足していた場合は差出人に戻される
はがきをポストに投函しても、郵送料金が不足していた場合は差出人に戻されるため注意が必要です。ただし、料金不足が発覚した場所によって対応が異なります。
- 差出人の管轄郵便局で発覚した場合:差出人に返送される
- 別管轄の郵便局で発覚した場合:料金不足のお知らせを添えて受取人に配達される
差出人が郵送に出した管轄郵便局ではなく、別の郵便局で発覚した場合は、料金不足のお知らせとともに受取人のもとへ届けられます。受取人は、はがきを受け取る際に不足分の料金を支払わなければいけません。
受取人は料金の支払いおよび、はがきの受け取りを拒否することも可能です。受け取り拒否されたはがきは差出人に返送されます。
なお、はがきに貼られた切手の値段が規定よりも高い場合は、問題なく配達されます。
喪中はがきの場合は「胡蝶蘭」の切手イラストを使用する
喪中はがきに「通常はがきを使用すべき」「私製はがきでなければいけない」などの決まりはありませんが、切手のイラストには注意が必要です。
通常はがきの切手イラストには、「ヤマユリ」「ヤマザクラ」「胡蝶蘭」の3種類があります。なかでも、喪中はがきには「胡蝶蘭」を使用するのが一般的です。
一方、私製はがきを使用する場合は、一般的な普通切手ではなく弔事用切手を貼りましょう。喪中はがきで使える切手イラストは1種類のみです。喪中はがきの値段は、通常はがきと同様一律85円です。
郵便料金の値上げに対する企業の対応策
郵便料金の値上げは、企業にとってコスト増に直結します。郵便料金の値上げに対する企業ができる対応策を紹介しますので、参考にしてください。
日本郵便が提供する割引制度を活用する
郵便料金の値上げに対する企業の対応策として、日本郵便が提供する割引制度の活用が挙げられます。具体的な割引制度は、以下の3つです。
- バーコード割引
- 区分割引
- 特約ゆうメール割引
バーコード割引
バーコード割引は、一定の条件を満たす定形郵便物およびはがきに、所定のバーコードを記載することで料金を割り引く制度です。
適用条件として通常はがき・往復はがきおよび条件を満たす定形郵便物であること、同時に1,000通以上出すことなどがあります。割引率は3%です。
参考:日本郵便「バーコード付郵便物」
区分割引
区分割引は、郵便区番号ごとに区分された郵便物の料金を割り引く制度です。条件として差出する前に、郵便物を配達先の郵便番号ごとに仕分けすることなどが求められます。また、同時に2,000通以上を郵送する場合が対象です。
区分方法や同時送付枚数によって、割引率が異なります。郵便番号ごとに区分をした場合、枚数に応じて3%〜6%の割引、差出郵便局が指定する郵便区番号ごとに区分された場合は1%〜4%の割引がされます。
参考:日本郵便「区分郵便物」
特約ゆうメール割引
特約ゆうメールは「ゆうメール」を大量に送る場合に、大口企業として契約することでゆうメールの料金を割り引いてくれる制度です。特約ゆうメールを適用したい場合は、郵便局と直接契約し、特約制度を利用しなければいけません。
なお、契約内容によって割引率は異なります。
日本郵便以外の手段を検討する
郵便料金の値上げに対して対策を講じたい場合は、日本郵便以外の手段も検討しましょう。国内には日本郵便以外にもDM等の発送ができる業者があります。
たとえば、有名なサービスは以下が挙げられます。
- ヤマト運輸:クロネコゆうメール
- 佐川急便:飛脚メール便
上記のほか、宛名のないDMを地域限定で送れるポスティングサービスもあります。
それぞれの料金やメリット・デメリットを比較し、コスト削減ができる自社に適したサービスを検討するとよいでしょう。
郵送ではなく電子データで送付する
郵便料金の値上げは、過去に幾度も行われています。今後のさらなる値上げに対するコスト削減を目指すのであれば、郵送ではなく電子データでの送付がおすすめです。
請求書や納品書などの書類をPDFに変更し、メールで送信することで郵送料金の大幅な削減が可能です。印刷コストや人件費の削減にもつながります。
各種書類の電子化は、データの検索や保存が容易になるなど、業務効率化も図れるでしょう。2024年1月より「電子帳簿保存法」で電子取引のデータ保存が義務化されていますが、専用システムは法律に則った機能も充実しており管理面でも安心です。
あらゆる帳票を電子データで作成・送付できる「バクラク請求書発行」
2024年10月以降の通常はがきの値段は1通85円です。2024年9月30日までの1通63円と比べて22円値上がりしています。
はがきを含む郵送料金の値上げは、会社の業務コストに大きな影響を与えます。割引制度や他社の利用検討といった対策もありますが、大幅なコスト削減や業務改善を目指す企業には「バクラク請求書発行」の導入がおすすめです。
バクラク請求書発行は、シリーズ累計の導入企業1万社を超えるAI請求書送付システムです。請求書、納品書、見積書など、あらゆる帳票を発行できるほか、現行の帳票レイアウトに合わせた柔軟なカスタマイズも可能です。
発行した帳票は、メールで一括送付もしくは個別送付ができます。仕訳や振込業務はAIによる入力自動で、ミスの防止や月次決算の早期化も図れます。
バクラク請求書発行を導入し、はがき・郵送にかかるコストや手間を削減しましょう。
またバクラク請求書発行の特徴は以下の資料を参考にしてください。